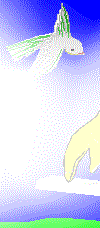 �ڎ��ɂ��ǂ�B
�ڎ��ɂ��ǂ�B�܂�����
�@�ŋ߁A�]�ˎ���̔o�l�m�ԁA�����A�ꒃ�̋�W��ǂނ悤�ɂȂ����B�ǂނ����ł͂Ȃ��A�����̋���u�A�N�Z�X�v�Ƃ����f�[�^�[�x�[�X�E�\�t�g�Ɉ����A����
���邱�Ƃɂ����B����ɓK���ȃL�[���[�h��ݒ肵�A�u�N�G���v�Ƃ����I�ʋ@�\���g���ƁA���p��͉����A�ނ�͉��ɊS�������Ă����̂��A�Ƃ������Ƃ������Ă���B�T���|�V���|�T�����v17���Ƃ��������̂ق��A�G��Ƃ�����������o��́A�ނ����Ȃ����A�����ȒZ���ł���B���̋����������͂ł�����
�Ƃ����B�ȉ��́A�m�ԁA�����A�ꒃ�𒆐S�Ƃ����A���̏���Ȕo��ӏ܂ł���B
�P�@�m�ԁu�Òr���v�@�Q�@�m�ԁu�����v�@�R�@�ꒃ�u��Ƃ����v�@�S�@�����u�t�����v�@�T�@�����u�q�K�v�@�U�@�ꒃ�u�~�������v�@�V�@�ꒃ�u���Ԃ���v�@�W�@�ꒃ�u�������v�@�X�@�ꒃ�u�q���v�@10�@�ꒃ�u�Ԃ̉A�v�@11�@�m�ԁu�c�ꖇ�v�@12�m�ԁu�s�t���v �P�R�m�ԁu�đ����v �@�P�S�m�ԁu�܌��J���v�@�P�T�m�ԁu�Ղ����v �@�P�U�m�ԁu�r�C���v�@�@�P�V�m�ԁu��Ƃ��v�@�P�W�m�ԁu���ɂ������v �@�P�X�m�ԁu�˂������v�@�Q�O�m�ԁu�����������v �@�Q�P�m�ԁu�߂Â炵���v
�����m�ԁE�m�Ԕo��W�E�����r��Z���E��g���ɂW�X��
�@���̋�͔o��̑�\�ł���A���w���ł��m���Ă�����A�L���Ȃ��̂ł���A�m�Ԃ��u�����̂ق����v�ɗ��������O�̒勝�R�N�i�P�U�W�U�N�j�A�m�ԂS�R�̎��̋�ł���i�m�Ԃ��u�����̂ق����v�ɗ���
�̂͂��̎O�N��̌��\�Q�N�A�P�U�W�X�N�ł���j�B
�@���̋���u�ꔭ�|��v�Ƃ����|��\�t�g�ʼnp����Ƃǂ��Ȃ邾�낤���B�u�Òr��^��т��ސ��̂��Ɓv��a����ƁA�a�X�uWith �� of the water that an old pond and a frog fly�v�Əo�Ă���B�����u��v���ז������Ă���悤�ŁA���܂��|��ł��Ȃ��B���Ƃ��Ɩ|��\�t�g�͔�g�̑������̘a��A�p��Ɍ����Ă��Ȃ��B
�@������u�Òr�Ɋ^��т��ސ��̉��v�ɂ���ƁA�ꔭ�ŁuThe sound of the water that a frog flies to the old pond�v�Əo�Ă��邪�A����ł͂��̋�̊����A����͑S���Ȃ��B�o��̉p��^�������邪�A�p��͑�ϓ���B
�@�n���[�E�u���{�@�N�i�Q�R�̗��w���j�́uThe old pond ah! A frog jumps in; water's sound!�v�ƖĂ���B
�@�ƌ����ĒZ���ł͓��{�ꂪ�\����i�Ƃ��ėD��Ă��邩�Ƃ����A�����ł��Ȃ��B��Ƃ��Ă͓K���ł͂Ȃ������m��Ȃ����A�u�o�ŏo�����M���͐o�ɂ�����v�͐����p��łł́uDust
you are, to dust you will
return.�v�ł���A�������Ȍ����������ɂ���iThe Revised English Bible A
Literary Selection5�Łj�B�܂����̂��̃z�[���y�[�W�̎Q�l��i�̒��ɂ���Q�[���[�E�X�i�C�_�[�́u�\�̔����v�Ƃ������̒��ŁA�������j�ƕʂ�鎞�u���邢�͏\�N��ɂ����邩���v�ƌ����̂��uAgain
someday, maybe ten years,�v�Ƃ���̂́A���{������f�G�Ȋ���������B
�@�z�[���y�[�W�p�����͏c�������\�ł͂��邪�A������PC�@�\��A�ǂ����Ă������͉������̕����X���[�Y�ł���B�o��̃C���^�[�l�b�g�T�C�g�ł͔o�剡�����^�����N�����Ă���B
�@�����ł��������ɂ��Ă��邪�A�����u�Òr��v�̋���ȉ��̂悤�ɂ�����A���o�I���ʂ�������B
��
�r
��
�^�@���
��
��
��
�@���̋���r�m�ԂS�R�͐[��m�Ԉ�����A���Ȃ킿�m�ԏn�����ɓ����邪�A���߂��̓����r���r�u������r���߂���Ė���������v���L���ł���B�u���^�v���r�o��͑������邪�A�u��т��ފ^�v�͔m�Ԃ��������Ă��܂����̂���B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �Q���͋㖜��炭��̉Ԍ��� |
�����m�ԁE�m�Ԕo��W�E�����r��Z���E��g���ɂP�S��
�@�u����v�Ƃ́u�Q�O�v�Ƃ����Ӗ��B���̔o�傪�r�܂ꂽ�̂́A�����U�N�A���Ȃ킿�A�P�U�U�U�N�i�m�ԂQ�R�j������A��R�R�S�N�O�B�Q�O�O�O�N�̍��������ɂ��ƁA���s�s�̐l���͂P�S�U���V�V�W�T�l������A�����̐l���͍��̂P�T���̂P�Ƃ������ƁB�ӊO�ɑ����̂��A���Ȃ��̂��A���Ƃ������Ȃ��B
�@���̋�ɂ��āA�m�Ԃ��u�㖜��炭��v�Ƃ������̂́A�m�ԓ��ӂ̕\�����@�̈�ł���u���肩�����\���v�ł���A�u��v���x�g�����߁A�{���Ȃ�u�㖜�M�G����v�Ƃ����̂��u�㖜��炭��v�Ƃ���
�A�Ƃ����l��������i�x�؎��E�\���Ƃ��Ă̔o�~�E��g���|���ɂP�X�Q�Łj�B
�@���̋�́A���s���̐l���F�A�Ԍ������Ă���A�Ƃ��������̋傾�낤���B�m�Ԃ͂P�U�S�S�N�A���̎O�d���ɉ���̋��m�̎��j�Ƃ��Đ��܂�A���N����A���叫�����V���Y�̒��j�ǒ��̏����Ƃ��ďo�d���A�o�~���n�ޗǒ�
�i�o�����j�̒m���Ă������A�P�U�U�U�N�i�����U�N�j�t�A�ǒ��͂Q�T�ŕa�v�����B�V���b�N�����m�Ԃ͒v�d���A�ǂ������s�ɏ�����炵���B���̌�͂Q�X�ō]�˂ɉ���܂ł͋��s�̑T�тŏC�s���Ă����炵���B���̗ǒ��̎��A���̌�̔m�Ԃ̏C�s�͔m�Ԃ̐l�Ԍ`����A�d��ȈӖ������Ƃ���Ă���i��L�m�Ԕo��W�E�����r��Z���E��g���ɂS�W�X�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@�Ƃ���Ƃ��̋�́A���s���̐l���F�A�Ԍ������Ă���A�Ƃ��������̋�ł͂Ȃ��A���s���̐l�͊F�A�Ԍ������Ă��邪�A�����͔߂����A�Ƃ����Ӗ������������A�ߒQ�̋�Ƃ������ƂɂȂ�B�ڎ��ɂ��ǂ�B
���шꒃ�E�ێR��F�Z���E�V���ꒃ�o��W�E��g���ɂP�Q�S��
�@�ŋ߁ANHK�ňꒃ�̃h���}�����������A�ꒃ�͕��P�R�N�i�P�V�U�R�N�j�A�_�Ƃ̒��j�Ƃ��āA��[���k�M�Z�i���쌧�j�����Ő��܂�A���i�U�N�A�P�T�ō]�˂ɏo���B���̌�͋�J���d�˂āA����Ɣo�~�t�ƂȂ�A���X�A��������A�e�n�ɔo��s�r�ɏo�����Ă������A�����P�O�N�A�T�P�̎��A�̋��ɋA��A�T�Q�ŎႢ�ȋe�����}���ĐV���т������A�����P�O�N�i�P�W�Q�V�N�j�A�S���Ȃ�܂ŁA���̒n�ŕ�炵���B���̋�͐M�Z�̒n�ō�����悤�Ɏv���邪�A���͕����V�N�A�S�W�̎��̂��̂ł��邩��A�̋����Â�ō�������A�����́A�ꎞ�I�A���̐܂�ɍ������Ƃ������ƂɂȂ�B�ꒃ�́u�������v�Ƃ��A�u�ǂ��ǂ��v�Ƃ��̋[���𑽗p���Ă���i�Q�ƁE�剪�M�E�S�l�S��E�u�k�ЂR�P�Łj�B�ڎ��ɂ��ǂ�B
�^�ӕ����E���`���Z���E�����o��W�E��g���ɂQ�P��
�@�����͂P�V�P�U�N���܂�P�V�W�R�N�v�B�ꒃ��菭����y�ł���B��㐶�܂ꂾ���A�Q�O���A�]�˂ɏo�Ĉꒃ�Ɠ����悤�ɋ�J���Ĕo�~�C�s���s���������ł͂Ȃ��A�G���C�s���A�o���ƍs�r�������悤�ł���B��J�̂����ŁA���̋�ɂ͉A�e���Z���A�����ɔނ̋�̖��͂�����B���s�ɂ������Α����^��ł���A�@�����Ђł�����āA�������������Γn��l�����̋����n�������Ƃ��낤�A���ꂩ��R�O�O�N�߂����o�����B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �T�q�K�l�����މ_�Ԃ�� |
�^�ӕ����E���`���Z���E�����o��W�E��g���ɂT�Q��
�@�����̋�͔_���̌��������ꒃ�́A�t�قƌ����Ă悢���炢�̏���A���C���Ɣ�ׂ�ƁA��ρA���_���ŁA������I�ŁA�V���[���ŁA�N�w�I�ŁA�����Ă���A�Ƃ�������������B�q�K�i�قƂƂ����j���_�Ԃ���l��͂ށA�Ƃ́A���A�_���̊G��A�z���Ă��܂��B
�@�쒹�́u�قƂƂ����ȁv�ɂ́u�z�g�g�M�X�v�̂ق��u�J�b�R�E�v�u�c�c�h���v�u�W���E�C�`�v�����邪�A���̎l�҂̎p�`�͂悭���Ă���i�����Ƃ��A�J�b�R�E���̒��R�T�Z���`�ʂň�ԑ傫���A�z�g�g�M�X�͑̒��Q�V�Z���`�ʂł���j�A�Ɣ���傫�������悤�Ȓ��ŁA�o�^�o�^�A�Ƃ��������Ŕ�сA��s�͗]����ł͂Ȃ��B�Y���͂��邪�A�����A�琗�����Ȃ����ŁA���������Ȃ̑��ɎY�����Ĉ琗�܂ł��Ă��܂��B���͂��������Ȃ̐��𑃂��痎�Ƃ��āA������菬�������������Ȃ̒�����a�����đ傫���Ȃ�Ƃ����A�����܂������ł���B�o���Łu�قƂƂ����v�Ƃ��Ă��Ă��A���̒����{���Ɂu�z�g�g�M�X�v�ł��邩�ǂ����͋^�킵���B�����Ƃ��u�z�g�g�M�X�v�̖����́u�������ǁv�ƕ������A�u�J�b�R�E�v�̖����́u�J�b�R�[�v�ł���B�u�c�c�h���v�́u�|�b�|�v�ł���A�u�W���E�C�`�v�́u�W���[�C�`�v�ł���A��ʂ��₷���B�u�z�g�g�M�X�v�̖�������ԔߜƂł��邩��A���̋�́u�q�K�قƂƂ����v�͐^�́u�z�g�g�M�X�v�Ƃ݂����B
���̋�́A�����̂��̂����L���Ğl��͂ޏu�ԁA���o�̎R�H���z���Ƃ��ɖ��Ƃ�����z�g�g�M�X�̉s���������_�Ԃ��畷������A�Ɖ��߂���Ă���i�������c�j�E�����W�E�u�k�Е��ɂP�Q�P�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@�����ɂ́u�̉Ԃ�@�~����炸�@�C������v�Ƃ����傪����i���`���Z���E�����o��W�E��g���ɂS�V�Łj�B���̌~�̗��Ȃ������C�Ƃ́A�������̊C�A�����̊C�A�����̊C
�A�Ƃ����A��̓I�ȊC�ł͂Ȃ��A�����̓��̒��̊C���낤�B�~�������ł���B�����~�A�����~�A���{�~�ł͂Ȃ��A�����̔]���Œ��𐁂�����ȊC���M���ނł���B����ł��āA��
�����́A��C���O�ɊJ�����A�g�������́A�̉Ԃ��炢���A�L�X�Ƃ��������z�������B
�@�����ЂƂA�����́u�{�Ёi�����̂ڂ�j�@���̂ӂ̋�́@����ǂ����v�i���`���Z���E�����o��W�E��g���ɂR�W�Łj���s�v�c�ȋ�ł���B�����A�����オ���Ă����́A�����ɂ�����̋�Ɠ����悤�Ɍ����邪�A�������͂Ȃ��B����ƍ����ł͎��Ԃ��Ⴄ�B��X�̌��݂͍��W�I�ɂ����A���Ԏ��Ƌ�Ԏ��̐ړ_�ł���B���i�͓����悤�Ɍ����Ă��A���Ԃ��߂���Γ������i�Ƃ͂����Ȃ��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���č�����傾�낤�B�����͓N�w�҂��B
| �U�~��������Ȃ��ǂЂƂ�� |
���шꒃ�E�ێR��F�Z���E�V���ꒃ�o��W�E��g���ɂT�O��
�@���̋�͏�L�̂悤�Ɉꒃ���A�����ď��т����O�́A�ꒃ�S�P�̎��̋�B�C���^�[�l�b�g���X�́u�A�}�]���v�Ō�������ƁA�����W�}���͖�V�O�A�ꒃ�W�}���͖�P�O�O�B�o�����ތ���A�����̕������[���悤�ȋC������̂����A���{�l�ɂ͈ꒃ�̏���A���C������̂��낤���B���̋���ꒃ�̌ǓƊ����o�Ă��āA�����ȋ� �ŁA������Ƃ́u�P�����Ă���l�v�Ƃ���c�R���́u��Ȃ��Ă킽������l�v���A�z�����B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �V�Q�Ԃ�����邼�����̂��~�i���肬�肷�j |
���шꒃ�E�ێR��F�Z���E�V���ꒃ�o��W�E��g���ɂQ�T�O��
�@���̊ێR�Z���̐V���ꒃ�o��W�ɂ́A�N��s�ڂ̂��̂��܂ݒ��x�A�Q�O�O�O�傪���^����Ă��܂����A�ꒃ�̋�œ����I�Ȃ̂�
�i�P�j墁A�^�A���̎q�Ȃǂ̏������ɍׂ����S�S����������A����u����������v���������ƁA
�i�Q�j�����̋��𗣂�Ă����̂ŁA��������̋��╃����Âԋ�A����u�������v���������ƁA
�i�R�j�N���Ƃ��Ă���q�����������̂ŁA������������A����u�e�����v���������ƁA
�i�S�j�V���}���Ă̋�s�A�Q���̋�A����u�V�l���v������
���Ƃ��������B
�@���̋������������̈�B�ꒃ�ɂ͓���̋�u墈�@�łĂ��Ȃނ��݂��@�����v�u��Ɨ��ā@�V�ׂ�e�́@�Ȃ����v�u�Q�w�́@�����ɂނ���ȁ@�@���̎q�v�u���^�@�܂���Ȉꒃ�@���ɗL�v�u���̎q�@�����̂������̂��@���n���ʂ��v�u���łȁ@墂��������@���������v������B
�@�R�I���M�̌Ö��̓L���M���X�ŁA�~���L���M���X���A�R�I���M���͂悭����Ȃ��B�l�Ƃɓ����ė���̂͌�҂̂悤�ȋC������B�L���M���X�͌x���S�������A�l�Ƃɂ͓����ė��Ȃ��B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �W�����ɌË��i�ӂ邳�Ɓj�����ė܍� |
���шꒃ�E�ێR��F�Z���E�V���ꒃ�o��W�E��g���ɂQ�Q��
�@����͏�L������̈�ł��B�ق��Ɂu�˂̉Ԃɂʂ��Â���i�j�Ë��Ȃ������v�u�Ë��Ɏ�����R���������Č������v�u������Ė��ڂ̌������c���v�ȂǓ��ނ̋傪����������B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �X�q����炫�����ɉ� |
���шꒃ�E�ێR��F�Z���E�V���ꒃ�o��W�E��g���ɂR�O�R��
�@���̋�͕�����N�A�ꒃ�T�V�̎��̋�ŁA��W�u���炪�t�v�ɍڂ��Ă���B�u�e����v�ɑ�����B�e���Ƃ̊Ԃ̎q�͎��X�ɖS���Ȃ�A�e�����S���Ȃ�A�ꒃ�̔ӔN�͋ɂ߂ė҂������̂������B���̓_���������āA�ꒃ�l�C�̌����̈�ɂȂ��Ă���̂��낤�B�ڎ��ɂ��ǂ�B
���шꒃ�E�ێR��F�Z���E�V���ꒃ�o��W�E��g���ɂR�U�R��
�@�l�ԒN�ł��A�ᎀ�ɂ��Ȃ�����A�N���Ƃ�A�V���āA����ł������́B��������̎��l�����Y�͂S�O��ł��łɉ��V������A�Ƃ��������̎�������Ă���B���ϔN��̒Ⴉ�����]�ˎ���͂Q�O�͑����ĔN����l����K�v������B�ꒃ�T�O�͍��̂V�O���낤�B�T�O�ɂȂ����Ƃ��A�ꒃ�́u���̂��ꍡ��\�̉Ԃ̏t�v�Ɖr��ł��邪�A�u�Ԃ̏t�v�ƌ����Ă���ʂ�����A�T�O�͖����䖝�ł���N���������낤�B���قljr�Q���ł͂Ȃ��B�������T�S�ł͂��炩���`��H�ׂ�N��ɂȂ������Ƃ��u���₵�����n�`���Ԃ̍��ɂ����v�ƒQ���B�T�X�Œ����ɂȂ�����͈�]���āu���Ƃ�����ׂ͊ۖ���O�k�V���v�ƈ�x�͊̂𐘂��邪�A�U�O�ɂȂ�ƁA���u�Z�\�N�x�����Ȃ��߂��������v�Ƃڂ₫�A�u���ɉ���Ƃ�����ה��[�����v�ƌ��݂������A�U�R�ɂ́u�ڂ�����Ǝ������ȕ����v�ƍ����ɁA�ۂ����莀��]�݁A�U�T�̈ꒃ�����N�A�ނ́u����⍡�ɉ䓙�����̒ʂ��v�Ǝ���\�����A���������B10�̋�����l�̋�B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �P�P�s�t�Ⓓ�e���i�Ƃ�Ȃ������j�̖ڂ͟� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂP�P��
�@�����̂ق����́u�����͕S��̉ߋq�ɂ��āA�s���ӔN�������l��B�v�Ƃ����L���Ȕ������̏����o���Ŏn�܂�B���͔�g�̕��w�ł��邪�A�l�������ł���A�l�͂��ׂė��l�ł���A�Ƃ������I�ϔO�́A�Â����瑽���̘a���m�̕��w�Ɍ���ꂽ�i��x�q�v��E�W���[�W�E���C�R�t�A�}�[�N�E�^�[�i�[�E���ƔF�m�E�I�ɍ������X�P�P�ňȉ��j�B�]���Ĕm�Ԃ̂��̏����o���͎a�V�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ނ�����Ƃ������ׂ����̂ł���B
�@�m�Ԃ͏Z��ł����������A�����������l�ɑ݂��A�����͐��̒u����ƂȂ�̂ŁA�o���ɐ旧���u���̌˂��Z�ւ�ゼ�ЂȂ̉��v�Ɖr��A���\�Q�N�i�P�U�W�X�N�j�A��R���Q�V���i�z��T���P�U���j�A��q�̑\�ǂ�A��ē��k�A�k���o�R�̈ɐ��ւ́A�W�������z�����ɏo��B���̗������̋傪���́u�s�t��v�ł���B
�@�o�~�t�ɂ͊����̑f�{���������̂ł��邩��A���́u���e�����̖ڂ͟��v�ɂ������̉e��������A�Ƃ����̂���L���ԏ��̉��߂ł���i��L��g���ɂP�U�V�Łj�B�����ƂȂ������̂����̈�́A�m��̗L����
�܌������u�t�]�v�ł���i����m��ҁE�m�ᎍ�I�E��g���ɂP�Q�P�Łj�B
���j��ĎR�͍݂�
��t�ɂ��đ��ؐ[��
���Ɋ����Ă͉Ԃɂ��܂��d��
�ʂ������ł͒��ɂ��S��������
�E�E�E
�@���̎��ɂ��u���v�͏o�Ă��邪�A�����ł͒����߂���ł���̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̕����߂���ł���̂ł��邩��A�u���e���v�ɂ͔m�Ԃ̃I���W�i���e�B����������B�u���̖ڂ͟��v�͍X�Ƀ��j�[�N�ȕ\���ł���B������ɂ��Ă��A���Ȃ�A�V�����𗘗p���ẮA�����ƌ����Ԃ̓��k�A�k���o�R�̈ɐ��ւ̗��ł��邪�A�����͕K���̊o������߂Ă̗��ł��������낤�B���̎v�������̋�ɍ��߂��Ă���B
�@����ɂ��Ă��u���̖ڂ͟��v�͔���ɂ����B���R���O�Y���́A�m�Ԉ�̔�҂��������R�����͋��≮�������A�Ƃ������Ƃɒ��ڂ��Ă���i�Βk�E�m�Ԃ��D���E�����o��E�Q�O�O�Q�N�Q�����U�V�Łj�B�ڎ��ɂ��ǂ�B
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂQ�P��
�@�����̂ق����ɍڂ��Ă����͋͂��T�O�B�p�\�R���ɊȒP�ɓ��͂ł���B����ɓK���ȃL�[���[�h��ݒ肵�A���ёւ�������ƁA���p��Ȃǂ��ȒP�ɔ���A���ɂȂ�B�����ŏ��Ɏ䂩�ꂽ�傪���̖��̋�B
���Ȃ݂ɁA�����̂ق����ň�Ԃ̑��p��͌��ƏH�i��������l�j�B�܌��J����A���������B
�@�u���v�Ƃ������{��ɑ��āA���{�l�͐F�X�ȃC���[�W������B�u�����v�u�����v�u�����v�͏����̕��e�Ɋւ��錾�t�ŁA�×��A�v���X�̉��l�������Ă������A���͂ǂ����낤�B�u���̉��̓D�Ӂv�͙F����Ӗ����A�u���ɕ��v�͖��̈ӊO�ȋ��Ղ��������Ă���B
�@�u���̉��̓D�Ӂv�́A���̑��݂�O��Ƃ��Ă���B�X�y�C���̎��l�����J�́u���܂萅�v�Ƃ������ɂ�
�����@���Ƃ����i�Ƃ߂�ꂽ���j
�����|�v���i�����̐��j
��Ȃ��i�[�����j
�E�E�E�v�Ƃ���i���J��l�Y�����J���W�݂������[�R�T�Łj�B
�@���͐��ӂɂ悭�����邩��A���A���Ȃ킿���ƘA�z����̂��B���s�̊���ł��o���ӂł́u�o�����v�Ƃ����n���������悤�ɁA��ӂɖ����������Ă���B
�@��A�����Ė��̎}���h���̂́A���낵���i�F�ŁA�ŋ��ŖS�삪�o��V�[���ɂ́A�����Ζ��������Ă���B����͖��̃}�C�i�X�̃C���[�W�B
�@�V�F�C�N�X�s�A�̔ߌ��u�I�Z���v�̓��b�V�[�j�i�P�V�X�Q�|�P�W�U�W�j�ƃ��F���f�C�i�P�W�P�Q�|�P�X�O�P�j�ɂ���ăI�y��������Ă��邪�A���̂ǂ���ł��A���̏I�Ջ߂��ŁA�I�Z���ɎE�����ȃf�X�f���[�i���u���̉́v�Ƃ����߂����A���A���̂��B���̗\�����������̂��낤�i���c�P����E�V�F�C�N�X�s�A�T�E�V�����E���w�P�T�W�ňȉ��ɖ��̉̂��ڂ��Ă���j�B
�@���̂悤�ɁA�u���v�Ƃ����ꎚ�ɂ͑�R�̃C���[�W�����邪�A�m�Ԃ͂ǂ̂悤�ȃC���[�W���������̂��낤���B
�@���h���Z���E�m�ԋ�W�E�V�����{�ÓT�W���P�V�W�ňȉ��ɂ́A���̂悤�Ȃ��̋�̑O�������L�ڂ���Ă���B�u���������̖��͈���̗��ɂ���āA�c�̔ȂɎc��B���̏��̌S��A�˕��^�́A���̖�������ȁA�Ɛ܁X�ɐ�Е������ӂ��A���Â��̂قǂɂ�Ǝv�������A�������̖��̉A�ɂ���������莘���v
�@���̖��͗w�ȗV�s���ɐ��s���u����粂ɐ����������������ƂĂ��������Ƃ܂��
�v�Ɖr�Ƃ���鈰��̗����V�s���̂��Ƃł���A�S��˕��^�Ƃ͓ߐ{�S����O��̗̎到�얯�����r�̂��ƂŁA�]�ː[��ɂɉ����~������A�m�ԂƂ͋��m�̒��ł������i�ȏ�ɂ����E�m�ԋ�W�P�V�W�ŎQ�Ɓj�B
�@�L���Ȓ��ߏ��u���ד����ԏ��v�ł́A�m�Ԃ͓����́u�������v�ł͂Ȃ��A�u�c�ꖇ�A��������������ȁv�Ƃ��Ă����A�Ƃ���i��L��g���ɂP�V�U�Łj�B�A�����J�̐����f��u�V�F�[���v�ŃK���}���ł���V�F�[�����u��������v�V�[�����v���o���܂ł��Ȃ��A�u�������v���u������v�̕����͂邩�ɗ]������B
�@���Ƃ��Ƃ��̋�͑O�L���s�́u����粂ɐ����������������ƂĂ��������Ƃ܂���v�i���X�ؐM�j�Z���E�R�ƏW�E��g���ɂT�S�Łj�ɓ���Ă̋�Ƃ���Ă���i�����̔o�~�t�͊����A�Z�̂̑f�{��g�ɂ��Ă����j�B���s���u�����ǂ܂�v�ƁA�ΉA�ł̋x����`���Ă��邪�A���m�o�g�̐��s�ƈႢ�A�_
�ɂ��������ł��낤���m�o�g�̔m�Ԃ́u�c��A���āv�ƘJ����
�r�����܂�������Ȃ������A�����ɔm�Ԃ�����������悤�Ɏv���B
�@�V�s���ɂ��ẮA�V�s�P�S������l�����쏄���̐܁A���̖��̐��������ɂȂ��Č����A�~�������߂��̂Ő����������Ƃ���
�`���A�������̕����R�N�i�P�S�V�P�N�j�A�V�s�P�X�����l�������̐܁A���̐����\�O���������A���������Ƃ����`��������A�ϐ������Y�M����Ɠ`������w�ȁu�V�s���v�̋��u�V�s��l�����͂̊ւ��߂���ƁA�V�l������Đ��̗V�s��l���ʂ����Ó��֗U���A���̖��A�Ƃ�������������B�����āA���s�@�t���u������ɐ����������������ƂĂ��������Ƃ܂��v�Ƃ���Ƃ����̎������A��l����\�O���������Ďp�������B���̖�A��l�̖��̒��ɖ��̐�������A�\�O�̂������Ő����ł���Ɗ�сA���ɂ��Ȃޘa���̌̎������A��ӂ̕����v�Ƃ������̂ŁA��
�̓`���ɂ��B
�@�m�Ԃɂ͖��ɂ��āA�ق��ɂT�P�Ύ��́u�Ԍ��ɂƂ����D�����������v�Ȃǂ�����A�������V�s���ɂ��āu���U�������Ώ��X�v�Ƃ����傪����B
|
|
| �P�R�đ��╺�i�͂��́j�ǂ������̐� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂS�P��
�@���\�Q�N�i�P�U�W�X�N�j�A��R���Q�V���A�]�˂��������m�Ԃ͓����A���H�A�S�R�A�����A���A�����A�Ί��A��ւ��o�āA�́A�������t�A��t�A�G�t�O�オ�h���ւ�������ɓ������̂͂T���P�R�����Ǝv����B
�����G�t�͋`�o��삵�����A�P�P�W�X�N�A�`�o�͓����t�ɎE����A�t�������ɍU�߂��A�Y�}�ɎE���ꂽ�B�m�Ԃ͏G�t�̏�Ղ͓c��Ɖ����A�`�o�̋��邾�������ق����Δ��Ɖ��������i�����āA���̊��S�����̋�ɉr���̂ł���B�܂��ɏ�L�u���j��ĎR�͍݂�@��t�ɂ��đ��ؐ[���v�Ƃ����m��̎��ɒʂ�����̂�����B����
�ɂ��L���ȁu�z�����Áv�Ƃ���������傪����i���Y�F�v�Җ�E�������I�E��g���ɂX�Q�Łj�B
�z�����H�@����j���ċA��
�`�m�@�ƂɊ҂�Đs���ш߂�
�{���@�Ԃ̔@���t�a�ɖ���
�����@�B���@�Y��̔�ԗL��̂�
�@���̎������̋�Ɠ������A�h���ڂ݂�����̂����ł���B�m�Ԃ͐ē������𓉂�ʼnr�u�ނ����ȁ@���̉��́@���肬�肷�v�Ƃ����������i�����r��Z���E�m�Ԕo��W�E��g���ɂP�X�O�Łj�B
���̗��ɓ��s�����]�ǂ́u�K�̉ԂɌ��[�݂�锒�т����v�Ƃ�������c���Ă���i�K�̉Ԃ̓E�c�M�̔����Ԃ��w���A���̔����Ԃɔ����Ő�����V�����[�����Ԃ点���̂ł��낤�B
�@
�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �P�S�܌��J�̍~��̂����Ă���� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂS�P��
�@���j�w������ҁE����œ��{�j�N�\�E����łɂ��ƁA�P�P�O�T�N�A�������t�͕���ɒ������������A�P�P�Q�U�N�A�����Ȃǂ̗��c���{���s�����Ƃ���Ă���B�m�Ԃ��u�����̂ق����v�̗���
�A�����͂����Ėk�サ�A�����K�ꂽ�Ƃ��́A�����O��̊���[�߂������A�O���̑���[�߂��o�����E�E�E���̔����ɂ�Ԃ�A���̒�����ɋ����āA�����p�̑p�Ɛ���ׂ����A�l�ʐV���Ɉ͂āA�O�ĕ��J�𗽁E�E�E�Ƃ����L�l�ł������Ƃ����i�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂS�P��
�Q�Ɓj�B���͂܂��ɉA��T���A�l�ʂɍ~�蒍���܌��J�����j�������ŁA����������Ă���̂��A�ƂT�O�O�N�O�̗��j����ڂ����ł���B���̔m�Ԃ̋傩������łɂR�O�O�N�]�o���Ă���B
�@�m�Ԃ͂��̗��ł�����A�L���Ȍ܌��J�̋���r��ł���B�u�܌��J���@���߂đ����@�ŏ���v�ł���B�܂��ŏ��ɂ��Ă͏������ƂŁu���������@�C�ɓ��ꂽ��@�ŏ���v���r��ł���B�ŏ������������̌�ȎR�ɔ����A�đ�|�R�`�|�V���̊e�~�n�𗬂�Ď�c�s�œ��{�C�ɒ����A���{�O�}���̈�B�S����Q�Q�X�L�����[�g���B �ڎ��ɂ��ǂ�B
| �P�T�Ղ����ɂ��ݓ���̐� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂS�U��
�@�m�Ԃ����͕����ɂ��ǂ�A�R�`�̔��ԑ�~�n�ɓ���A��Γc���o�ĉH���R�A���R�Ɍ��������A���̓r���ŁA��ɐ��Ղ̒n�ł���A�Ɛl�X�������߂�̂ŁA�킴�킴���ԑ�쉺���ė��Ύ��i�� �ӂ��Ⴍ���j�ɎQ���Ă���B�u�����̂ق����v�ɂ��ƁA���̎��͎��o��t�̊J�������̂ł��邪�u��Ɋނ��d�˂ĎR�Ƃ��A�����N�Â�y�ΘV���đۂȂ߂炩�ŁA�������������A���i�┙ �v�Ƃ��Ă����B���͗z��łV���P�R�����ł��邩��A���R��̐��ɖ����Ă����Ǝv����B���̐䂪����ł��邩�ɂ��Ă͏������X�Ƃ��Ă��� �i�ē��g�̓j�C�j�C����A�����������j�B�G�߁A�n�`�A���Ԍn�̕ω��Ŕ��f���邱�ƂɂȂ邪�B��̓J�����V�ڃ��R�o�C���ڃZ�~�Ȃ̍����ł��邪�A�֓��ł͂V����{�Ƀq�O���V�A�j�C�j�C�[�~�A�V�����{�ɃA�u���[�~�A�N�}�[�~���o������A�Ƃ����Ă���B�Z�~�����̏o���͂��̔N�̓V��Ȃǂɂ��x�z����A�܂������̃Z�~�����݂��邱�Ƃ���������A�m�Ԃ��P�U�W�X�N�A��T���Q�V���A���Ύ��ŕ������̂����Z�~�����m�肷�邱�Ƃ͍���낤�B�܂��m�肵�Ă��A���قǂ̈Ӗ��͂Ȃ��B ���R���O�Y���͂��̐�̓Z�~�ł͂Ȃ��A�m�Ԃ��Ⴂ���h�����Ă��������ǒ��ł���A���̂Ȃ�A�ǒ��̔o���́u���v������A�Ǝ咣����i�Βk�E�m�ԍD���E�o�咩���Q�O�O�Q�N�Q�����U�U�Łj�B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �P�U�r�C�⍲�n�ɂ悱���ӓV�̉� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂT�T��
�@�m�Ԃ������߉����o�ē��{�C�ɖʂ����c�ɒ������̂͂U���P�R���i�z��V���Q�X���j���ł������B�ނ�͖k�サ�ďۊ���������A���{�C�����̖k������쉺����B���̉E��ɂ͂����ƍ��n���������Ă���B
�@���n���͐V���̖�R�T�L�����[�g�����ɂ���W�H���̖�P�E�T�{�̑傫�ȓ���
�A�]�ˎ���̗��l�̓��Ƃ��Ă��m���Ă���B�����O�N�ԁA�V���������ɋΖ����Ă������Ƃ�����A�V���ɏo��������A�o�_��ɗV�тɍs�����܂�ȂǁA���x�ƂȂ��A���{�C�ɕ����ԍ��n����ڂɂ������A���Ɨ��l�̓��Ɋό��ɍs���C�����̂ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�@�m�Ԃ������e�m�炸�q�s�m�A�s�U�ɒ����͖̂�ꃖ����ł��邩��A�������点�A���n���͂��̊Ԃ������ƁA�m�Ԃ̖ڂɉf���Ă������ł���B
�@�ꏊ�ɂ�낤���A��͍��n���̓����������ł��낤���A����ɂ́A���Ƃ͌��Ⴂ�́A�N�₩�ȋ�͂��������Ă����B
�@���{�C�̊C�͑����m���ƈႢ�A�F��������ŁA�ݐF�̓��������A���������Ɣg�������B
�@���̓��{�C�����̖k�����̗��̏W���̋�ł��낤�B�m�Ԃ̋�̉��l�͐S�ۋ�ɂ���B���̋���P�Ȃ�ʐ���ł͂Ȃ��A���낢��ȗv�f����ꂽ�S�ۋ�̈�ł��낤�B
�u�r�C�v�Ƃ��u�V�̉́v�́A�̋����v���Ȃ�������̓��ʼnʂĂ������̗��l�����̉^�����v������ďo�ė��錾�t�ł��낤�i���|����F�j�E�m�ԁE�W�p�АV���P�R�Łj�B
�@�ꒃ�ɂ��S�P�Ύ��A�V�̐���r�����傪����u�䐯�́@�ǂ��ɗ�����@�V�̐��v�B�ڎ��ɂ��ǂ�B
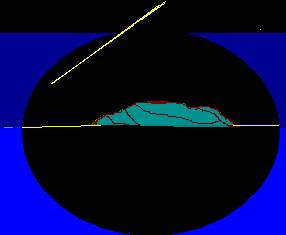
| �P�V��ƂɗV�����˂��蔋�ƌ� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂT�V��
�@�k�����ɖʂ����L���ȓ�u�e�m�炸�q�s�m�v�A���ł͍������H���ʂ��Ă���B���̓���߂����ӂ�Ɂu��U�v�������́u�s�U�v�Ƃ����n������B�����̏h�ɔm�ԁA�]�ǂ����܂�����A�V����l�ƕt���Y���̒j�Ɠ��h�����B�V�������͐V���̗V���ł���B�V���ɂ͈ɐ��Q��̕��K������A�V���͕�����ɖ��f�ňɐ��Q��ɏo�āA�����͕t���Y���̒j�͋A��A�������̗��ɂȂ�s������A�n���߂̑m���p�̑]�ǂ����ƈꏏ�Ȃ���S�ƁA�����𗊂ށB�������m�Ԃ́u��X�͏��X�ɂĂƂǂ܂�����ق��B�_���̉���A���Ȃ炸���Ȃ���ׂ��v�Ɠ�����f���ċ��邪�A�C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��B���͉A��V���P�Q���i�z��W���Q�U���j���A�k�����ɂ͑����������ڂɕt�������A�����͓��ӂ̐S�ۂ������̂��A���̋�͔��ƌ��ɂȂ��Ă���B������ɂ��Ɣm�Ԃ̖��m���͑�ςȔ��j�ŁA�m�Ԃ̗��l�ł������Ƃ����i�O�f�Βk�E�m�ԍD���E�o�咩���Q�O�O�Q�N�Q�����U�W�Łj�B�]�ǂƂ͂ǂ������W�������̂��낤���B����ɂ��Ă��V�������Ă̎l�l���͋C���d���̂Œf�����̂ł��낤�B
| �P�W���ɂ�����������Ƃ�Ώ��ʂׂ� |
�����m�ԁE�m�Ԕo��W�E�����r��Z���E��g���ɂS�T��
�@�����ɂ̓V���E�I�Ȃ̂��̂ƃn�[�Ȃ̂��̂����邪�A�O�҂̕����������������B�m�Ԃɂ͔��u���ڂ̂�@���狛���낫�@���ƈꐡ�v�u������@�����ڂ𖾃N�@�@�i�̂�j�̖��v�Ȃǔ����̋傪����B
�m�Ԃ́u�살�炵�I�s�v�Ȃ���S���Ȃ�܂ł̏\�N�Ԃ��d�v�Ȕm�Ԕo��̌`�����Ƃ����Ă��邪�A���̊ԁA�ނ̋�ɂ́u���vwhite�����p����Ă���A�Ƃ̎w�E������i����F�j�E�m�ԁE�W�p�АV���U�R�ňȉ��j�B�����Ƃ��A���̋�͂�����O�́A�m�ԂR�W�Ύ��̂��̂ł���B���Ɋ��W�܂��Ă��锒���̓��������悭�o�Ă���B
�@
�ꒃ�ɂ��S�U�Ύ��́u�����́@�ǂ��Ɛ����@���ڂ���v������B
| �P�X�˂������䋃���͏H�̕� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂT�X��
�@�]�ˎ���A�O�c��̗̒n�ł���������B���A���Ƃ̍Ȃ܂𒆐S�Ƃ���NHK�̑�̓h���}�����f���ł��邪�A�s�U�����m�Ԃ����͊���A�x�R���o�ĉA��V���P�T���i�z��W���Q�X���j����ɒ������B����ʉ߂̍��͏��C�������A���炭���ł��c���̌��������Ƃł������Ǝv����B����ɂ͈�Ƃ����Ԗ�̔o�l���������A�m�Ԃ̗��K��҂����ɂR�U�Ő�������A�Z�̔o�������i�ׂ����傤�j�Ƃ����҂��Ǔ������Â����B�V���Q�Q���̂��Ƃł���B���̋�͂��̎��̂��̂ŁA�u�ˁv���Ȃ킿�u��v�ɂ��Ă͓������\�Q�N�A�m�Ԃ́u�����́@����߂���@���˝Ȃ��v�Ƃ�������r��ł���B�s�U�ʉ߂̍ہA�m�Ԃ͂��łɁu��ƂɗV�����˂��蔋�ƌ��v�Ɖr��ł��邭�炢�ł��邩��A�����͏��C�������Ă������A�[���Ȍ�͂������ɏH���������Ă������Ƃł��낤�B�����ł͏H�����o�ꂷ��B����ɂ��Ă��u�˂������v�A�u�䋃���i�킪�Ȃ������v�Ƃ́A�e�Ղɂ͖͕�ł��Ȃ��A����������\�o�ł���B
| �Q�O���������Ɠ��͓�ʁi��Ȃ��j�������̕� |
�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���ɂT�X��
�@�m�Ԃ͋���ɂ͈�T�ԗ]�؍݂������A��L�Ǔ����̂ق��ē��ꌺ�̏������ɂ�������u�H�����@������ɂނ���@�Z�֎q�v�Ɖr���A�r����Ƃ��āA
���́u���������E�E�v���r�B�u���������v�̏�܉��́u�����̕��v�Ƃ������܉��Ɩ�������悤�Ɍ����邪�A�u�����̂ق����v���ڋ�̖w�ǂ́A�܁X�̐S�ۋ�ł��邩��A����
���̂��������Ӗ��������Ă���B
�@�m�Ԃ��u�����̂ق����v�s�������s�����̂͌��\�Q�N�ł��邪�A�I�s�u�����̂ق����v�͐��Ȃ��d�ˁA�m�Ԃ̎��㌳�\�P�T�N�Ɋ��s����Ă���̂ł��邩��A���ڂ̋傪���s���ɉr�܂ꂽ���́A���̂܂܂Ƃ͌���Ȃ��B���]�Ȑ܂��������Ǝv����B
�@��ʁi��Ȃ��j�Ƃ͖����A������w���B
�@��g��A�H�̕��͐F�Ƃ��āu���v�������Ηp������B�m�Ԃɂ́A�������\�Q�N��Ƃ��āu�ΎR�́@��蔒���@�H�̕��v�Ƃ����傪����B
�@�������c���̍��̗[���߂��̗z�́A�t���ł́u���������Ɓv�R���Ă���B
�@�m�Ԃ͂V���Q�S�����A������A�����A�։�A��_���o�āA�X���U���A�ɐ��������ŁA�R���Q�V���ȗ��̒����ɏI�~����ł����B�ڎ��ɂ��ǂ�B
| �Q�P�߂Â炵��R���o�H�i���ł́j�̏��֎q |
�����m�ԁE�m�Ԕo��W�E�����r��Z���E��g���ɂP�W�P��
�@�m�Ԃ����͂U���P�O���i�z��V���Q�U���j�߉��ɔ��܂����B�u�����̂ق����v�ɂ��ƁA���܂����̂͒��R�ܗljE�q�咷�s�Ƃ������m�̉Ƃł���B
�@����|�P�O�Q���Q�U�ňȉ��ɁA���̎��̔m�Ԉ�s�̂��Ƃ������Ƃ���Ă���B�����A�̒��̗ǂ��Ȃ������m�Ԃ͊���H�ׂ����A���̍ہA�o���ꂽ�A��Ђ����ꂽ�A���Ԃ�̏��֎q�̖��Ɋ��������B���s���o�l�ŁA���܂�������ɂ��ȒP�ȋ��Â��ꂽ�B���̐܂�A�m�Ԃ͐�قǂ̏��֎q��J�߁A�o���Ă����H���R�A���a�R�A���R�̏o�H�O�R��z�N���A�o�H�ɂ����āA���̋��������A�Ƃ����̂������̍��q�ł���B
�@���̓��̂��Ƃ́u�����m�ԁE�����̂ق����E�������j�Z���E��g���Ɂv�̂W�R�ňȉ��́u�]�Ǘ����L�v���̂P�P�Q�łɋL�ڂ�����
���A���̋�́u�����̂ق����v�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ����ł��u�����̂ق����v�ɂ͌��I���ꂽ�傾���ڂ��Ă��邱�Ƃ�����B
�@���A�֎q���ӉZ����N���A�X���ɂ���B�{�i�����j�̖��A����𖡂키�����͎����Ă��܂����B