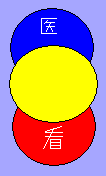
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�ڎ� |
�@�����o�G�W�v�g�L�S�O�͂ɗL���ȁu���[�[�̏\���v������B����̓��[�[���V�i�C�R�Ő_������Ƃ������߂̌��t�ł��邪�A�u���������Ăق��ɐ_�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v����n�܂�A�u�אl�̉Ƃ�~���Ă͂Ȃ�Ȃ��E�E�E�v�ŏI���\�̉��߂��q�ׂ��Ă���B
�@�́A�א��҂͂����u����͐_�̌��t�ł���v�ƍ����āA�������������A�܂��͈ȑO���炠��l�X�ȎЉ�K�͂����Еt���A���̒ʗp�������߂����̂ł���B
�@���Ƃ��ƎЉ�`�������Ƃ������Ƃ́A���炩�̎Љ�K�͂��`������邱�Ƃ��Ӗ����邪�A�Љ�K�͂ɂ́A�𗝂��Ȃ킿�����I�Ȃ��́A�@���I�Ȃ��̂���͂��܂�A����ɕ��G�ȎЉ�̐����ł���ɂ�āA�@�K�͂��`������A�]���̓����I�A�@���I�K�͖͂@�K�͂ɋz�����ꂽ�肷��B
�@���[�[�̏\���ɂ́A���̍��A���łɑ��݂��A�א��҂��猩�č������s�ׂƂ���Ă����A�E�l�A�����A�ޓ��A�U�̋֎~�������܂܂�Ă���B������������n�I�Ȉ�Ís�ׂ͂��������낤����A��Éߌ���������ł��낤�B��������Éߌ�����߂�����͂Ȃ��B��Éߌ듙�͈א��҂̊S���Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ������̂ł��낤�B
�@��w�A��Ð��x�����B��������ł́A��Éߌ�͌�ʎ��̂������l�̂���o�����ɂȂ�A��Éߌ�̐ӔC����������莋�����悤�ɂȂ����B
�@�����̍��ɂ͓����K�́A�@���K�͂̂ق��ɁA���łɁu�U�v�̉��߂�����ʂł��邩��A�ٔ����x�����݂��A���ł����Y���I�ӔC�A�����I�ӔC�̒Nj����Ȃ���Ă����ɈႢ�Ȃ��B����̎Љ�K�͍\���͋����̎���ɔ�ׂ�Ƒ����A���G�ɂȂ������A��{�I�ɂ͕ς���Ă��Ȃ��B���ł����Љ�I�s�ׂɂ��Ă͓����K�́A�@���K�͏�ł̕]���Ɣ��Ȃ���邪�A�̂ɔ�ׂ�ƁA��萸�k�Ȗ@�I�]���Ɣ��Ȃ����B
�@�Ⴆ�A�����Ԃő��l��瀂�����ʎ��̂ɂ��ẮA�����I�ӔC�̂ق��ɁA�@�I�ӔC�������I�ɒNj������B
�@���̎��̂ʼn^�]�Ƌ���~�A������Ȃ���邱�Ƃ�����i���H��ʖ@�P�O�R���E�s���@�I�ӔC�j�A�ŌY�A�����Y�ɏ������邱�Ƃ�����i�Y�@�Q�P�P���E�Y���@�I�ӔC�j�A���Q�������������邱�Ƃ�����i���@
�S�P�T�A�V�O�X���E�����@�R���E�����@�I�ӔC�j�B
�@��Éߌ�ɂ��Ă������ł���B�s�҂����t���Ƌ��̎���A�Ɩ���~���邱�Ƃ�����i��t�@�V���E�s���@�I�ӔC�j�A�ŌY�A�����Y�ɏ������邱�Ƃ�����i�Y�@�Q�P�P���E�Y���@�I�ӔC�j�A���Q�������������邱�Ƃ�����i���@
�S�P�T�A�V�O�X���E�����@�I�ӔC�j�B
�@�Y���ӔC�Ɩ����ӔC�Ƃ̑傫�ȑ���́A����A�����ړI�Ƃ����Y���ӔC�ł��̈��ӔC�����S�ł���A�ߎ��s�ׂ͓��ʂȋK�肪�Ȃ��Ɣ������Ȃ��i�Y�@�R�W���j�̂ɑ��A�����A���Ȃ킿�����ړI�Ƃ��������ӔC�ł͌̈ӁA�ߎ�������������Ă���i���@�V�O�X���j�Ƃ����_�ł���B
�@��Ís�ׂ̉ߎ�����Ɩ���ߎ��v�����߁i�Y�@�Q�P�P���j�͗�O�I�K��ł���i�����Ƃ��A�����Ԃ�瀂��ꂽ��Q�҂����������ē������鈫����瀂����������ɖ��K�̌̈ӗ��_���g���āA�Y�@�P�X�X���̎E�l�߂�K�p����P�[�X������悤�ɁA����\���A�F�e���đ��s���������Ȏ�p���s����ɖ��K�̌̈ӂɂ��E�l�߂�K�p����P�[�X��z�肷�邱�Ƃ͂ł���j�B
�@�����O��̖@�I�ӔC�͌�ʎ��́A��Éߌ낪��������ΕK���A��ɁA�Nj������Ƃ͌���Ȃ��B�s�҂̈����i�ߎ��j�̑召�A��Q�̑召���ӔC�Njy�̌��ƂȂ�B�ߎ��A��Q����������ΐӔC���Njy�����\���͏������A�ߎ��A��Q���傫����ΐӔC���Njy�����\�����傫���Ȃ�B
�@���Ȃ݂ɁA��Éߌ�̌Y���ӔC�Njy�ɂ����ẮA�ߎ��ɑ������Ȃ��A�������d��łȂ����̂̑����͌Y���i�ז@�S�U�P���ȉ������������ŏ�������A�����Y�ɏ������Ă���悤�ł���i�k���J�m�u��Éߌ�̌Y���ӔC�v���E�����ҁE����ٔ��@��n�V��Éߌ�R�P�R�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@���̂悤�ɁA��t���̈�Ï]���҂���Éߌ���N�������ꍇ�̐ӔC�ɂ͓����I�ӔC�A�@���I�ӔC�����邪�A���ɂ��܂��ďd��ȐӔC�͖@�I�ӔC�ł���B����ɂ́A��L�̂悤���s���@�I�ӔC�A�Y���@�I�ӔC�A�����@�I�ӔC�̎O��ނ�����̂ł���B
�@���̓��{�ł͈�Ë@�ւŐ��܂�A��Ë@�ւŎ��ʐl�����|�I�ɑ����B�l�̐����Ɉ�Â��ւ��̂ł���B�Ƃ��낪�A�l�������܂ꂽ���ƂɂȂ�A���ʂ��ƂɂȂ邩�A�Ƃ�����{���ɂ����͑����B
�@���@�P���m�R�́u�����m���L�n�o���j�n�}���v�ƋK�肵�Ă��邪�A���o���Ƃ݂邩�ɂ��āA���@�̓h�C�c�A�X�C�X���@���u�o���̊����v�ƋK�肷��̂��A�َ�����ق���S���I�o�������_���o���Ƃ݂�A������u�S���I�o���v���Ƃ�B
�@����ɑ��A�Y�@�ł��ꕔ�I�o�����Ƃ�A�ꕔ�I�o��̎��E�Q�ɂ��E�l�߂̐�����F�߂�B
�@���̂悤�ɏo���ɂ��Ă����Y�Ŏ��_���قȂ�̂ł��邩��A���S�ɂ��Ă����R�A��肪����B����@���ł͎��̎��_��傫�����ɂ��炷���Ƃ�����A���ꂪ�����ŌY���ӔC��肪�N���邱�Ƃ�����B���ɂ��Ă͏]���͐S������������ł��������A����ڐA�̖�肪�N�����Ă���͔]�������䓪���A�������Η����Ă���i���ɂ��Ă̖@��w�I�l�@�ɂ��R���t�v�u���̊T�O����ё���ڐA�ɂ��āv���c�K�v�ҁu�V�E�ٔ�������n�P��Éߌ�i�ז@�v�я��@�R�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@��́A���̒�`�͒N�����߂�̂��낤���B���S�ȎЉ�I�펯������҂ł���A���̏펯�̑�\�Ƃ��č���A���Ȃ킿�@����������߂�A�Ƃ����l�����Ó��Ǝv����B
�@���R�̎����ł��鎀���A���ꂪ�ǂ̂悤�ȗ��j�I�Љ�w�i�Œ�`����邩�ő傫���قȂ�B����A�����l�Ԃ̑��킪���Y����A���Y����ڐA���s���鎞��������A�܂����̒�`�������A�S����������������邩���m��Ȃ��B
�@���݂̑���̈ڐA�Ɋւ���@���͎��̒�`�͂��Ă��Ȃ��B���@�U���P���́A�E�o�Ώێ��̂ɂ͔]�������҂̐g�̂��܂ށA�ƋK�肵�Ă��邩��A�ނ���S�����A�]���̓���m�肵�Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@���Ɏ��̒�`������A���Ȃ킿�@���ŋK�肳��A�����Ŕ]�������̗p����Ă��A�`���I�S��������]���鍑���̊�]�A�I�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�]������S�����܂ł̊Ԃ��l�ԂƂ��Ĉ����A���N�ی��������A�Ƃ݂�ׂ��ł��낤�i�O�c�ق��u�㎖�@�v�P�S�O�Łj�B
�@�]���ł͑̂͒g�����A�����Ƃ�A���A�܂𗬂��A�Ґ����@�\���Ă��邩��A�̂������Ƃ�����A�o�Y���\�ł���B�ɂ݂�������̂��A�����E�o����Ƃ��A�������Q�O�|�R�O�オ�邱�Ƃ�����B�A�����J�ł͒ɂݖh�~�̂��߁A�����q�l��^���Ď�������Ƃ��������A�Ƃ������Ƃł���i�������F�u���̊Ǘ��V�X�e���Ƃ��Ă̑���ڐA�@�v�w�����w���킩��x�����V���ЂP�Q�ňȉ��j�B
�@��Â͊��҂̕a�C�̎����A���N�̉A���Ȃ��Ƃ����P��ړI�Ƃ��čs���鎖���s�ׂł��邪�A���̖ړI���ʂ����ꂸ�A���҂̕a�C�����������A�܂��͉��P���ꂸ�A�a�C������������A�ň��̏ꍇ�A���҂�������Ƃ����āA���ꂾ���Œ����A��Éߌ낪���������A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�Ȃ�炩���s�s���i����͐ϋɓI�ɁA�������Ís�ׂ��Ȃ��ꂽ�ꍇ�Ə��ɓI�ɁA�K�Ȉ�Ís�ׂ��Ȃ���Ȃ������ꍇ���܂ށj���������ꍇ�Ɉ�Éߌ날��A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
�@�Y���A�����ӔC���킸�A��Éߌ�ɂ�����ӔC�͉ߎ��ӔC�A���Ȃ킿�s���ӂł��������Ƃɑ�������S�ƂȂ邪�A��L�̂悤�ɁA���Ɉ����Ȏ�p���s���ᓙ�Ŗ��K�̌̈ӂ����ɂȂ�\���͂���B
�@��Ís�ׂɂ͓��̓I�N�P�i�葫��ؒf����BX�����Ǝ˂���B�ٕ��ł����𓊗^����j�y�ѐ��_�I�N�P�i���҂̃v���C�o�V�[�ɑ����鎩�ȁA�e���̕a�����j������̂���ł���B
�@���̐N�P�͌̈ӓI�ɂȂ����̂ɁA��҂������I�ɁA�Y���ӔC�A�����ӔC�����Ȃ��͉̂��̂��B
�@���҂̌ʓI�����I�A��̓I���Ӌy�ѐ���I���ӂɂ��A�N�P�s�ׂ̈�@�����j�p�i������邱�Ɓj����邩��ł���B
�@����I���ӁE��Ís�ׂ͈�t�̍ٗʂ��啝�ɔF�߂��Ă���B����̎�p�Ő؏����ʂ��w�肵�ē��ӂ��Ă��Ă��A�����J����p��������A�ق��̏ꏊ������זE���������Ă����悤�ȏꍇ�A���̐؏����ً}���ň�@����j�p�����邱�Ƃ��ł��邪�A���ӂ̐�������邱�Ƃ��\�ł���B���ꂪ����I���ӂł���A���C���I���ӂł���B
�@�ً}���E���҂��~�}�Ԃ��^��A�ӎ��s����Ԃ̂܂��u���邱�Ƃ�����B���҂̓��ӂ͂����Ă��Ȃ����A��ÓI�N�P���ً}���i���@�V�Q�O���Q���A�Y�@�R�V���j�ɂ���Ă��̈�@���j�p�𗝗R�t���邱�Ƃ��ł���i���̏ꍇ�A���҂ɑ��Ĕ�p�𐿋��\���H�����Ǘ��̂V�O�Q���Ő����\�ł��낤�j�B
�@��t�����҂̊�]�Ŗ�^���ĐϋɓI�Ɉ��y��������s�ׂ͎��E�֗^�߂ƂȂ�i�Y�@�Q�O�Q���j�A�܂��D�P����ɂ��Ă���ٕی�@�P�S���̎葱�A�v�����������ٍ̂͑߁i�Y�@�Q�P�S�A�Q�P�T���j�ɓ����邪�A����͈�Éߌ뎖���Ƃ͂����Ȃ��B���R����̈ӂ̌Y���ƍ߂ł���B
�@�ۈ牀�Ŏ��X��������N���̎��e�����̓ˑR���nj�Q�́A���̏��u�ɂ��Ĉ�Ë@�ւ��֗^�����ꍇ�͂��̉ߎ������ƂȂ邱�Ƃ͂����Ă��A���a�A���̔�����̑[�u�ɂ��Ă͕ۈ牀�̐ӔC�����ɂȂ�i�����Ƃ��A��Ë@�֓���SIDS���������邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�͈�Éߌ뎖���ł���Bhttp://user3.allnet.ne.jp/mahiro/index.htm�Q�Ɓj�B
�@���_�a�@�Ɏ��e���ꂽ���҂́A�@���O�ɂ����鎖�̎��ɂ��Ă͎厡��A�a�@�̎w���A�ēA�Ǘ��ӔC�����ƂȂ�A���҂��@���O�ŋN�����������ɂ��Ă͈�t�A�a�@�̊Ǘ��ӔC�����ƂȂ�B��������Éߌ뎖���̈�ł���i���_�a�@�ɂ���ޖ��ɂ��Ă͑O�c�ׁE�Q�叕�����̍Ŕ������W�N�X���R�������P�T�X�S�E�R�Q�ɂ��Ẳ���E�N��㎖�@�w�P�R���E�P�R�T�ŁA�ҐL�s�u���_��Q�҂ɂ��E�����̋y�ю��E�Ƒ��Q�����ӔC�P�|�T�v�����P�T�S�X���A�P�T�T�Q���A�P�T�T�T���A�P�T�T�W���A�P�T�U�P���A�蓈�L�u����]�߁v����]�_�R�X�W���Q�T�Ŋe�Q�Ɓj
�@�����Ԏ��̂�z�肷��ƁA�^�N�V�[�ɏ���Ă�����A�^�]��̕s���ӂŎ��̂ɑ����A����������B�^�N�V�[�ɏ�Ԃ���Ƃ��A��q�͎��Ɨp�^�N�V�[�̏ꍇ�͉^�]��ƁA�^�N�V�[��Ђ̉^�]��̏ꍇ�̓^�N�V�[��ЂƉ^���_�������ł���i�傰���ɁA�^���_����������A�Ƃ����悤�Ȗ����̈ӎv�\���͂Ȃ����A�Öق̈ӎv�\���A���Ȃ킿�َ��̈ӎv�\���Ƃ��ĉ^���_��������Ă���̂ł���B�d�ԁA�D�ԁA�o�X�ɏ��Ƃ��ɂ������ł���A���̂ق��̓���̔����_�������ł���B�傰���Ɍ_��s�ׂ������҂ɔF�������̂͌_���쐬�����s���Y�����_��̂Ƃ����炢�ł���j�B�]���ĉ����������q�͉^���_��̍��s���s�i��q�����S�ɉ^������Ƃ������̕s���s�B���@�S�P�T���j�𗝗R�ɑ��Q�������������邱�Ƃ��ł���B
�@���f����������Ă�����A�i�s���Ă����O���s���ӂ̎����Ԃɂ͂˂��A����������ꍇ�́A��Q�҂Ǝ����ԉ^�]��Ƃ̊Ԃɂ͌_��W�͂Ȃ�����A�s�@�s�ׂ��咣���đ��Q�����̐��������邱�ƂɂȂ�i���@�V
�O�X���B��Q�҂͂��̂ق��A��Q�ҕی�̂��߂ɏd�v�ȑ��_�ɂ��Ă̗��ؐӔC�̕��S�����Q�ґ��ɕ��킹��A�����@�R���Ƃ������ʖ@�������ɂ��邱�Ƃ��ł���j�B
�@���̂悤�ɁA��Q�҂́A���Q�҂ƌ_��W�ɂ���ꍇ�͍��s���s�A�_��W�ɂȂ��ꍇ�͕s�@�s�ׂ������ɑ��Q�����̐��������邱�Ƃ��ł���̂ł��邪�A���̗��������͔r�˂��������̂ł͂Ȃ�����A�_��W�ɂ���ꍇ�ł��A�s�@�s�ׂ������ɂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă���i�������̋����j�A��Q�҂͎����̑I���łǂ��炩��I�Ԃ��ƁA�������͗������A�܂��َ͈��I�Ɏ咣���邱�Ƃ��ł���B
�@�s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����������̏��Ŏ����͂R�N�A���s���s�̂���͂P�O�N�ł��邩��A�R�N�o�߂�����̔��������͍��s���s���g�����ƂɂȂ�B���Q�҂̉ߎ��A�s���ӂ̑��ݗ��ɂ��ẮA���s���s�\���̕�����Q�ґ��ɗL���ƂȂ��Ă��邪�A�i�ׂ̎��ۂɂ����ẮA������̎咣���ؐӔC�̕��z�ő傫�ȍ��͂Ȃ��B�����A�ǂ̐��������咣���邩�͖��炩�ɂ���K�v������A�i��ɂ����鐿���̌����̏������͑����A����Ă���i��Éߌ�i�ׂ̎��Ԃɂ����ẮA�����͕s�@�s�\���������A����ɍ��s���s�\���ɌX�����߂Ă���悤�ł���j�B
�@��Éߌ�̏ꍇ����{�I�ɂ͌�ʎ��̂̏ꍇ�Ɠ����ł���B��������ʎ��̂ƈႢ�A��Î��̂ɂ��ẮA�����@�̂悤�Ȕ�Q�ҋ~�ς̂��߂̓��ʖ@�͂Ȃ�����A���ґ��̗��ؕ��S�͑傫���B�܂���Î��̂͌�ʎ��̂ƈقȂ�A�_��W�ɂ���ꍇ�ɔ������邱�Ƃ�
�@
�@���̂悤�Ɍ�ʎ��̂̏ꍇ�ƈႢ�A���҂ƈ�Ë@�ւƂ̊W�͎��ԓI�ɁA��_��i�K����_��i�K�ցA�ƕω�����_�ɂ�����������i���s���s�\�����s�@�s�\�����̖��ɂ��ẮA���ؖu��Éߌ�i�ׂɂ�������s���s�\���ƕs�@�s�\���v���{�v�ҁu�ٔ�������n�P�V�E��Éߌ�i�ׁv�я��@�R�ňȉ��e�Q�Ɓj�B
�@���s���s�͌_���Ŕ������邱�Ƃ��������A�`���Ȃ����đ��l�̂��߂Ɏd�������鎖���Ǘ��ɂ����Ă����s���s�͔�������B�����̋K��͂Ȃ����A���l�̎����Ǘ��҂͑P�ǂȊǗ��҂Ƃ��Ă̒��Ӌ`���������Ď������������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����i�V�Œ��ߖ��@�P�W���Q�Q�X�ŎQ�Ɓj�A����Ɉᔽ�����ꍇ�͍��s���s�ɂȂ�B�ʍs�l���A��Ă��Ēu���Ă��������҂����Â�����t�ɉߎ�������ꍇ�́A���҂͎����Ǘ��̍��s���s���咣�ł���B���@�U�X�W���͌̈ӁA�d�ߎ��Ɍ��葹�Q����������悢�A�Ƌً}�����Ǘ��ɂ�����Ǘ��҂̐ӔC���y�����Ă��邪�A��Âɂ��Ă͂��̋K��͓K�p���Ȃ��A�Ƃ����Ă���i䴁E����ҁu��Éߌ�i�ׁv�я��@�W�O�Łj�B
�i�P�j�_��̐���
�@���{���@��A���l�̓����𗘗p����_��ɂ͌ٗp�A�����A�ϔC�A���������B�ٗp�͑��l�i�J���ҁj�ɑ���ٗp��̎x�z����ϋ������̂ł���i���@�U�Q�R���ȉ��j�A�����͎d���̊�������Ȍ_��ł���i���@�U�R�Q���j�A�ϔC�͂��C�������F�ŁA��C�҂̒m���o��������̌_��ł���i�U�S�R���ȉ��j�A����͕��̕ۊǂ��ړI�ł���i���@�U�T�V���ȉ��j�A���ꂼ����F������B
�@��Ì_��̓h�C�c�ł͓���Ȍٗp�_��Ƃ݂��A�t�����X�ł͐����_��Ƃ݂��Ă��邪�A����͂��ꂼ��̖@�I����i�Ⴆ�h�C�c�̂悤�ɈϔC�ɕ�V�����������S�ɔے肳���ƁA�ϔC�Ƃ݂͂��Ȃ��Ȃ�j���Ⴄ����ł����āA���{�ł͎��Ì_��͈ϔC�i���ÂƂ��������s�ׂ̈ϑ��ł��邩��A�����ɂ͖��@�U�T�U�������ϔC�j�ł���A�Ƃ��������L�͂ł���B������Ƃ����āA�ϔC�Ɋւ���K�肪�S���K�p����邩�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�����ґo���͉����ł����R�Ɍ_������ł���A�Ƃ������@�U�T�P���P���Ƃ��A�ϔC�ҁA��C�҂̔j�Y�ňϔC���I������A�Ƃ������@�U�T�R��O�i���̓K�p�͔ے肳��˂Ȃ�Ȃ��i���̐����_�ɂ��Ă͑O�c�ق��u�㎖�@�v�L��t�Q�P�S�ňȉ��A�蓈�L�u��t�̖����ӔC�𒆐S�Ƃ��Ĉ㎖�@���j�v����A�L�c�ҁu�������@���l����v�P�O�U�ňȉ��e�Q�Ɓj�B
�@�Ȃ��ϔC�ɂ����Ă͖����̋K��͂Ȃ����A���@�P�O�S����ސ����ĕ��ϔC���������i�V�Œ��ߖ��@�P�U���Q�Q�W�Łj�B���̂��Ƃ��炵�Ă���t�͂�ނ����Ȃ��ꍇ����f��������邪�A��f��t�̑I�C���ɂ��Ă͖{���̈�t���ӔC�����ƂɂȂ�B
�@��Ì_��͖��@���K�肷�鏀�ϔC�_�̂��̂ł͂Ȃ����A����ɍł��߂��_��ł���Ƃ��āA�g����͈͂ňϔC�̋K�肪�K�p�A�������͗ސ��K�p�����̂ł���B
�i�Q�j��������
�A�@���Â��鑤�͊��҂�����z�肷��悢�B��Âɂ����Ă͉Ƒ����d�v�ȑ��݂ƂȂ邪�A�Ƒ��͈�Ó����҂ł͂Ȃ��A���ӓ����҂Ƃł������ׂ����݂ł��낤�B
�C�@���Â��s�����Ƃ��Ă͌l�J�ƈ�̏ꍇ�͊J�ƈ�t�������҂ł���B�����J�ƈオ�����o�c�ł���ꍇ�A���̊��҂̎��ÂɑS���W���Ȃ���t�͎��Ó����҂ł͂Ȃ����A�ꕔ�ł����ÂɊW���Ă���ꍇ�͂��̈�t�����Ó����҂ł��낤�B�J�ƈ�t���ٗp���Ă����t�A
�Ō�t���̏]�ƈ��͊J�ƈ�t�̍������s�⏕���ł���A���s�⏕�҂ɉߎ�������ꍇ�A���̉ߎ��͂��̎��̂ɂ��A�ٗp��̉ߎ��Ɠ��������B
�E�@���Â��s���҂���Ö@�l�Ƃ��A�����a�@�Ƃ��A������w�t���a�@�Ƃ��A����t���a�@�Ƃ��A�n�������c�̂̕a�@�A���{�ԏ\���a�@�̂悤�ɖ@�l�ł���ꍇ�͖@�l�����Ó����҂ƂȂ�A�@�l�Ɍٗp����A���Âɏ]�������t��
�Ō�t���̐E���Ɠ������A���s�⏕�҂Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���s�⏕���ɂ͎g�p�҂̖��߁A�ēɏ]���A���̎葫�ƂȂ��ē����ҁi�H��J���ҁA�^�]�蓙�E���`�����s�⏕���j�̂ق��A�@�l�͎��ÂƂ��������s�ׂ͎����ł͂ł��Ȃ�����A����ɑ����Ď��Â��s���A��C�҂Ɠ����x���̊w���o����L����ҁi���s��p���j������A�܂��g�p�҂ɑ����ĕ����L������L�⏕��������i�ȏ�̓_�ɂ����ߖ��@�P�O���S�P�W�ňȉ��Q�ƁB��t�͗��s�⏕�҂ł͂Ȃ��A�㗝�l�ł���A�Ƃ�����������B�O�c�ق��u�㎖�@�v�L��t�Q�P�R�Łj�B
�i�R�j�_��̎���
�@��L�̂悤�Ɉ�Éߌ�i�ׂɂ����Ă͍��s���s�A�s�@�s�ׂ������I�Ɏ咣�ł��邤���A���Ƃ��ƁA�w�ǂ̌_��ɂ��Đl�͒����ӎ��Ȃǂ͎����Ȃ�����A��ÂɊւ��Ă����҃T�C�h�́A�_��̒����ɂ��ĊS�������Ȃ��̂����ʂł���B�����牽���A���Ì_�������������A�Ƃ����_�ɂ��Ă̔F���͖w�ǂȂ��B���������Âɂ��Ĕ�p�A��V�𐿋����Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ñ��͊��҃T�C�h���͌_��ɂ��Ă̊S�x�������B�ƌ����Ă����Ñ��ɉ����`��������A�܂������F�ی��̍��ł�����{�ł́A�����������ҕ��S���̎x���\�͂����Ñ��̊S���ł���A���ʂɕ��S���̑傫����p���̏��u�A���@���̏�ʂɂ����āA�͂��߂Č_��A�ꍇ�ɂ���Ă͎x�����ۏؓ�����莋����邱�ƂɂȂ�B
�@�]���ĉ����A���Ì_��������邩�A�Ƃ������͕��ʂ͂��قǂ̏d�厖�ł͂Ȃ��B�~�}���@�̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�����Ǘ���Ԃ��������A���҃T�C�h�Ŏ��Ìp���̊�]���q�ׂ��鎞�_���_�_�Ƃ݂���ł��낤�B�ʏ�̎��ÊJ�n�̏ꍇ�́A���f���ɐf�@�̐\�����݂��Ȃ���A���N�ی��̒��Ȃ���A�f�Ð\�����݂���t����ꂽ���_���_��������_�ƂȂ낤
�i��Ì_��������P�R�N�S���P���ȍ~�����̂��͕̂����P�Q�N�@���U�P���̏���Ҍ_��@�̓K�p�����邪�A���̓K�p�Ɋւ��Ă��A�ʏ�̏ꍇ�͐f�Î�t�I�����_�Ɉ�Ì_��͐�������A�Ƃ����Ă���B�o�ϊ�撡���������Ǐ���ҍs�����ەҁw�����������Ҍ_��@�x�����@��������P�U�A�P�W�Łj�B
�@�ی��̏������Ȃ��A����NJ����ꂽ�ꍇ�ł��A�f�@���Ȃ��ꂽ�ȏ�A���f�����_��������_�ł��낤�i���Ì_��������P�R�N�S���P���{�s������Ҍ_��@�̓K�p���邪�A��Ís�ׂ̓�����A��Ñ�����Â����U���邱�Ƃ͏��Ȃ��A�܂���t�����Ì_�����Ƃ݂���ȏ�A���Ì_��ɓ��@�S���̌_�������Ƃ�����肪�N����\���͋ɂ߂ď��Ȃ��ł��낤�B�o�ϊ�撡���������Ǐ���ҍs�����ەҁu�����������Ҍ_��@�v�P�U�A�P�W�ŎQ�Ɓj�B
�i�S�j�_����
�A�@��Ì_��̌����I�����҂͈�Â���ҁA���Ȃ킿�����ƈ�Â��s���ҁA���Ȃ킿��t�ł���̂��A�����I�p�^�[���ł���i���c�M�u���@�U���e�_�v�Q�W�O�ŎQ�Ɓj�B
�@��Ҍ_�̖@���s�ׂ̒��j���Ȃ��̂��ӎv�\���ł���A��Ì_����@���s�ׂ̈�ł��邩��A���̒��S�͈ӎv�\���ł���B�ӎv�\���ɂ������ӎv�\�����\���ł���Ζ��͂Ȃ����A���ꂪ�s�\���ł���Ζ{�l���s�ה\���̐�������ق��A�@��㗝�l�ɂ��T�|�[�g���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��A�ӎv�\���ɖ��͂Ȃ��Ă��A�����͈͂��L���邽�߂��C�ӑ㗝�l�𗘗p���邱�Ƃ�����B�܂������҂��@�l�ł���ꍇ�A�@�l�͎���s�ׂ͂ł��Ȃ�����A�@�ւɂ����\�Ƃ�����肪�N����B
�C�@���̏��Ȃ���Ñ�����l���悤�B
�@�l�J�ƈオ���Ì_����������ꍇ�A�ʏ�͂��̈�t�{�l���_���҂ɂȂ邾�낤�B��t���g���A���̈ӂ���������������t�̔C�ӑ㗝�l�܂��͈ӎv�\���⏕�҂Ƃ��Č_������ɓ����邱�ƂɂȂ�B���̈�t���J�݂����@�A�a�@����Ö@�l�g�D���Ƃ��Ă���ꍇ�́A�@�l�̑�\�҂��_���҂ɂȂ�˂Ȃ�Ȃ��B��\�Ҏ��g���A���̈ӂ��������������C�ӑ㗝�l�܂��͈ӎv�\���⏕�҂ƂȂ��Č_������ɓ����邱�ƂɂȂ�B��Ì_��͉c�ƓI���s�ׂł��邩��i���@�T�O�Q���V���B��������u���s�ז@�v�L��t�@���w�S�W�W�P�Łj�A������t��ɂ�鋤���o�c�̕a�@�ɂ����Ă͍��s���s���ɂ��S�����A�ѐӔC���i���@�T�P�P���P���j�B�܂����@��ł͏��l�Ɩڂ���邪�i���@�S���P���j�A��Ƃ̓�����A�����炳�܂ȉc���ړI�͔r�˂���i��Ö@�V��
�T���j�A��`�L���ɂ��Ă̋K������i��Ö@�U�X���j�B��ƁA��Ís�ׂ͑��p�I�Ȗ@�I�]���A�K�����Ă���̂ł���B
�@������w�t���a�@�A�����a�@�͂��̕a�@���J�݁A�^�c����͍̂��ł��邩��A�����_���҂ɂȂ�B���ۂ̈ӎv�\���͕a�@�W�̈ӎv�\����S������ƒ�߂�ꂽ�a�@��\�@�ցi�a�@�����j����\�҂Ƃ��Č_���������邩�A��\�҂���C�ӑ㗝����^����ꂽ�ҁA�������͈ӎv�\���⏕�҂��_����������B�n�������c�̕a�@�A�ԏ\���a�@�ɂ��Ă��������Ƃ�������B
�E�@���ґ�
a�@�Ⴆ�~�}�������ꂽ���҂��ӎv�\���\�͏�A��Q������Ă��邢��悤�ȏꍇ�A���Ì_��͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B�t�Y���̎҂Ɋ��҂�@��㗝�܂��͔C�ӑ㗝���錠��������A���̑㗝�l�Ƃ̊ԂɎ��Ì_����������Ƃ������Ƃ͂��肤�邵�A���ɕt�Y���̎҂ɂ��̂悤�Ȍ������Ȃ��Ĉӎv�\�������ꍇ�́A���҂��ӎv�\�͂������i�K�ň�Ì_���ǔF���邱�Ƃɂ��k���Č_��͗L���ƂȂ�i���@�P�P�U���j�B�����m�������҂����Â̌p������]����悤�ȏꍇ���ǔF�����肳���B�~�}�������ꂽ���҂ɕt�Y���̎҂����Ȃ��ꍇ�ɂ͎��Â������Ǘ��Ƃ��ď�������邾�낤�B���̏ꍇ�A���Ñ��͔�p�Ƃ��Ď��Ô�̐������ł���i���@�V�O�Q���P���j�B���Ƃ��ƁA���̂悤�Ȋ��҂ɏ��f�����玡�Ì_����l���邱�Ǝ��̂����������B�ӎv�\�͂����Ă���A������莡�Ì_����������Α����̂ł���B
b
���҂������N���̏ꍇ�E�����N�̈ӎv�\�͍͂��Y�I�s�ׂ̏ꍇ�͏A�w�N���A�g���s�ׂɂ��Ă͂P�T����i���@�V�X�V���j�ƂȂ�B�����Ƃ��Ď��Ô�x�����邩���L���o���_���ł��鎡�Ì_��͍��Y�s�ׂ̈��ł���B�]���ĂV�ΑO��̖����N�͈ӎv�\�͂�������A���炪���Ì_�������ł���B�������@��㗝�l�̓��ӂ����Ă��Ȃ��_��͌�Ŏ������邩��i���@�S���Q���j�A��Ñ��͖����N�҂̖@��㗝�l�̓��ӂӏ��Ƃ��A�g���ۏ؏��Ƃ��Œ����Ă����悢�B�������҂������N�𗝗R�Ɏ��Ì_������������ꍇ�ł��s�������@���őÓ��Ȏ��Ô�̏��҂͋��߂邱�Ƃ��ł���B�������������Ƃ��Ĉ�Ñ����V�̎q�ƌ_������Ԃ��Ƃ͂Ȃ��낤�B
�@�����N�҂͈ӎv�\�͂����A�����Ȃ����킸�A�s�ז��\�͎��ł��邩��A���̖@��㗝�l�i�e���҂܂��͖����N�㌩�l�j�������N�҂�㗝���Ď��Ñ��Ǝ��Ì_���������邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�A�ӎv�\���҂͖@��㗝�l�ł��邪�A�_���҂͖����N�ł��銳�҂ł���B
�@���̂ق��A�����N�҂̐e���ҁA�����N�㌩�l�͖����N���Č삷�錠���`�������邩��i���@�W�Q�O���A�W�T�V���j�A�@��㗝�l�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�_���҂Ƃ��Ď��Ì_�������ł���A�Ƃ����l��������i�O�c�ق��u�㎖�@�v�Q�O�X�Łj�B���l����a���������l���L���ɂ��ĕۊǎ҂��C�U�_������邱�Ƃ͉\�ł���B����Ɠ����悤�ɁA���ÑΏۂ�a�C�ɂȂ��������N�҂Ƃ��āA�Č�҂ł���e���ҁA�����N�㌩�l���g�����Ñ��Ǝ��Ì_���������邱�Ƃ��\�ł��낤�B���҂��c���܂��͏A�w�O�̎q�ǂ��ł���ꍇ�́A���̕��������ɍ����i�������ٕ����P�R�N�Q���U�����������P�V�S�Q���P�O�Q�ł́A�����ڐA��p�ɍۂ��A�e�����l�̎q�̎��Ì_��̓����҂ł͂Ȃ��A�Ƃ���j�B
c
���҂����_��Q���ł���ꍇ�E���_��Q�҂Ƃ́u���_�����a�A���Ő����_�a�A���_����A���_�a�����̑��̐��_������L����ҁv�ł���i���_�ی��y�ѐ��_��Q�ҕ����Ɋւ���@���T���j�B���̐��_�����ی��@�͌㌩�l�A�z��ғ��̐e���Ƃ��s�����������[�Ă����ی�����x���K�肵�A���̕ی�҂͊��҂̊ēA��t�ւ̋��͓��̐Ӗ����Ă���ق��A���@�͐��_��Q�҂̐��_�a�@�A�C�ӁA�[�u���@�ɂ��ē��ʂ̋K���u���Ă��邩��A���҂̐��_��Q�ɂ��Ă̎��Âɂ͐悸���@���Q�Ƃ����ׂ��ł���i�����c���u���_��Âɂ����鎩�Ȍ���Ƒ�s����v�N��㎖�@�w�P�T���V�O�ňȉ��A���v�T�I�u���_��Âɂ����鐸�_�\�́v�N��㎖�@�w�P�T���W�P�ňȉ��j�B
�@��ʕa�@�ɂ����鐸�_��Q�҂̎��Ì_��ɂ��Ă͎��̂悤�ɍl����B
�@���_��Q�҂���Q�̒��x�ɉ����āA�㌩�A�ۍ��A�⏕���J�n����Ă���A���@�V���ȉ��̋K��ɏ]�����ƂɂȂ�B������ɂ��Ă���Ì_��ɂ����Ă͕��ʂ̍��Y����Ɣ�r����ƁA���Җ{�l�̈ӎv�̂���w�̑��d���}����ׂ��ł��邤���A�V�����㌩�A�ۍ��A�⏕���x�ɂ����Ă͕ی����{�l�̎��Ȍ��茠���d������Ă��邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B
�@�ł����傫�����N�㌩�i���Ƃ̋֎��Y�j���������Ă��銳�҂ł��A�ӎv�\�͂�L���鎞�_�ɂ����Ă͎��炪�L���Ȏ��Ì_���������邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ��A���N��㌩�l�͍s�ה\�͂���������A�����N�҂̏ꍇ�Ɠ������A��Ŏ��������\��������i���@�X��{���j�B���̂悤�Ȏ��Ԃ������ɂ́A�����N�҂̏ꍇ�Ɠ������A���N�㌩�l�Ǝ��Ì_����������悢�B���̏ꍇ�A���N�㌩�l�͖@��㗝�l�Ƃ��Ċ��҂��_���҂Ƃ��Č_�邱�Ƃ��ł��邪�A���҂̗×{�Ō�`�������N��㌩�l�͎��ÑΏێ҂����҂Ƃ��Ď������_���҂Ƃ��Ď��Ì_���������邱�Ƃ��ł���B
�@���҂ɂ���Q�̒��x���ꃉ���N�Ⴂ�ۍ��i���Ƃ̏��֎��Y�j���������Ă���ꍇ�ł��A��ۍ��l�ł��銳�҂͎���L���Ȏ��Ì_���������邱�Ƃ��ł���B�������L���o���_��ł��鎡�Ì_��͏d�v�Ȍ������r�s�ׂł��邩��A���@�P�Q���P���R���ɂ���Ō_������������\��������i���@�P�U���S���B���Ís�ׂ������ɊY�����邱�Ƃɂ����я��F�ق��u�V���N�㌩���x�̉���v���Z�����������W�R�ŎQ�Ɓj�B���̂悤�ȏꍇ�͕ۍ��l�̓��ӏ����Ă����悢�B�ۍ��l�����ӂ��Ȃ��ꍇ�͐R���œ��ӂɑウ��Ƃ������Ƃ��\�ł���i���@�P�Q���R���j�B�܂�����s�ׂɂ��ۍ��l�ɖ@��㗝����^����R���i���@�W�V�U���̂S�j�𗘗p���邱�Ƃ��ł���B
�@�ł���Q���x���Ⴂ�⏕���������Ă���ꍇ�A��⏕�l�ł��銳�҂͎��玡�Ì_�������ł���B�������R���ł��̂悤�ȍs�ׂɂ��⏕�l�̓��ӂ��K�v�Ƃ���Ă���ꍇ�i���@�P�U���P���j�A���ӂ��Ȃ���Ύ��������\��������i���@�P�U���S���j�B���̂悤�ȏꍇ�̑Ή��ɂ��Ă͕ۍ��̏ꍇ���Q�l�ɂȂ�B�Ȃ��⏕�l�ɖ@��㗝����^����A�Ƃ������x������i���@�W�V�U���̂X�j�B
�@�������_��Q�҂ɂ��ĉ���̐��N�㌩���x���������Ă��Ȃ��ꍇ�A�ނ������������Ì_��͓��l�̈ӎv�\�͂̑��ۂɂ��̌��͂����E�����B�ӎv�\�͂����������ꍇ�͖����ł���A�ǔF���ł��Ȃ��i���@�P�P�X���j�B
d�@��t�������a�A���Õ��j���ɂ������m�A����������ꍇ�̑Ώێ҂͒N���H
�@�Ή����Ĉ�t���玡�Â���Ƃ����_��͖��@��ł����ϔC�Ɉ�ԋ߂��_��ł��邩��A�ϔC�҂ł��銳�҂͎�C�҂ł����t����ϔC���������i�a�C�̎��Áj�Ɋւ�����̒��邱�Ƃ��ł��锤�ł���i���@�U�T�U���A�U�S�T���j�B
�@�������]������A���҂ƈ�t�Ԃɂ͂��̂悤�Ȍ_��W�ɂ��Ă̖��m�ȔF�����Ȃ��A���f�̑Ή����u���ԑ�v�Ƃ������̂ŌĂ�Ă������オ���������Ă����B
�@���Ăł�����͓����ŁA��t�͗l�q���݂Ċ��҂ɐ�������悭�A�ꍇ�ɂ���Ă͉R�����Ă��悢�A�Ƃ����ė������A����ɂ�����i�`�X�̔������I�Ȉ�w�����i�l�̎����j�ɑ���ᔻ����A�P�X�S�T�N����P�X�S�U�N�ɂ����čs��ꂽ�j���[�����x���N�ٔ��ɂ����Ĕ팱�҂̌��茠���d������j���[�����x���N�j�̂����\����A���̉e������P�X�U�S�N�A���E��t��팱�҂̗��v�A�����̗D������������w���V���L�錾�\���A�P�X�V�R�N�A�A�����J�a�@������\�����u���҂̌����͓T�v�̂Ȃ��ɂ͂��߂āA���҂͏��u�A���ÊJ�n�O�ɁA�m�炳�ꂽ��̓��Ӂiinformed
consent�EIC�j��^����̂ɕK�v�ȏ������錠��������A�Ƃ������t���o�ꂵ���i���씣�u�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�v�����V���P�V�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@���{�ł������F�ی��A��×��p�p�x�̌���A��Î��̕A�i�ׂ̑��哙���_�@�Ƃ��āA��ÊW���_��W�Ɗ����A���݂̌����`�����m�F����X���������Ȃ������A���̒��S���Ȃ��̂���t�̐����A���m�`���̖��ł���B
�@�����ł͈�t�������A���m������ꍇ�̑�����ɂ��čl���Ă݂�B
�@�P�ɕa��̐����A����Ȏ��a�̕a�������m���邱�Ƃɂ��Ă͑���������Җ{�l�ł���A���̎��͂̉Ƒ��A�Č�ӔC�҂ł���A�]����͂Ȃ��B���ʁA��t�͊��Җ{�l�ɂ��A�����킹��Ƒ��ɂ������A���m���邾�낤���A�Ƒ��I�x�����K�v�ȏꍇ�͉Ƒ��ɑ�������ɗ͓_��������邱�ƂɂȂ�i��t�@�Q�R���́A�×{�̕��@���ɂ��Ċ��ҁA�ی�҂ɕK�v�Ȏw�������邱�Ƃ��߂Ă���j�B
�@��t�̐����A���m�����҂ɑ��鉽�炩�̐N�P���ꍇ�́A���҂̎��Ȍ��茠���d�̗��ꂩ��A���҂��ɒ[�ɔN���ł���ꍇ�������ẮA���Җ{�l�ɑ�������A���m���K�v�ƂȂ�B
�@���ɁA�a���̍��m�������҂ɉ��炩�̍D�܂����Ȃ��e��������悤�ȏꍇ�́A���҂ւ̍��m�͂ނ���֊��Ƃ���A�Ƒ��ւ̍��m���P���Ƃ���邱�Ƃ�����B�P�X�X�T�N�S���Q�T���ō��ّ�O���@�씻�������P�T�R�O���T�R�ł́A�_�̂�����P�[�X�ň�t���_�ΏǂƐ������Ė{���̕a�������Җ{�l�Ƃ��̉Ƒ��ɍ��m���Ȃ������͍̂��s���s�ɂ͓�����Ȃ��A�Ɣ������Ă���B
�@��ʓI�ɂ́A�@���Ƃ͂��̍��m�`����S�ʓI�ɓ��R������̂ɑ��A��t�A���ɂ���Տ���t�͔ے�I���A�����I���m�_�҂������B
�@�Տ���ł���Ð�r���i�c���`�m��w��w���O�ȁj�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@��������ɑ���R����܂̌��ʂ͒Ⴂ�B�P�Ɠ��^�̏ꍇ�̑t�����͂Q�O���ɗ��܂�B���p�Ö@�ł͑t�����T�O������ƕ���Ă��邪�A���ϐ������͂U��������P�N�B�R����܂̕���p�͕K�����d�lj����邩��A�������@���K�v�ɂȂ�A�Ō�̎Љ�I�������]���ɂȂ�B���҂̑����́u����v�Ƃ����a�������m����A�R����܂̑t�����̒Ⴓ�͗����ł��Ă��A���Ȃ�̐������҂������Ă���B���҂ɑ���A���P�[�g�����ɂ��ƁA���m�̊�]���e�Ƃ��Ă͉ߔ������a��A���Ö@�܂łƂ��A�\���܂łƂ���̂͏����ł������A�Ƃ����A�܂��͂V�O���͊����m�͎��錩���݂̂���Ƃ��Ɋ�]����A�Ƃ��������邩��A��ΓI�\��s�ǂ̂��m�͊��҂͊�]���Ă��Ȃ��Ƃ�����B���錩���݂��Ȃ��ꍇ�ł��ϋɓI�ɍR���Â���]���銳�҂��R�U�������A�Ƃ��������邩��A�s�\���ȏ����킪��ɑ��鉻�w�Ö@���T���Ċ��҂̈ӎv����͂͂��ꂽ���̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��i�u����������w�Ö@�̗Տ������̖��_�v�N��㎖�@�w�P�R���P�V�ňȉ��j�B���̈�t�͍��m�ے�܂��͕����I���m�_�҂ł��낤�B
�Ƃ��낪�A�����Տ���ł���n�Ӌ��i��������Z���^�[�����a�@���ȁj�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�R����܂̓����Ƃ��Ă͌��ʂ������g�p�ʂŁA�����ɕ���p�������A�Ƃ������Ƃł���B�����܂͈��l�̂W�O�|�X�O���Ɍ��ʂ�����邪�A����p�i�̏�Q���j�͂��������T���ʁB�R����܂ł͂R�O���ʂ̐l�ɏd�Ăȕ���p�������i���Ô䂪�������j�B�킪���ł́A���܂ł����m�̐����_���镗�������邪�A�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�Ɋ�Â����Â��s���ɂ́A���m�͕s���ł���A���͂₪�m�̐����_���鎞��͏I������A�Ƃ����ׂ��ł���i�u�킪���̗Տ������̌���v�N��㎖�@�w�P�R���Q�U�Łj�B
�@���̈�t�͑S�ʍ��m�_�҂ł���B
�@������l�A�Տ���ł���_�O�i�i�a�@�Ζ����Ȉ�j�́A������ᇁi����j���܂߂āA�����I�ɂ͊��҂ɂ��ׂč��m���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���m���Ă����Ȃ��ƁA�������{���̎��Â��ł��Ȃ�����ł���B���������Җ{�l�ɒs�����F�߂��鎞��Ƒ����{�l�ւ̍��m��]�܂Ȃ����͍��m���Ă��Ȃ��i�u���Ҋw�v�}�K�W���n�E�X�P�O�Q�Łj�B
�@���̌l�I�ɒm���Ă���Տ���ɂ͌Ð�A�_�O��t�^�C�v�������B�\�߈�t�Ƃ̊ԂɐM���W���\�z����Ă���A���Җ{�l�ւ̐����A���m�͖��Ȃ��s����͂��ł���B���Җ{�l�Ɉӎv�\�͏�A�d��ȑj�Q���R������ꍇ�Ɍ���A�z��ҁA�e���҂Ƃ��A���l�㌩�l�ւ̑�p�I�����A���m���s����ׂ��ł���A�{�l�ɑ�������A���m���D�悷�ׂ��ł���B��t���Ƒ��ւ̐����A���m�ɐ旧���A���Җ{�l�Ǝ��͂̉Ƒ����Ƃ̐l�ԊW�ɂ��ڂ������Ă����ׂ��ł���B�������O�̔z��҂ւ̐����A���m�̓i���Z���X�ł�����肩�A���낵�����ƂɂȂ�B�����N�҂ɑ��Ă��A�ɒ[�ȔN���̏ꍇ�͕ʂƂ��āA�{�l�ɑ�������A���m���K�v�ł���B����҂ɑ��Ă��A���̎��Ȍ���̗D�挴�����炵�Ă��A�o�������A�{�l�ɑ�������A���m���D�悷��i����Җ��ɂ��Ă͐Έ���q�q�u����҂̈�ÂƉƑ��̓��Ӂv�N��㎖�@�w�P�T���X�W�ŎQ�Ɓj�B
�@�����������A�����A���m�̑�����Ƃ��Ċ��Җ{�l�ƉƑ������I�ɂ����Ă��锻���͋^��A�Əq�ׂĂ���i�u��t�̐����Ɗ��҂̔��f�E���ӂɂ��āv����^�C���Y�V�V�R���P�T�ŁA�����N�u��Ñi�ׂ̎����I�ۑ�v�V�W�Łj�B
�@������Ƃ����āA���Җ{�l�ɑ��Ă��������A���m����Α����A�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�a�C�ɂȂ����҂͌��N�Ȏ��Ƃ͈Ⴄ�B��Ȃ菬�Ȃ�A�F�X�Ȕ\�͂��_���[�W���Ă���B�a�C���ʉ@���x�ł���Α債�����Ƃ͂Ȃ����A���@�ƂȂ�ΉƑ��ɂ��Ō�̖�肪�N����A�a�@��p�̎x�����A�ۏ̖��A�މ@���̈�������������A����A���S�̏ꍇ�͈�̈������̖�肪�N����A�����ɂ͊��Ҏ��ӂ̗L�͉Ƒ����W���Ă���B���҂̋ߐ���a�C�Ɩ����ł͂Ȃ��B���҂����@���̒����×{�A���ɍۂ��A�f�f�����ߐ�ɒ�o����̂͋ߐ�ɑ���a�C�̐����ł���B��t�͊��Ҏ��ӂ̊��҂ɑ���L���Ȑ����A���m���ӂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���i�O�ؒm���u���m�ƌ���ɂ�����Ƒ��̖����v�N��㎖�@�w�P�T���W�W�Łj�B
�@���݂̐f�Õ�V�̌n�ł́A��t�̌����ɂ������́A���ꂪ�����璷���Ԃɂ킽���Ă������ł���B�������҂ɑ�������A���m�͈�t�ɂƂ��Ď��ԁA�J�͂̂����ő傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă��邪�A��V�͂Ƃ�Ȃ��B�×{�w�������ʂōs����ꍇ�i�Ⴆ�Γ��@���̗×{�w���v�揑�̌�t�j���͂����ėL���ł��������A�����P�Q�N�S���̉����Ŗ����ƂȂ����悤�ł���B��t�̐����s���ɑ��銳�҂̕s���͑傫�����A��t�̐����J�͂ɕ�V�̎蓖���Ȃ����Ƃɂ����ӂ��ׂł�����B
�i�T�j��Ì_��
�@��Ì_��ɍۂ��A�_������邱�Ƃ͂Ȃ��B�_���҂̗��ꂪ�D�z����ꍇ�͉��X�ɂ��Ă����ł���B�������ŋ߁A���ґ��̌�����i�삷��_���ň�Ì_�쐬���Ă��錤�������\����Ă���B���É��ٌ�m��Q�O�O�Q�N�R���u��Ì_�Ɋւ��錤�����v������ł���B����ő��t���ĖႦ��悤�ł���i����̓d�b�ԍ�052-203-1651�j�B
�@�ߎ��͕��ϓI���Ӕ\�͂���ɔ��肷��̂��A��̓I�s�҂̒��Ӕ\�͂���ɔ��肷��̂��A�Ƃ�����肪����B�O�҂����ۓI�ߎ����A��҂���̓I�ߎ����Ƃ����B
�@���̂悤�Ȗ��ɂ��Ă̍ٔ����̔��f�͌Y���ٔ��ɂ����錋�_��`�Ɠ����悤�ɁA���̎����ɂ����ĉߎ����m�肷������悢�̂��A�ے肷��̂��悢�̂��A�Ƃ������_���ɏo���Ă����āA��ł��̗��R�t�����l���āA���A�Ƃ����X�������邩��A���ۓI�ߎ��A��̓I�ߎ��Ƃ����Ă��A�����̂��������A�Ƃ����������ۂ߂Ȃ��B
�@���������݂͒��ۓI�ߎ������ʐ��Ƃ����Ă���i���ߖ��@�P�X���Q�R�Łj�B���̂Ȃ��̓I�s�҂̒��Ӕ\�͂���ɂ���ƁA���f����s���ӂȐl�Ԃ��ӔC��A���Ӑ[���l�Ԃ��ӔC���Ղ��A����͌����ł͂Ȃ��A�܂��s���ł���Ƃ���������l�ɗ^���邩��ł���B
�@��t�͐l�̌��N�A�����ɑ傫���֗^����E�Ƃł���A���Ì_��̍ŏI�ڕW�͌��N�ł��邩��A��t�ɑ���`�����s�ɑ�����҂͍q��@�A�d�ԓ��̍�����ʋ@�ւ̃h���C�o�[�ɑ��邻��ɕC�G����B
�@�����Ĕ~�Ŋ��҂������������t��w�l���҂ɗA�����Ĕ~�łɜ늳�������L���ȓ���~�Ŏ����łP�X�U�P�N�i���a�R�U�N�j�Q���P�U���ō��ّ�ꏬ�@�씻�������Q�T�P���V�ł́u�l�̐����y�ь��N���Ǘ�����Ɩ��ɏ]������҂́A���̋Ɩ��̐����ɏƂ炵�A�댯�h�~�̂��ߕK�v�Ƃ�����őP�̒��Ӌ`����s�������Ƃ�v�������v�Ɣ������Ă���B
�@���̂悤�Ɉ�t�̒��Ӌ`���ɂ͌������ڂ��������邪�A��������߂�_���̈�����L�̈�Ð����ł���A��������߂�_������Ð������s�_���ł���B
�@��w�̐i���͓��i�����ł���A����͍ŐV�̎��Ö@�A��ł��������̂��A�����͐V�������Ö@�A��ɂƂ��đ����A�Â����̂ɂȂ�A�Ƃ����L�l�ł���B���قǁA�����ߋ��ł͂Ȃ������i�Ⴆ�P�X�X�O�N�j�ɕs���Ƃ��ꂽ�a�C�iA�a�j�����i�Q�O�O�O�N�j�͗l�X�Ȏ��Ö@���J������A�������͂X�O���ɂ��B�����A�Ƃ������Ƃ͂܂܂��邱�Ƃł���B���A�s���Ƃ���邢�����̎��a���A�����͈�`�q���Ó��Ŏ�������\��������B
��t�Ɉ�Éߌ�ӔC��Njy����̂ɍ��s���s�A�s�@�s�ׂ̂�������g���Ă��A���_�̒��S�ƂȂ�͈̂�t���s����A���Ȃ킿�f�f�A�����p���̊e���u�ɂ��Ă̈�t�̒��Ӌ`���ᔽ�A�ߎ��ɂ��Ă̔���Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̏�ʂɓo�ꂷ��̂���Ð��������ł���B
�@�������W������L������Éߌ딻��̂Ȃ��ň�Ð������ߎ�����Ɏg�����̂͑S�W�O�O�����S�R���i�T�E�R���j����A���̂����R�����ߎ��m�莖���A�S�O�������̏��u�͈�Ð������ނ����Ȃ������A�Ƃ����_���ʼnߎ���ے肷����̂ł���B
�@���́u��Ð����v�ɂ��Ă̔��f�͂��ꂪ��w�����A��w����̏�ʂł͈�w��̔��f�A���Ȃ킿��w���f�ł��邪�A��t�̉ߎ��A���s���s���̖@�I���f�ɏ�ʂł́A�ߎ����f�Ɠ������A�@�I���f�̈�ł���B���̖@�I���f�͒N�ł����\�ł��邪�A�i�ׂɂ����Ă͍ٔ����i�ٔ����j���ŏI���f�҂ƂȂ�B
�@��Î��̂Ƃ͕ʂɁA��X����t�ɂ�����Ƃ��A��Ɂu�ǂ���t�E����v�ɂ����肽���A�Ǝv���B�ʂ����āu�ǂ���t�E����v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȉ�t���w�����B
�@�_�O�i��t�́u���Ҋw�v�ɂ��ƁA�u����v�̏����͂Q�Q�����邪�A���̈�Ԗڂ̏����́u�L�x�Ȓm�������邱�Ɓv�ł���i�����P�V�ŁB�Ȃ�����h���t�́u�J���e�ƃ��Z�v�g���킩��{�v�ɂ��A�����̂����ɐf�Â����藧�������������ł͂Ȃ��A�e�Ȉ�t�A���Ȃ킿�Lj������߂��鎞��ł���A�Ƃ������Ƃł���B�����P�R�S�ňȉ��j�B
�@��X�����߂��t�͊i�i�ɖL�x�Ȉ�w�I�m������������t�ł͂Ȃ��A���ϓI�A���Ȃ킿����̈�w�����Ɍ������m������������t�ł���B�����đ�s��́A�����ȑ�w�t���a�@�Ƃ��A��a�@�̈�t�́A��قǐV�Ă̈�t�͕ʂƂ��āA����N���A��t�𑱂��Ă����t�͂��̐��������Ă��邾�낤�A�Ǝv���āA��s�s�܂Őf�Âɒʂ��A�n���̕a�@�̈�t�ɂ͔��R����s�����������Ă��܂��B
�@���쎟�Y��t�́u��f�v�ɂ��ƁA��x�A��t�Ƌ����Ƃ�ƏI�g��t���i�����Ă���{�ƈقȂ�A�A�����J�ł͂R�N�����ɖƋ��̍X�V���s���邩��A��t�͊w������ȏ�Ɍ��s��ς܂˂Ȃ炸�A�ƒn�̈�t�ɑ��Ă���s��Ɠ����J���L�������ł̌��C���s���Ă���A�n�捷�͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���i�����X�W�ňȉ��j�B
�@���ɂP�X�X�T�N�A����n���̊��҂�����a�C�ň����t�ɂ�����A���Âɂ��Ĉ��������ʂ��������Ƃ��悤�B���̈�t�ɉߎ��̐ӔC�����邩�ǂ����̔��������ꍇ�A���ɂȂ�̂́A���̊��҂̕a�C�̐f�f�A���Â̓�Ր��ł��邪�A���̔��f�͌��݂̂Q�O�O�O�N����ɂ��Ă͂����Ȃ��B�P�X�X�T�N����ɂȂ�B�P�X�X�T�N�̈�Ð������炵�Đf�f�A���Â��e�Ղł���ꍇ�͉ߎ��m��ɌX���B���ɁA��Ð�����A���̕a�C�̐f�f�A���Â�����ꍇ�͉ߎ��ے�ɌX���B�����A�P�X�X�T�N���݁A��Ð����ɒn�捷������ꍇ�͂ǂ����B��s�s�̑�a�@�ɂ����Ă͐f�f�A���Ö@���m������Ă������A�n���ł͂����ł͂Ȃ������ꍇ�͂ǂ����B��Ð������͈̂�Ë@�ւ̐����A�n�搫�ɂ���Ă�������邩��A�ꗥ���f�͋�����Ȃ��B�]���Ĉ�Ë@�ւ̐����A�n�搫���炵�Ĉ��鏈�u���ł��Ȃ��ꍇ�͂��̕s����͔̂���Ȃ����A���̂悤�ȏꍇ�ł���t�ɂ͈�Ð����c���A���s�̋`�������邩��A���s���Ēm�������l�����Ă���A��s�s�A��a�@�ւ̓]��w�����\�ł���B�����犳�҂ɑ��A�ق��̈�Ë@�ւɂ�鎡�Ẩ\��������A�w������`���i�]��w���`���j������A�����ӂ�Ήߎ������邱�ƂɂȂ�i�������A���҂��]������ۂ���Έ�t�ɐӔC�͂Ȃ��j�B
�@��Ð����������Ύg��ꂽ�����͖��n���Ԗ��ǂł���B���n����ۈ��Ɏ��e���Ď_�f����������Ɩڂ̖Ԗ��Ɍ��ǂ��ُ푝�B���Ď����Ɏ���A�Ƃ����a�C�ł��邪�A���Ö@�Ƃ��ẮA���ÌŖ@������A�Ƃ��ꂽ�B���n���Ԗ��ǂ͎��R����������������A���ÌŖ@�Ŏ������������R�����������͔��R�Ƃ��Ȃ��A�Ƃ����l�����������B�܂���Ð�����A���̎��Ö@���m�������̂͂������A�Ƃ�����肪�������B���̎��Ö@�m�����_�̔c���@�������i�s�i�̌��_�����E�����B
�P�X�W�Q�N�i���a�T�V�N�j�R���R�O���ō��ّ�O���@�씻�������P�O�R�X���U�U�Łi����A�����j
�u�����Ɣ����v���a�S�S�N�P�Q���Q�Q���ɑ̏d�P�P�Q�O�O�����Ő��܂ꂽ�q���ۈ��Ɏ��e����A���N�P���Q�W���܂Ŏ_�f�̋������A�Q���S���Ɋ�ꌟ�����A�����P�Q������X�e���C�h�܂̓��^���A�R���P�V���ɓV���a�@�ʼni�c���m�̐f�@�������A�E��͎��ÓK�����߂��Ă���A����͌��ÌŖ@�������A���ʂȂ����Ꮈ�������B��R�͓]�㎞���̜�ӓ��Ő����F�e�B��R�͐������p�B���̍ō��ٔ����͌��R�������x���B���R�Ƃ��̔����́A���a�S�S�N�A�S�T�N�͌��ÌŖ@�ɂ�鎡�Â͈�Ð����ɒB���Ă��Ȃ���������A����ɂ��Ĉ�t���l�����Ȃ������̂ɂ͐ӔC�͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ𐿋����p�̗��R�Ƃ����B
�@�P�X�W�Q�N�܂ł̖��n���Ԗ��ǂɂ��Ă̈�A�̔������炷��ƁA���a�S�U�N�ɂ͌��ÌŖ@�͈�Ð����ɒB���Ă����A�Ƃ����l�������������i�����P�O�R�X���U�V�ł̃R�����g�Q�Ɓj�A���̂悤�Ȃ��̌�̍ō��ٔ�������A���̂悤�ȍl���͔ے肳�ꂽ�B
�P�X�X�Q�N�i�����S�N�j�U���W���ō��ّ�@�씻�������P�S�T�O���V�O�Łi����B�����j
�@���̍ō��ٔ����́A�l�̐����A���N�Ǘ��ɓ������t�͊댯�h�~�̂��ߍőP�̒��Ӌ`����s�����˂Ȃ�Ȃ����A���̒��Ӌ`���̑O��ƂȂ���̂́A��ʓI�ɂ͐f�Ó����̗Տ���w�̎��H�ɂ������Ð����ł���A���҂Ɠ��ʂ̍��ӂ����Ȃ�����A��t�͈�Ð���������Â��s���`���܂ł͕��킸�A���̈ᔽ�𗝗R�Ƃ������s���s�A�s�@�s�אӔC�����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ��Č������j���B�������p�B
�@���̔����̃R�����g�ɂ��ƁA���a�S�V�N�ɂ͌��ÌŖ@�ɂ�鎡�Â͈�Ð����ɒB���Ă��Ȃ������A�Ƃ������Ƃł���i�����P�S�T�O���V�P�ŎQ�Ɓj�B
�P�X�X�T�N�i�����V�N�j�U���X���ō��ّ�@�씻�������P�T�R�V���R�Łi����C�����j
�u�����Ɣ����v���a�S�X�N�P�Q���P�P���ɑ̏d�P�T�O�W�O�����Ő��܂ꂽ�q���ۈ��Ɏ��e����A�_�f�̋������A���a�T�O�N�Q���Q�P���ɑމ@���A���N�S���P�U���A��ȂŐf�@�����Ƃ���A����Ƃ����n���Ԗ���ፍ��R�x�Ɛf�f���ꂽ�i���͂͂O�E�O�U�j�B���R�́A���ÌŖ@���L���Ȏ��Ö@�Ƃ��Ċm�������̂͏��a�T�O�N�W���ȍ~�ł��邩��A���҂Ɍ��ÌŖ@�����{���Ȃ��������Ƃ͈�Ð�����A��ނ����Ȃ��A�Ƃ��Đ������p�B
�@�������{�����́A�V�K�Ȏ��Ö@��O��Ƃ��Č����A�f�f�A���Ó��ɓ����邱�Ƃ��f�Ì_��Ɋ�Â���Ë@�ւɗv��������Ð����ł��邩�ǂ�����������ɂ��ẮA���Y��Ë@�ւ̐��i�A���ݒn��̈�Ê��̓������̏��ʂ̎�����l�����ׂ��ł���A�E�̎�����̏ۂ��āA���ׂĂ̈�Ë@�ւɂ��Đf�Ì_��Ɋ�Â��v��������Ð������ꗥ�ɉ�����̂͑����łȂ��B�V�K�̎��Ö@�Ɋւ���m�������Y��Ë@�ւƗގ��̓������������Ë@�ւɑ������x���y���Ă���A���Y��Ë@�ւɂ����Ă��E�m����L���邱�Ƃ����҂��邱�Ƃ������ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���i�̎���Ȃ�����A�E�m���͉E��Ë@�ւɂƂ��Ă̈�Ð����ł���Ƃ����ׂ��ł���A�Ƃ��A���ÌŖ@���i�c��t�̎{�p���\��A���a�S�U�N�����瑽���̌����҂ɂ���ėL���ł���Ƃ̒ǎ��̔��\������A�����Ȃ̌����ǂ����a�T�O�N�R���A�L���̔��\�����Ă���A���ԕa�@�����a�S�W�N�P�O��������A�{�ǂɂ������ȂƊ�Ȃ̘A�g�̐����Ƃ�A��ꌟ���A�]����s���Ă������ƂȂǂ��炷��ƁA���R�͈�Ð����̔��f�Ɍ�肪����\��������A�Ƃ��Č������j�����߁i���̔����ɂ��Ă͓c���L�������̉��������B�@����ō��ٔ��������������ѕ����V�N�x�i���j�T�S�X�ňȉ��j�B
�@���̔����͖��n���Ԗ��ǂɂ��Ĉ��Ղȏ��a�T�O�N�����������߂�ƂƂ��ɁA��Ð������f�͌X�̈�Ë@�ւ��Ƃɍl����̂ł͂Ȃ��A��Ë@�ւ̐����A�n�搫���l�����ėގ���Ë@�ւ��m���������A���̈�Ë@�ւ����̂悤�Ȓm���������Ƃ����҂����悤�ȏꍇ�ɂ͂��̒m���͈�Ð����ɒB���Ă���ƍl���Ă��悢�A�ƈ�Ð������f�̊���������_�����ڂ����B
�Q�O�O�P�N�i�����P�R�N�j�P�P���Q�V���ō��ّ�O���@�씻�������P�V�U�X���T�U��
�@�u�����Ɣ����v�����R�N�Q���A������œ��[�̂ӂ���݂�S���Ƃ�Ƃ������؉������[�؏��p�����������A���[�����p�̐������Ȃ������Ƃ������R�ŁA���s���s���Q���������i�ג�N�B��R�͓������[�����p�͈�Ð����ɂ͒B���Ă��Ȃ��������A���{��Ë@�ւ����Ȃ��Ȃ��A�ϋɓI�]�����Ă����A�Ƃ��Đ����`���ᔽ��F�߁A�Ԏӗ��Q�O�O���~�F�e�B��R�͈�t�͈ꉞ�̐����͂��Ă���A�Ƃ����������j���B�{�����͓��[�����p�͓����A��Ð����ɂ͒B���Ă��Ȃ��������A���{��A���̕]���͑����Ȃ��̂ł���A���҂ɏp�@�I���̉\����^���邾���̐��������ׂ��ł������A�Ƃ��Č������j�������߂��B
�@��L�̂悤�ɁA�A�����J�ł͈�t�Ƌ��X�V���x������A�n���ɏZ�ވ�t�����C���s���Ă���A�Ƃ������A����͈�t�͒����œ��������A�n���œ��������A�N����킸�A�ȂׂāA�����̈�Òm����������I��Ð����ɂ���悤�Ɍ��s���ׂ��ł���A�Ƃ����w�͋`�����ۂ����Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B
�@�Ƌ��X�V���x�������Ȃ����{�ł��A��t�͂��̂�
���Ȍ��s�A�w�͋`�������̂ƍl����B�����łȂ��ƁA�N�ł��������̑�a�@�ł̎��Â����Ȃ��A�Ƃ������ł́A�����͕s�����Ȏ��Â��ÎȂ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ邩��ł���B�]���Ă��̌��s�A�w�͋`����ӂ�A���̂��Ǝ��́A�ߎ�������Ƃ�����\��������B
�@��Éߌ�̗ތ^�͉ߎ��̗ތ^�Ƃ������Ƃ��ł��邪�A����͐F�X�Ȋϓ_���炦����B
�Ⴆ�Έ�Î�̂ɂ���Ă����ނ����B��t�ɂ���Éߌ�A���Ȉ�ɂ���Éߌ�A
�Ō�t�A���Y�t�ɂ���Éߌ�A�a�@�Ǘ��҂ɂ���Éߌ듙�ł���i�����̉ߌ�͈�̈�Î�̂����ŋN����ꍇ�Ƒ��̈�Î�̂��������ċN����ꍇ������B��t��
�Ō�t�̈�Éߌ�͋������邱�Ƃ������j�B
�@���Ƃ��āA�Ō�t�A���Y�t�ɂ���Éߌ�ɂ��ċL���ƁA�������W������L��Éߌ�f�[�^�ɂ��ƁA�Y����Éߌ딻��S�Q�Q���̂����̂U���i�Q�V���j��
�Ō�t�����ł���i���قȂ��̂�������ƁA�T�̊��҂̎��̏[�U�������o�����Ƃ����Ō�t���A�����J���Ȃ����҂�����A�S���T���̉���������āA�����P���~�ɏ�����ꂽ����������B�P�X�V�V�N�Q���Q�W����㍂�ٔ��������W�X�V���P�Q�S�Łj�B
�@��L������Éߌ딻��S�W�O�O���̂����̂Q�X���i�R�E�U���j��
�Ō�t�A���Y�t�����ł���B
�@�ق��ɐf�ÉȂɂ���ĕ��ނ�����@�i�����펖���A�ċz�펖���A���@��A�Ȏ����A�Y�Ȏ����A���_�Ȏ����A���e���`�Ȏ������ɕ�������@�j������B
�@�ł���ʓI�ȕ��ޕ��@�͈�Ís�ׂɂ�镪�ޕ��@�i�f�f��̉ߌ�A������̉ߌ�A�����̉ߌ�A��p��̉ߌ�A�A����̉ߌ듙�ɕ��ނ�����@�j�ł���B
�@�����̕��ޕ��@�͒P�Ǝg�p�ł͂Ȃ��A���p����邱�Ƃ�����i�Ⴆ�ΉS�F���ҕʍ��W�����X�g�u��Éߌ딻����Łv�L��t�̕��ޖ@�j�B�ȉ��A���̗L��t�̔���S�I�̗ތ^���炢������I��ł݂�B
�i�P�j�u�����E�����E���m�E���Ȍ����\����̍��m�v
�P�X�X�T�N�i�����V�N�j�S���Q�T���ō��ّ�@�씻�������P�T�R�O���T�R��
�u�����v���f�̊��҂ł���A���̐��i���s���ł���A�����Ƃ��ẮA��ނ����Ȃ����u�ł���A���s���s�ɂ͂Ȃ�Ȃ��i����͗Y�u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����łQ�W�ŎQ�Ɓj�B
�i�Q�j�u�딻�f�E��f�\�S�؍[�ǂ��̑������ƌ�f�v
�P�X�X�O�N�i�����Q�N�j�S���Q�V����㍂�ٔ��������P�R�X�P���P�S�V��
�u�����v�����R�P�̊��҂͌ߌ�P�O���R�O�����~�}���@�B������t�͖{�l��f�@�A�{�l�̐f�@�y�ѓ��s�̂��̕ꓙ���玖����A�̑��a�Ɛf�f���A�܂����_�a���^���A�����A�������������悤�Ɠ��@�������B�����ߑO�X���R�O���A�e�ԋ}�ρA���S�B�����͐S�؍[�ǁB
�u�����v��Ð�������݂Č�f��ނ����Ȃ��A�Ƃ������ʂ̏ꍇ�������A��f�͍��s���s�ƂȂ�B�{���͋}�Ȕ��ǁA�㕠���ɁA�c�����A�S�g���ӊ��A�ċz��A�f���C�ȂǐS�؍[�ǂ��^���Ă��悢�Ǐ������̂ɁA���R�A�̑��a�Ɛf�f�B��f�ō��s���s�B�����F�e�i�e�r�]���u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����łR�S�ŎQ�Ɓj�B
�i�R�j�u���u���߂�����E��Z��̉ߌ��\�H���Ö�ᎍǐ��p�����v
�P�X�X�P�N�i�����R�N�j�P�Q���X�������n�ٔ��������P�S�R�T���P�P�U��
�u�����v���҂͏��a�S�V�A�W�N�ɓf�����A�H���Ö�ᎂƐf�f�����B���a�T�U�N�ɂ��f�����A��w�a�@�ŐH���Ö�ᎍǐ���p�������A��p���ɐS�s�S���N�����A�S���ڂɎ��S�B
�u�����v���҂ɂ͐H���Ö�ᎂ���̏o������������o�C�p�X�I�ȐÖ��ǂ������Ă���A�f���Ƃ����ً}���ȊO�ɂ͍ǐ��p�͕s�K���Ȃ̂ɁA���̃o�C�p�X���ǂɂ��Ă̏ڍׂȌ�����ڍׂȐ����Ȃ��Ɏ�p�����͕̂s���B�����F�e�B
�@���̔�������Z�̎����ł͂Ȃ��A�Ö@�I���̌��A������ӂ̎����ł��낤�i���o���F�u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����łS�S�ŎQ�Ɓj�B
�i�S�j�u���u���߂�����E���u�ɍۂ��Ă̎����\�����o�[���V���b�N�ɂ��]�o���v
�P�X�V�T�N�i���a�T�O�N�j�P�O���Q�S���ō��ّ�@�씻�������V�X�Q���R��
�u�����v���҂͎O�̂Ƃ��������̂��ߏ��a�R�O�N�X���U���A����a�@�ɓ��@�B�A���A���t�̎�ƃy�j�V���������̃����o�[���i���Ő��h�j�����{���A�y���������A�X���P�V���A�Q�O���ɂ킽���ă����o�[�����{�B�q�f�A�z�����̔�����N�����A�����Q���̏�Q�c��B�����͔]�o���B��R�͈��ʊW�͔F�߂����A�ߎ���ے肵�Đ������p�B��R�́A���삪�����o�[���ɂ��]�o���ɂ����̂��A�ق��̉��^���������ɂ����̂��s���A�ƈ��ʊW�ے肵�Đ������p�B
�u�����v�{���a�ς̓����o�[���ɂ��]�o���������ł���A�ƈ��ʊW�m�肵�āA�j�������߂��i�j�����R�͌��R���S������B�����i�ז@�R�Q�T�����j�B�����߂��R�́A�����o�[�����~���ׂ��ł������A�Ƃ��Đ����̈ꕔ�F�e�i�����N�u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����Ŏl���Łj�B
�i�T�j�u���u���߂�����E�◯�\�K�[�[�◯�����v
�P�X�W�R�N�i���a�T�W�N�j�P���Q�U�����É����ً���x����������^�C���Y�S�X�Q���P�P�V��
�u�����v���҂͋��ň������܂ŏ��a�R�W�N�T���A�퍐���ҒŌŒ��p����B��N����A��p�����Ղɒɂ݁A��B�ق��̕a�@�Ŕr�^�̂��ߐ؊J��p�������A�Ǐ���P�����B��x�ڂ̎�p�i���a�S�T�N�����H�j�ŏ������Ȃ����Ԃ��K�[�[����Д����B������Ƃ�Ǝ���B��R�͂��̃K�[�[�͔퍐��t���ԗ��������̂Ƃ��Đ����F�e�B
�u�����v�b�A���Ӓ�l�́A�K�[�[�̕a���g�D�������炷��ƁA�{����p�̍ۂɈ◯���ꂽ���̂ł͂Ȃ��B���Ӓ�l�͈◯�K�[�[�ƊӒ�B���ق͉��Ӓ���̗p���A�������j���������p�i���҂͂ق��̕a�@�Ŕr�^�̂��ߐ؊J��p���Ă��邩�炻�̎��̃K�[�[���◯�̉\��������B�Ӓ茋�ʂ̍̔ۂ̓�������������B���{���u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����łT�W�Łj�B
�i�U�j�u�N�X���E����p�\�X�g�}�C����p�S�W�����v
�P�X�W�P�N�i���a�T�U�N�j�S���Q�R���������ٔ��������P�O�O�O���U�P��
�u�����v����\���ɂق��̔��]�A�_�o�ɓ��̏�Q�ƕ��L���đ攪�_�o�i���_�o�j��Q�Ə������x�ł́A�S�W��Q�܂Ŕ������镛��p�ɑ���K�Ȍx���Ƃ͂����Ȃ��A�Ƃ��Đ����F�e�i�����N�F�u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����łV�O�ŎQ�Ɓj�B
�@��ɓY�t����Ă����\���͏d�v�ł���B�P�X�X�U�N�i�����W�N�j�P���Q�R���ō��ّ�O���@�씻�������P�T�V�P���T�V�ł́A�V�̏��N�̒�������p�Ŗ����܃x���J�~���r�ō��Ŗ�����A���s�ɏ]���A�T�������Ɍ����`���G�b�N�������A������P�Q���ʂ̂��ɋC���������Ȃ�A�V���b�N��ԂɊׂ�A�d�x�̏�Q���������ŁA���R�͊��s�ʂ�̌����`�F�b�N�ʼnߎ������A�Ɣ����������A�ō��ق̓y���J�~��S���\���ɂ͂Q�������̌����`�F�b�N�K�v�Ə����Ă���A�\���ᔽ�͉ߎ������A�ƌ������j���A�����߂��B
�@���́w�����̎��Ö�Q�O�P�O�x��]�����d�Ă���i�Q�O�P�O�N�V���Q�R���lj��j�B
�i�V�j�u���ː��\�������ː���Q�����v
�P�X�U�X�N�i���a�S�S�N�j�Q���U���ō��ّ�ꏬ�@�씻�������T�S�V���R�W��
�u�����v�����ɑ�����ː����Â͍����Ö@�ł͂Ȃ��A�ΏǗÖ@�ł���A���������ˑ��ʂ͋��e�ʂ������Ă���B�����Ƃ����a���A���̕a��ƕ��ː����Â̊댯�x���r����ƁA��t�̒��Ӌ`���ᔽ�͖����B�������ێ��i����I�B�u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����łX�Q�ŎQ�Ɓj�B
�i�W�j�u���҃P�A�\�V�������Ⴆ�����v
�P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j�X���Q�O���ߔe�n�ى���x�����������X�S�X���P�P�P��
�u�����v�F�e�B�F�e�z�E�q�͂��ꂼ��R�O�O���~�A�e�͂��ꂼ��Q�O�O���~�B�ːВ��������A�q�͉����B�J�E���Z�����O���Ă���i����u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻����łP�Q�O�ŎQ�Ɓj�B
�@��t�@�P�X���P���u�f�Âɏ]�������t�́A�f�@���Â̋����������ꍇ�ɂ́A�����Ȏ��R���Ȃ���A���������ł͂Ȃ�Ȃ��B�v
�@���̋`������t�������`���Ƃ����B��O�A���̉����`���ᔽ�ɂ͋��Y�@�A���x�@�Ə����߂Ŕ����̒�߂����������A���s��t�@�ɂ͔����̋K��͂Ȃ��B
�@���̉����`���̍����E��t�ɂ����ƓƐ��i��t�@�P�V���j�A�Ɩ����������ɂ���B
�@���̋`���ᔽ�ɂ��A���҂̐g�̐����Ɋ댯�������A���`���ᔽ�ɐ������R���Ȃ��ꍇ�ɂ́A��t�͊��҂ɑ��Ė��@�V�O�X���̕s��ׂɂ��s�@�s�אӔC���A���O�Ɋ��҂Ɛf�Ì_���������Ă����ꍇ�ɂ͍��s���s�ӔC����������\��������B
�@�X�ɂ��̂悤�ȉ����`���ᔽ���������������ꍇ�ɂ́A�㓹�R�c��i��t�@�Q�T���j�̎�����o�āA������b�����t�Ƌ���~�A��������i��t�@�V���j���邱�Ƃ�����B
�@��t�����������ސ������R�Ƃ́A���O�ł��邱�ƁA��ԋx���f�Ë@�ւ����݂��邱�ƁA��t�̕s�݁A�a�C���̎��R��������Ă���A�y�x�̕a�C���R�͐������R�ɊY�����Ȃ��Ƃ���Ă���i�ȏ�̓_�ɂ��O�c�B���ق��u�㎖�@�v�L��t�V�R�ŁA�P�U�P�ŎQ�Ɓj�B
���@�Q�Q���͐E�ƑI���̎��R�Ɠ����ɁA�E�Ɛ��s�̎��R���ۏႵ�Ă���B��t�̉����`���͂��̐E�Ɛ��s���R�̗�O�ł��邪�A��L��̗��R�i��ƓƐ�A�������j���牞���`�����߂���t�@�̋K��͌��@�ᔽ�ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ă���i�O�c�ق��u�㎖�@�v�P�S�S�Łj�B
�@�~�}���҂̂�����A���炢�����i�f�Ë��ێ����j�����̉����`���ɊW����B��L�̂悤�ɁA�a�@�̐ӔC��F�߂������A�ے肵������������B
�@���̈�t�̉����`������ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�h�C�c�ł́A��t�����҂Ƃ̊ԂɐM���W���Ȃ��Ɗm�M�����ꍇ�͋~�}�̏ꍇ�������A�f�Â����ۂł���B�h�C�c��t��u�h�C�c��t�̐E�ƋK���v�P�X�X�R�N�E�������v�z�[���y�[�Whttp://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/D101�Q��
�@���҂̌������ɂ��Ă͉p�Ă͐�i���ƌ�����B
�@�P�X�W�S�N�A�f�[�^�ی�@���������C�M���X�ł́A�R���s���[�^�[�������\�ȃf�[�^�Ɋւ��A�f�[�^��́i�Ⴆ�Ί��ҁj�́A�f�[�^���p�ҁi�ۗL�ҁj�Ƀf�[�^�ۗL�̗L���A���̃R�s�[�̌�t��v���ł��錠����F�߁i�Q�P���j�A�f�[�^���s���m�̏ꍇ�͂��̏C���������\�ƋK�肵���i�Q�S���j�B�P�X�X�O�N�ɂ͈�ËL�^�A�N�Z�X�@�𐧒肵�A�d��������Ă��Ȃ���ËL�^�Ɋւ��Ă����҂ɓ����悤�Ȍ�����F�߂��B
�@�A�����J�ł͂P�V�V�S�N�A�A�M�����Ȍ��O�q���Ǐ��ǂ̕a�@���A�A�M���{�n�a�@�Ɋւ��Đ��肳�ꂽ�A�M�v���C�o�V�[�@�́A�J���e�̉{���A�R�s�[������F�߁A�T�O�B�̂�����������������B�����҂̃A�N�Z�X����F�߂�@���𐧒肵�Ă���i�ێR�p��u��ËL�^�ɑ��銳�҂̃A�N�Z�X���E�p�Ă̖@���v�W�����X�g�P�P�S�Q���S�X�ňȉ��j�B
�@���{�ł͂ǂ����B�W�����X�g�P�P�S�Q���S�ňȉ��̍��k��u�J���e���̐f�Ï��̊��p�Ɋւ��錟��������߂����āv�ɂ��ƁA�P�X�X�U�N�P�P���̍�����Ñ��������R�c��ԕ��y�ї^�}��Õی����x���v���c��́A�J���e�A���Z�v�g���ɂ���Ï��̌��J�A�J���̐ϋɓI�Ɏ��g�ނׂ��A�Ƃ����ӌ����q�ׂĂ��邪�A���{��t��͂���ɔ����Ă���B
�@�ŋ߁A�s���^���Ƃ��Ă��J���e�A���Z�v�g�i�f�Õ�V�������j�̊J�������߂鐺�����܂�A���̒c�̂̃z�[���y�[�W������������i�Ⴆ�A��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�̃z�[���y�[�W�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
http://homepage1.nifty.com/khr/simin/index.htm�j�B
�@���̃J���e�A���Z�v�g���J�A�J���̉^���A�X���́A�O�L�̃C���t�H�[���h�E�R���Z���g�̗���Əd�Ȃ���̂ŁA����̐����Ƃ��킴������Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A�ӊO�ɂ��A�i���I��t�Ƃ�����l���J���e���J�A�J���ɂ͔��A�Ƃ����ԓx���Ƃ�l������B�Ⴆ�ΐ_�O�i��t�͂��̒����u���Ҋw�v�Łu���҂ɂ͏\���ɐ�������悢�B�J���e�͊��҂Ɍ����邽�߂ɏ����Ă͂��Ȃ�����A���҂����Ă�����Ȃ��B���҂ɔ���悤�ɏ����Ƃ���ƙˑ�Ȏ��ԂƘJ�͂�������B�J���e�͈�Éߌ�i�ׂ̂��߂ɂ������p�������̂ł���B�v�Əq�ׂĂ���i�����W�R�Łj�B
�@��t�@�Q�S���P���́u��t�́A�f�Â������Ƃ��́A�x�Ȃ��f�ÂɊւ��鎖����f�Ø^�ɋL�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�A�����Q���͂��̕ۑ����Ԃ��T�N�Ԃƒ�߂�B���̕ۑ����Ԃ͒Z���߂���B���@�V�Q�S���ɂ��A�s�@�s�\���̏ꍇ�A���ˊ��Ԃ͂Q�O�N�ł��邩��A�Œ��Q�O�N�Ԃ̕ۑ����K�v�Ǝv����i���|�O�c�ق��u�㎖�@�v�V�U�Łj�B�J���e�͈�Éߌ뎖���ɂ����āA���ґ������ɖ𗧂��̂ł͂Ȃ��A��t�A�a�@���ɂ��𗧂��̂ł���B
�@�J���e���L�ڎ����͈�t�@�{�s�K���Q�R�����u�f�Â����҂̏Z���A�����A���ʁA�N��v�u�a������ю�v�Ǐ�v�u���Õ��@�i���u����я����j�v�u�f�@�̔N�����v�ƋK�肷�邾���ł���A�p����܂߁A��̓I�ȋL�ڕ��@�A�L�ڕ����͈�t�̑I���Ɉς˂��Ă���B�P�X�U�S�N�ɃC�M���X��weed,L.L���������u���V�X�e�������iProblem Orented System�j�̃J���e����������Ă��邪�i�_�O�i�u���Ҋw�v�W�T�Łj�A�ق��ɂ��쐬���ԒZ�k�̂��߁A�l�X�Ȏ��݂��Ȃ���Ă���B
�@�Ⴆ�A��m���T��t��POS�����̃J���e��O��Ƃ��āA�R���s���[�^�[�ɂ��J���e�쐬�Ɗ��҂ւ̉{������Ă���i��m���T�u�J���e�ԋp�ɂ��Ă̎��āv�N��㎖�@�w�P�S���V�V�Łj�B���Z�ȓ��{�̈�Âł́A�R���s���[�^�[�����ɂ��J���e�L���̓������K�v�ł��낤�B
�@�Ƃ���ŁA�������Ì_���O���Ƃ��ăJ���e�̊J�������߂����҂̐�����ے肷��B�P�X�W�U�N�i���a�U�P�N�j�W���Q�W���������ٔ��������P�Q�O�W���W�T�ł�����ł���B
�u�����v�����̏�Q�̂��ߍ����a�@�ŃC���^�[�t�F�����ɂ�鎡�Â������҂����Ì_��i����ɂ́A�C���^�[�t�F�����ɂ�鎡�Â͈�w��A�m������Ă��Ȃ����Ís�ׂ��܂܂�A���̂��߁A�\�����Ȃ����ʂ��������ꍇ�A�a�@�͖Ɛӂ����A�Ƃ������t�����Ă����j�y�ь_��̓��ꐫ�Ɋ�Â��J���e�̉{���𐿋������B
�u�����v��Ì_��ɂ̓J���e�J���`���܂ł͊܂�ł��炸�A�_��̓��ꐫ���l���Ă������ł���A�Ƃ��Đ������p�B
�@���̔����͊��҂��i�O�ŃJ���e�̉{���𐿋����������ł��邪�A�����������i�ׂɂȂ�Ί��҂������i�ז@�̋K��ŁA�������t�A�a�@���J���e���ٔ����ɒ�o����|�̖��߂̔��z�����߂邱�Ƃ��ł���B�����i�ז@�Q�Q�O����������o���ߐ��x������ł���B��t�A�a�@�����i�ׂŃJ���e�����p�����ꍇ�͊��ґ��͓����P���ŁA���̒�o�����߂邱�Ƃ��ł��邵�A�����łȂ��Ă������R���i���������؎҂̗��v�̂��߂ɍ쐬����A�͋��؎҂ƕ����̏����҂Ƃ̊Ԃ̖@���W�ɂ��č쐬���ꂽ�Ƃ��j�ŁA���̒�o�����߂邱�Ƃ��ł���B�������i�ז@�R�P�Q���R���͌��s�K��Ɠ���̋K��ł��邪�A�����O�i�ɓ�����Ƃ������̂ɂP�X�V�W�N�U���Q�O����㍂�ٌ���ŗ����̍ٔ����X�O�S���V�Q�ŁA�P�X�V�W�N�V���R�P���������ٌ��蔻���X�O�W���T�Q�ł�����A������i�ɓ�����Ƃ������̂ɂP�X�V�W�N�R���U����㍂�ٌ��蔻���W�W�R���X�ŁA�P�X�X�Q�N�X���W���������ٌ��蔻���P�S�W�R���V�P�ł�����B
�@���̒�o���߂����z���ꂽ�̂ɃJ���e����o����Ȃ��Ƃ��́A�ٔ����̓J���e�̋L�ڂɊւ��銳�ґ��̎咣��^���ƔF�߂邱�Ƃ��ł���B�J���e���s��o�ł����ꂾ���ň�t�̉ߎ��A�L�ӂ��������킯�ł͂Ȃ����A�Ⴆ�A��t�������҂ɑ����鏈�u�������Ǝ咣���A���҂������۔F���A�J���e�ɂ����̂悤�ȋL�ڂ͂Ȃ��A�Ƃ����咣�����Ă���ꍇ�A��t������o���߂ɉ������A�J���e���o���Ȃ����Ƃɂ��A�퍐�̎咣���������ƍٔ����͔F��ł���̂ł���B
�@��������O�ҏ����ł���ꍇ�́A�R�q�̂�����o���߂����z����邪�i�����i�ז@�Q�Q�R���Q���j�A��O�҂��������o���Ȃ��ꍇ�́A�Q�O���~�ȉ��̉ߗ��̏�������i�����i�ז@�Q�Q�T���P���j�B
�@���ґ�����t�A�a�@����C�ӂɃJ���e�̃R�s�[�𑗕t���ĖႤ�A�Ƃ����P���ȕ��@����������\���͏��Ȃ��B���҂��ٌ�m�ɈϔC���Ĉ�t�A�a�@����J���e�R�s�[���擾���邱�Ƃ́A���Җ{�l���s�����́A�������������i����h���t�����`�����ٌ�m����̈˗�������A�S�O�Ȃ��J���e��������A�ƌ����Ă���B����h��u�J���e�ƃ��Z�v�g���킩��{�v�R�P�Łj�B
�@�܂��A�ٌ�m�ٌ͕�m�@�Q�R���̂Q�ɂ��A�����ٌ�m��ɑ��Ĉ�t�A�a�@�ɕK�v�Ȏ����������������߂�A�Ƃ����`�ŃJ���e���t�����߂邱�Ƃ��ł���B
�@�J���e���̓���ōł��L���s���Ă���̂��A�����i�ז@�Q�R�S���ȉ����؋��ۑS���x�𗘗p���čs���J���e�̌��ł���B����͑i�ג�N�O�ɍs����̂����ʂł��邪�A��N��ł��\�ł���B�葱�̓��ꐫ����ٌ�m�ɈϔC���čs���̂��]�܂����B
�@�ٔ������J���e�����A�Ƃ���������������Ȃ����A���̂ł���B�J���e�͈�t�������銳�҂���l�����ŁA�f�f�A���u���P���ł���Εs�K�v�ł��邪�A���Ґ��������A�f�f�A���u�����G�ɂȂ�ƁA�L������̂���ςł��邩��A���Y�^�Ƃ��ăJ���e����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B�J���e�͈��̔��Y�^�A���Ȃ킿�����ł��邩��A�K�����K�肷�鎖���ȊO�ɂ��A��t�͐��X�̋^��_�A���̐f�f�A����̌����|�C���g�A�]��\��擙���L�ڂ���ł��낤���A���҂Ɋւ���l���i���҂̐��i�A�E�ƁA�n�ʓ��j���L�ڂ���B�����̋L�ڂ͈�t�ɂƂ��Ă͎����ȊO�ł́A�X�^�b�t�A���a�@�̈�t�ȊO�̎ҁA���Ɋ��ҁA���̉Ƒ��ɂ͌��������Ȃ����̂ł���B
�@�ٔ��������J���e�́u��T���v�ƌĂ�邪�A�ٔ����������̎���������A�咣�A�؋�����������A���Y�^�Ƃ��āA�������ƂɁu��T���v�����B����͓����҂̐����A�咣�A�؋��̋L�ڂ����S�ƂȂ邪�A�^��_�A�ߖ��_�A�\�蓙�̂ق��A�����ҁA�㗝�l�̐��i�A�X���A�@��ł̑ԓx�A�������A�����ҁA�㗝�l�ٌ�m�̌l����������Ă���A�i�ׂ̌��_�\�������������Ă��邱�Ƃ�����B�]���āu��T���v�̌��J���͂��肦�Ȃ��B���Ƃ��ƈ�t���������̘J���ɑ���V���Ⴆ���ÊW�Ƃ͈Ⴂ�A�ٔ��͌������Ƃ��Ă̐E����s����̂ł��邩��A�J���e���J�Ǝ�T�����J�͑S���̕ʘ_�ł���B
�@�������ٔ������A�����҂̎咣�̐����A���̐����Ɋւ��镔���A����Αi�ׂ̋q�ϓI�����E�E�N���ώ@���Ă��哯���قł���ׂ������E�E�͓����҂Ɍ��J���āA���������̂悤�Ɏ咣�A�؋��̐��������Ă���A�Ƃ������Ƃ��������Ƃ͂��肤�邱�ƂŁA�ǂ����Ƃł�����B
�@�J���e�ɂ��Ă������ŁA���J�������Ȃ킿�q�ϓI�����Ɣ���J�������Ȃ킿��ϓI�������Ă͍��Ȃ����낤���B��t�����҂ɂ͌��������Ȃ������͕ʕ����i�Ⴆ�Ί��҃����j�ɋL�ڂ���̂ł���B�����ċK�����K�肷��q�ϓI�����͌��J���邱�Ƃɂ�����ǂ����낤���B
�@��t�͈ꃖ�����Ɋ��҂̌��N�ی��̎x������܂��͍��ۘA����ɐf�Ö����i���Z�v�g�j�𑗕t���ĕی����̎x�����𐿋�����B����ɂ͈�Ís�ׂ͓_��������A�P�_�P�O�~�Ƃ���Ă���B�@
�@���Z�v�g�Ɋւ��āA�����Ȃ͂P�X�X�V�N�U���Q�T���A���Җ{�l�A�⑰�A�@��㗝�l�A�ٌ�m����㗝�l�̐���������ΊJ������悤�ɒʒB���o��������A�K�v�ȏꍇ�̓��Z�v�g�����邱�Ƃ��ł���i�J���e�A���Z�v�g�̌����ɂ��Ă͌���h��u�J���e�ƃ��Z�v�g���킩��{�v�������X�Q�Ɓj�B�@�����F�ی��̂����ŁA���{�̊��҂͐f�Õ�V�ɖ��S�ł���B�V�l��ÂɂȂ�ƁA�܂��܂��f�Õ�V���A�T�[�r�X�ɊS�������Ă��܂��B��̐����͌����ł���Ɩ���V�����A���������쐬���Ċ��҂ɓn���Ɠ_�������ĕ�V�̑ΏۂƂȂ�悤�����A���̂悤�Ȃ��ƂɊ��҂͖��S�ł���B
�@��Éߌ���̔F�m�A���W���@�ɂ́A���Ȃ��Ƃ��ȉ��̂��̂�����B
�P�@���{��w��ɓo�^����Ă����w��w��A���Ԕ��s�̈㎖���i�Ⴆ�Γ��{�㎖�V��j�Ɍf�ڂ̈�Éߌ�f�[�^������B
�Q�@���N�Ɉ��A�w��ƂɈ�Î��̒���������̂ŁA���̌��ʂ�m��B
�R�@�a����U���̈�Éߌ�������B
�S�@���A���̔���W�ɋL�ڂ̈�Éߌ딻���ǂށB
�T�@��Éߌ�ی���̔����Ă���ی���Ђ̎����Ă����Éߌ�f�[�^�������ĖႤ�B
�U�@��Éߌ��Q�҂̉���W���Ă���f�[�^������B
�V�@��Éߌ�ٌ�c�������Ă����Î��̏��Z���^�[�����W���Ă����Éߌ�f�[�^������B
�@�w��͉���ɔz�z����A����W�͎G���Ƃ��Ĕ̔�����Ă���B��Q�҂̉�A��Q�ٌ�c�̂�����Z���^�[�Ȃǂ̓C���^�[�l�b�g�z�[���y�[�W��Ńf�[�^�����J���Ă���B�ڎ��ɖ߂�B
�@����W�ɂ́A�ٔ������o���Ă������I����W���A���Ԋ�Ƃ��o���Ă������I����W������B�ō��ٔ�����������W�A�����ٔ�����������W�A�����ٔ�����������W���͌��I����W�ł����A����^�C���Y�A����͎��I����W�ł���B
���I����W�����Ђ����邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A���I����W�̍v���x���傫���B�Ⴆ���A����^�C���Y�ɂ͌Â����画��̂ق����A�ٔ����ɂ�閯���A�Y���A�A�s���A�Ǝ������Ɋւ��錤���A�_�����������f�ڂ���Ă��Ă����A���̎����@�w�̔��W�ɑ傫����^�����B
���I����W�̈�ł���������͂P�X�T�R�N�i���a�Q�W�N�j�U����1�������s�����A�Q�O�O�Q�N�i�����P�S�N�j�U��
�Q�T�������A�P�V�W�P�����o����B
�@�����͓����A�@������o�����Ə̂����A���s���͓��{�]�_�V���A�ҏW���͔���s��ł��������A���̌��A���{�]�_���A�����Ђ��������s�l�ƂȂ��A���݂͊�����Д����Ђ����s�l�ł���B
�@�����͏{�����ł��邪�A���̓��F�͑S���ɃR�����g���t�����Ă��邱�Ƃł���B�R�����g�͏d�v����ł����A���������ł͎�ڍׂɂȂ邪�A���ڍׂȔ����]�͔����ʍ��̔���]�_�Ɍf�ڂ����B
�@�����̃T�C�Y��B5�łł����A���s�����͂P�O�O�Ŗ����̏����q�ł��������A���݂͂Q�O�O�őO��ł��邱�Ƃ������B
�@���͂P�X�U�S�N�i���a�R�X�N�j�ז������ɂȂ�A�����n�a�@�ŋN�����Éߌ떯�������̔퍐�w��㗝�l�Ƃ����̎d���ɏ]������悤�ɂȂ����������A�����͒�����������Éߌ뎖���ɋ����������A��Éߌ딻����p�̃m�[�g�Ƀ�������悤�ɂȂ��A���[�v��������o���A�����p�\�R������ł̓f�[�^�x�[�X�\�t�g�i���݂̓A�N�Z�X�j���g���Ĉ�Éߌ딻�������A���W���Ă���B���̔�����W�Ώێ��͔�����ł���B
�@�킪���̊��҂ƈ�t�Ԃ̈�ÊW�ɂ����Ă��A�����ȗ������A��t�����҂̖ʓ|�����A����������A�ی삷��A�Ƃ����A�p�^�[�i���Y���ipaternalism�E�ƕ��I�ی��`�j���x�z�I�ł������B�������A���̈��鎞���i�P�X�U�P�N���j���獑���F�ی������{�����A��Õp�x�������A�]���Ĉ㎖���������債�A���ꂪ��Éߌ뎖���A�����Ƃ��ĕ����ɔ����A��ÊW�ɂ��Ă̌_��I�ώ@�A�Ђ��Ă͊��ґ��̌����ӎ������܂��A���҂̎��Ȍ��茠�A�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�c�_���䓪����悤�ɂȂ����i���̓_�ɂ��A�ؓN�u��Â̖@���w�v�L��t�P�P�R���Q�ƁB�؈���{��t������{�̈�Â̈����_�̓p�^�[�i���Y���ɂ���Ǝw�E���Ă���B�Βk�u��Â̐V���I�ց\���������Љ�v���{�㎖�V��S�O�O�O���P�U�Łj�B
�@���̂悤���A��Éߌ딻��͈�ÊW�̋ߑ㉻�ɍv�����Ă���̂ł���B
�@�w�ҁi���q�A�蓈�j�͓��{�̈㎖�@�j���A��������I��܂ł̈�t�D���̑����A��ォ�珺�a�S�T�N�܂ł̔����̑����A���̌�̑�O���ƕ����Ă��邪�i�蓈�L�u��t�̖����ӔC�𒆐S�Ƃ��Ĉ㎖�@���j�v�\����������I��܂Ł\�v����A�L�c�ҁu�������@���l����v�@�������ЂP�O�T�Łj�A��O���͊��ҕی�̐V�����㎖�@�̑n�����ƌ����Ă悢�ł��낤�B�Ȃ���L�̂悤�ɁA���a�S�T�N�A���Ȃ킿�P�X�V�O�N���ȍ~�A�����ɂ������Éߌ딻��f�ڐ��͑����X���������Ă���B
�@��L�̂悤�Ɉ�Éߌ낪�N�������ꍇ�̖@�I�ӔC�ɂ��s���@�I�ӔC�A�Y���@�I�ӔC�A�����@�I�ӔC�̎O��ނ����邩��A��Éߌ딻�������ɑΉ����āA�s����Éߌ딻���A�Y����Éߌ딻���A������Éߌ딻���ɕ�������B
������P������ŐV�̂P�V
�W�P���܂ł��s����Éߌ딻���͂V���f�ڂ���Ă���B���̂Ȃ��ł́A�P�X�W�O�N��A�{�錧�ň�t��w��̎Y�w�l�Ȉ�ł������e�c��t���{�e�ƂȂ�l�̎��q�Ƃ��ďo���͏o���쐬���ĐԂ����̈��������������ň�t��̎w����������ꂽ��A�Ɩ���~�������������i��䍂�ُ��a�U�O�N�R���Q�X�����������P�P�T�P���S�W�Łj���L���ł���i��t��͔C�Ӓc�̂ł��邪�A��̕ی�@�i���Ƃ̗D���ی�@�j��ł͒����w�茠���������Ă���j�B
�@������A�Y����Éߌ딻���͂Q
�T������B���̂Ȃ��Œ����Ȃ̂́A�@���������i�f�Â������x�m���Y�w�l�ȕa�@�����ł���B������P�X�W�O�N��̎����ł��邪�A�����@�����A���̕v���L�ߔ������Ă���B
�@�ł������̂�������Éߌ딻���ł���B������P������P�V
�W�P���܂łɂW�T�Q���f�ڂ���Ă���B���̂Ȃ��ɂ͏�L�̂悤�ɓ��c���ˑR�������͊܂܂�Ă��Ȃ����A���_�a�@�����͓����Ă���B
���̂ق��A��Éߌ�Ɋւ��Ă͕�����o���߂̋��ۂƂ��A�ۑS���������ƂȂ邱�Ƃ�����B�����͂������Éߌ�G�����Ƃ������ׂ����̂ł��邪�A�����ł͏ȗ������i��Éߌ�G�����ŏd�v�Ȕ����Ƃ��Ă��A�J���e�̉{�����������ɂ������A�����I�ɂ͊��҂̃J���e�{����������ے肵����L�P�X�W�U�N�i���a�U�P�N�j�W���Q�W���������ٔ��������P�Q�O�W���W�T�ł�����j�B
�@����͈�Éߌ�ɂ��Ė����ӔC�A���Ȃ킿�_��ӔC�A�s�@�s�אӔC�A���Ɣ����ӔC��Njy�����i�ׂłȂ��ꂽ�����Q�ł���B
���̖�����Éߌ딻���͈�t�̌�f���̓T�^�I��Éߌ�i�����̂ق��A�����Ђ̐ӔC���������Q�i�����Ƃ��A�\�h�ڎ�i�����Ƃ��A���_�a�@�̊Ǘ��Ɋւ���i�����Ƃ��A�����t�̏��u�Ɋւ���i������O��Ƃ�����̂ł���B
���̒T���ł��A���̂悤�ȈӖ��ł̖�����Éߌ딻��͔����P������P�V�W�P���܂łɂW
�T�Q���f�ڂ���Ă���i����l�̒T���Ȃ̂��A�����̐����͊����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����f�肵�Ă����j�B
�@�����Ɍf�ڂ��ꂽ�n���P�����猻�݂̂P�V
�W�P���܂ł̖�����Éߌ딻���̐����A�������Ɋ�Â��āA�N�����Ƃɕ��ׂ���A���̂悤�ɂȂ�B
�P�X�T�R�N�O��
�P�X�T�S�N�O��
�P�X�T�T�N�O��
�P�X�T�U�N�P��
�P�X�T�V�N�P��
�P�X�T�W�N�O��
�P�X�T�X�N�O��
�P�X�U�O�N�O��
�P�X�U�P�N�Q��
�P�X�U�Q�N�P��
�P�X�U�R�N�P��
�P�X�U�S�N�T��
�P�X�U�T�N�Q��
�P�X�U�U�N�Q��
�P�X�U�V�N�Q��
�P�X�U�W�N�R��
�P�X�U�X�N�T��
�P�X�V�O�N�R��
�P�X�V�P�N�X��
�P�X�V�Q�N�P�R��
�P�X�V�R�N�P�S��
�P�X�V�S�N�P�P��
�P�X�V�T�N�P�Q��
�P�X�V�U�N�P�U��
�P�X�V�V�N�X��
�P�X�V�W�N�P�V��
�P�X�V�X�N�Q�T��
�P�X�W�O�N�R�O��
�P�X�W�P�N�Q�V��
�P�X�W�Q�N�S�T��
�P�X�W�R�N�S�Q��
�P�X�W�S�N�Q�X��
�P�X�W�T�N�S�R��
�P�X�W�U�N�R�R��
�P�X�W�V�N�R�U��
�P�X�W�W�N�R�P��
�P�X�W�X�N�R�W��
�P�X�X�O�N�R�R��
�P�X�X�P�N�Q�U��
�P�X�X�Q�N�R�X��
�P�X�X�R�N�Q�S��
�P�X�X�S�N�R�U��
�P�X�X�T�N�R�O��
�P�X�X�U�N�R�U��
�P�X�X�V�N�Q�T��
�P�X�X�W�N�R�R��
�P�X�X�X�N
�P�V��
�Q�O�O�O�N �Q�R��
�Q�O�O�P
�����f�ڂ̖�����Éߔ��ᐔ���ɂȂ����̂͂P�X�V�Q�N�ȍ~�ł����A�P�X�V�X�N����͂Q�O���ȏ�̔������f�ڂ����A�P�X�W�Q�N�A�P�X�W�R�N�A�P�X�W�T�N�ɂ͂S�O����̔������f�ڂ���Ă���B�P�X�X�X�N�ȍ~�f�ڐ����������Ă���B
��������A�����f�ڐ��͈�Éߌ뎖���̔������A��Éߌ떯�������̒�N���A���ϐ��A���������̂��̂ł͂Ȃ��B�������A���Ɉ�Ì���ň�Éߌ뎖�����N�ԂɂP�O�O���������Ă��A���̂����̉��������������ɔ��W���邩�͕s���ł����A�܂�������É���i�����͂P�O�O%�A�����ŏ����������̂ł͂Ȃ��A�܂������������Ă��A���I����W�̕ҏW�҂����̂����̉�%��c�����邩�A�܂��c�����������̉�%���f�ڂ��邩�͕s���ł��邩��ł���B
�������A�O�L�����f�ڔ��ᐔ�̐��ڂɂ�����A������Éߌ�i�����̒�N���A�������̑�̂̐��ڂ͑z���ł���B
�@����u��Éߌ�W�����i�������������i�ȉ��A���������Ɨ��́j�v�́u�ō��ٔ��������ٔ������v�P�W�O�����o�ł������̂ł��邪�A���̂X���ɂ����A������Éߌ�i�����̊��ϐ��i���ό����ɂ͔����̂ق��ɁA�a���A�i���̎扺�������܂܂��j��
�P�X�V�U�N�P�S�S��
�P�X�V�V�N�P�T�R��
�P�X�V�W�N�P�W�S��
�P�X�V�X�N�P�V�X��
�P�X�W�O�N�P�V�U��
�P�X�W�P�N�P�X�T��
�P�X�W�Q�N�Q�R�U��
�P�X�W�R�N�Q�Q�S��
�P�X�W�S�N�Q�P�X��
�P�X�W�T�N�Q�U�Q��
�P�X�W�U�N�Q�U�V��
�P�X�W�V�N�R�O4��
�ł���A�ѓ����u�ٔ����v���猩����Éߌ�i�ׂ̎���v����ٔ��@��n�V��Éߌ�V���{�@�K�P�ňȉ��ɂ��ƁA������Éߌ�i�����̊��ϐ���
�P�X�W�W�N�Q�V�X��
�P�X�W�X�N�R�O�P��
�P�X�X�O�N�Q�W�Q��
�P�X�X�P�N�R�P�O��
�P�X�X�Q�N�R�O�R��
�P�X�X�R�N�Q�X�Q��
�P�X�X�S�N�R�Q�W��
�P�X�X�T�N�Q�X�R��
�P�X�X�U�N�S�R�Q��
�P�X�X�V�N�S�S�P��
�ł���B
�܂��A���������P�P�łɂ����A�P�X�W�P�N����P�X�W�V�N�܂ł̖�����Éߌ�i�����̊��ό����̂����A�����͂S�S%�ł����A�P�X�W�Q�N�ɂ����锻�����͂X�T���Ƃ���Ă���B�����O��Ƃ��Ĕ����̖�����Éߌ딻���̔c������z�����Ă݂���A�P�X�W�Q�N���ɂ����������f�ڂ̖�����Éߌ�i�����̔������͂S�T���ł��邩���A�����̔c�����͂S�V%�Ƃ������ƂɂȂ�B���̎��Z���������Ă���A�����Ɍf�ڂ���閯����Éߌ딻��ɓ�{�ȏ�̖�����Éߌ딻���������n����Ă���A��������鐔�̎����������ȊO�̘a���A�i���̎扺�����̌����ŏI�����Ă��邱�Ƃ��z�������B
�@�Ⴆ�Γ������̊J���A�̗p�ŕ��@�o����p�ɂ�������q�������˂��j���Ď��_�o��A�Ƃ������̂͌��������A��w�͔��B���Ă���̂ɉ��́A��Éߌ�i�ׂ͑�����̂ł��낤���B���́A��w�̔��B�A��Éߌ�h�~�V�X�e���̊J���ʼnߌ뎩�̂͌����X���ɂ��邪�A�ߌ��e�F���Ȃ����������܂��Ă��邩��ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă���B
��L������Éߌ딻��W
�T�Q�����A���������i�i�ꕔ���i���܂ށj�������̂͂T�S
�X���A�s�i�������̂�
�R�O�R�����A�������i���͂U�S%�ƂȂ�B
�������A�����ɂ͈�Éߌ떯�������̑S�������f�ڂ���Ă���̂ł͂Ȃ��A���̈ꕔ���f�ڂ����ɂƂǂ܂邩���A���̏��i�����疯����Éߌ�i�����ɂ����錴�����i���𐄒肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���Ƃ��ƁA������Éߌ�i�����ɂ����錴���̏��i���͒Ⴂ�̂ł���B���������P�Q�ňȉ��ɂ����A�P�X�V�U�N����P�X�W�V�N�܂ŊԂ̒ʏ햯�������ɂ����錴�����i�������ςW�U�E�T%�i���Ȕ������܂܂��ΐȔ��������̏ꍇ�͂V�U�E�U%�j�ł���̂ɑ��A������Éߌ�i�����ɂ����錴�����i���͕��ςR�S�E�Q%�ł���B
�]�����A�����f�[�^�ɂ�閯����Éߌ딻��ɂ����錴�����i���������̂��A������W�ɓ�������������s�i������茴�����i�����̕������l�������Ƃ݂��A�����I�ʂ��A�f�ڂ������߂Ɛ������ׂ��ł���B
���Ȃ݂Ɏ��������ɂ��ƁA�P�X�V�U�N����P�X�W�V�N�܂ł̊Ԃ̖�����Éߌ�i�ׂɂ����錴�����i���͕��ςłR�S�E�Q���ł���A�ѓ����O�f���ɂ��ƁA�P�X�W�W�N����P�X�X�V�N�܂ł̊Ԃ̈�Éߌ�i�ׂɂ����錴�����i���͕��ςR�P�E�X���ł���Ƃ���Ă���B
�����P�R�N�S���Q�P���A������Ì������̑�R���v����������V���|�W���[���Ŕ��\�����Ƃ���ɂ��ƁA�����P�Q�N�̈�Éߌ�i�����͑S���łV�Q�V���A�������V�W���A�O�ȂP�V�V���A�Y�w�l�ȂP�P�S���A���`�A�`���O�ȂP�O�X���ȂǂŁA�������i���͂S�V���Ƃ������Ƃł���i�����V���z�[���y�[�W�����P�R�N�S���Q�Q���t�H�j�B
�@��X����Ë@�ւƂ����������̂��A�ʏ�͉��炩�̕a�C�ɂ��������ꍇ�ł���B���͕a�C�ł͂Ȃ����A���ł͕a�@�ɍs�����Ƃ������B�\�h�ڎ�͕a�C�̗\�h�̂��߂Ɏ���̂��A�a�C�ł͂Ȃ����A��Ë@�ւ����{����B���̎��W�f�[�^��́u�a���v�͍L���A�l����Ë@�ւɉ��炩�̂����������Ɏ����������Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���B
���́u�a���v�Ńf�[�^��������A�����ȏ�̂��̂������Ă݂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
���P�Q
�S��
���n���Ԗ��ǂS�S��
�������Q
�P��
�݂���P �W��
�\�h�ڎ�P�V��
���_�����a�P�U��
�b���P
�R��
�x���j�P�P��
�����P�P��
���̂������n���Ԗ��ǂ͕��؎��ɋN������̂ł��邩���A��������؎����̈��ł���Ƃ�����B��������Z������A���؎����̑����͂P
�U�W���Ƃ������ƂɂȂ��A�S�����W�T�Q���̂����̂P
�U�W���A�]���ăf�[�^���A������Éߌ�i�����̖�
�P�X%�����Ɋւ��Ĕ������Ă��邱�ƂɂȂ�B�Y�w�l�Ȉオ�ő�̈�Éߌ�댯���Ă���A�����ӔC�ی��ɉ����̕K�v�����ł��������ƂɂȂ�B
�@�����A�����ɂ����Ĉ�Éߌ�̔������������̂��낤���B�����ĕ��ɂ�����D�w�A�َ��A�V�������u���ҁv�ƌĂׂ��A�Y�w�l�Ȉ�͓��Ȉ��O����ƈႢ�A���ɍۂ��A��ɕ����i�����̏ꍇ�͓�l�B���َ��̏ꍇ�͎O�l�A�l�l�j�̊��҂��������邩��ł��낤�B�V�����̎��S�������������Ƃ����Ă��A���̐����݂���A�����̑�ς����킩��i�A�����J�ɂ����Ă�����͓������A����f�[�^�ɂ����A��Éߌ뎖���̂Q�U�E�U%���Y�w�l�Ȏ����Ƃ���Ă���B�A�ؓN�O�f���T�O�Łj�B
�C���^�[�l�b�g��̌����Ȃ̃z�[���y�[�W�Ŏ������݂���A�l���P�O���l�̎����͂P�X�T�O�N�i���a�Q�T�N�j�ł͌��j�����ʂłP�S�U�E�S�ł��������A�P�X�W�P�N�i���a�T�U�N�j�ȍ~�͈����V�����i�����j�����ʂƂȂ�A�P�X�X�V�N�i�����X�N�j�͂Q�Q�O�E�S�ƂȂ�A���ʂ͐S�����łP�P�Q�E�Q�A��O�ʂ͔]���ǎ����łP�P�P�E�O�ƂȂ��Ă���B
�@�����V�����Ƃ�������w���B��ᇂɂ͗ǐ��̂��̂ƈ����̂��̂������A�����̂��̂͏�琫������ᇂƔ��琫������ᇂɕ�������A�O�҂͂���i���j�ƌĂ��A��҂͓���ƌĂ�邪�A��ʓI�ɂ��A����Ɠ�����܂ޏ�琫������ᇂ��u����v�ƌĂ�ł���i��R���u���w�厫�T�v�����P�V�łP�P�ňȉ��Q�Ɓj�B
�����f�[�^���u����v�Ō��������
�U�Q���A�q�b�g�����B���̂Ȃ��ł͈݂���P�W�����ł��������A
����Ɏ����̂͒_�̂�����A������A�x����e�T���ł���B
�@�f�[�^����ᇂŌ�������ƂQ�P���q�b�g�����B���̂Ȃ��ł����
�T�����ő��ŁA�ق��ɔ]��ᇂ��R���A�Ґ���ᇂ��Q������B
�@�u����v�Ɓu��ᇁv�����v�����
�W�R���ł��邩��A�S�W�T�Q���̂����̂X�E�V��������n���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����ōł��L���Ȃ̂��A�_�̂�����s���m�����������P�X�X�T�N�i�����V�N�j�S���Q�T���ō��َO�����������P�T�R�O���T�R�łł��낤�B
�������͐s�N�ɑ�����ʓI�ȕa�C�ł����A��L�̂悤������̐��������B�������ɑ��Ă��A���ǂ��N�����Ă��钎���؏��̂��߂̊J����p�������s����B���̎�p�O�̍��Ŗ����i�����j�̖����܂Ƃ��ĉ��_�W�u�J�C�����听���Ƃ���y���J�~��S�A�܂��̓l�I�y���J�~��S���g�p�����A����ɂ��V���b�N���N���������҂����S�������A�d�ĂȔ]��Q���N�������Ƃ�����B�l�I�y���J�~��S���A�킪�����L�̂��̂ł����A�y���J�~��S�ƂƂ��ɍ����܂Ƃ��Ďg���Ă��邪�A�A�����M�[�������̕���p�����邩���A�����20���܂ł͖����A�ċz�A�������̐�������i�o�C�^���j���`�F�b�N���ׂ��Ƃ���Ă���i�|��Е��ҁu��p���EICU�Ŏg����܃m�[�g�v�U�Q�ňȉ��Q�Ɓj�B
���W�f�[�^�ł��A�����������Q�W���̂����P�P�������̖��������ł���B�ł��d�v�Ȃ̂��P�X�X�U�N�i�����W�N�j�P���Q�R���ō��َO�����������P�T�V�P���T�V�łł���B
���̎����ɂ����Ă��A�����J�n�T�A�U����Ɉُ킪�N�����A�ً}�[�u���s�������A�]�@�\�ቺ�ǂɊׂ����B���R�����͂��̌����Ƃ��ăA�i�t�B���L�V�[�V���b�N�A���ʍ����V���b�N�A�����V���b�N�A�����_�o���˃V���b�N�̊e�\���𒀎��������������A�����_�o���˃V���b�N�i�����܂ɂ�莩���_�o�̈���ł�������_�o���}�����ꂽ�����A�����̎����_�o�ł�������_�o���D�ʂɂȂ��A��p�Ƃ����@�B�I�h���Ŗ����_�o���˂��N�����ď����A�����~���A�ċz�}���������A����ɂ���_�f�ǂ������_�o���˂������ĐS��~�A�]���Ɏ���j�ƔF�肵���B�l�I�y���J�~���r�̐������i�\���j�ɂ��A����������P�O�Ȃ����P�T���܂ł��Q�������Ɍ����𑪒肷�ׂ��Ə����Ă���̂��A��t���T�������̌��������
�Ō�t�Ɏw�������̂��A���R���A��Ê��s�ł͂T�������ł����A���ɂQ�������Ɍ����𑪒肵���Ƃ��Ă��A���͖̂h���Ȃ������A�Ƃ��Ĉ�t�̐ӔC��ے肵���̂ɑ��A���̍ō��ٔ������A�\���ᔽ������Ήߎ������肳���Ƃ��������A���҂͎����J�n���㍠���猌���ቺ�̌X���ɂ������̂ł��邩���A�Q�������Ɍ����𑪒肵�Ă���Ύ��̂�h�����\��������A�Ƃ��Č�������j�����A���R�ɍ����߂����B
ᄐ����̎��̂Ƃ��čł����낵�����̂̈���u�����ߍ��M�v�ł����A�f�[�^�ɂ͂T������B�����͂���������S���̂ł��邪�A��Ð������A�\�h�A�~���̉\���͂Ȃ��Ƃ������R�őS���A���ґ����s�i���Ă���̂ɑ��A�y���J�~��S�A�l�I�y���J�~��S�����i�����S���͍��x�̏�Q�A�T�������S�j�ɂ����Č��������s�i�����̂͂Q���A���i�����̂͂V���ł���B�@�������ȊO�̎��a�i��ڍ����܁j�ɑ����p�O�̍����Ńl�I�y���J�~���r���g���ăV���b�N�����������ň�t�̐ӔC���m�肵�Ă�����̂�����i�P�X�W�P�N�i���a�T�U�N�j�T���W�����n�ٔ��������P�Q�Q�P���V�S�ŁB�Ȃ���������u�������M�v�ٔ������̌n�P�V�u��Éߌ�i�ז@�v�U�V�Q�ňȉ��A�іL�u����ᄐ��v�O�f�u��Éߌ�i�ז@�v�U�W�P�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@�Ȃ����W�f�[�^�W�O�O���̂����̂U�P���������W�����ł���i�V�E�U���j�A�����R�V�������ґ����i�A�Q�S�����s�i�ł���B
�@���ꂩ�炵�Ă��A��p�ɂ����閃����̖������d�v�ł��邱�Ƃ�����i�|��Е��u��p���̒����\�����ォ��̃��|�[�g�v�W�p�АV���Q�Ɓj�B
�@�V���b�N�͂��낢��Ȍ����ŋN����i��R���O�f��w�厫�T�X�R�S���j�A�l�I�y���J�~��S�A�l�I�y���J�~��S�����͖�����ɃV���b�N���N�����������ł��邪�A����ȊO�ɂ��V���b�N�Ǐ���N�����Ď��S���鎖���������B
�f�[�^�ł��A�L�V���J�C���A���{�i�[���A�X�g�}�C���̖������A�R�������A���e�܂ɂ��V���b�N�������ł������P�W���A����
�����A��p������ʏo���ɂ��V���b�N�������T���ł���B�����s�i���P�R���A���i���P�X���ł���B
�X�e���C�h�܂̓V���b�N���ɑ�ʂɎg�p�����A���̏ꍇ�̕���p�͏��Ȃ��Ƃ���Ă��邪�i�|��O�f�u��܃m�[�g�v�P�V�W�Łj�A���W�f�[�^�ɂ̓A�g�s�[���畆�����҂ɃX�e���C�h��p���g�p���ăX�e���C�h�畆�����N�����������Ŋ��҂��s�i���������ł���P�X�X�Q�N�i�����S�N�j�T���Q�Q�������n�ٔ��������P�S�T�V���V�T�łȂǂX�����X�e���C�h�܂ɂ��������̂ł���B
�A�ؓ��u��Ô���K�C�h�v�L��t�P�V�Q�Łi�S�����䖞�j�����グ�Ă���P�X�W�T�N�i���a�U�O�N�j�T���Q�W�������n�ٔ��������P�Q�P�P���V�V�ł��A�����ԃX�e���C�h�܃v���h�j���p���Ă����������҂��b������œ��@�������A�S����t�͊��҂̃v���h�j����p��m��Ȃ��炻�̓��^�𒆎~���A��ʚb���܂ɂ��肩�������A������N�����������A�X�e���C�h�܂𓊗^�������A���҂͎��S�����������A��t�̉ߎ����m�肵�����̂ł���B
�O�L�X���̊��ҏ��i�͂R���A�s�i�͂U���ł��邪�A����̑傫���X�e���C�h�܂͈ˑ��ǂ�����ǒ�ᇂ��N�������n�̌��ł����A�X�e���C�h�����͍ٔ����������̈�Éߌ뎖���̈�ł���B�ڎ��ɖ߂�B
�@�~�}�a�@�̎��Ԃ�`�����e���r�h���}�����邪�A�~�}�ԂŔ�������Ă��銳�ҁi�~�}���ҁj�̊ւ�鎖���͑����B���̎��W�f�[�^�ł͂R�Q�����~�}���Ҏ����ŁA������̌��ʂ͂R�����A���l�ԉ������ق��͑S���A���S�ł���B���S�A�Ƃ������ʂ������̂́A�������҂��늳�������a�̐�����A�a��̐i�s�������A�����Ȃǂɂ�鐳���f�f�̂Ȃ����O�ɕa�C���[��������A���Ȃ킿���Â���x��ɂȂ邱�Ƃ��������ƂɋN������B�i�ׂ̌��ʂ͔s�i�������̂��P�P���A���i���Q�P���ł���B��t���s�i�̗��R�́A�C���m�ہA�����A�������^�̊e��ӓ��̕s��ۂɂ����̂������A��f������B
�@�킪���̋~�}��Â͂P�X�U�S�N�Q���Q�O���A�����Ȃ��u�~�}�a�@�����߂�ȗ߁v���߂āA�O�Ȍn�𒆐S�Ƃ����~�}�a�@�̍������͂��߂��̂��n�܂�ł��邪�A�P�X�V�V�N�ȍ~�A�~�}��Ñ̐�����������A�P�X�W�U�N�̏��h�@�Əȗ߉����ɂ��A���Ȍn�̋~�}���҂ւ̑Ή����F�߁A�P�X�X�P�N�ɂ͋~�}�~���m�@�����肳��A�~�}�������ɂ��~�}�~���[�u���Ƃ��~�}�~���m���x������ꂽ�B
�@�~�}�a�@�́A�~�}��Âɂ��đ����̒m���y�ьo����L�����t���펞�f�Âɏ]�����Ă��邱�ƁA�~�}��ÂɕK�v�Ȏ{�ݐݔ���L���邱�ƁA�~�}���ɂ�鏝�a�҂̔����ɗe�Ղȏꏊ�ɏ��݂��A�������ɓK�����\���ݔ���L���邱�ƁA�~�}��Â̂��߂̐�p�a���܂��͗D��a����L����a�@�A�f�Ï��̐\�o�ɂ��A�s���{���m�����F�肵�����̂ł���i�~�}�a�@�����߂�ȗ߂P���j�B
�@�����W�߂��f�[�^�̂Ȃ��ł́A�ȉ��̂Q�����~�}�a�@�ɂ����鉞���`���ᔽ�����ɂȂ��Ă���i�~�}��Âɂ��Ă͐���k�B�u�~�}��ÂɊւ���@�I���v���c�K�v�ҁw�V�E�ٔ�������n�P��Éߌ�i�ז@�x�S�P�W�ňȉ��A�����N�u�~�}��Â�����@�����ɂ��āv�w��Éߌ�̎��I�ۑ�x�R�Q�W�ňȉ��A�S�F��u�~�}��Â̖@���I���v�w�㎖�@�w�̕��݁x�R�Q�X�ňȉ��Q�Ɓj�B
�P�X�W�R�N�W���P�X�����É��n�ٔ��������P�P�O�S���P�O�V��
�P�X�X�Q�N�U���R�O���_�˒n�ٔ��������P�S�T�W���P�Q�V��
�@�x���A���ƂȂ������Ȏq�A��̕v�w���@���̊��U�ɗ��邱�Ƃ�����B�G�z�o�̏ؐl�ւ̓��M���U�ł���B
�@�G�z�o�̏ؐl�Ƃ́u���݂̂̓��v�������q����Watch
Tower Bible And Tract Society�Ƃ����A�V���A�����̂ǂ���ɂ������Ȃ��L���X�g���̈�h�ł���B
�@�P�W�V�O�N���A�A�����J�Ő������A�������ہA�A�����ۓ��̌������ϗ��K�͂����B��Ï�Ŗ��ɂȂ�̂��A�������ł���B
�P�X�W�T�N�i���a�U�O�N�j�P�Q���Q���啪�n�ٌ��蔻���P�P�W�O���P�P�R��
�@���̌���ɂ��ẮA�R�c�쐶�u����v�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻��S�I���łP�O�Q�ŎQ�ƁB���̖��ɂ��g�c�M�F�u�M�Ɋ�Â��A�����ۂƈ�Áv���c�K�v�ҁu�V�E�ٔ�������n�P��Éߌ�i�ז@�T�R�ňȉ��Q�ƁB
�@�A�����J�ł͕a�@�̐\���ōٔ����������ăG�z�o�̏ؐl���҂ɗA�����s����A�Ƃ������Ƃł���B���������u�㎖��������v�J���������P�X�R�ŎQ�ƁB
�Q�O�O�O�N�i�����P�Q�N�j�Q���Q�X���ō��ّ�O���@�씻�������P�V�P�O���X�V��
�i�lj�����j���n�ٕ����P�V�N�P���Q�W���������^�P�Q�O�X���Q�P�W��
�@�T�V�̏����������P�R�N�T���R�������A��O�Í����ŋ~����ÃZ���^�[����f�B�S�d�}�ُ�Ŕ퍐�a�@�ɓ��@���A�����̌��ʁA�S�[�Ɋ����d�ʂ˂��铴���߁i�y�[�X���[�J�[�j�̋@�\�s�S�ǂƐf�f���ꂽ�B���Ö@�ɂ́A�l�H�̃y�[�X���[�J�[�A�����݁A�ƁA�o��I�ɃJ�e�[�e����}�����Ĉُ�ȓd�C��H��d�C�Ìł���A�J�e�[�e���E�A�u���C�V�����A�Ƃ����������A��t���͌�҂�I�����A���҂�����ɏ��������B�Ƃ��낪�A���҂̓G�z�o�̏ؐl�̐M�҂������̂ŁA��p���ɂ͗A�����Ȃ����Ƃ���]���A���̌��ʂɂ��Ă͈�Ñ��̐ӔC�͒Njy���Ȃ��A�Ƃ����A���Ӑ⌓�Ɛӏ؏����쐬�A�퍐���Ɍ�t�����B���N�U���U���A��p���s��ꂽ���A�J�e�[�e����}�����A�ُ핔�ʂ��������A�E�S�[�O�ǂɐ��E�������A�o�����ʂŊ��҂͎��S�����B���҂̕v�Ǝq���A���҂ɂ̓J�e�[�e���E�A�u���C�V�����Ƃ������Õ��@�͕s�K���������A��p�O�̐������s���ł������A�o����A�S�X���h�Ō��t�������ł����̂ɍs��Ȃ������A�Ǝ咣���đ��Q���������i�ׂ��N�����B
�@�ٔ����́A�����ߋ@�\�s�S�ǎ��Âɂ̓y�[�X���[�J�[�A�����݂���ʓI�ł��������A��U�A�y�[�X���[�J�[�A�����݂�������ɂ̓J�e�[�e���E�A�u���C�V�����͍s���ɂ����Ȃ邩��A�J�e�[�e���E�A�u���C�V�����I���ɂ͌��͂Ȃ��A�o����̑Ή��ɂ��Ă������̎咣����S�X���h�͍X�ɗA���̉\�������܂邩��A�A���ł��Ȃ����̎����ł͓K���ł͂Ȃ��A�Ƃ��Č����̎咣��r�˂������A�A�������ۂ��Ă��銳�҂ɂ͎��S�̊댯������������A�ʏ�̏ꍇ����w�A���m�A�ڍׂɎ��Ö@�ɂ��Đ������ׂ��ł������̂ɁA�W���I�Ȏ��Õ��@�ł���y�[�X���[�J�[�A�����݂ɂ��Ċ��҂ɏ\���������Ă��Ȃ��A�Ɣ퍐���̐����`���ᔽ��F�߁A�Ԏӗ��T�Q�T���~�ƕٌ�m��p�̔����𖽂����B
�@�˖{�i�u����v�i�N��㎖�@�w�Q�Q���P�Q�S�Łj�́A���̔����́A�A�������ۂ���G�z�o�̏ؐl���҂ɑ��鎡�Â̍����O���ɂ����Ă��Ȃ��A�Ɣ�����ᔻ����B�ڎ��ɖ߂�B
�@���N�u�[���̍����A�n�������́A�E��łȂ����W�c���f������A�����I�ɐl�ԃh�b�N�Ō��N�f�f����l�������B��Ñ����o�c��̈�Ƃ��Đl�ԃh�b�N�̐�`�A�L�������Ă���̂��悭������B���̌��f�͂���Ȃǂ̐��ݓI���a��������A�팱�҂��X�Ȃ鐸�������A���Âɓ�������A���A�a���̐����K���a�����t���Đ����w�����s���A���a�̐[������h�����Ƃ�ړI�Ƃ���B�������ڂ������̎��{�@�ւ�����A�������ԁA�����A��p�Ȃǂɂ���āA���l�����A���������ԕa�@�̓��A��l�ԃh�b�N�ł́A�g�̌v���A���A�A���ցA���������A�����A���A�a�����A�����A���t�w�����A�����w�����A�S�d�}�����A���������g�Q�������A�x�@�\�����A������X�������A�����g�f�w�����A���͊ሳ��ꌟ���A���͌����̂P�U���ڂŁA�����͂���ɍזE�f�i�q�{�j�������i�W�c���f�A�l�ԃh�b�N�̖��ɂ��Ă͉i�J�T�Y�u���N�f�f�v���c�K�v�ҁw�V�E�ٔ�������n�P��Éߌ�i�ז@�x�S�S�P�ňȉ��A�����N�u�l�ԃh�b�N������@�����v�w����^�C���Y�x�W�W�W���Q�W�ňȉ��A�����N�u��Éߌ�̎����I�ۑ�v�S�O�W�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@���̃f�[�^�ɂ͏W�c���f�������R���i���ґ����i�P���A�s�i�Q���j�A�l�ԃh�b�N�������P���i���ґ����i�j�������B
�u���ҏ��i��v
�P�X�W�T�N�X���P�V�������n�ٔ��������P�Q�O�P���P�O�T��
�u�����Ɣ����v����(�S�S�̒j��)�͏]������d�ǂ̚b���ł��������A���a�T�S�N�S���A�Ζ�����W�c���f���A�x�̃����g�Q���ʐ^�ɉA�e������A�f�w�B�e�̌��ʁA�x�Ɉُ킪����Ƃ���ꂽ�̂ŁA�T���V���A��������̔퍐��t�̐f�@�����B�퍐��t�͊��҂����Q���������g�Q���ʐ^��lje���A���t�������s���A�������x���̍��ł���Ƃ��āA�b���̎��Â̂ق��x�����Â̂��ߍR�������𓊗^�����B���̌�A�a�D�]�����A���N�V���ɂ͑��ꂵ���A�b���F�߂�ꂽ�̂ŁA�����P�O���A�����g�Q�������������Ƃ���A�E�x���t�S�̂ɟ��o�t�̒������F�߂�ꂽ�̂ŁA�퍐��t�͘]�����Ɛf�f���Ď���×{�𖽂����B���̌���a��͈������A�W���V���A�s���a�@�ŋ�������鎡�Â�������A�����a�@�Ɉꎞ�I�ɓ��@�����ہA�x����Ŏ�x��Ɛf�f����A�X���Q�T���A�����a�@�ɓ]�@�������A�P�O���P�O������ӎ���Q���N�����A���T�T�N�P���R���A�x����Ŏ��S�����B���҂̍Ȏq���편���v�A�Ԏӗ������v�P���~�̔��������i�ג�N�����B�{�����́A���҂��퍐��t�ɐf�@�����T���V�������A���҂̔x�̎�ᎂ͂T�Z���`�������[�g���ȏ゠��A�@TNM���ނł�T�RN�Q�ő�R��������ł���A�x�؏���̂T�N�������͂P�R���ŁA���҂̂悤�ɂP�O�O�~�����b�g���ȏ�̋��������܂��Ă���ꍇ�͍�����p�͍���ŁA�����̈�Ð������炷��Ɗ��҂̋~���͕s�\�ł���A�܂������̉\�����^�킵�����A�����퍐��t����������x����Ɛf�f���Ă���A���҂͂��K�Ȏ��ÁA�Ō����ꂽ�\���͂���A�Ƃ��Ă��̂悤�Ȋ��҂𗠐�ꂽ���Ҏ��g�̈Ԏӗ��Ƃ��ĂU�O���~���m��A���͊��p�B
�@�{���͏W�c���f��A�~�X���������̂ł͂Ȃ��A�܊p�A�W�c���f�Ŕx����̒����t�����Ă����̂ɁA��������̈�t�������x�����ƌ�f�������ƂɃ~�X�������������ł���B�Ȃ��{���ł͔퍐��t�͊��҂��x����ł��邱�Ƃ�����^���Ă������A���Â��Ă�������Ȃ��Ǝv���A���m���Ȃ������A�Ǝ咣�������A�ٔ����͂��̎咣��F�߂Ȃ������B����ɂ��Ă��A�Ԏӗ��͂��U�O���~�����F�e�ł́A�s�i�ƕς��Ȃ��ł��낤�B
�P�X�X�O�N�P�Q���P�X���É��n�ُ��Îx�����������P�R�X�S���P�R�V��
�u�����Ɣ����v���S�����U�T�̒j�����҂͏��a�T�W�N�V���A�퍐�a�@���l�ԃh�b�N�Ŕ퍐��t�S���ɂ�茒�N�f�f�����B�퍐��t�͑O�ɍ������A���A�a���̂ق��A�����ɕa�ς�F�߁A�����\�ɒ�������̋^���A�咰�t�@�C�o�[�X�R�[�v���K�v�ƋL�ڂ����B�O�͂V���P�T�����珺�a�U�O�N�S���܂Ŕ퍐�a�@�Ɏl����@���A�ʉ@�����ē��A�a���̎��Â������A��������ɂ��Ă͌����A���Â��Ȃ������B���a�U�O�N�S���W���A���ւ�����A�퍐�a�@�ɓ��@�����̌��ʁA��������A�̓]�ڂƐf�f����A���N�T���P�S���A�����A�̑��̐؏���p���A���N�X���P�P���A�މ@���A���a�U�Q�N�P�O���A��������Ĕ��Ɛf�f����A�Ď�p�������A�x�ɓ]�ڂ��A���a�U�R�N�V���P�V���A���S�B�Ȏq�͐l�ԃh�b�N�̌������ʂŒ�������̒����F�߂Ă���Ȃ���A���������A�K�Ȑ����A�w�����̑[�u��ӂ����A�Ƃ��đ��Q���������i�ג�N�B�{�����́A�퍐��t�͌����ɂ����āA�����̕a�ς�F�߂Ă����̂ł��邩��A����咰�t�@�C�o�[�X�R�[�v���������邩�A�ق��̈�Ë@�ւł���f����悤�ɐ����w�����ׂ��ł������̂ɂ�����ӂ����A�Ƃ��ĉ������v�r���̈Ԏӗ��T�O�O���~�i�����͂Q�O�O�O���~�j��F�e�B
�u���ґ��s�i��v
�P�X�W�S�N�T���Q�W���_�˒n�ٔ��������P�P�R�X���X�Q��
�u�����Ɣ����v���ҁi���a�W�N�P�����E�����j�͏��a�T�S�N�X���P�W���A�_�ˎs�����ی����Ő_�ˎs���{�̃G�b�N�X���ԐڎB�e�ɂ��݂��W�c���f���A�����Q�P���A�ُ�Ȃ��A�̒ʒm�����B�Ƃ��낪�A���N�P�P�����{�A���҂͚q�f�A�������N�����A�����Q�X���A�a�@�Ŏ�f�����Ƃ���A�H�哴�݂���i�{���}���V�^�j�Ɛf�f����A���R�O���A���̕a�@�Őf�@�������A���l�f�f�������B���҂͓��N�P�Q���S���A�_�ˑ�w��w���t���a�@�Őf�@�������A���l�Ȑf�f�ŁA�����P�O���A���a�@�ɓ��@���A�����Q�O���A�J����p�������A���҂݂̈���͐i�s���̂��̂ŁA�̑��A�X���ɓ]�ڂ��Ă���A���a�T�T�N�Q���P�O���A���S�����B�����l�S���͕ی����̌��f���ɂ͊��҂͈݂���ɜ늳���Ă����̂ɁA�ی����͂���������Ƃ����A�܂��G�b�N�X���ԐڎB�e�ɂ����@�͕s�m���Ȃ̂ɉ��P�����ɖ��R�Ǝ��{�����ȂǂƎ咣���Đ_�ˎs�Ɉ편���v�A�Ԏӗ����̑��Q���������i�ג�N�B�{�����́A�ی��������{�������f���@�͈�ʓI�Ȃ��̂ł���A�s�K�ł͂Ȃ��A�ی��������҂݂̈���������Ƃ����\���͂��邪�A���ɂ��̍ہA�݂�������t���Ă����Ƃ��Ă��A���҂݂̈���͐i�s���̂��̂ł���A���҂��~���A���������Ƃ͎v���Ȃ��A�Ƃ��Đ������p�B
�@�W�c���f�ɂ����Ă͔x�A�݂Ƃ��Ƀ����g�Q���̊ԐڎB�e���s���Ă������A��t�ɂ�鑽���̃t�C�����̓lje�ɂ͌����Ƃ��Ȃǂ̃~�X�̉\���������A�M�������Ⴂ����A���p�҂͏\���A���ӂ��ׂ��ł���B
�@�P�X�W�Q�N�S���P���ō��ّ�ꏬ�@�씻�������P�O�S�W���X�X�ŁA�w���W�x�R�U���S���T�P�X�ł��A���a�Q�V�N�U���A�Ŗ����E�����E��̒�����N�f�f�ɍۂ��A�ی����ŋ��������g�Q���ԐڎB�e���A�ُ�̒ʒm���Ȃ��������A���Q�W�N�U���̒�����N�f�f�ŏd�ǂ̔x���j�늳���������A�����×{��]�V�Ȃ�����A���a�S�P�N�A���R�ɏ��a�Q�V�N���{�̌��N�f�f�̋��������g�Q���ԐڎB�e�t�C�����������Ƃ���A�x���j�늳�������A�e���ʂ��Ă����A�Ƃ��������̑��Q���������i�ׂɂ����āA�ی����̈�t�����f���s�����ȏ�A���͍����@��̐ӔC�A���@�̎g�p�ҐӔC�͕���Ȃ��A�Ɣ����������A���̍ہA���ʏ����Łu�����҂ɑ��ďW�c�I�ɍs���郌���g�Q�����f�ɂ������̉ߌ�������Ē����ɑΏێ҂ɑ���S����t�̕s�@�s�ׂ̐�����F�߂邩�ǂ����ɂ͖�肪����E�E�E�v�Ɣے�I�ȋL�ڂ����Ă���B���̔����̉���҉��Β��������A�����g�Q���ԐڎB�e�͑�ʏ����̊ȈՒ���̌��f���@�ł���A���f���ʂɂ��Ă͑S���̐M����u�����Ƃ͂ł����i���a�S�R�N�����A�V�O�~���t�C�����̓lje�����Ƃ����͂Q�R�E�T���j�A��f�҂����̂��Ƃ͏\���A���m���ׂ��ł��邩��A�늳���ʼn߂���Ă������ɑ��Q�����������\���͖��ł���A�Ƃ��Ă���i�ō��ٔ��������������я��a�T�V�N�x�@����R�R�U�ňȉ��Q�Ɓj�B
�P�X�X�U�N�P�Q���P�U�����n�ٔ��������P�U�O�R���X�S��
�u�����Ɣ����v���ҁi�����j�͏��a�U�R�N�ƕ������N�A�퍐���c�@�l���j�\�h��{�錧�x���ɂ�����W�c���f�ŋ��������g�Q���ԐڎB�e�����B������̃t�C�����ɂ��ُ�A�e���ʂ��Ă������A�퍐��t�ُ͈�Ɣ��f���Ȃ������B���҂͕����Q�N�W���A���������̌��ʁA�����̌������x����Ɛf�f����A���@���Â������A�����R�N�Q���P�V���A���S�����B�v�Ǝq���편���v�A�Ԏӗ����̑��Q���������i�ג�N�B�{�����͏��a�U�R�N�t�C�����͉A�e�̈ʒu�A�傫�����炵�Ĉُ�A�e�Ɣ��f�͍���ł���A�������N�t�C�����ɂ��Ă��ُ�A�e�ƔF�߂Ȃ������̂͂�ނ����Ȃ��A�Ƃ��Ĉ�t�̉ߎ���ے肵�A�������p�B
�@���̎����ł͂P�O�O�~���t�C�������g���A�lje��t�͈ꎞ�ԂɂS�O�O���̃t�C�������P�E�T�{�Ɋg�債�ēlje���A�S���̓̈�t���d���lje���s���A�^�킵����f�҂ɂ��Ă͉ߋ��̃t�C�����Ƃ̔�r�lje���s���Ă����Ƃ̂��Ƃł���A�ԐځA���ڎB�e�ɂ͑���͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�W�c���f�ɂ����ẮA�a�ψُ킾�������邱�Ɓi���ِ��j�ƁA�a�ψُ���ʼn߂��Ȃ����Ɓi���j�Ƃ������������v���������ɒ��a�����邩����Ԃ̖��ł���A�����Ɏ��������܂���Ղ�����B
�@�푈���ʎ��̂Ŋ�ɏX�������̂��A��p�Ő��`����̂͒N�ł����ꂪ��Ís�ׂ̈�ł��邱�Ƃɋ^��������Ȃ��ł��낤�B�������A�Ⴂ��������d�ق��d�قɂ�����Ƃ������e���`��p�͈�Ís�ׂ��낤���B������p�ɕs��ۂ�����A�{�p�҂ɉߎ�������A���Q�����ӔC����������ł��낤���A����͈�Éߌ뎖�����낤���B�������e���`����Ís�ׂ̈�ł���A��t���i�̂Ȃ��҂��p�����Ĕ��e���`��p���s���A��t�@�P�V���ᔽ�ƂȂ�A�����̑ΏۂƂȂ�i���@�R�P���j�B
�@���N�ی��@�S�R���A�������N�ی��@�R�U���́A�ی����t�͔�ی��҂̎��a�A�����Ɋւ��ĕی����t���Ȃ����Ƃ��K�肵�Ă��邩��A�a�C�A����ł͂Ȃ����e���`�ɂ͕ی��͂����Ȃ����ƂɂȂ�B�������A�ی��O�̎��Ís�ׂ͂ق��ɂ����邩��A�ی��@�K�p�̗L������Ís�ׂ��ۂ��̔��f�w�W�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B
�@��Â͐l���l�ɑ����̍s�ׂł��邪�A��Ö@���̂́u��Ís�ׁv�̒�`�͂��Ă��Ȃ��B��ʓI�ɂ͈�Ís�ׂ́A�A���a�̎��ÁA�y���A�C���a�̗\�h�A�E��`�̋����A�G���Y�A��p�I�فA�I���ÖړI�ł̊��҂ɑ��鎎���A�J��p��̐i���̂��߂Ɏ����̘Z��ނƂ����Ă���i���q�L���̕��ށB���������w�㎖��������P�W�Łx�B
�@�A�����a��������\�I��Ís�ׂ����A���a�A�a�C�Ƃ́A���鍑�ꎫ�T�i�厫��Q�Q�T�X�Łj�́u���̂����̌`�ԁA�����A���_�@�\�ɏ�Q���N�����A��ɂ�s�������A���N�ȓ��퐶�����c�߂Ȃ���ԁv�ƒ�`���Ă���B��Q�̒��x���y����Γ��퐶���͉\�ł��邩��A�����ł́u���́A���_�ɓ��̓I�A���_�I��ɂ���Q�������邱�Ɓv����ȗv���ƂȂ�B�@�����ɒႭ�A�@�����S���Ȃ��悤�Ȋ�́A�{�l�ɓ��̓I��ɂ͗^���Ȃ��Ă��A���_�I��ɂ͗^����ł��낤����A���̕@�����������闲�@�p�͈�Ís�ׂ̈�ł��낤�i��Ö@�U�X���͍L���L�ڎ����ɐf�ÉȖ��������Ă��邪�A�f�ÉȖ��͈�Ö@�{�s�߂���߂�Ƃ���i��Ö@�V�O���j�A�{�s�߂T���̂R��P���́A��Ƃ̐f�ÉȖ��̂Ȃ��ɁA���e�O�����K�肵�Ă���A���̗��@�p�͔��e�O�Ȃ̎���͈͂ł��낤�j�B
�@�@�������Ⴂ�Ƃ��A���ʂ̍����ł��A�l�ɂ���Ă͂������ɂƎv������A��d�ق̏�������d�ق������A��d�قɓ��ꂽ��A����������p���A�L���ȋ���]�ޏ���������B���������̐l�ɑ�����e���`����ÂƂ݂Ȃ���A�{�p�҂͈�Â̊�b�m���A�P�����Ă��Ȃ��Ă��A�{�p��]�҂̓��ӁA���������āA�N�P�s�ׂƂ��Ă̔��e���`��p��K�@�ɍs�����Ƃ��ł���B����͊댯�Ȃ��Ƃł���B��������]�����l���Ȃ��Ă��A�l�Ԃ̊���͋ɂ߂Ĕ����Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�����B�a�C�A���a���L���Ӗ��ɉ����A��Ís�ׂ̈Ӗ����L�������āA���̂悤�ȁA�K�{�I�łȂ��Ă��A�{�l����]������e���`����Â̈�Ɏ�荞�݁A���̉ߌ�͈�Éߌ�Ƃ��ď�������i�{�p�҂���t�Ɍ��肵�A��t�Ɉ�t�Ȃ݂̒��Ӌ`�����ۂ��j�����悢�̂ł͂Ȃ��낤���i���m��w���嗬�ł���킪���ł́A���A���A�}�b�T�[�W�Ȃǂɑ��Ă͂��̌��ʂɋ^�������҂������B�����́u��×ގ��s���v�ƌĂ�邱�Ƃ�����i�A�������u���e���`�̈�Éߌ�v���c�K�v�ҁw�V�E�ٔ�������n�P��Éߌ�i�ז@�x�R�U�S�Łj�A��L�̂悤�ȕK�{�I�łȂ����e���`������Ís���ƌĂ�邱�Ƃ�����i�A���O�f���R�U�T�Łj�B
�@���̃f�[�^����e���`�Ō�������ƂV���A�q�b�g�����B�����P���i�P�X�W�X�N�P�O���P�X�������n�ٔ����w�����x�P�R�T�Q���W�U�Łj�́A���a�S�P�N�A�V���R�������ė��@�p���s�������A�@�̐�[������ŁA���ҁi�j���j�Ɏ��s���������A���a�U�P�N�ɑ��Q���������i�ׂ��N�������A���Ŏ��������Ŕs�i�������̂ł��邪�A�ق��̂U���͑S�āA���ґ����i�ł���B��ۂƂ��ẮA�ٔ����͕K�{�I���Âł͂Ȃ����e���`�ɂ��ẮA�{�p��̒��Ӌ`���A�����`���Ȃǂɂ��A��t�ɂ��Ȃ茵�����ڂ������Ă���悤�ł���B
�u���ґ����i��v
�P�X�V�R�N�S���P�W�����n�ٔ��������V�P�O���W�O��
�u�����Ɣ����v���ق̂�������Ƃ��p�������A�������ĉ��ق��߂���A������ׁ[�����Ă���悤�Ȋ�ɂȂ��Ă��܂����B�{�����́A���ق̊O�|��\�����Ȃ������_�ɉߎ��m��B
�P�X�V�X�N�U���P�����s�n�ٔ��������X�T�V���X�O��
�u�����Ɣ����v��d�ق�����d�ُp���s�������A��p�p�������c�����A�p��A���ɁA�ڂ�ɂɋꂵ�B�{�����́A�������c�����������ƁA�������u���s�\���ł������_�ɉߎ��m��B
�P�X�W�P�N�P�P���P�W�����É��n�ٔ��������P�O�S�V���P�R�S��
�u�����Ɣ����v�������яǂ̂��ߒʉ@���ĒE�т��Ă��������ɑ��A�Ō�t���m�[�x���R���i�Ƃ����d�C�E�ъ��p���ĒE�т������A���ʂ��Ȃ������B�{�����́A���ʂɂ��Ă̐����s����F�߁A�x���������Ô�ȂǍ��v�T�T���~�]�̑��Q����������F�e�B
�P�X�X�S�N�R���R�O���L���n�ٔ��������P�T�R�O���W�X��
�u�����Ɣ����v���w���̐^����Ƃ��ĕ@�����ɑ}�����ĕ@�̒i�����Ȃ������p�������A���҂͂������ĕ@���傫���Ȃ����悤�Ȋ����ŁA���ɂ킽���đ}�����̏�����p�����B�{�����́A����A�ٗ�̎�p���@�ł���̂ɁA�������s�\���ł������_�ɉߎ����m��i�Ԏӗ��S�O���~�F�e�j�B
�P�X�X�T�N�V���P�R�����s�n�ٔ����P�T�T�W���P�O�S��
�u�����Ɣ����v�R�O�̏�������d�ق�����d�ُp���s�������A�p��̊����ǂŗ���p����ᇂƂȂ�A���͂��ቺ�B�{�����́A�p��̎w���w�����s�\���ł��������Ƃ�F�߂Ĉ편���v�A�Ԏӗ������v�Q�V�X�T���~�]�̑��Q����������F�e�B
�P�X�X�U�N�Q���V�������n�ٔ��������P�T�W�P���V�V��
�u�����Ɣ����v�������\���A��ڕ��̎��b�z���p�������A�p���A�������ቺ�����̂Œ��f���A��ɋz���p���ĊJ�������A���ʓI�ɂ͍��\������͖�V�O�OCC�A�E�\������͖�W�O�OCC�̎��b���z���������ƂɂȂ�A���E��ΏہA�ʉ����������B�{�����́A���ڂ̎{�p�̕s��ۂ�F�߁A�Ԏӗ������v�P�O�P���~�]�̑��Q����������F�e�B�ڎ��ɖ߂�B
�@���Y �t�Ƃ́A������b�̖Ƌ����āA���Y���͔D�w�A���傭�w�i�q��ŎY��ɂ��鏗���j�Ⴕ���͐V�����̕ی��w�����Ȃ����Ƃ��ƂƂ���҂ł���i �ی��w���Y�w�Ō�w�@�E�����P�R�N�P�Q���A�ی��t���Y�t�Ō�t�@�Ɖ��̂���A�ی��w�͕ی��t�A���Y�w�͏��Y�t�A�Ō�w�͊Ō�t�A���Ō�w�͏��Ō�t�Ɖ��̂��ꂽ�B�ȉ��A�ۏ��Ŗ@�Ɨ��́E�R���j�A�Ō�t�Ƃ́A������b�̖Ƌ����āA���a�҂������͂��傭�w�ɑ���×{��̐��b���͐f�Â̕⏕���Ȃ����Ƃ��ƂƂ���҂ł���i�ۏ��Ŗ@�T���j�A���Ō� �t�Ƃ́A�s���{���m���̖Ƌ����A��t�A���Ȉ�t���͊Ō�t�̎w�����āA���a�҂������͂��傭�w�ɑ���×{��̐��b���͐f�Â̕⏕���Ȃ����Ƃ��ƂƂ���҂ł���i�ۏ��Ŗ@�U���j�B
�@���͕a�C�ł͂Ȃ����A�l�X�Ȋ댯������A��Ís�ׂɏ�������������B���Y���ɂ��Ĉ�Ö@�͔D�w�Ȃǂ̎��e�l�����X���Ɍ��肵����i��Ö@�Q���Q���j�A���Y���̊Ǘ��҂� ���Y�t�Ɍ��肷��i���@�P�P���j�Ȃǂ̋K���u���Ă���B
�@���Ƃ��� ���Y�t�A�Ō�t�ȂǂɊւ���@�߂̐�삯�͖����R�Q�N�̎Y�k�K���ł���B����Ɏ����ő吳�S�N�A�Ō�t�K�����A���a�P�U�N�ɕی��t�K�������肳��A���a�Q�R�N�A���s�̕ۏ��Ŗ@�����肳�ꂽ�B����B�u �ی��t���Y�t�Ō�t�@�̉���v�w��{��ØZ�@�����P�O�N�Łx�S�S�U�Łj�B
�@ �ی��t�A���Y�t�A�Ō�t�̂Ȃ��ŊJ�Ƃł���̂͏��Y�t�����ł��邪�i��Ö@�Q���A�ی��t���Y�t�Ō�t�@�R���A�R�O���j�A�t�����X�ł͊Ō�t�y�ђj���Ō�m�̊J�Ƃ��F�߂��Ă���i�o�萳���u�t�����X�ɂ����鎩�R�J�ƊŌ쐧�x�Ɍ���Ō�̓Ɨ��I��含�Ɩ@�I�ӔC�v�w�N��㎖�@�w�x�X���T�Q�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@����k�B�̕ɂ��ƁA���a�Q�N�ȍ~�����S�N�܂ł̊ԁA �Ō�t�W�̌Y���A���������͍��v�P�Q�T���A�����Y�������͍��v�R�R���A���������͂X�Q���A�����S�S�����Ō�t���s�i�i�s�i���͂S�V�E�W���j�ł���i����k�B�u�Ō쎖�̂Ɩ@�I�ӔC�v�w�N��㎖�@�w�x�X���X�R�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@CNN.co.jp�̃z�[���y�[�W�ɁA�V�J�S�E�g���r���[�����̓`����Ƃ��āA���v�R�O�O�����̈�ËL�^�͂������ʁA�P�X�X�T�N�ȍ~�A�A�����J�����̕a�@�ŁA �Ō�t�̉ߌ�ɂ��A���Ȃ��Ƃ��P�V�Q�O�l�̊��҂����ɁA�X�T�S�W�l�����������A�����͊Ō�t�̐l���s���A�ߘJ�A�g���[�j���O�s���ł���A�Ƃ̋L�����f�ڂ���Ă���ihttp://www.cnn.co.jp/2000/US/09/10/medical.error.index.html�j�B
�@�Ō�t�͈�t�ƂƂ��Ɉ�Â̏d�v�ȒS����ł���B�]�O�� �Ō�t�͈�t�ɏ]�����A��t�̎葫�A�⏕�҂ł���A�Ƃ����F������ʓI�ł���A���ł���t�̐f�Âɂ��Ă͊Ō�t�͂��̕⏕�҂̈ʒu�ɂ��邪�i�ی��t���Y�t�Ō�t�@�T���j�A�a�l�Ȃǂ̊Ō�ɂ��Ă� �Ō�t������̒m���A�o���A�ӔC�̊�Â��s���Ō�t�Ǝ��A�ŗL�̋Ɩ��ł���A�����ɂ͈�t�̊��͋y�Ȃ��B
�@ �Ō�t�̋Ɩ��͑傫�������Ĉ�Â̕⏕�I�Ɩ��ƓƎ��̊Ō�Ɩ��ɕ�������B���҂�f�f���A�a���f���A���Õ��j���l���A���肵�A�������Ȃ��͈̂�t�̐ꑮ�Ɩ��ł��邪�A��������f�@���A�a���ɂ����銳�҂̉�A���ˁA��̕��p�Ȃǂ� �Ō�t�̈�Õ⏕�s�ׂł���A���@���҂̊ώ@���܂ފŌ�t�̊Ō�͎��Ï�A�ɂ߂ďd�v�Ȗ������ʂ����B
�@���̋Ɩ������͑��ΓI�Ȃ��̂ŁA��t�̎��A�ʂ��\���ł���A �Ō�t�͈�Õ⏕�ƊŌ삾���ő���邪�A��t���v�ɑ��������s�\���ɂȂ�ƁA�Ō�t�̋Ɩ��͈͂͊g�傷��B�A�����J�ł͊Ō�t�������̗v���ƂȂ鎀�S�鍐��������A��̏��������錠����^�����Ă���B������̂́A����ŏI�����}���邱�Ƃ���]����V�l�̑����A�����J�Љ�ł̈�̑Ή���Ƃ����Ă���i�����~�q�u�A�����J�ɂ����� �Ō�t�̐ӔC�v�w�N��㎖�@�w�x�X���S�S�ňȉ��Q�Ɓj�B
�u���Y�t�����v
�@�ŋ߂͕a�@�ł̏o�Y�������A����܂��͏��Y���ł̏o�Y�͌����Ă���B������
���Y�t�͊Ō�t���i�����̂ŁA�����a�@�Ȃǂ̎Y�w�l�ȕa�@�ɋΖ�����҂������A���Y�t�W�������N����B
�@����������Éߌ딻���f�[�^���u���Y�t�v�Ō�������ƂR���A�q�b�g�����B�S���A���ґ����i�i���Y�t���s�i�j�ł���B
�P�X�V�T�N�R���Q�W�����n�ٔ��������W�O�O���W�O��
�u�����Ɣ����v���ؗ\����̂T���O�ɔj�������̂œ��@���������A�w�ɂ��Ȃ��̂őҋ@�����Ă����Ƃ����`�ђE�o�Ŏ��Y�B���ꂪ�a�@�J�ݎ҂̍���퍐�Ƃ��đ��Q���������i�ג�N�B�{�����͖��R�ҋ@�������͕̂s���Ƃ���
���Y�t�̉ߎ��m��B
�P�X�W�R�N�P�O���Q�V���������ٔ��������P�O�X�R���W�R��
�u�����Ɣ����v�ߋ��A�l�H���Y�A�z�������������Ƃ̂���D�w�������a�@�Y�w�l�Ȃɓ��@���A�����A�D�w����ُ�o���̑i���������Y�t���Y���ƌ�����ē�����ɘA�����Ȃ������̂ŁA�َ��͏�ʑٔՑ��������Ŏ��S�����B�{������
���Y�t�Ɍo�ߊώ@�A�`���̜�ӂ�F�߁A�ߎ��m��i�F�e�z�E���e�ɈԎӗ��ȂǂS�T�O���~���j�B
�P�X�W�V�N�P�O���V���_�˒n�ٔ��������P�Q�W�T���P�P�Q��
�u�����Ɣ����v�퍐���Y�t���J�݂��鏕�Y���ŁA�퍐�Y�w�l�Ȉ�t������̂��Ƃɒj���������ARh����q���t�^�s�K���ɂ��j���t�Ŕ]����Ⴢ̌��ǂ��c�����B�j���A���̕���͔퍐�����ɑ��A���Q���������i�ג�N�B�{�����͔퍐
���Y�t�͕�q���t�^�̊m�F���ӂ��A�o����̉��t���y�������_�ɍ��s���s��F�߁A�Ԏӗ����v�P�O�O�O���~�̐�����F�e�������A�퍐��t�ɂ��ẮA�f�Ì_��͈̔͂�����I�ɉ����Đ��������p�B
�P�X�X�W�N�R���Q�R�������n�ٔ��������P�U�T�V���V�Q��
�u�����Ɣ����v��w��w���t���a�@�Ő��܂ꂽ����O���ڂ̐V���������Y�t���������ɂ����Ƃ���S�O����ɐS��~�B��U�͑h���������]����ჂƂȂ�A�W������ɋC�����啨���l�܂点�Ď��S�B�a�@���͓��c���ˑR���Ǝ咣�����B�{�����́A�������ɂ����̂Ŗ��Ȃǂŕ@��������������Ē�_�f��ԂɂȂ�A�q�f�����z�����Ē����������̂Ɛ��F���A
���Y�t�̐Q��I���A�o�ߊώ@�`����ӂ�F�߁A���S�Ƃ̈��ʊW���m�肵�āA���Q���������F�e�i�F�e�z�E���e�Ɉ편���v�Ȃǖ�Q�S�Q�V���~�]���j�B
�@�ȏ�͏��Y�t�ɑ��閯�������ł��邪�A ���Y�t�ɑ���ȉ����Y������������B
�P�X�V�X�N�P���P�Q�������n�ٔ��������X�Q�S���P�S�P��
�u�����Ɣ����v�������Ő���W�S���̓������_�炩���z�c�ɐQ�������Ƃ���A�����������̂ŁA���Y�t�ő������̌o�c�҂��Ɩ���ߎ��v���ŋN�i���ꂽ�B�{�����́A���S�����͕s���ł���A�Ƃ��Ė��߁B
�u�Ō�t�����v
�@��Éߌ�̂��� �Ō�t�̎����A���Ȃ킿�Ō�ߌ뎖���͓K�@�A�s�K�@���킸�A�Ō�t���s�����Ɩ��Ɋւ��Ĕ�������B�Ō�t�̓K�@�Ɩ��͕ۏ��Ŗ@�T���̋K�肩�炵�Ă��A���a�҂Ȃǂ̐��b�i�Ō�Ɩ��j�ƈ�t�Ȃǂ̎w�����ĂȂ��f�Õ⏕�Ɩ��̓��ނł���B�����}������Ɖ��}�̂悤�ɂȂ�B
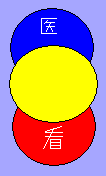
�F�̈�͈�ƁA���Ȃ킿��t���Ɛ肷��A�f�f�A�����Ȃǂ̈�t�������̔��f�A�ӔC�ōs���ŗL��ËƖ�����A�ԐF�̊ł� �Ō�t�̊Ō�Ɩ��ł���A�Ō�t�������̔��f�A�ӔC�ōs���ŗL�Ɩ��ł���B���F�͊Ō�t����t�̎w�����čs���f�Õ⏕�ł���A���̗̈�͈�t���s�����Ƃ��ł��邩��A��t�A �Ō�t�̋Ɩ��̋����A��������ł���i�Ō�t�̋Ɩ��̈�ɂ��Έ�g�N�u�Ō�Ɩ��̖@�I�ӔC�v�w�N��㎖�@�w�x�X���R�X�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@���� �Ō�t���F�̈�̎d��������Γ��Y�Ō�t�͈�t�@�ᔽ�̌Y���ӔC�����Ƃ�����i��t�@�P�V���A�R�P���j�A �Ō�t���s�����F�̈�Ís�ׂɉߌ낪����A���Y�Ō�t�����@�V�O�X���̉ߎ��ɂ���Éߌ�ӔC���ق��A���̌ٗp�傪���@�V�P�T���̎g�p�ҐӔC�Ƃ��A��Ì_���̍��s���s�ӔC�����Ƃ�����B
�@�Ō�ߌ뎖���ōł������̂��ԐF�̊Ō�Ɩ������F�̐f�Õ⏕�Ɩ��ł���B
�@�Ō�Ɩ��Ɋւ��Ă͌����I�ɂ͈�t�̊֗^�͂Ȃ�����A�Ō�t���s�����Ō�Ɩ��ɉߌ낪����A���Y�Ō�t�����@�V�O�X���̉ߎ��ɂ���Éߌ�ӔC���ق��A���̌ٗp�傪���@�V�P�T���̎g�p�ҐӔC�Ƃ��A��Ì_���̍��s���s�ӔC�����Ƃ�����B
�@�f�Õ⏕�Ɩ��ɉߌ낪����A���Y�Ō�t�����@�V�O�X���̉ߎ��ɂ���Éߌ�ӔC���ق��A�����Ɋ�Â��A��t���w���A�w���A�ēӔC�Ȃǂ�Njy�����\��������A���R�̂��Ƃł��邪�A
�Ō�t�A��t�̌ٗp�傪���@�V�P�T���̎g�p�ҐӔC�A��Ì_���̍��s���s�ӔC�����Ƃ�����B
�@���Ō�t�͂��ׂĂ̋Ɩ��Ɉ�t�A�Ō�t�̎w����K�v�Ƃ��邩��A�ԐF�̊Ō�Ɩ����⏕�I�Ō�Ɩ��Ƃ������ƂɂȂ�B���̏�
�Ō�t�̋Ɩ��ɂ������t�A�Ō�t�̎w���̕s��ۂ͖ܘ_�A�w���҂̐ӔC�Ƃ������ƂɂȂ�B�s�҂̏��Ō�t�����@�V�O�X���̕s�@�s�אӔC�����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�u�Ō�t�Y�������v
�@�Ō�t����݂̋Ɩ���ߎ��v���������A���Ȃ킿�u�Y�������v�ɂ͊Ō�t���P�ƁA�܂��͈�t�ƂƂ��ɋN�i���ꂽ��A�w���A�w���A�ēӔC����t�������N�i�����ꍇ������B
�@���L�Ō�t�Y�������͂���������F���f�Õ⏕�Ɩ��Ɋւ�����̂ł���B
�@�P�X�U�R�N�U���Q�O���ō��ّ�ꏬ�@�씻�������R�S�O���R�Q��
�u�����Ɣ����v�D�P�����p�ɍۂ��A��t�Ɏw�����ꂽ�Ō�t���Ö��ł͂Ȃ��A�����ɑS�g�����܃I�C�i�[���𒍎˂������߁A�E�r�������B�Ō�t�͌��R�Ŕ����P���T�O�O�O�~�ɏ������A�{�����͂��̗L�ߔ������x���B
�A�P �X �V
�Q�N�X���P �W����t�n�ٔ��������U�W�P���Q�Q��
�u�����Ɣ����v��t��t���a�@�Ō����ɂ�����̌��ɍۂ��A�Ō�t���A���̍̌����u��z���ɂ������߁A�Ö����ɋ�C��Q�O�OCC���t�����A�����҂���C�ǐ��ǂ��N�����A�]��ǂɂ�����A���S�����B�{���͈�t�ɑ���Y�������ŁA�{�����͈�t���T���~�ɏ������B
�Ō�t�͕��������œ����������Y�ɏ�����ꂽ�i�����̔����͉��L�B���ٔ����Ŕj�������j�B�⑰����̑��Q���������i�ׂ͉��L�̂Ƃ���ł���B
�B�P �X �V
�R�N�T���R �O���������ٔ��������V�P�R���P�R�R��
�u�����Ɣ����v�{���͇A�ɑ���T�i�����ŁA�{�����͔����Y�ɏ��������R������j�����āA��t���łP�O���ɏ������B���̔����ɑ��锻���R�����g�ɂ��ƁA�Ō�t�ɑ��锱���Y�������j������A
�Ō�t���łP�O���ɏ�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B
�C�P �X �V �S�N�U���Q�P���_�˒n�ٓ��x�����������V�T�R���P�P�P��
�u�����Ɣ����v���{�s���a�@�ŏ\��w����ᇊ��҂̎�p���ɏz��������̏C�{���x�Ǝ_�f�{���x���ψ��S�����Ō�t���Ԉ���Đڑ��������߁A���҂����S�B���͈�t�ɑ��鎖���B�{�����͈�t�̈��S�m�F�`���ᔽ���m�肵�A�łU���ɏ������B
�Ō�t�͕ʌ��Ŕ����Y�ɏ�����ꂽ�B
�D�P�X�V�S�N�U���Q�X���D�y�n�ٔ��������V�T�O���Q�X��
�u�����Ɣ����v�����NJJ���ǂɑ��鍪����p�̍ہA�Ō�t���d�C���X�̒[�q����ڑ��������߁A�E���ɔM�����A���ؒf�B��t�ƊŌ�t���N�i���ꂽ�B�{�����́A�Ō�t�̉ߎ��m�肵�A�����T���~�B��t�ɂ��ẮA���̂悤�ȋH�Ȍ�ڑ��ɂ��Ĉ�t�ɗ\���`���͂Ȃ��A�Ɩ��ߔ����B
�E�P�X�V�U�N�R���P�W���D�y���ٔ��������W�Q�O���R�U��
�u�����Ɣ����v�{�����D�����ɑ���T�i�R�����B�T�i���p�B�������ێ��B
�u�Ō�t���������v
�@ �Ō�t�̃~�X�ő��Q���������̖����������N�����Ă��A�K�������Ō�t���퍐�ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��B�J�ƌ��̂Ȃ��킪���̊Ō�t�͕K���N���Ɍٗp����Ďd�������Ă���B�]���� �Ō�t�̃~�X������ꍇ�A��Q�҂͊Ō�t�@�V�O�X���̕s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������i�ׂ̔퍐�ɂ��邱�Ƃ��ł��邪�A�����\�̖͂R�����Ō�t�����A���̌ق���ł���J�ƈ�Ƃ��A�a�@�i��Ö@�l�`�Ԃ̂��Ƃ������j�A�ꍇ�ɂ���Ă͒n�������c�́A���Ȃǂ�퍐�ɂ���B �Ō�t���퍐�ɂ��ĊŌ�t�ƌٗp�嗼�҂������퍐�ɂ��邩�A����Ƃ��ٗp�傾����퍐�ɂ��邩�ǂ����͌����̍l���Ɛ�p����ł���B�퍐�Ƃ��ꂽ�ٗp�傩�炷��ƊŌ�t�������퍐�ɂ��Ă��������]�܂����B�����łȂ��Ɣ퍐�łȂ� �Ō�t���I���ɂȂ�A�i�ׂɋ��͂��Ȃ����Ƃ����邩��ł���B
�@���̖�����Éߌ�i�ׂ̃f�[�^�� �Ō�t�Ō�������ƂP�X���A�q�b�g�����B���̂����D�G�H�I�L�M�Q�R���ԐF�̊Ō�Ɩ��Ɋւ�����̂ł���A���̗]�����F�̐f�Õ⏕�Ɩ��Ɋւ�����̂ł���B�Ȃ����Ō�t���֗^���������������Ɋ܂܂��B���̃f�[�^�ɂ́A�ߎ����� �Ō�t���퍐�ɂ��ꂸ�A���̌ٗp�傪�퍐�Ƃ��ꂽ���́A���n�ȊŌ�t���g�p������t�����̓_�̉ߎ��Ŕ퍐�Ƃ���Ă�����̂��܂܂�Ă���B
�@�P�X�U�T�N�V���P�S�������n�ٔ��������S�Q�W���U�V��
�u�����Ɣ����v�C�ǎx���̐���T�����̗c���Ɍ��K�Ō�t�����܂����܂����Ƃ��뒂�������A���e�����K�Ō�t�ƌٗp��̈�t��퍐�Ƃ��ĈԎӗ������i�ג�N�B�{�����́A���K
�Ō�t�̃~�X�ƈ�t�̉ߎ��i���ܓ��^�ɂ��Ă̎w���~�X�j��F�߂ĈԎӗ����v�R�O�O���~�F�e�B
�A�P�X�V�P�N�R���P�T����t�n�ٍ��q�x�����������U�Q�S���R�S��
�u�����Ɣ����v��L�Ō�t�Y�����������A�B�̐�t��̌��~�X�����̖����i��R�����ł���B�����́A��t��t���a�@�Ō����ɂ�����̌��ɍۂ��A�Ō�t���A���̍̌����u��z���ɂ������߁A�Ö����ɋ�C��Q�O�OCC���t�����A�����҂���C�ǐ��ǂ��N�����A�]��ǂɂ�����A���S�����B
�Ō�t�A��t�Ƃ��łP�O���ɏ������Ă���B�{�i�ׂ̔퍐�͍��B�{�����́A�Ō�t�A��t�̉ߎ����m�肵�A�ߎ��̑傫�����ƂȂǂ���Ȏq�A����̈Ԏӗ����v�W�O�O�O���~���܂ލ��v�P���Q�W�S���~�]�̐�����F�e�B��t�̌��~�X�����ɂ��Ẳ���E�F�ÖؐL�E�ʍ��W�����X�g��Éߌ딻��X�U�ŁB
�B�P�X�V�Q�N�R���R�P���������ٔ��������U�U�R���U�T��
�u�����Ɣ����v��L��t�n�ٍ��q�x�������̍T�i�R�����ł���B�{�i�ׂ̔퍐�͍��B�{�����́A�Ԏӗ����P�R�O�O���~�Ɍ��z�A�편���v�Q�R�O�O���~�]��F�߂��B
�C�P�X�V�Q�N�V���Q�P�������n�ٔ��������U�X�P���U�W��
�u�����Ɣ����v���������쑽���a�@�Ō�t�����Í܃O�������i�v���r�^�[���j�����S�NJ��҂̏��M���ɋؓ����˂������Ƃ���A��t���_�o�ɐZ�����A�_�o��Ⴢ��N�������B���҂͕������ɑ��Q���������i�ג�N�B�{�����́A���˕��ʑI���~�X��F�߁A�편���v�A�Ԏӗ����v�S�S�V���~�]�F�e�B
�D�P�X�V�Q�N�X���P�W���R�`�n�ٔ��������U�X�Q���W�T��
�u�����Ɣ����v��ʎ��̂Ŏ�p���ɓ��@���̊��҂��K�X�X�g�[�u�̕s���S�R�Ăň�_�����łɂ�����A���N�㎀�S�B�⑰����t�ɑ��Q���������i�ג�N�B�{�����́A��t�̊Ō�t�ɑ���w���s�\���A����
�Ō�t�̊Ď���ӂ𗝗R�ɁA�편���v�A�Ԏӗ��ȂǍ��v�S�S�V���~�]���m���m�B
�E�P�X�V�Q�N�X���P�X���R�`�n�ِV���x�����������U�X�S���X�W��
�u�����Ɣ����v�ݒ�ᇂ̊��҂��J����p��T�Ԍ�Ɋ�a�̒��Ԗ��Ö������ǔ��a���A���S�B�⑰�͈�t�ɑ����Q���������i�ג�N�B�{�����́A��a�ł���A�\���\�����Ȃ��A�Ɛ������p�B�Ȃ����̈�t�͖����i
�Ō�t���l�l�g���Ă������A�����̊Ō�t�͂��̊��҂̎��ÂɊ֗^���Ă��Ȃ������̂ŁA���̓_�ɂ��Ă̌����̎咣���̗p����Ȃ������B
�F�P�X�V�R�N�X���Q�U�������n�ٔ��������V�P�X���T�Q��
�u�����Ɣ����v�D�w���o�Y���Ɏq�{��ǂ��j�đ�o�����A���S�B�⑰�͈�t�ɑ��Q���������i�ג�N�B�{�����́A��t�����K�Ō�t�ɎY��Ǘ��ώ@��C���A����
�Ō�t���ُ�o���ɒ��ӂ��Ȃ������_�ɉߎ���F�߁A�ӔC�m��B
�G�P�X�V�T�N�T���Q�W�����˒n�ٔ��������W�O�P���W�O��
�u�����Ɣ����v�N�b�V���O�a�Ō����F���a�@�ɓ��@���̊��҂ƊŌ�t���{�[���V�ђ��Ƀ{�[���̎�荇�������Ċ��҂��]�|���A������܁B���҂͈�錧�ɑ��Q���������i�ג�N�B�{�����́A
�Ō�t�w����̉ߎ��͔F�߂����A�V�Z���̎��̂ł���Ƃ��Ĉ�@����ے肵�A�������p�B
�H�P�X�V�U�N�X���Q�X���������ٔ��������W�R�U���T�U��
�u�����Ɣ����v��L���˒n�ٔ����̍T�i�R�����B�{�����́A���R���f���w�����A�T�i���p�B
�I�P�X�V�U�N�P�P���Q�T�������n�ٔ��������W�T�X���W�S��
�u�����Ɣ����v���t���a�@�ɓ��@���̐��x���E�����̂���S�������̓��@���҂���t�A�Ō�t�̐��~���������A��э~�莩�E�B�⑰�����Q���������i�ׂ����ɒ�N�B�{�����́A�Ō�̌��E���Ă���s�ׂł���A�Ɛ������p�B
�J�P�X�W�R�N�W���Q�Q�������n�ٔ��������P�O�X�V���V�O��
�u�����Ɣ����v���ǖ�����Q�œ��@�����������҂��P���P�R���A�}�X�N�����ɂ��S�g�����ŊJ����p�������A�������オ�S�������A���n�ȊŌ�t���s�������߁A���C�o�b�N�̑���s���̂��ߎ_�f�������s�\���ƂȂ�A�]�������_�f��Ԃ������A��������o�������A���̌�̏��u�̕s�K�Ƒ��܂��Ċ��҂͂P���Q�O���A���S�����B�⑰�͌ٗp��̈�Ö@�l�ɑ��Q���������i�ג�N�B�{�����́A��t�������Ǘ���s����
�Ō�t�ɔC�������Ƌy�ю���[�u�̕s�K�𗝗R�ɐ����F�e�B
�K�P�X�W�V�N�P�P���Q�V���L���n�ٔ��������P�Q�W�V���P�Q�S��
�u�����Ɣ����v�D�w���j�������̂ŁA�ߌ�X���R�O���A�퍐��t���J�݂̎Y�w�l�Ȉ�@�ɓ��@���A���̌�A�j���A�o��������A�w�ɊԊu���Z���Ȃ����̂ŁA�����̏��Ō�t�Ɉ�t�̐f�@�A�S�������v���������A��
�Ō�t�͈�t�ɘA�������A��������̏��u�������A�����ߑO�U���R�O���ɔD�w�̗v���ŏ��Ō�t���َ��̐S���������A���łɐS���Ȃ��A�����ߌ�P���S�T��������؏o�����B���e�����s���s�܂��͕s�@�s�ׂɊ�Â��A�퍐��t������퍐�Ƃ��Ĉ편���v�A�Ԏӗ��Ȃǂ̑��Q���������i�ׂ��N�B�{�����́A�퍐��t�̔D�w�ɑ���o�ߊώ@��ӂ𗝗R�ɈԎӗ��ȂǍ��v�S�T�O���~�F�e�B�{���ł͒S��
�Ō�t����t�A�Ō�t�̎w���ŋƖ����s�����Ō�t�ł��������߁A���̉ߎ��ł͂Ȃ��A��t���g�̜�ӂ��������R�ɂ���Ă���B
�L�P�X�X�R�N�P�Q���Q�S���_�˒n�ٔ��������P�T�Q�P���P�O�S��
�u�����Ɣ����v�Ō�t���ɒO�s���a�@�ɓ��@���̐�V����ӈُ�̂S�̒j���ɐl�H�ċz��̒E����m�炷�A���[���̃X�C�b�`��ON�ɂ��邱�Ƃ�Y�ꂽ���߁A�ċz�킪�͂��ꂽ���Ƃ̔������S�O���x��A�j�����ċz�s�S�Ŏ��S�B���e���ɒO�s����ɈԎӗ������i�ג�N�B�{�����́A
�Ō�t�̉ߎ��m�肵�A�Ԏӗ��ȂǍ��v�P�U�T�O���~�F�e�B
�M�P�X�X�S�N�X���Q�W���F�s�{�n�ٔ��������P�T�R�U���X�R��
�u�����Ɣ����v�R�T�����̗c���i�g���P�E�O�Q���[�g���j���㕠��������ᇂŎ�����ȑ�w�a�@�ɓ��@���A�������N�P�O���Q�T���A�Ō�t���������S��ň͂܂ꂽ�x�b�h�i���P�E�O�P���[�g���A�c�Q�E�O�P���[�g���A������}�b�g���X�܂ł̍����O�E�U���[�g���A�}�b�g���X�̌����O�P���[�g���A������S���[�܂ł͂P�E�R�P���[�g���j�Ŋ��҂ɖ{��ǂ�ŕ������Ă������A���p�Ńx�b�h�𗣂��ۂɁA���i�ɃZ�b�g����ƍ����O�E�Q�V�T���[�g���A��i�ɃZ�b�g����ƍ����O�E�V�P���[�g���ɂȂ�]���h�~�̈��S��𒆒i�ɃZ�b�g�������A�X�g�b�p�[���͂���A���҂̓x�b�h����]�����A�]���o���Ȃǂ̏d�����A�����Q�N�Q���T���A���S�����B���҂̕���Ō�t��������ȑ�w��퍐�Ƃ��đ��Q���������i�ג�N�B�{�����́A
�Ō�t�̓X�g�b�p�[���b�h�����b�h�Ɋm���Ɋ|�����Ă��邱�Ƃ̊m�F��ӂ����A�Ƃ��ĉߎ����m�肵�A�Ԏӗ��ȂǍ��v�T�T�O���~�̐�����F�e�B
�N�P�X�X�T�N�S���P�P�������n�ٔ��������P�T�S�W���V�X��
�u�����Ɣ����v���a�U�P�N�Q���Q�W���A�퍐��@�Ŏ{�s�̎q�{�؎�E�o��p�ɍۂ��A���Ŗ����Ƃ��ăJ���|�J�C���𒍓����A�S�g�����܂Ƃ��ăt���[�Z�����z�����������A��p���Ɋ��҂͌ċz�}����ԂɂȂ�A�S��~�����B���҂͂��̌�A�h���������]�@�\��Q���A�S���S���A���S�����B�⑰���J�ƈ�t��퍐�Ƃ��āA���Q���������i�ג�N�B�{�����́A�����̈ʓ�
�Ō�t�����n�ŁA���҂̌ċz�}���������Ƃ��A�퍐��t�͖��n�ȊŌ�t���g�������Ƃ̔��F�߁A�����F�e�B
�O�P�P�X�U�N�U���Q�W�����n�ٔ��������P�T�X�T���P�O�U��
�u�����Ɣ����v���{�ԏ\�����t�Z���^�[�̌��ۋΖ��Ō�t�������ɉ������퍐�̉E�O�r���ɍ̌��p���ːj����h�����Ƃ���A�ɂ݂�����A�퍐�j���͍��O�r��_�o�����Ɛf�f���ꂽ�B�����Ŕ퍐�͓���
�ɑ����Q��������L����Ǝ咣����̂ŁA���Ԃ͔퍐�ɑ����s���݊m�F�i�ׂ��N�����B�{�����́A�O�r��_�o�Ԃ�\�����Ē��ːj��O�r�ɐ��h���邱�Ƃ͈�Ð�����A�s�\�ł���A�Ƃ���
�Ō�t���ߎ���ے����A�����̍��s���݊m�F������F�e�B
�P�P�X�X�W�N�P�Q���Q�����n�ٔ��������P�U�X�R���P�O�T��
�u�����Ɣ����v�}���ݒ����̏������҂��퍐�a�@�ɓ��@���A�Ō�t���獶��ɓ_�H��������A���ɂ�����A���҂͔��ː������_�o���ىh�{�ǂɂ��������B���҂͔퍐�a�@�����Q���������i�ג�N�B�{�����́A
�Ō�t�ɂ͊��҂��_�H�p���ːj�h�����ɒɂ݂�i�����̂����ē����ꏊ�ɐj���h�������_���ߎ����m���B
�Q�P�X�X�X�N�P���P�S�����n�ٔ��������P�V�O�O���P�T�V��
�u�����Ɣ����v�P���a�҂ő̂����܂�ƂĂ삪�N����₷���P�R�̒j�������@��̕a�@�œ������A�t�Y�Ō�t���P�T���A�������痣�ꂽ�Ԃɒj���͂Ă���N�����A�M�������B�⑰���O��C��Еی���������ɑ������ی����̎x���������B�{�����́A
�Ō�t���ߎ��i�Ď��`���ᔽ�j���m�����A�ی���Ђ̖Ɛӎ咣��F�߁A�������p�i���L�P�X�X�X�N�X���P����㍂�ٔ����Ŕj�������j�B
�R�P�X�X�X�N�X���P����㍂�ٔ��������P�V�O�X���P�P�R��
�u�����Ɣ����v��L���n�ٔ����̍T�i�R�����B�Ō�t�̉ߎ��i�Ď��`���ᔽ�j���m�����A�ی���Ђ̖Ɛӎ咣�r�˂��A��������j�����A�����F�e�B
���L�E�Q�O�O�T�N�X���P�X���A�{�z�[���y�[�W�@���̕��Ɂu�Ō�ߌ�̖@�I�ӔC�v���f�ڂ����B�@
�@���A���S�����̃g�b�v�͊��ŁA���ɓ��{�l�̎O���̈�͊��Ŏ��S����Ƃ����Ă���B�ȉ��͍R���܂Ɋւ��锻��ł���B
�@�@���n�ُ��a�T�V�N�R���Q�T�����������P�O�U�O���P�O�U�Łi�ے��j
�u�����v���ҁi�Q�W�̏����j�͏��a�S�S�N�T���U���A�D�P�O�����̐f�f�������A�E���فi���ˋN�ł����O�т̏�炪�ُB���ĖE��Ɏ�傷�鎾�a�B�P�`�Q������������Ƃ����Ă���j�̋^���œ��N�T���Q�R���A�������a�@�ɓ��@���A�����R�O���A�q�{���e������p���s�����Ƃ���A�E���ق��O�я���ɕω����Ă���Ƌ^��ꂽ�̂ŁA�R����
MTX�i���g�g���L�T�[�g�E��ӝh�R�܁j���10mg�T���ԓ��^�����B�X���R�������犳�҂͍��M���A�����������ǂ��A��ʕ���A���������u�ɁA�q�f�A�����������A�����V���A���S�����B�⑰���́A�R���܂̕���p�ɂ�鎀�S�Ƃ��đ��Q���������i�ג�N�B�u�����v
MYX�ɂ́A���O�Ȃǂ̔S���т��A�����A������Q�ȂǁA���Ȃ苭�x�̕���p�����邪�A���S���̍����O�я���ɂ͂T�O�`�U�O���A�j�E���قɂ͂P�O�O���̊��𗦂������A�X�ɏ��a�S�Q�N���A��ُ�����A�O�я���A�j��ق𑁊��ɗ}�����邽�߁AMTX��\�h�I�ɓ��^������@�����݂��A�w���ʂŎx�������悤�ɂȂ����B�{���ł͎�p���x��Ă��邱�ƁA��p�œE�o�������e�������Ă��邱�Ƃ����O�я���ɕω��̉\��������A���҂̑S�g��Ԃ͈��������Ƃ͂����A�\�h�I��MTX�̍Œ�p�ʂ𓊗^�����̂͂�ނ����Ȃ��[�u�ł���A�R���܂ɂ�鎀�S�ƔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B�������p�B�A�@���l�n�ٕ����P�Q�N�S���Q�U�����������P�V�R�S���V�P�Łi�m���j
�u�����v���ҁi���a�R�N���܂�̒j���j�͕����S�N�T������ʕ��Ɣ�含�S�؏ǂő�a���B��a�@�ɒʉ@���Ă������A�����U�N�R�����A�P�A���ꂪ�o���̂Ō��������Ƃ���A�x���̋^��������A���N�S���P�P���A�_�ސ쌧������Z���^�|�ɓ]�@�B�����̌��ʁA���҂͗]���������̖����x���ł��邱�Ƃ������B���N�T���P�P���A���a�@�ɓ��@���A�T���P�Q���A�R���܂Ƃ��ăs�V�o�j�[���i����ٓI�Ɖu�����܁j�ƃV�X�v���`���i�������܁j�����o���ɒ������^���A�T���Q�T���A�V�����R���܂ł��鉖�_�C���m�e�J���i�g�|�C�\�����[�[�T�j�Q�܁j
96mg�ƃV�X�v���`��128mg�p���^���A�X�ɂU���P���A���_�C���m�e�J��96mg�𓊗^�����B���̂V����̂U���W���A���҂͋}���t�s�S�Ŏ��S�����B�ȓ��̈⑰�����Q�����i�ג�N�B�u�����v�T���Q�T���̍R���ܕ��p���^�ł���܂ł��ቺ���Ă������҂̐t�@�\����w�ቺ���A�U���P���̉��_�C���m�e�J���̓��^�ł��̐t�Ő��̂��ߐt�@�\�͍X�Ɉ������A�t�����牖�_�C���m�e�J���̔r�o���ł����A�̓��ɒ������ꂽ���߁A����p�ł��鍜���}����p�������\��Ĕs���ǃV���b�N����N���A���̂��߂̌����ቺ�ɂ��t�����ቺ�������A�}���t�s�S��̂Ŋ��҂͎��S�����B�t�@�\���y�����ĉ��_�C���m�e�J�����ē��^���邱�Ƃ͌��ł���B���҂͗]���͂R�����ł���A���Q�Ƃ��ĔN���ɂ��Ă̈편���v�r�����Q�R�U���~�]�A���҂̈Ԏӗ��T�O�O���~���m��B
�B�@���É��n�ٕ����P�P�N�S���W�����������P�V�R�S���X�O�Łi�m���j
�u�����v���ҁi���a�P�R�N���܂�̏����j�͕����S�N�R���A�w���ɒɂ݂������Ĉ�Ö@�l��m��o�c�̃N���j�b�N�Ŏ�f�����Ƃ���A�����̌��ʁA�a���U
c�{�V�^�̏����݊��Ɣ������A���@�̂����A���N�S���P�V���A�݂̐؏���p���A���N�T���P�U���A�މ@���A�����O���A�R����UFT�i��ӝh�R�܁j������U�J�v�Z���P�T�ԕ�����������ĕ��p���A���̌�܉�ɂ킽���ē��ʂp�����ق��A�U���S���ȍ~�A���v�l��A�R���܃}�C�g�}�C�V��C�i�R�������j��4mg�_�H���^���A�X�ɓ��N�U���Q�X���A�N���j�b�N�ɍē��@���������Ƃ��̗����A�R���܂T�|FU�i��ӝh�R�܁j1250mg�̓_�H���^���A�V���Q���A�މ@�������A���ɂ̂��ߗ��R���A�āX���@���A�������������A�Ǐ��P����Ȃ��ŁA�V���V���A���m��ȑ�w�t���a�@�ɓ]�@�����B���W���A�ċz��~���A�����P�W���Ɏ��S�B�v���T�������Q���������i�ג�N�B�u�����v���҂̂悤�ȑ����݊��ɑ��Ă͉��w�Ö@�͖��Ӗ��ł�����肩�A����p�̕��Q�ɂ��L�Q�Ȃ��̂ł���̂���ʓI�m���ł���̂ɁA
UFT�y�у}�C�g�}�C�V��C�̕���p�ɂ�艺���A�����������Ȃǂ̏Ǐo�Ă��銳�҂ɑ�ʂ̂T�|FU��lj����^�������ł���B�편���v�r�����Q�R�W�O�R���~�]�A�⑰�̈Ԏӗ��Ƃ��č��v�Q�S�O�O���~�A���V��p�P�R�O���~�A�ٌ�m��p�S�O�O���~���m��B�@�ŋ��A�����f�ڂ̖�����Éߌ딻�����͌����X���ɂ���B����͖�����Éߌ�i�����������������߂ł͂Ȃ��A������Éߌ�i���������������̂łȂ��Ȃ������A������Éߌ딻�������W����Ȃ��Ȃ������߂��A�������́A���W����Ă��f�ڔ���ɑI��Ȃ���������ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă���B
�����A�}�X�R�~�ɂ���Éߌ�������ǂ��납�A�����X���ɂ���A�����̊S���W�߂Ă���B
�V��Љ�̌����A��X����Ë@�ւɂ����������\���͑��傱�������A�����Č��邱�Ƃ͂Ȃ��B��w�͐i�����Ă��A���ꂾ���댯��s�ޏ��u�A����̋@��͑��������ł��邩��A��Éߌ�͕s���Ȃ��̂悤�Ɏv����B
�@�]���Ĉ�Éߌ�̖h�~�����ł͂Ȃ��A�N��������Éߌ뎖���́A�K���ŁA�v���ȉ������@���H�v����K�v������B
�@���݂ł����L�̂悤�ɁA��t��Ɉ�Î��̏����@�\�����݂���B���������������ٌ�m��ƈႢ�A��t��͉������R�̔C�Ӓc�̂ł���A���̑����͎Вc�@�l�ł���i�Ⴆ�A�鋞��w��t��Ȃǂ͎Вc�@�l�ł͂Ȃ��j�A���{��t��A�s���{����t��A�S�s��E�n���t����邪�A����ɂ͊J�ƈ�A�Ζ���̑���������Ă���A��̕ی�@�P�S���P���́A�s���{����t��̎w�肷���t�i�w���j���l�H�����p�����邱�Ƃ��ł���A�ƒ�߁A��t��͖@�I�ɂ��F�m����Ă���B
�@���̓s���{����t��́A��Éߌ�Ɋ�Â���t�A�a�@�̑��Q�����ӔC������ی����̂Ƃ����Éߌ딅���ӔC�ی��ƌ��ѕt�����u�㎖���������ψ���E�E���̖��͓̂s���{���ɂ��قȂ�B�Ⴆ���s�{��t��͈�Î��̑v��u���Ă���B
�@��L��Éߌ�ӔC�ی��͓��{��t��ی��_��҂Ƃ��ĕی���Ђƒ���������{��t���t�����ӔC�ی�����\�I�Ȃ��̂ł���A��ی��҂͉����t�ł���A�ی����͓��{��t��̉���x�����Ă���B
�@��Éߌ낪��������ƁA��t�̏�������s�Ȃǂ̈�t���ʂ��ēs���{����t��Ɂu���̕��v����o����A����t��́u�㎖���������ψ���v�ŐR�����A�����z���傫���ꍇ�͓��{��t��̔����ӔC�R����R�����A�ψ���A�R����̌���ɏ]���Ĉ�t�͊��ґ��Ƃ̕��������ɓ����邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@��t��ɓ���Ȃ��a�@�͕ʂ̈�t�����ӔC�ی��ɉ������邪�A���̕ی����x�����ɂĂ��s���{����t��̐R����R�����邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@��L��Î��̏����ψ���͔����ӔC�ی����x��w�i�ɂ�����̂ł��邩��A���ґ�����̐\���͌����I�ɂ͔F�߂Ă��炸�A���������Éߌ땴���̖��ԏ����@�\�Ƃ��Ă͌��E������B�܂��ψ��̑命���͈�t��̉���A���Ȃ킿��t�ł���A�������Ɍ����悤�i��t��̈�Éߌ땴�������@�\�ɂ��Ă͓��c�N�K�ҁu��Î��̑Ώ��}�j���A������l���ЂP�U�S�ňȉ��A���C�����u��t��̈㎖���������@�\�v�ٔ�������n�P�V��Éߌ�i�ז@�T�Q�X�ňȉ��A���u��t��̈㎖���������@�\�̊T�v�v����ٔ��@��n�V��Éߌ�V���{�@�K�R�Q�T�ňȉ��Q�Ɓj�B
�i�P�j��w������̉��v
�@��ÊW���_�����w���̓��ɂ��������ޕK�v������B�܂���t�̓��ɂ͖������������paternalism���c���Ă���B����@����ɂ͈�w����������v����K�v�����낤�B
�i�Q�j��ʂ̊��҂�����鍑���A�s���a�@�N���X�̑�a�@�A��w�t���a�@�ł͈�Éߌ�̔����͕K�{�ł���B�]���Ă����̕a�@�ł͕K����Éߌ��V�X�e�����\�z����K�v������B���̃V�X�e���͈�Éߌ�̖h�~���ł͂Ȃ��A��Éߌ낪���������ꍇ�̑Ή�����܂݁A���ׂȉߌ�͂��̃V�X�e�����ʼn��������̂��]�܂����B���ґ��̃N���[���ɑ��ẮA�悸�a�@���Ő�������s���K�v������B�����ז���������A�����w�a�@�Ŕ��������A��p���Ɋ��ҁi�c���j�����S�������̂ŁA�⑰�A���̑㗝�l�ٌ�m�ɑ����������J���A���̂��s���ł��������Ƃ̗��������āA�i�ג�N��������ꂽ�o��������B
�@���ҁA�⑰������Éߌ�i�ׂ��N���闝�R�Ƃ��ẮA�����A���̌����̋����A��t�A�a�@���ɕs��ۂ��������ꍇ�̎Ӎ߁A�Ĕ��h�~�̎O����������B�u�Ӎ߁v�͓��{�I�ȐF�ʂ��Z�������A���ҁA�⑰�����炷��ƒɐȗv���ł���A��t�A�a�@���ɔ��邱�Ƃ����m�ɂȂ�A���K���������悢�A�Ƃ����l�����̂āA�^���ɎӍ߂̈ӎv�\�������邱�Ƃ��厖�ł���B�@���O�̎Љ�ł́A�߂�������Ύӂ�A�Ƃ������O���Ƃ��Ă���A��Éߌ뎖���͖@�������ʼn����ł�����̂ł͂Ȃ��̂ł���B
�i�R�j��t��͏�L��a�@�ȊO�̏��a�@�A�f�Ï��ɑΉ����邽�߂̈�Éߌ��V�X�e�������K�v������B
�i�S�j��t�A�@���ƁA��ʎs������Ȃ��@�����k�Z���^�[������A��Q���҂̑��k�ɉ�����B
�i�T�j��L�����o�[����Éߌ뒇�كZ���^�[������B
�i�U�j��Éߌ���N��������t�ɑ��Ă̖Ƌ���~�A������������s���B
�i�V�j��Â��ٔ��Ǝ��āA��H�ƓI���ʂ�����A�d���̍������A�ߑ㉻���x��Ă���B�������ʂōł���J���A�i��ł���A���̊�ƁA�Y�Ƃ̐��i�Ǘ���̃m�[�n�E���w�ׂA�Ⴆ�Γ���~�X�Ȃǂ͂��Ȃ�h�~�ł��邾�낤�B
�@�{�e�͋��s�ٌ�m���Â̎s�������̍u�`���e�Ƃ��č쐬�������̂ł���A�e�̈ꕔ�́A�����ċ���o�ϑ�w�_�W�R�Q���R���P�ňȉ��Ɂh�w�����x�ƈ�Éߌ뎖���h�Ƒ肵�ď��������̂ł���B
�O�c���i�ق� �w���I�m����K�v�Ƃ��閯���i�ׂ̉^�c�x�@����
�����N
�w��Ñi�ׂ̎����I�ۑ�\���҂ƈ�t�̂���ׂ��p�����߂āx����^�C���Y��
����h��w�J���e�ƃ��Z�v�g���킩��{�x�������X
�_�O�i �w���Ҋw�x�}�K�W���n�E�X
���쎟�Y
�w��f�x�W�p��
�O�c�B���ق�
�w�㎖�@�x�L��t
��������
�w�㎖��������x�J���������
���{�v��
�w��Éߌ�i�ׁE�ٔ������̌n17�x�я��@
���c�N�K��
�w��Î��̑Ώ��}�j���A���x����l����
�|��Е� �w��p���̒����x�W�p�АV���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���{�v��
�w�ٔ�������n17��Éߌ�i�ׁx�я��@
�S�F��
�w�㎖�@�w�ւ̕��݁x��g���X
�A�ؓN�w��Â̖@���w�x�L��t
�r�i��
�w���҂̌����x��B��w�o�ʼn�
�A�ؓN�ق�
�w�����K�C�h�x�L��t
䴗����E������Y�� �w��Éߌ�i�ׁx�я��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�N��㎖�@�w�W�[�P�T�����{�]�_��
����� �w���҂̎��Ȍ��茠�Ɩ@�x������w�o�ʼn�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�蓈�L�u��t�̖����ӔC�𒆐S�Ƃ����㎖�@���j�v����A�L�c�� �w�������@���l����x�@��������
���c�K�v��
�w�V�E�ٔ�������n�P��Éߌ�i�ז@�x�я��@
����ꐽ�ҁw�R���܂̑I�ѕ��Ǝg�����x��]��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�{�e�ڎ��b�g�b�v�y�[�W�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@