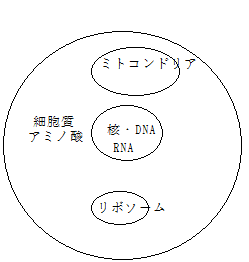国民の健康を増進するためその生活条件を改善管理する学問は、医学の一分野である衛生学であるが、この国民衛生のため収集され、参照される統計を衛生統計という(
参照文献1の165頁~)。
2007年の衛生統計では327.1/1000(約3人に1人)は有訴者で、この率は当然、高齢者ほど高くなり、65歳以上は2人に1人が病気を訴えている。この有訴者のうちの85.5%は市販薬購入を含めて治療を受けているが、「腰痛」「肩こり」「体がだるい」という程度の症状では治療を受けている者は少ない。
医療機関に通院している国民の割合は333.6/1000であるが、65歳以上では約6割が通院している(日野原前掲書167頁)。
1889~1898年(明治22~31年)の統計では男42.8歳、女44.3歳が平均寿命であったが、1947年(昭和22年)では男50.06歳、女53.96歳になり、2008年(平成20年)には男79.29歳、女86.05歳となった(
参照文献1の170頁)。厚生労働省はこの平均寿命を出すとき、少数の非常に高齢な者のデータは除外している。2009年では98歳以上の男のデータ、103歳以上の女のデータを除外し、控え目に計算している(Wikipedia平均寿命参照)。
1947年(昭和22年)の日本人口は7810万1473人、その年の死者は113万8238人、死亡率は14.6/1000であった。2008年(平成20年)の日本人口は1億2769万2000人に増えたが、
年間死者は114万2467人、死亡率は9.1/1000と激減している。激減の最大の理由は、結核が治療薬の開発で克服されたことである。
1947年(昭和22年)の死因の第1位は結核で、実数は14万6241人、第2位は肺炎・気管支炎で実数は13万6524人、第3位は脳血管疾患で実数は10万1095人
、悪性新生物は第6位であったが、2008年(平成20年)では第1位は悪性新生物(悪性腫瘍、がん)で、実数は34万2849人、第2位は心疾患で、実数は18万1822人、第3位は脳血管疾患、実数は12万6944人となり、悪性新生物が第1の死因となった。死因の第1~第3位は生活習慣病が占めており、これに対する予防、治療対策が医療における重要テーマとなっている。
目次に戻る
患者学という聞き慣れない言葉。googleの自由百科事典Wikipediaで「患者学」とひくと、以下の短い記事が出ている。
患者学とは、病気を持つ患者自らが内省し、身体的・心理的・社会的な健康を勝ち取るために統合する、全ての科学的思考。
英国国営医療サービスNational Health Service NHSによって2002年から「慢性疾患セルフマネジメントプログラムChronic Disease Self-Management Program CDSMP」を発展的に改組し、「患者学プログラム」が開始された。長期慢性疾患患者の自助と家族の援助を強化するために、国家政策として熟達患者
(熟練患者)を育成している。
柳原和子・がん患者学に関する著作を多く持つノンフィクション作家。3年間の闘病生活を体験し、医療過誤・薬害訴訟に関心をもつ。平成23年9月1日、柳原のドキュメントの再放送があった。最初の手術、抗がん剤治療後、がんが再発し、抗がん剤治療、手術、放射線治療を受け、がんとの悪戦苦闘が続いたが、2008年3月2日、再発がんにより死去した。
高柳和江・長年にわたり、放送大学(通信制大学)で患者学の教鞭をとる。「癒し」という言葉の提唱者で、癒しの環境研究会代表。放送大学客員教授、医学博士(日本医科大学)、文京学院大学客員教授。
患者学という表題を含む本は、『ガンに打ち勝つための患者学』グレッグ・アンダーソン2005年1月刊、『薬剤師のための患者学』山村憲司2009年8月刊があるが、ここでは、以下の3冊を参照した。
(1)神前格『患者学―誰でもいつかは患者になる』参照文献2。本書は内科医である著者が、医師に医学があるように、患者には患者学があるべきである、という観点から書いた患者のための啓蒙書である。著述はいい医師、医療機関の見つけ方、医師との付き合い方、医師が嫌がる患者の言葉など、多岐に亘っている。
(2)柳原和子『がん患者学―長期生存をとげた患者に学ぶ』参照文献3。私が最初に読んだのは、神前格の本より1月遅れて出版されたこの本である。著者はノンフィクション作家で、卵巣がんとの長い闘病経験を持つ。本書は3部構成で、第1部「患者は語る」は、末期がん、再発がん、進行がんを宣告されて5年以上生存した患者またはその家族らの闘病記であり、代替療法を含む闘病生活が語られており、第2部「専門家にきく」は、筆者の闘病中に関わった医師などへのインタヴュー、対話集であり、第3部「再生―私とがん」は筆者自身の闘病記である。
(3)上野直人『最高の医療をうけるための患者学』参照文献4。本書は在アメリカの内科医である著者の日本人患者に対する啓蒙書である。患者メモ、患者ノート、経過表作成等、患者としての努力の必要性、標準医療と先進医療の比較などについて述べている。
googleや図書の検索で見えてきたのは、原則としてすべて国費で医療を受けるイギリスでの患者学は、長期慢性疾患(糖尿病、高血圧症など)、日本でいえば生活習慣病患者とその家族の啓蒙を狙いとしているように思われるが、わが国の患者学は必ずしも疾病を生活習慣病に限定せず、あらゆる疾病の患者の啓蒙を目的としている。
もっとも、柳原前掲書は『がん患者学』と銘打っているから、明らかに対象はがん患者限定である。
googleを検索すると、がん関連商品、その先駆商法としてのゼミナーに集客ための修辞として「患者学」が用いられることに注意すべきである。健康志向に便乗した悪徳商法は、サプリメント販売や各種の民間療法を含めて大変多い。どのような言葉、表現を用いるにしろ、高額な費用、代価を請求する療法は便乗商法であり、これに冷静に対処するのが患者学の第一歩である。かって国立がんセンターの高上医師は免疫療法に関して「いい薬は安い。月に2万円を越える薬は怪しい・・・」と述べている(
参照文献3の79頁における近藤発言)。
医師は医師になるためには補助学問として化学、物理、分子生物学、語学、社会学などなどを学ぶ必要があろうが、何よりも学ぶ必要があるのは言うまでもなく「医学」であり、この医学のなかでも基礎医学(ここでは身体の構造、生理などを学ぶ)と臨床医学(ここでは病気の診断、治療の方法を学ぶ)の学習は必須である。
「医療」は、医師と患者が存在しなければ成立しない。医師と患者の関係を法律的にみれば、それは原則的には契約関係であるが、この関係を捨象して、医師対患者という人間関係をみると、それは親と未成年者の親子関係に似た人間関係である。疾病治療において医師は医療知識、技術を持つ専門家、患者は疾病というハンディキャップを持つ者であり、力関係は圧倒的に医師が強く、患者は弱
い。
明治以来、わが国で医師と患者関係を「パパさん関係・パターナリズムPaternalism」ととらえていたのは、この点に着目したためである。
この構図は、インフォームド・コンセントの普及、カルテの公開などが象徴するような患者権尊重で緩やかに崩れつつあるものの、医師側有利という基本的力関係にはいささかも変わりはない。
患者学とは、医師から医療を受けるという弱い立場にある患者が、疾病の治癒、少なくとも軽快という目的のため、あやまちなく、妥当な医療を受けられる
ために習得すべき最低限の実用的医療知識の総体であり、現在のところ、学問というだけの系統的、体系的知見とはいえないが、無力な患者が医療世界では大過なく生き延びるための処世術ともいうべき実用的知識の総和である。
もっとも2008年における医師の数は約27万人、歯科医師数は約9万9000人であるから、上記死亡率をかけると、毎年3000人強の医師、歯科医師が多くは患者を経て死亡しているであろうから、これらの医師、歯科医師たる患者には患者学は不要であろう。
目次に戻る
自分に何かの病気が発見されたときにも、①急に症状が出て受診し、病名を指摘されることもあるし、②症状はなくても、健康診断で病気が見付かるなど色々あろう。
病名が軽い場合とか、高血圧とか糖尿病のような生活習慣病の場合は、一刻を争うという緊迫感はないから、悠々と医療情報を収集できるが、病名が悪性腫瘍・がんのような重たい病気では人によって気持ちが動転し、冷静な情報収集ができない恐れがある。
従って情報収集の時期は病気でない、健康な時期、もしくは軽い病気(或いは持病)を持っている時期がベストである。
病気、医療の情報源については
①医療従事者(医師・看護師・薬剤師など)
②マスコミ(テレビ、書籍など)
③知人、友人(クチコミ)
があげられている(参照文献6の25頁)。
ベストは①の医療従事者であるが、多忙などを理由に、なかなか相談、質問に応じて貰えないのが欠点である。
②マスコミからの情報収集で注意しなければならないのは、マスコミ、特にテレビは視聴率を気にするメディアであり、先進医療と銘打たねば視聴率は上がらないこと、先進医療はいまだ十分なエビデンス(科学的根拠)を得ていないもので、それが標準医療となるには相当の年月を必要とすることを忘れてはならない(
参照文献4の116頁~)。
テレビでは、しばしば、「神の手」と賞賛される外科医が登場し、がんの摘出などをいとも易々と行うシーンが放映されるが、注意して見ると、その患者が手術後、
どうなったかの放送はなく、退院姿がテレビに映ることはあるが、普通のがんでは5年生存率を根拠に5年経過で治癒判定をするが、5年後の患者に迄言及するテレビはない。
書籍も「家庭の医学」的一般書では不十分である。せめて自分の病気が載っている病理学入門くらいは買って読むか、図書館で検索して読むことが望ましい。医学書は看護師、栄養士、検査技師用のものは、医師用のものより平易に書いてあるから読みやすい。
③の友人、知人も医師であればよいが、素人の場合は民間療法の宣伝だけ、ということもあるから注意すべきである。また、自分より重篤な患者への質問は悲観的回答で役立たないこともあろう。聞くべき人の選択が難しい。
注意すべきはインターネットによる検索である。グーグルなど検索エンジンをつかって検索をすると、糖尿病など一般的な病気だと、何万と記事が出てくる。記事はアクセス数の多いものの順番
で並んでいるから、トップのものから読むのが普通だが、記事には価値あるもの、無価値のものが混然としているから、取捨選択が大事である。取捨選択能力の決め手は読書などで手に入れた自分の知識、教養である。
下記は参照文献6末尾ⅰ記載のサイトのほんの一部であるが、医療情報も今や選択力が試される過剰時代に入っていることを忘れてはならない。
医療法上では医療機関は入院ベッドの有無、数によって20以上のベッドを持つものを病院、ベッドが0~19のベッド数の医療機関は診療所と呼んでおり(第1条の5)、地域医療の中心となる大病院(京都第1、第2日赤病院、京都市立病院、国立病院機構京都医療センターなど)を地域医療支援病院と呼び(第4条)、高度の医療の提供する大學病院(京大病院、京都府立医大病院)を特定機能病院と呼んでいる(第4条の2)。
我々の周囲にあって、ちょっとした病気で利用する普通の規模の病院、開業医、クリニックなどの一般病院は1次医療提供機関、日赤病院のような規模の病院は2次医療提供機関、京都の京大病院、府立医大病院とか、各地のがんセンタ-、国立循環器病研究センターなどは3次医療提供機関といわれている。
医療法の建前は中小の一般医療機関を経て大病院、最後は特定機能病院へと段階的に受診し、治療を受けることを望んでいるのだが、つい近くに大学病院があると、風邪をひいても大学病院に行きたくなるのが人情である
。
このような軽い症状、危険性の少ない病気は1次医療機関が担当し、2次医療機関を経て3次医療機関に行くのが本筋であるから、2、3次医療機関での受診は医療機関の紹介状を持参するのが原則になっている
。
紹介状がなくても受診できるが、地域支援病院で2次医療機関である京都第2日赤病院で調べたら、紹介状がない新規受診者は選定療養費名目で5250円(税込み)を自己負担で徴収し、特定機能病院で3次医療機関である京都府立医大病院は保険外負担金として2100円を徴収することになっていた。
自分がよく罹る病気とか、素人的にも大きな、深刻な病気とは思えない病気に罹ったときは、行きつけの近所の医療機関を受診すれば、既往症歴もカルテで判るし、待ち時間もさほど長くないからそれでよいが、深刻な病気らしいときには病院選択に迷う。時々、良い病院を紹介する雑誌の特集号が出版されるが、地域が違ったり、時間が経てば使えないし、宣伝臭い記事もあって、余り信頼がおけない。
一番良い方法は行きつけの医師(ホームドクター)に一度受診して相談するのがよい。 もしそういう医師がいない場合は、自分の居住地域の病院の評価を「公益財団法人日本病院機能評価機構」のホームページを読むという方法がある。(
参照文献6の60頁では、2009年2月現在、約2550病院が評価ずみとのこと)。
日常経験するような頭痛、腹痛、手足の怪我なども、場合によっては深刻な病気の前兆かもしれないし、長引けばほかの病気に進展する可能性があるが、普通はそれだけで大病院を受診する必要はなく、紹介状がないとお金をとられるし、近所の医師1人程度の開業医、クリニック受診で済ませ、それで一件落着して治ることが多い。
さて、近所の開業医、クリニックといっても、内科と外科を標榜しているクリニックとか、内科と産婦人科を標榜しているクリニックがあるが、そこの医師は何が専門だろうか。やはり専門の医師にかかる方がよい。
内科専門の医師は、不得意で、行えば過誤を犯す危険性のある外科、産婦人科を標榜することはないから、内科と外科を標榜する医師の専門は外科であり、内科と産婦人科を標榜する医師の専門は産婦人科である。後記のように内科受診患者数は外科の約5倍はあるから、内科を専門とする医師は内科を標榜するだけで生活ができる。反対に
、外科専門の医師は外科だけでは生活が大変なので、内科も標榜するのである。
皮膚科、泌尿器科、麻酔科などと内科を併せて標榜する場合も同じ、内科以外が専門の医師であろう(神前前掲書132頁以下参照)。
少しややこしそうな病気では、誰でも大きな病院、上記2次か3次の医療機関、例えば日赤病院とか、医大病院を受診したいし、その考えに誤りはない。仮に京都で3次医療機関を選べば、京大病院か府立医大病院しかない。人によって京大派と府立医大派に分かれている
ようだ。
日本医学会には100を越える分科学会があるが、各学会は登録医、認定医、専門医、指導医制度をおいて、多くの専門医(5年以上の研修などが必要)を作ろうとしている。 日本人には大病院志向があるといわれているが、大病院のメリットはこの専門医が多いということと、他科との連携がスムーズなので、女性が腹痛で内科を受診したら、子宮内膜炎の疑いがあることで、すぐ婦人科を受診できるということ
にある。
しかし、大病院は待ち時間が長いというデメリットを覚悟しなければならない(大病院の長所、短所については参照文献2の153頁参照)。
公衆又は特定多数人のために医業を行うべき場所である医療機関は、診療できる科目(診療科目)は利用者のため、何らかの方法で広告、標榜すべきであるが、標榜
すべき診療科目無については医療法規が規定している(医療法第6条の5第1項第2号、第6条の6、医療法施行令第3条の2)。
2010年3月22日改正までの旧医療施行令第3条の2第1項第1号の診療科目の規定は比較的単純で、①内科、②心臓内科、③精神科、④神経科、⑤呼吸器科、⑥消化器科、⑦循環器科、⑧アレルギー科、⑨リウマチ科、⑩小児科、⑪外科、⑫整形外科、⑬形成外科、⑭美容外科、⑮脳神経画家、⑯呼吸器外科、⑰心臓血管外科、⑱小児外科⑲皮膚泌尿器科、⑳性病科、?こう門科、?産婦人科、?眼科、?耳鼻いんこう科、?気管食道科、
リハビリテーション科、?放射線科の27科であった。
この診療科目でも精神科と神経科との違い、整形外科と形成外科の相違は素人にはわかりにくい。
改正後の新施行令は以下のように、一層難しくなっている。
第3条の2 法第6条の6第1項 に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
一 医業については、次に掲げるとおりとする。
イ 内科
ロ 外科
ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1)頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
(2)男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3)整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
(4)感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
(1)精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科
(2)(1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
二 歯科医業・・以下省略
平成23年現在、京都府立医大での新患申込書記載の診療科目は以下のようなっている。
内科・総合診療部
・消化器内科
・循環器内科
・腎臓内科
・呼吸器内科
・内分泌・糖尿病・代謝内科
・血液内科
・膠原病・リウマチ・アレルギー科
神経内科(老年内科)
消化器外科
心臓血管外科
呼吸器外科
内分泌・乳腺外科
移植・一般外科
形成外科
脳神経外科
整形外科
産婦人科
小児科
眼科
皮膚科
泌尿器科
耳鼻咽喉科
心療内科
精神神経科
放射線科
ペインクリニック(麻酔科)
歯科
小児循環器・腎臓科
小児外科
小児心臓血管外科
漢方外来
紹介状なしに内科を受診すると、総合診療部が初診外来を担当するらしい。
目次に戻る
昔は頭痛も腹痛も内科に行けばすんだ。診療科目の細分化が進んだ今でも近所の開業医、クリニックに行けば、診療科目は内科と外科、皮膚科、耳鼻咽喉科などとの併科
が多いので、さほど迷うことはなく、概ね、受付で聞けばすむことが多い。
紹介状なしに大病院、特定機能病院に行った場合、診療科目選びに迷うことがある。もし新規外来患者(新患)として初めて大病院などに行き、診療科目が判らぬ場合は、必ず、新患受付近に相談場所があり、看護師が教えてくれるから、それを利用すればよい(医療法第6条の5第1項第8項は、患者の相談に応ずる措置も広告事項としている)。
京都府立大学病院は新患受付を午前11時で打ち切っているが、これは医師法
19条の応召義務違反にならないだろうか。午前11時以降の急患は救急で処理する、と弁解するであろうが、徳洲会病院は新患の時間制限はないということである。
風邪は呼吸器系の炎症性疾患であるが、原因の多くはウイルス、細菌の感染である。症状も頭痛、発熱、悪寒、咳など多様であ
り、対処はさほど簡単ではない(風邪薬の過剰投与で患者が死亡した事件もある。最高裁平成9・2・25民集51・2・502)。腹痛も大腸炎だけではなく、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、すい炎、胆石症などが疑われるから、近所の開業医、クリニックで可能な血液検査、超音波検査などを経て、軽ければその医師の治療を受け、問題があれば、大病院などに転医すればよい。
こういう症状の場合はどういう病気が考えられるか、という本とか、記述は多い(例えば、参照文献8の『図解症状でわかる医学百科』、参照文献7の『患者のための医療相談』123頁~、
参照文献2の109頁~)。
しかし、ある症状について、そのような文献だけ読んで素人判断をするのは困難かつ危険である。例えば、前掲『図解・症状でわかる医学百科』書76頁~によると、脳血管拡張で起こる片頭痛でも神経科、脳外科、眼科、耳鼻科、整形外科領域の病気が考えられ、嘔吐があれば髄膜炎の疑いがあるから即時受診が必要とされているから、目視できる外傷、皮膚症状以外は
、自己判断で受診の要否を決めるのは危険であり、疑わしきは病院に、医師に、という対応をとるのがベストである。
原因が何であれ、苦痛が激しいときとか、出血が多いときとか、意識障害があるときは119番で救急車を呼ぶしかないが、救急受け入れ病院もは1次、2次、3次と分けられており、救急車の中での救急救命士の判断と受け入れ病院の事情で搬送先が決まる。
ところで、患者に接して具体的治療に当たるのは病院ではなく、医師という人間であるが、良い医師と良くない医師の見分けも難しいし、事前に患者がそれを判別して選択することは
困難である。
大学病院の外来待合には、曜日ごとの担当医師名と資格(医局員、講師、准教授、教授)が掲示されている。政財界の有力者であれば、誰かの紹介で教授に診て貰ったり、教授に執刀してもらうこともできる
だろうが、普通の市民は、新患で行けば、受付の裁量で、暇そうな医師とか、新患専門の若い医師に当たることが多い。
医師は医師からの紹介があれば、診察も慎重になるが、逆に、医師の紹介でかかった医師の診断には不服が言いにくい、という欠点もあるらしい(神前前掲書64頁~)。
もともと良い医師の見分け方は難しい。神前前掲書はよい医師(名医)の条件を22もあげており、第1、2番に、豊富な知識と経験をあげているが、これを患者が判別することは、患者が医師でない限り、極めて難しい。
アメリカの陪審員裁判におけるように、陪審員候補者に対する質問とか忌避制度があればよいのだが、医療にはそのような制度はない。
患者ができるのは、初診後の数回の接触で医師から受ける印象、例えば年齢、地位、注射がソフトで痛くない、とか、疑問を述べても怒らずに対応してくれる、という些細のことから、医師の経験、技術、性格を推測する程度のことである。
裁判官はその審級での最終判断者であり、開廷した場合には法廷警察権という権力を持つ権力者である。だから、1番忌むべき裁判官の欠点は傲慢であり、望まれる性格は謙虚さである。
医師も医療場面、特に診断においては裁判官に等しく専断的で、手術という侵襲的執行もできる点では検察官も兼ねているから、権力者に当たる。だから、私は最低の資質として、傲慢ではなく、謙虚さを持っている医師に当たりたいと思っている。もし、この医師が通常レベルの医療知識と技術を持ち、患者サイドでものを考え、患者との対話を拒まぬ優しい医師であれば、
良医の称号を与えてもよい。
目次に戻る
中程度以上の病気になったら、患者は自分でその病気に関するノートを作ろう。医師は診察したら診療録カルテを作って保存しなければならず(医師法第24条)、その記載事項は①患者の住所、氏名、性別、年齢、②病名、主要症状、③治療方法、④診療の年月日である(医師法施行規則第23条)。病院は原則としてこのカルテを個人情報として本人に開示しなければならない(個人情報保護法第25条。但し過去6ケ月内に取扱い個人情報が5000以下のものは除かれる。同法施行令第2条)。
初診時に問診が行われるが、医師が質問するのは、主訴(どこが悪いか、痛いかなど)、現病歴(いつからおかしいか)、既往歴(今までの病歴)、家族歴である。これは患者が知っている情報だから、これを自分のノート(患者ノート)に簡単に書いておく。もし、当日、医師が診察して病名が判ればそれをノートに書く(筆記用具があればその場所で書く(難しい病名だと、医師に書いてもらう)。
投薬などの処置を受ければそれも書く。帰宅して書いてもよい。薬を貰うときには薬の説明書がついているから、それを別の薬ノートに書く。最近は院外処方が多く、院外薬局は
「薬手帳」をくれるから、それを薬ノートに代用してもよい。
検査が続き、診断が遅れたら、病院に行った都度、ノートを書く。予約表をくれるからそれを保管してノートを作成する。
入院したら「計画書」をくれるから、それをノートを書く。ノートには治療経過、内容、疑問点を簡潔に書くが、感情的なこと(しんどいとか・・)は書かないこと(日本の患者は自分の薬も答えられない人があるが、アメリカの患者は過去の症状、治療などを簡潔に答え、1、2枚の紙に書いたものを医師に渡す人がいるとのこと。賢い患者は患者ノートを作成する、ということである(
参照文献4の21頁~)。
もし患者がパソコンができれば、「患者ノート」というフォルダに診療経過、投薬経過などを時系列に記載し、病院に行って医師に見せる必要があるときは、その部分を印刷して持参すればよい。
医療においては、患者は医療費支払義務のほか、医師と患者の相互座用である医療の本質に照らし、医師に対する適切な情報提供義務がある。
例えば、肺疾患においては喫煙の有無、喫煙歴を話すことは診断、治療に重大な意義があるし、薬剤処方、投与においても薬剤の相互作用(薬剤同士に禁忌性が存在することがある)の判断、薬剤耐性の判断(例えば、ある種の抗生物質を連用していると細菌にその抗生物質に耐性が生ずることがある)などにおいても患者が使用、使用歴のある薬剤情報を医師に提供する必要がある。
心臓疾患患者にビタミンK拮抗薬であるワーファリンを投与している場合、凝血、止血能力が低下しているから、手術を受ける前に数日間の休薬が必要となる。患者は必ず医師にワーファリン服用を告知しておく必要がある。自分の命を守るためにもそれが必要なのである(
南江堂
『今日の治療薬』2010
年版544
頁参照)。
患者を診察し、病気の本体、病名を診断して治療の要否、その方法を決定、実施するのが医師の勤めであるが、現在の医療では、診断の前提となるのは診察(これは従来と同じく問診、聴診、視診、触診、打診によって行われる)だけではなく、検査(臨床検査)が
大変重要の意味を持っている。
臨床検査のうちでも、心電図検査、X線検査、脳波検査、肺機能検査等は検査終了後に行われる検査結果の報告、説明で大体判る。もし不明の点があれば、説明時に質問をすればよい。最も難解なのは血液検査である。前立腺がんの疑いで血液検査を受けると、腫瘍マーカーPSAの数値くらいは一目瞭然であり、正常値、異常値も事前の説明で知っているから余り問題はないし、検査結果表はコンピューター処理されているから数値が正常値より高いとhighのHが記載され、低すぎるとlowのLが記載されているから判りやすい。
しかし、それ以外の検査結果表の略語類は素人には不明であり、これを全部、教えてくれる医師はいない。京都府立医大病院では血液検査室の近くに検査説明室があり、検査技師が待機している。技師から説明を聞いたり、各種検査の名称、基準値、検査の意義、疾患との関係などを記載した説明用紙のコピーを貰うことができる。検査結果が異常の場合は医師が説明するし、検査結果を記載したものもくれる。帰宅して不明な点は次回受診日に聞くか、書籍やインターネットで検索し、調べておこう(臨床検査を説明する本は多い。その1例・
参照文献6の『新・検査マニュアル』)。
臨床検査では精度が肝要である。精度が落ちると適正医療の実施に影響し、医療過誤を招く。従って、病院では、内部、外部検査を問わず、精度管理が行われている(
参照文献17の54頁)
2008年度人口1444288人の愛媛県内には4つの県立病院があるが、2008年度における診療科別外来患者数は以下の通りである。
内科138509
その内訳
①総合診療科 21499
②消化器内科 24454
③循環器内科 19849
④呼吸器内科 19515
⑤糖尿病内分泌代謝内科 26301
⑥血液腫瘍内科 7582
⑦腎臓内科 12864
⑧神経内科 6445
精神科 5171
東洋医学 10749
小児科 17154
その内訳
①小児科 11260
②新生児科 5894
外科 24181
その内訳
①一般消化器外科 13261
②呼吸器外科 1594
③小児外科 1059
④乳腺甲状腺外科 8267
整形外科 22174
形成外科 6626
脳神経外科 8800
心臓血管外科 8612
皮膚科 19545
泌尿器科 30337
産婦人科 24593
眼科 27137
耳鼻咽喉科 11273
放射線科 8011
麻酔科 6617
歯科 14730
人間ドック・健康診断 18359
合計 402578
1日平均 1656
診療日数 243
外来患者総数402578人を人口1444288人で割ると、愛媛県の通院率は27.8%である。
これは県立病院だけの通院者を前提としているが、県内の他病院のデータを加算すると、通院率はもっと高率である。
臨床医学の基礎、中心となるのは内科であり、小児科は小児の疾患の特殊性を考慮して内科から分科したものとされている(日野原前掲書37頁)。そうすると、愛媛県立病院の2008年度外来患者総数402578人のうち内科系患者数は小児科患者を含めると155663人であるから、外来患者の約38%は内科系患者ということになる。
医師(主治医)との関係を良好に保つことは極めて大事であるが、どうしても関係がぎくしゃくしてうまくいかず、コミューニケーションもとれず、その原因は自分にはなく
(自分側に原因があれば自分を改めるしかないが、これは大変難しい)、医師側にあると判断した場合、また、不和原因が治療法の選択のような医療上の重要問題にかかわる場合には、医師、患者側の見解の当否の判定は第三者に委ねるしかない。カルテの借り出しを受けて、第三者的医師から、いわゆるセカンド・オピニオンを聞くのがベストである。もし、不和原因が治療方針の食い違いというようなものでない場合は、病院に苦情相談窓口があれば、そこで相談する。
医療法6条の11で設置された京都府医療安全支援センター(月~金曜日の9~16時30分075-451-9292)に相談するのも一つの方法である。この支援センターは医療機関のかかりかたについての相談にも応じている。
医療契約は患者と医療機関間の契約であり、医師が医療機関に雇われた者(履行補助者)である場合は誰に医療を担当させるのは医療機関が決めることであり、患者側が決めることはできない。担当裁判官や検察官を自分で決められないのと同じである。
医師1人の診療所では、医師を変えることは診療所を変えることであるが、医師が履行補助者である場合でも、医師を変えるのには医療機関をかえるしかない(
参照文献7の76頁)。
もちろん、医療機関の意思で医師を交代させてくれればよいが、そのような場合は、また似たような問題が起こりやすい。以下は、病院が検査結果を告知しなかったことから起こった苦情申立事件であるが、患者と医師、医療機関の感情的衝突解決の難しさを示す1例である。
1997年、ある60歳台の男性が胃がんと診断されて切除手術を受けたが、術後の病理検査の結果はno cancerだったが、患者にはそのことを告知しなかった。5年後、この検査結果を知った患者は、自分は胃がんではなかったのではないかと考えるようになり、病院に説明を求め、院長が1回、担当医師が数回、職員が数10回面接して、術前の病理検査ではがん細胞が見付かっている。微小ながんは術後の検査で見付からないこともある、と説明した。2003年8月、病院は1500枚の標本を作って再検査したところ、がん細胞が発見されたので、そのことを患者に告げたが、患者は納得しなかった。2004年1月、患者から苦情の申立てを受けた東京のNPO法人患者の権利オンブズマン会議は約3ケ月調査の結果、術後の病理検査の結果を患者に告げなかったのは不当であるが、患者の胃がんは術前検査で判明しており、手術には適応性があった、と判断し、患者は一時はこの判断を了解したが、1カ月後、了解を取り消した(
参照文献12の193頁~)。
目次に戻る。
医師は単に診断、治療をすればよいのではなく、例えば、入院患者が退院する場合は退院後の生活について必要な注意事項を述べて療養上の指導をしなければならないが(医師法23条)、この指導を受けるまでもなく、患者は入院治療(例えば、抗がん剤治療)で痛んだ臓器、組織、細胞などの回復、増強を
自力で図らねばならない。
参照文献3の柳原第3部には患者(筆者)の抗がん剤との苦闘の日々が綴られている。手術後、4回にわたって抗がん剤の入院治療を受けたが、5回目の抗がん剤治療を断るところで第3部は終わる。同室患者らの闘病と終焉は鬼気迫るものである。
全身に転移したがんだけではなく、手術で殆どの病巣は摘出したが、微小ながらがんが残存している場合には手術後の補助療法として、抗がん剤治療を行うことが多い(谷口直之・杉山治夫・松浦成昭『がんをどうして治すか』中山書店1996年10月第1刷74頁)。
がん細胞は非常に増殖が早いが、それは活発に分裂するための細胞周期を廻っているからであり、抗がん剤はその点に着目してがん細胞を攻撃するが、正常細胞でもがん細胞に似て増殖の盛んな造血細胞、粘膜上皮細胞、毛根母細胞は抗がん剤の影響を受け、白血球減少、口内炎、脱毛などの副作用が起こる(谷口ら前掲書75頁~)。
抗がん剤にはアルキル化剤(シクロホスファミドなど)、代謝拮抗剤(メトトレキサートなど)、抗生物質(マイトマイシンなど)、植物アルカロイド(エトポシドなど)、その他(シスプラチンなどの白金化合物類)などがあるが、歴史的にみると、アルキル化剤のシクロホスファミドがその嚆矢である。
第1次大戦時、ドイツは毒ガス兵器としてマスタードガスを開発し、1917年、カナダ軍に対して使用した。当時、アメリカではがん治療法にはX線照射しかなかったが、このマスタードガスに改良を加えたナイトロジェンマスタードが白血球減少の効果があることに着目し、これを改良した抗がん剤シクロホスファミドをがん患者に使用した。これが抗がん剤の始まりである。
あらゆる薬は、毒をもって毒を制する、ものであるが、抗がん剤(過少量、過大量では駄目)はその毒性が顕著なものであり、抗がん剤はがん細胞のDNAを攻撃してその増殖を止めることを目的とするから、正常細胞も同様攻撃を受け、特に細胞増殖が活発な骨髄は抗がん剤の影響を受け、白血球、特に好中球が減少して免疫力が弱まり、感染症の危険が高まる。好中球が1000/mm3以下になると肺炎が起こりやすく、数時間内に有効な抗生物質を静注する必要がある(
参照文献13の83頁)。
参照文献3の柳原は抗がん剤の入院投与を批判するが(518頁)、入院治療の必要性はないわけではない。肺がんに対する抗がん剤イレッサは、錠剤で在宅投与が可能
であったため、重篤な肺疾患が手遅れとなる例があった
。
参照文献3の柳原第3部の中心は抗がん剤との闘いの記事である。入院して抗がん剤治療を受けるために、それに耐える体力作り、臓器の強化、体質改善のために入院中は入院患者という制約を破ってでも外出、外泊して生気を回復し、抗がん剤治療の間の退院期間は試せる限りの健康食品、代替療法、無農薬無添加食品、玄米食、山登り、温泉、気功、深呼吸、灸、あらゆる神仏への祈りなど、可能な限りの健康療法を実施
している(参照文献3の525頁~)。
前掲高柳和江医師は、放送大学で「患者学」という講座を持ったことがある。
そのシラバスSyllabus(学習計画)によると、2011年第2学期に、高柳医師は仙波医師(さいたま市立病院精神科部長)とともに、「かしこくなる患者学」という講座を持った。その講義概要は「かしこくなる患者学では、医療を患者の視点から考えていきます。初めの回の「エンパワメント」では、体の持つ健康を強めていくことを学ぶ。しかし、その基盤にあるのは生き物としての人間の自己治癒力である。この自己治癒力をしっかり理解し、笑いや統合医療などでこれを高める方策を知ったうえで、わが国の医療のシステムの特徴を把握し、さらに医療情報の評価や選択の基礎を学ぶ。この科目の後半では「患者としての権利」、「EBMとNBM」、「患者から社会への発信」、「ヘルスリテラシー」、さらにはヒトの「死」などを取り上げ、徹底的に人間の立場から、わかりやすく解説する。」とある。
この講座では、患者の体力増強Empowermentや自然治癒力、ストレス解消のための笑いの効能も語られている。
ここの「EBM」Evidenced-based Medicineは、証拠、科学的根拠に基づく医療、「NBM」Narrative-based Medicineは、患者の訴え、物語、すなわち患者の生活史、社会的背景に基づく医療、Health Literacyは健康のための情報収集能力である。
日米のがん医療の格差がよくいわれるが、アメリカの病院勤務の日本人医師は真の格差は患者の賢さにあると言っている(参照文献4の21頁~)。
医療、医師制度の改革は一朝一夕で片付く問題ではないが、患者の改造は医療の改革ほどは難しくない。
目次に戻る。
(2)免疫力の増強
A 細胞
生物の最小構成単位は細胞cell→ヒトは約60兆の細胞から構成。細胞(10~30ミクロン1/1000mm)で、内部には核(中には父母から受け継いだDNAが畳み込まれた46本の染色体がある。うち2本は性染色体で、女性はXX、男性はXY)、リボソーム、ミトコンドリアなどの器官を持つ。細胞ごとに分裂期間、寿命は異なる。無核、多核細胞もある。
DNAはデキオシリボ核酸で一部がAアデニン、Gグアニン、Cシトシン、Tチミンという塩基の並び方で遺伝子信号を示しており、信号が発動すると、命令はRNAメッセンジャーにコピーされ、この命令によってリボソームは細胞質内の20種類のアミノ酸で抗体、酵素など必要なタンパク質を合成する。例えば、小腸で吸収されたアルコールはアルコール脱水素酵素で肝毒性のあるアセトアルデヒドに変わるが、2型アルデヒド脱水素酵素で無害な酢酸に変わる。
細胞の分割周期は皮膚28日、胃の上皮細胞は数日、小腸の内壁絨毛表面細胞は3~5月、肝臓細胞は1年といわれている。全細胞には寿命があってDNA末端の無意味な信号部分テロミア部分が短くなりすぎると細胞は分割しなくなり自然死する。ヒトの寿命が120歳といわれているのもそのせいである。36億年前に誕生した生命体の始原生物は単細胞生物で、分裂再生を繰り返し、死はなかったが、35億年前、多細胞生物が誕生し、雌雄生殖が行われるようになってから、生物は死ぬようになった(参照文献20の136頁以下)。今、人間の細胞は1日3000億~5000億も死んでいるが、その多くは再生で補充されるが(参照文献20の39頁)、脳の中枢細胞とか心筋細胞は補充されない(参照文献20の49)。従って
最大
でも120歳、普通は100歳くらいで人間の寿命は尽きるが、地球全体のことを考えると死は必要不可欠なものである(参照文献20の160頁以下)。
細胞は事故(火傷など)で壊死(事故死)したり、寿命が来て自然死したり、自殺(アポトーシス)する。1日で3000億個の細胞が死ぬがその殆どは自然死である(参照
文献
15の81頁、参照文献20の52頁)。アポトーシスには種々のプラスの
効用がある。
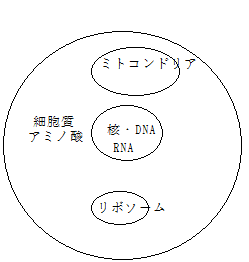
B 血液
人間は成人体重60kgで4.6㍑(約2.5升)の血液を持つ。毛細血管を含めた血管の全長は約10万キロメートルで、地球の赤道2週半。この血管には毛細神経がずっと張り付いている(参照文献21の79)。
血流の速さ大動脈は63cm/sec、毛細血管は0.01~0.1cm/sec)の血液を持つ。あらゆる種類の血球はすべて「造血幹細胞」という一種類の原始的細胞から分化生成したものである。
血液は体温の保持、発汗、尿の排出を行ふほか、血液中の赤血球のヘモグロビンHbは組織に酸素O2を運び、組織から二酸化炭素CO2を
回収し、白血球は生体防御作用を行い、血小板 は血液凝固を行う。
血液の成分は、栄養などを運ぶ血漿55%、血球成分45%であるが、血球の96%は赤血球、3%は白血球、血小板は1%である。
C リンパ液
体内には無色透明のリンパ液がリンパ毛細管
(毛細血管より大きな間隙を有する)
を流れて栄養を補給し、リンパ毛細管の途中にある
リンパ節ではリンパ球を増殖して免疫を行っている(参照文献9の324頁)。
T細胞、B細胞はリンパ腺、リンパ節の中に多く見られるので「リンパ球」とも呼ばれる(参照文献14の57頁)。
この
T細胞のTは胸腺ThymusのT(胸腺で生成し訓練を受けるから)、B細胞のBは骨髄のBone
marrowのBである。人間の免疫細胞は約1~2兆個で、重さは1キログラムで、脳より重く、1000万種類の抗原に対応できる(参照文献14の60頁)。
D 免疫
人間は白血球を中心とする免疫作用で異物侵入を排除して生命を守っている。そのためには自己と他者の区別をしなければならない。もと東大の免疫学教授の故多田富雄は『免疫の意味論』青土社1995年3月第26刷と『生命の意味論』新潮社1997年4月第5刷
でそのことを私に教えてくれた。
外部から侵入したインフルエンザウイルス、食中毒菌とか、自分の中で自分の命令を聞かずに造反し、クーデターを起こしたがん細胞も、自分からみれば自分を否定し、殺そうとする
他者、異物であり、免疫で排除されねばならない。
E 白血球
白血球には、細胞内に殺菌作用を行う顆粒を持つ「顆粒白血球」と顆粒を持っていない「無顆粒白血球」があり、「顆粒白血球」には好中球53.5%、好酸球3.0%、好塩基球0.5%があり、
「無顆粒白血球」にはリンパ球38.0%、単珠5.0%がある。
白血球はアミーバ状、不定の形状で、大きさは10~20ミクロン(ミクロンは1/1000mm)で、標準的には血液1mm2中に6000~8000個ある
(感染菌が増えると白血球が増えるから、感染病の診断に使う)。10000個以上だと白血球増多症、4000個以下だと白血球減少症という
(数の減少で抗がん剤の副作用を判断する)。
白血球の中で最多は「好中球」であるが、これは毛細血管を通過し、偽足を出して細菌などを補足し、細胞内に取り入れて捕食する。捕食後の好中球は死んで膿となる。
「好酸球」は弱い補食能を持つが、主にはアレルギー反応の制御を行う。「好塩基球」の作用ははっきりしない。
「単珠」は骨髄から血流に入り、約72時間循環した後、組織内に入り、「マクロファージ」になる。これはT細胞から分泌されるリンホカインで活性化し、抗原を捕食し、その情報をインターロイキンを放出してTリンパ球に伝える。
リンパ球にはBリンパ球(30%)とTリンパ球(70%)がある。これらは椎骨、骨盤、胸骨、肋骨内の骨髄で作られるが、Tリンパ球は胸腺で訓練を受け、5%は血流に入り、95%はアポトーシス(自殺apoptosis)し、Bリンパ球は肝臓、脾臓を経由する。
免疫を行う細胞を免疫細胞と総称するが、これを以下のように分類することがある。
①獲得免疫系→細菌などの抗原が侵入したときに出動して対応、防衛するもの。
T細胞・主に免疫戦争の司令塔となるヘルパーT細胞とか、自ら抗原を捕食するキラーT細胞など。
B細胞・バクテリアなどの病原菌が侵入したときにT細胞の指令を受け、抗体を作って対応、防衛する。
②自然免疫系→常時防衛を担当するもの。
マクロファージ・異物を取り込み、その情報を提示する。
NK細胞・T細胞、B細胞とも異なり、がん細胞などを捕食する。
③NKT細胞→細菌発見された第4の免疫細胞。T細胞とNK細胞の両面を持ち、がん細胞を攻撃する(参照文献10の59頁)。
F 免疫反応
生体に細菌などの異物(抗原antigen)が侵入すると①これを認識して、②分解、無毒化、排除して、③生体を防御する。これを免疫反応というが、免疫には2種類がある。
(1)抗原を無毒化する抗体を産生してこれを放出して免疫を行う「液性免疫」。これはBリンパ球が行う。
(2)リンパ球が直接抗原に接触して分解、無毒化する「細胞性免疫」があり、これはTリンパ球が行う。
「抗原」とは異物が生体に侵入したとき、これに応じて抗体、または異物に特異的に反応する感作Tリンパ球を生成する物質と定義される。抗原の構造に応じて抗体産生細胞によって特異抗体が作られる。通常1個の抗体産生細胞の細胞膜にはある特定の抗原にのみ結合する受容体receptorがある。
「抗体」は血清タンパクのグロブリンであり、特定の抗原に対して1:1の対応を持つ。鍵と鍵穴の関係である。これらは免疫グロブリンIgと呼ばれ、IgG、IgA、IgM、IgD、IgEの5種類である。
リンパ球の免疫作用には、前記のように(1)「液性免疫」と(2)「細胞性免疫」がある。
(1)液性免疫
Bリンパ球が産生する免疫グロブリン抗体(血漿タンパクの一種)で行う。
Bリンパ球の表面には抗体様のIg(immuno globulin免疫グロブリン・グロブリン血漿タンパク)である受容体があり、対応した抗原と結合すると増殖する。ヘルパー/インヂューサーT細胞の助けで、一部は記憶Bリンパ球に分化し、一部は形質細胞になって免疫グロブリンIgG~IgE5種類となる。
(2)細胞性免疫
Tリンパ球が行う。Tリンパ球は①殺害キラーT細胞、②救助ヘルパー/誘導インデューサーT細胞、③抑制サプレッサーT細胞、④記憶メモリーT細胞に分かれる。
①殺害キラーT細胞・抗原を破壊する。この細胞の中にはリンホカイン(活性化物質)を分泌するものがあり、リンホカインによってマクロファージ(組織内単珠)を集め、貪食能を増加させる。このT細胞を実効性エフェクターT細胞という。
②救助ヘルパー/誘導インデューサーT細胞・キラーT細胞やエフェクターT細胞の出現を助ける。特定抗原に反応して免疫応答ができるように導くことを「感作」というが、キラーT細胞などを感作するのがヘルパーT細胞の働きである。
また、B細胞に抗体を作るように指令する。
③抑制サプレッサーT細胞・抗体産生などの免疫反応を抑圧的に調節する。
④記憶メモリーT細胞・一度抗原に接した経験を持つT細胞であるが、同一抗原に遭遇すると、エフェクターT細胞になる。
⑤NK細胞natural killer cell」はTリンパ球、Bリンパ球に属しない大型リンパ球で細菌、がん細胞を攻撃する。(参照文献9の4
6頁)。また、感染細菌、がん細胞を攻撃するNKT細胞natural killer
T cellの存在が認められている(参照文献16の32頁、参照文献10の89頁~)。
⑥がん治療における抗がん剤治療は今、転換期にあるといわれている。抗がん剤が効く体質、そうでない体質、抗がん剤が耐性を持ちやすい人かそうかが遺伝子診断で判明するので、診断を経たうえで抗がん剤治療を行うようになりつつあるからである。
更に、リンパ球のうちのkiller T cellキラーT細胞、natural killer cell ナチュナルキラー細胞、natural kilee T cell NKT細胞(NK細胞とT細胞の機能をあわせ持つもの)ががん治療に有効とされている。特にNKT細胞は正常細胞は攻撃せず、がん細胞を非自己と認識して攻撃する。
小児にみられる神経芽細胞腫のうちのⅣs型のように全身にがんが転移しても自然にがんが消えて完治する場合、患者には必ずkiller T cellが発見され、この型以外の患者にはkiller T cellが発見されず、予後がある医療機関ということは免疫系の活動の証拠となる。
NKT細胞もがん細胞だけを攻撃し、正常細胞は攻撃しない。千葉大の谷口教授はきキリン研究所と共同でNKT細胞を活性化させるアルファガラクトシルセラミドを発見した。これを樹状細胞(抗原提示細胞)に取り込ませ患者に投与するとNKT細胞を活性化させられ、活性化したNKTががん細胞を攻撃するようになる(
参照文献10の89頁~)。
目次に戻る
「消化管の内と外」
口から肛門までは約8メートル。胃、小腸、大腸は口から摂られた食物(食物は糜汁びじゅう状体で小腸を通過し大腸で水分が吸収され、便になる)の通路であるが、食物から栄養は内部、すなわち主に小腸の腸壁からその内側に吸収される。従って、食物が流れる腸管は体の外側、外部であって、栄養が吸収される腸壁の内部が内側、内部でである(だから内視鏡は本当は外視鏡)。
この腸管を流れる食物は抗原の固まりであるから、人体を防御するため多量のB細胞が腸壁に分布し、腸管1cm当たり1億個、B細胞が1日当たり分泌する免疫グロブリンIgAは体重60kgの人で4gといわれる。このIgAは腸管を移動する食物の中に静かに存在するだけで各種細菌が増殖するのを防ぐためのバリア的役割を果たしている(参照文献14の170頁~)。
G その他の免疫問題
①高齢者の免疫
人類の祖先は皮膚、口と肛門を結ぶ腸管だけの海中に住む多細胞生物であったが、その時代では、マクロファージ、NK細胞、胸腺外分化T細胞、初期のB細胞が免疫を
担当していた(古い免疫集団)。
その生物が地上に上陸してからは、鰓は退化してその一部が胸腺となり、そこで進化したT細胞が教育を受け、進化したB細胞らと免疫を担当するようになった(新しい免疫集団)。
加齢により胸腺が萎縮、消滅すると(40歳で10%以下になり、急速に脂肪の塊になる)、新しい免疫集団にかわって古い免疫集団、すなわち腸、肝臓で作られる胸腺外分化T細胞、HK細胞、初期のB細胞が働き出すのである(
参照文献11の270頁~)。
②
免疫と
アレルギー症
花粉症、アトピー皮膚炎などが増えたのは、昔の洟垂れ小僧がいなくなったため。感染菌が侵入するとヘルパーT細胞のうちのTh1細胞が働いて感染を抑えるが、Th1はアレルギーを起こすTh2細胞を抑制する。食品も抗生物質で感染が防止されている清潔生活の現代はTh1細胞の出番がないのでTh2細胞が活発になり、アレルギー症が多発する。解決はTh1人間のTh2人間化しかない
とのことである
(参照文献10の79頁)。
H 神経
血液と並んで神経も重要な働きをしているが、その神経は脳と脊髄にある「中枢神経系」とこれにつながる「末梢神経系」から成り立っている。
末梢神経は動物性機能(運動とか感覚)を調節する「体性神経系」と植物性機能(呼吸・循環・消化など)に関与する「自律神経系」に分けられる。
「体性神経系」には中枢の指令を末梢に伝える「遠心性神経」と感覚情報を中枢に伝える求心性神経があり、自律神経系には、交感神経系と副交感神経系がある(
参照文献9の153頁~)。
免疫に関係するのはこの自律神経系である。自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があり、交感神経は昼間の活動、興奮時に働き、副交感神経は夜間やリラックス、休息時に働く神経である。両者はシーソーのように一方がアップすると、他方はダウンする。
交感神経が優勢な昼間には外敵侵入の可能性があるので、アドレナリン(腎臓のトップにある三角帽的な副腎の髄質から放出)というホルモンを放出して、その受容体を持つ顆粒白血球(好中球、好酸球など)を増やす。
副交感神経が優位な時期には、神経末端からアセチルコリンというを分泌してリンパ球を増やす。両神経のバランスがとれておれば顆粒球とリンパ球も適度の増減を繰り返し問題はないが、交感神経が異常に緊張すると顆粒球が増えすぎ、これが出す活性酸素で周辺正常細胞が酸化、炎症を起こし破壊され、リンパ球が減少するので異物に対する免疫力が低下する。また、増えた顆粒球は常在菌と反応するので粘膜のある場所で炎症を起こし、肝炎、すい炎、急性肺炎を超すたり、自己免疫疾患を起こすことがある。また、副交感神経が抑制されるのでがん細胞を攻撃するリンパ球の数が減りがんが発病する可能性がある。
また、交感神経と副交感神経のアンバランスで低体温状態に陥り、免疫力が低下する(参照文献11の48頁~)
。
自律神経のうち副交感神経が優位になると、抗がん作用があるリンパ球が増加するので、リラックス、睡眠、入浴(シャワーではなく湯船につかる)などで体温を上げ、笑い健康法で免疫力をあげるとよいとされている(安保など前掲書68、256、278頁)。しかし、増え過ぎたリンパ球が花粉などの抗原に過剰に反応し、花粉症、ぜんそくなどのアレルギー反応を起こすことがある(安保など前掲書50頁)。
I 消化
器
生命はその誕生から死滅までの間、その維持には栄養の補給が不可欠である。生命とは食物である、と言う人もいる。
人間の生命は食物からの栄養補給が不可能な状態では、点滴による栄養補給がなされるが、そのような特殊状態以外では消化器による栄養補給が行われる。
消化器は口から肛門までの全長約9メートル(小腸6~7m、大腸1.5~1.7m)の消化管(口腔、食道、胃、小腸。大腸、肛門)と付属消化器(唾液線、肝臓、胆嚢、膵臓)から構成され、食物は約1~3日で消化管を通過し、その間に栄養の吸収が行われる。
食物は口腔で咀嚼、唾液分泌で消化(細分化)され、胃で胃液の分泌など細分化(消化)され、小腸(十二指腸、空腸、回腸)でも膵液、胆汁、腸液などで化学的消化が行われ、蠕動などで機械的にも細分化が行われ、同時に栄養素、水分、ビタミンなどの吸収が行われる。大腸(盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸)は主に水分、ビタミンなどを吸収する(参照文献9の354頁~、16の65頁~)。
J 糖尿病 胃の後ろ辺に長さ約
15cm、幅約2cmの膵臓があるが、膵臓は膵液を分泌するほか、ランゲルハンス島にあるβ細胞からインスリンinsulinというホルモンを分泌する。食事をすると、
インクレチンというホルモンの影響で膵臓のβ細胞はインスリンを分泌し、インスリンは血流中のブドウ糖(グリコース・活動源)を組織細胞に取り込むが、ストレス(多食もストレス)で膵臓機能が低下すると、血中のブドウ糖が増え(血糖値が高くなる)、糖尿病と診断される。糖尿病は神経障害、網膜異常、腎不全などの合併症の原因となる。治療法としてはインスリン投与(注射)、インスリンの分泌を高める薬剤投与などがある。生活習慣病なので、生活改善が予防上、治療上、必要
である。
(3)最後の方法
①病気の治療で一番大事なのは標準治療法の実施である。がんは難病だが、世界中多くの人が罹るので、世界上の医師、研究者、研究機関がその治療法を考案、発表し、審査されて各機関、地域における標準医療が作られ、実施のためのガイドラインが作られている。
この標準医療はその時点における最良医療であるから、医療はまずこれに従わねばならず、もし貴方の医師がこれに従わっていない場合はその理由を聞くべきであり、その理由が納得できない場合は標準医療を行う医療機関にかわるべきである(上野前掲書115頁~)。わが国の医療過誤事件における過失認定基準となる医療水準はこの標準医療が基準となる。
②不幸にも標準医療が効果をあげられない場合は、標準医療実施後に医師と別の特異な医療(例えば、最新医療)を実施するかどうかを相談すべきである。
③厳密な意味での医療ではなく、治療後の一時的退院期間、それが新治療のための待機期間である場合には、民間で普遍的な健康方法を行うことが望ましい。それも迷信とか、新興宗教的な団体が奨めるものは好ましくない。そこでも最低の科学性が維持されねばならない。禁酒、禁煙とか当然で、軽い運動、音楽を聴くなどの誰もが行う健康法は行う価値がある。また、玄米食は
少なくとも便秘解消に役立つであろうし、民間の健康食品でも副作用のないものならOKである。これが最後の方法である。
④死生観確立努力→現代の医療は大体の病を治療できるが、難病指定を受けているような病気は不治であるし、事故以外で病で死ぬ場合の死因となる病(最後の病)は医療も治せない。だからヒトは死ぬのである。日野原博士も最後の病は治せない、だから医師の究極の仕事は患者を看取ること、看護である、と述べている(前掲書
1の154頁~)。
不治と判った場合でも、ある期間生きていくとき、嘆き悲しみつつ生きるのか、覚悟を決めて悠々と生きるのか、どちらをとるかは各自の自由だが、ボクは後者を選びたい。そのために必要なのは死生観の確立である。
前記のように、全細胞には寿命があり、DNA末端の無意味な信号部分テロミア部分が極端に短くなると細胞は分割しなくなり、自然死する。ヒトの寿命が120歳といわれているのもそのせい。
36億年前に誕生した生命体の始原生物は単細胞生物で、分裂再生を繰り返し、死ななかったが、35億年前、多細胞生物が誕生し、雌雄生殖が行われるようになってから、生物は死ぬようになった(参照文献20の136頁以下)。今、人間の細胞は1日3000億~5000億も死んでいるが、その多くは再生で補充され
てい
る(参照文献20の39頁)。しかし、
脳の中枢細胞とか心筋細胞は補充されない(参照文献20の49)。従って最大でも120歳、普通は100歳くらいで人間の寿命は尽きる。地球全体のことを考えると、死は必要不可欠(参照文献20の160頁以下)。
さて、どうして死生観を確立するのだろうか。
参照文献1で日野原は、医師は時には癒やせる、しばしば和らげることができる、常に慰めることはできる、という医師の言葉(出典は不詳)を引用し、今の医師はすべての病気を治せるわけではない医学の全力投球をしている、患者に和らぎや慰めを与えるアートを習得すべきである、としている(156頁)。病で治るのは一部の病で、死因となる最後の病(死病)は誰も治せないことを知るべきである。
⑤死の受容
最近、週刊朝日から『だから死ぬのは怖くない』(朝日新聞出版2011115版)という特集号が出ている。同書24頁以下で、1000人以上の死をみてきた大津医師の「死ぬとき人はどうなる?こうなる」によると、
人の死に方は、がん等で死ぬ場合、心・肺疾患で死ぬ場合、認知症・老衰で死ぬ場合で多少違うが、余命数週間から全身倦怠感等が現れ、余命数日になると傾眠状態等が現れ、余命数時間になると昏睡状態になり、最後は呼吸は下顎呼吸になって呼吸は停止し、酸素供給がなくなり、心臓を動かす筋肉が停止し、心臓が止まり、数分で脳の活動は停止し瞳孔の対光反応がなくなる。この呼吸停止、心臓停止、瞳孔散大で医師は死を認定する(前掲特集号24頁以下。上杉・これは在来的死の認定要件で、臓器移植法の脳死は、脳の全機能が停止を脳死という)。
また、同医師は、がんなどで死が近いことを宣告された患者の心を「否認→怒り→取引(代替医療、神仏依存)→抑うつ→受容」と分析する(前掲特集号31頁以下)。
これは参照文献23のロスが述べているものであるが、参照文献23は自分が末期患者になった場合だけではなく、身近にそのような患者を持つ人必読の書である。
一日も早く死を「受容」することが死を楽にするはずである。我々高齢者は、がんを宣告されていてもいなくても、死を宣告されていることには変わりない。慌てて神仏に走らず、自分なりに死を受容することが肝要だと思う。
もし医療過誤で弁護士に頼みたいが、弁護士に心当たりがないときは、下記方法で京都弁護士会のホームページhttp://www.kyotoben.or.jp/で医療過誤担当弁護士を検索するか、同会で法律相談を受けるか、京都医療過誤弁護団に電話(075-222-0011)してみる。
●京都弁護士会ホームページでの弁護士検索
京都弁護士会ホームページ→トップページ→弁護士を探す→注意事項ページ・同意する→京都弁護士検索・医療事故(患者側)にチェック入れる→検索
目次に戻る
1・日野原重明『医学概論』医学書院2010年2月第1版第10刷
2・神前格『患者学―誰でもいつかは患者になる』マガジンハウス2000年6月第1刷
3・柳原和子『がん患者学―長期生存をとげた患者に学ぶ』晶文社2000年7月初版
4・上野直人『最高の医療をうけるための患者学』講談社+α新書2006年7月刊
5・北澤京子『患者のための医療情報収集ガイド』ちくま新書2009年6月第1刷
6・橋本信也責任編集『新・検査マニュアル』照林社2004年7月第2版第15刷
7・石川順子・谷直樹『患者のための医療法律相談』法学書院2010年9月初版第1刷
8・『症状でわかる医学百科』主婦と生活社1997年8月第34刷
9・伊藤直樹・平井直樹『生理学』医学評論社2001年7月第3版第2刷
10・谷口克『免疫、その脅威のメカニズム』2007年5月第11刷
11・安保徹・石原結實・福田實『非常識の医学書』実業之日本社2009年5月初版第3刷
12・患者の権利オンブズマン全国連絡委員会『オンブズマン・レポート苦情調査報告書集』株式会社エビック2004年10月刊
13・谷口直之・杉山治夫・松浦成昭『がんをどうして治すか』中山書店1996年10月第1刷
14・多田富雄『免疫の意味論』青土社1995年3月第26刷
15・多田富雄『生命の意味論』新潮社1997年4月1997年4月第4刷
16・内藤通孝『解剖生理学入門』昭和堂2007年11月初版
17・内藤通孝『病理学入門』昭和堂2011年4月初版第1刷
18・中川恵一『ドクター中川の”がんを知る”』毎日新聞社2008年9月第3刷
19・中川恵一『続☆ドクター中川の”がんを知る”』毎日新聞社2009年4月第1刷
20・田沼靖一『ヒトはどうして死ぬか―死の遺伝子の謎』幻冬舎2010年7月第1刷
21・小林弘幸『なぜ、「これ」は健康にいいのか』サンマーク出版2011年9月第12刷
22・週刊朝日MOOK『だから死ぬのは怖くない』朝日新聞出版2011年1月刊
new
23・E・キューブラー・ロス『Death and Dying・死ぬ瞬間―死とその課程について』鈴木晶訳2011年2月13刷
new
目次に戻る|トップページに戻る