�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�܂�����
��@����
�܂�����
�@�N���Ƃ�ƒi�X�A���������Ȃ�B������N�Ɉ�炢�͎����a�Ŏ���҂̂����b�ɂȂ�B�u�e�m�炸�E�q���i��O�P���j�v�̎��͂����Ɉ����Ȃ�B
�������ꎕ������B
�@���s�{���Ȉ�t��͖����܂��͈ψ����鎕�Ȉ�t�P�`�R���ɂ�鎕�ȕ����̖������ق��s���Ă��邪�A�����P�Q�N�̐\�������͂P�T�O���i���s�{��t��ւ̈�ʈ㎖�����ɑ��钇�ِ\���͂Q�P���j�B
�N�ԏI�������͖�P�T�O���B���Ӑ����͖�P�O���A�A�h�o�C�X�ŏI���͖�P�S�O���B���ȂɊւ��镴���͑����B
�@�����ŋ��s�ۑP�ɍs���A�����L�ڂ̂悤�Ȗ{���ēǂ݁A����G���w�����x���玕�ȊW�̈�Éߌ딻����W�߂Ă݂�
�i���Ȃ̈�Éߌ�ɂ��ẮA�ᏼ�z�q�u���Ȉ�Éߌ�i�ׂ̉ۑ�ƓW�]�v���E�v�z�Ђ�����j�B
�@
�@��ƁA���Ȉ�Ƃ̍L���ɂ͐f�ÉȖڂ��܂܂�i��Ö@��U�X���P���Q�A�R���j�A�f�ÉȖڂ͐��߂���߂邱�ƂƂȂ��Ă���i���@��V�O���j�B ��Ö@�{�s�ߑ�R���̂P�P��Q���́A���Ȃ̈�ÉȖڂ��A���ȁA�������ȁA�������ȁA���Ȍ��o�O�Ȃ̎l�Ƃ��Ă���B
�@
�@������Ȏ��ȑ�w���_�������R�F�Y�w���w�T�_�x�㎕��o�łɂ��ƁA���Ȉ�ÂƂ́u���҂̌��o���ɑ��݂��鎾���������A�������C����Ԃ��āA����Ȍ��o�̌`�Ԃ�@�\�����A����
���x��Ȃ��Љ�����c�߂�悤�ɂ��邱�Ɓv�Ƃ���Ă���i�P�Łj�B
�@���̓�厾���͒����iꚐI�Eꚁ����{�Z�ނ��j�Ǝ����a
�Ƃ����Ă���B���J����ɂ͂����̜늳���͒Ⴉ�����B�������A��炩�����́A�Â��H�i������������A�����Ǝ����a�����������B
�@�����������a�����ʂ͒��ڐ����̋��ЂƂ͂Ȃ�Ȃ����A���̌��N�͊ԐړI�ɂ͑S�g�̌��N�ɏd�v�ȊW��L���邱�Ƃ��m���Ă�������łȂ��A���̌��N���K���ȓ��퐶���𑗂邱�ƂɕK�{�ł��邱�Ƃ��ӎ������悤�ɂ�
��A��i���ł͎��Ȉ�Âɑ�����v���}���ɑ��債�Ă���i���R�O�f�w�T�_�x�R�V�Łj�B
�@���̎��Âɂ͈�ʂ̈�ÂƂ͂������邵��������m����\�͂�K�v�Ƃ���B���͐F�X�ȐH�������ݍӂ��A���݂Ԃ��đ̓��ɑ��荞�܂˂Ȃ�ʂ��߁A���̑g�D�̒��ł��ł��d�łȍd�g�D�ō���Ă���A���̍d�g�D�͍Đ��\�͂̂Ȃ����Ύ��g�D�ł��邽�߂ɁA����ɐ��������a�ɂ́A�ق��̑g�D�ɂ݂���悤�Ȏ��R�������Ȃ��A�l�H�I�Ɉٕ�����
���镨���ɂ��U��C�����K�v�ɂȂ�B
�@�܂����̙@�\�����邽�߂ɂ͍��x�̗͊w�I���S�ɑς���悤�ɁA�H�w�I�Ȋw����p���Z�p�����x�ɋ�g���Ȃ���Ȃ炸�A���̂ق����ɂ͋����R���I�v��������̂ŁA���x�̌|�p�I���o�Ǝ����K�v�Ƃ���B���̂��ߎ��Ȉ�Â͈�Â̈ꕔ��ł���̂�������炸�A��Â̂ق��̕���Ƃ͂��̎d���̓��e���������邵���قȂ�A���̏]���҂�{������ɂ���ʈ�ÂƂ͈ق�
�鋳��P�����K�v�Ƃ���Ă���i���R�O�f�w�T�_�x�R�V�`�R�W�Łj�B
�@��ʂ̈�w����ɔ�r����Ǝ��w����ɂ͎��K�������B���w����ɂ����Ă̓q�g�̑̑S�ʂɂ킽��ڍׂȒm���̊l���͗v�����ꂸ�A�{���o�̈�ɂ��Ă̒m���l������̓I�Ȃ��̂Ƃ��āA���ȗՏ�����ړI�Ƃ������炪�Ȃ����i�O�㔪�Y�u���Ȉ�Éߌ�i�ׂ̖��_�v���o���F�A�������i�ҁw����ٔ��@��n�V��Éߌ�x�V���{�@�K�Q�T�O�Łj�B
�@
�P�@���Ȉ�Â̎菇
�@���Ȏ��Â̎菇�͂ق���ʈ�ÂƓ������A�����I�ɂ́A��Â̐\���A�i��Ì_��̐����j�A��Â̎��{�A���Ô�̎x�����i�Љ�ی��f�Õ�V�x������Ȃǂɑ���
�f�Õ�V�����A���҂̈ꕔ���S���x�����j�Ƃ����o�߂��Ƃ�B
�@
�Q�@���҂ƈ�t�̖@���W
�@�g���s���̊��҂��ӎ��s���̏�Ԃŋ~�}�a�@�ɔ�������A�ً}��Â��n�܂�A�Ƃ����悤�Ȉُ�A���ʂȏꍇ�i���̂悤�ȏꍇ�A�����͖��@�U�X�V���ȉ��̎����Ǘ��W�ŏ�������A�ً}��Ԃ����������A�ʏ�̌_��W�A���Ȃ킿��Ì_��W���\�z�����̂����ʂł���B�A���_��W���\�z����Ȃ��܂܂Ɋ��Ҏ��S�ň�Â��I�����邱�Ƃ�����j�������ẮA���ґ��͈�Ë@�ցi��Ö@��ł́A�Q�O�l�ȏ�̊��Ҏ��e�{�݂�L�����Î{�݂�a�@�A�P�X�l�ȉ��̎��e�\�͂�L������̂�
�f�Ï��Ƃ����B��P���̂T�j�ɑ��i���҂��O���l�Ŗ��ی��̏ꍇ�͕ʂƂ��āj�e�팒�N�ی�����Ď�f��\�����݁A���ꂪ�t�����邱�Ƃň�ÊW���������Ĉ�Â��J�n�����B
�@���̍ہA�����ҊԂɂ͈�Ì_������A�Ƃ��������̈ӎv�\���͂Ȃ��A�܂��_�쐬�Ȃǂ̌`���I�s�ׂ��Ȃ���Ȃ����A��ÊJ�n�̑O��Ƃ��Ă̈�Ì_��i���ґ��̈�Ð\�����݂ƈ�Ë@�ւ̏����j�����������A�ƍl������̂ł��� �i���É��ٌ�m��ҁw��Ì_�Ɋւ�����x�Q�O�O�Q�N�R���́A��Ë@�ւƊ��ҊԂɒ������ׂ���Ì_���f�����Ă�����̂ł���j�B
�@
�R�@��Ì_��̐���
�@���̈�Ì_��͂ǂ̂悤�Ȍ_��ł��낤���B
�@�䂪���@��A���l�̘J�͂𗘗p����_��ɂ͌ٗp�i���@�U�Q�R���ȉ��j�A�����i���@���ȉ��j�A�ϔC�i�U�S�R���ȉ��j�A����i�U�T�V���ȉ��j�����邪�A��Ì_��͂��̂����̐����_�A�ٗp�_�A�ϔC�_�A����Ƃ�����Ȗ����_��ł��낤���B
�@
�@�@�ٗp�_��ɂ����ẮA�ٗp�傪�J���҂̒���J���͂̎x�z�҂ɂȂ�̂ł��邩��A��Ì_����ٗp�_��Ƃ݂�̂́A��t�̕����D�z�҂Ƃ����ׂ���Â̎��Ԃɂ�����Ȃ��i�h�C�c�ɂ����Ă͈ϔC�_��̐�Ζ���������
��Ì_��͔�p�҂̍��x�̔\�͂Ɉˑ��������Ȍٗp�_��Ƃ݂��Ă���B�O�c�B���E��_���E�蓈�L�Ғ��w�㎖�@�x�L��t�Q�P�S�Łj�B
�@�����_��͎d���̊�����ړI�Ƃ�����̂ł���i���@�U�R�Q���j�B��Â̂Ȃ��ɂ͔��e���`�Ƃ��A�`��������s�ׂ̂悤�ɁA�d���̊�����ړI�Ƃ���Ƃ��������Ȃ��̂����邪�A�����łȂ��A���a�̑��푽�l���A���a�ɂ���Ă͕a���s���Ƃ��A���Ö@���m�������邱�ƁA�����ɏd��ȉe�������銳�҂̑S�g��Ԃ̑��l���Ȃǂ���A�����A�~���ɂ��Ă̒f���I���f������A�s�m��v�f�̑�����ʈ�Âɂ����ẮA�����Ƃ��A�~���Ƃ��Ƃ����d���̊����͌_��̖ړI�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ǝv����i���ґ��͎����A�~�����_��̖ړI�ɂ��������낤���A��Â̕s�m�������炷��ƁA�_��̑�����ł����t�͂���ɂ͉����Ȃ����낤�B�����҂̈�������錋�ʂ���]���Ă����肪����ɉ����Ȃ���A���Ӑ����A���Ȃ킿�_���Ƃ͂����Ȃ��̂ł���j�B
�@��Âł͎����A�~���͊��ґ��A��Ñ��o���̍ŏI��]�ł͂��邪�A��Â̎��Ԃ��炷��ƁA���̎����͊m���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�s�m���ł��邱�Ƃ͊��ґ�����Ñ����\�����m���Ă���B�]���Ĉ�Ì_��͒ʏ�͐����_��ɓ���܂Ȃ��B
�@
�S�@���ϔC�_��
�@���{�̖��@�ł͈ϔC�̑Ώۍs�ׂ͖@���s�ׂɌ��肳�ꂸ�A�����s�ׂł��悢�Ƃ���Ă���i���@�U�S�R���A�U�T�U���j�A��҂�ΏۂƂ�����̂��u���ϔC�v�Ƃ����B
�@���{���@�͉��v�I�ɂ̓��[�}�@�ɑk�邪�A���[�}�@���ł��@���s�ׂ����ł͂Ȃ��A�����s�ׂ��ϔC�̑ΏۂƂȂ�A��Â��ϔC�̑ΏۂƂȂ�J���̈�Ƃ��ꂽ�B�A���A�ϔC��̍��͋`���ƗF��Ɋ�Â����̂ł��邩��A�����łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ���Ă����B
�@���̂��߁A���ł����{���@�́A�ϔC�͖����������Ƃ���A�ƒ�߂Ă���i���@�U�S�W���P���j�B�����Ƃ��A���[�}�@���ł��ϔC�̎ӗ���͍m�肳��Ă���A���{���@��������Ε�V����������������ƒ�߂Ă���i���@�U�S�W���P���j�A�̂����Â̎��ۂł́u���ԑ�v������A��Â̗L�������蒅���Ă����B
�@�h�C�c�ł͈ϔC�̖������͌������K�肳��A���߂���Ă��邩��A��Ì_����ϔC�_��Ƃ݂�ƈ�t�̕�V�擾���ے肳��邩��A�O�L�̂悤�ɁA��Ì_��͓���Ȍٗp�_��Ƃ݂��Ă���B���̂悤�ȁu�ϔC�̖������v�̐���̂Ȃ��䂪���ł́A��Ì_��͏��ϔC�ł���A�Ƃ݂�̂��ʐ��Ƃ���Ă���i�����̖��ɂ��Ă͊���ʁE�L���r�Y�ҁw�V�Œ��ߖ��@�x�L��t�P�U���Q�P�P�ňȉ��A�Q�R�R�ŁA�O�c�B���ȂǑO�f�w�㎖�@�x�Q�O�W�ňȉ��A�蓈�L�u��t�̖����ӔC�𒆐S�Ƃ����㎖�@���j�v����~�E�L�c��Ғ��w�������@���l����x�@�������ЂP�O�T�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@
�T�@���Ȉ�Ì_������ϔC�_�H
�i�P�j���Ȉ�Â̂����A���Ȉオ�������⎕���a�����Â���s�ׂ͔畆�Ȉオ���]��畆�^ᇂ����Â���̂Ƃ����ς��͂Ȃ�����A���̈�Ì_��͏��ϔC�_��ƍl������B
�@
�i�Q�j���������Ȉ�Â̂����̕�ԁi�{���̎���l�H���ɒu�������邱�ƁB�����ŋl�ߕ���������A�N���E�������Ԃ�����A�����������ƂɃu���b�W����ꂽ��A�������ꎕ����ꂽ�肷�邱�Ɓj�Ƃ�������̎��Ȏ��Âɂ��Ă͐����I�F�ʂ�
����i�A�ؓN�u���_�v�A�ؓN�ق��w��Ô���K�C�h�x�L��t�Q�S�ł��A���Ȉ�Â̂��镪��ł͐����_�������ӎ������A�Ƃ����B���F�l�c�B�A���ٔ����ł���W���[�b�y�E�x���b���u��t�\���ҊW�̕ω��v�}���A���|�U�E�_���E�R�X�^�Ғ����c�R���E���۔���q��w��w�̖\�͂ɂ��炳��鏗���x�C���p�N�g�o�ŎЂW�P�ł́A�ȒP�Ȑf�f�⎡�Â��p�ł́A�ӔC�̘g�g�݂��A���ʍ��ƌ��т����]���������i�Ȃ��̂ƂȂ����B�E�E�E�E���ɔ��e�O�Ȃ̗̈�ł́A�O�Ȉ�͎�i���������ł͂Ȃ��A���҂����������ʂ�B�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���l�̊�͎��Ȋw�ōs���镜����p�ɂ����Ă͂܂�A�Əq�ׂ�j�B
�@�؍ށA�S�ށA�R���N���[�g�Ȃǂ̑f�ނ��g���ĉƂ�A�Ƃ����s�ׂƎ�X�̑f�ނœ��ꎕ�����Ƃ����s�ׂ́A���m�̑召�̈Ⴂ�͂����Ă��쐻�Ƃ����s�ׂ̖{���ɂ͂��قǂ̑���͂Ȃ��B
�@
�i�R�j�܂���Õی��̖ʂł���ԕ��͓�N�Ԃ̕ۏ�����A�����W�N�ȍ~�ł͂��邪�A��N�ȓ��ł���Εs�s���̕�Ԃ͖����ł�蒼���Ă����Ƃ̂��Ƃł���i�������ȕی���Éۓ��ďC�w���ȓ_���\�̉��ߕ����P�O�N�Łx�Љ�ی��������R�U�W�ŁA�O��O�f�u���_�v�Q�T�P�ŁB�j
�@�Ȃ��ɂ́A�ܔN�ȓ��̏ꍇ�͖����ŁA�\�N��ł����z�ł�蒼���Ƃ������Ȉ������B�ۋ����w���E�ǂ����È������Â̌��������x�P�S�P�Łj�B
�@�ی��O�̎��Ȏ��R�f�Âɂ����Ă��A���l�ɓ�N�ԕ�Ԃ̕ۏ��s���Ă���Ƃ��낪����A�Ƃ������Ƃł���i�O��O�f�u���_�v�Q�T�P�Łj�B
�@
�i�S�j��������ԂƂ������Ȉ�Â���Ԃ�v���鎾�a���Ⴆ�Β����ł���A�����ɕ�Ԃ��s����̂ł͂Ȃ��A�܂���f�A���f�A�ꍇ�ɂ���Ă�X�������A�����̐f�f�i����ꚐI�̒��x�j�AꚐI���̏����A�E�ہAꚐI�������܂ŋy��ł���ꍇ�͖��������Ď��������A���ŁA���|�ȂǏd�v�Ȏ��Ȏ��Â̈�ł��鍪�ǎ��Â���s����B
�@���̌�A���^�i��ہj���Ƃ�A�����̓��i���ݍ��킹�j���Đp�͌^��ŕ�ԕ������A���o���Ŏ������ĕ����A�Ƃ������Ƃňꉞ���Â͏I�����邪�A���̌����Ԃ̕s��A��Ԃɂ�鎕���a�̈����A�����̕s����甭������{�ߏǂȂǂ��܂��܂ȏ�Q���������A����ɑΉ�����������Ȃ����Ƃ�����B
�@
�i�T�j�������l����ƁA��Ԃ���ʂ̈�ÂƓ������A�P�Ƀ��m�̐���Ƃ�����Ƃł͂Ȃ��A���܂��܂ȕs�m��v�f����������Ís�ׂł���A���ϔC�_��̑ΏۂƂȂ���̂ƍl����̂��Ó��ł��낤�i���|�O��O�f�u���_�v�Q�T�Q�Łj�B
�@�������Ȃ��Ǝ��Ȏ��Â̂��镔���͏��ϔC�A���镔���͐����A�Ƃ������ƂɂȂ�A���G�Ȗ@���W�ɂȂ��Ă��܂��A��ςł���B
�@
�i�U�j�O�L�A��ԕ��Ɋւ���ۏ́A��ԂƂ������Ȏ��Âɑ��݂����̐����I�F�ʂ��l�����āA���Ȉ�Â̎��ۂŌ`�����ꂽ�S�ۊ��s�ł���Ǝv���B
�@�Ȃ��A��ÑS�ʂɂ����Ď��Ô�͎��Â̓s�x�̌ʓI�㕥���ł��邪�A�����ł��ϔC�ł���V�͌㕥���������ł���i�U�R�R�A�U�S�W���j�A���̓_�͎��Ȉ�Âł������ł���B
�@
�i�V�j���R�f�Â̕�Ԃɂ͍��z�ȋM�������ޗ��ɂ����邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�A���앨�̏��L���͒N�̂��̂��낤���B
�@�ޗ��͎��Ȉ㑤������̂����ʂł��邩��A���앨�̏��L���͓����͎��Ȉ㑤�ɂ���B��Ԃ��I��莡�Ô���x����ꂽ�ꍇ�́A�ŏI��Ԃ̎��Ɉ��n���������Ƃ��āA���̎��_�ɏ��L���͊��ґ��Ɉړ]����B
�@�����s�������A���҂�����̈ꕔ���x����Ȃ��ꍇ�A���Ȉ�͐��앨�����҂Ɉ����n���Ȃ����Ƃ�����B�܂�œ��Y�̔����ɂ����Ĕ���͔����ړI���ɐ������i���@��R�P�P���U���j��L����悤�ɁA�����Ȑ��앨���S�ۂɂȂ��Ă���̂ł���B
�@���̂悤�ȏꍇ�A��Ԏ��Â̂����̓K�������ɂ��Ă͎��Ȉ�͕�V���擾�ł��邪�A������Ԃ��s��ł���A�s��ɑΉ������Ô�͐����ł��Ȃ��B�s��ɂ��Ă̑����͍ŏI�I�ɂ͍ٔ����̔��f�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���҂���Ô�S�z���x�����ς݂̏ꍇ�͕�Ԃ̍ۂɐ��앨�͊��҂Ɉ����n����A���҂̏��L���ɂȂ����̂ł��邩��A�O�L��Ê��s�Ɋ�Â��A���̏C����C�𐿋����A�ǂ����Ă��s��̏ꍇ�͊��҂͈�Ì_����������Ďx�����ςݎ��Ô�̕Ԋ҂𐿋��ł���B���̏ꍇ�͐��앨�͎��Ȉ㑤�ɕԊ҂��邱�ƂƂȂ�i���̏ꍇ�͓������s�ƂȂ�B���@��T�S�U���j�B
�@���Ƃ��ƁA���Ô�̊z�͍��ӂŌ��肳�����̂ł��邪�A���N�ی����ł͈�Ñ������肵�A�_�����������ÁA����A�����Ȃǂ̔�p�A��V�����̂܂��Ô�z�ƂȂ�i�����Ƃ��A�H�ɂ͉ߏ��V���x������̐R���Ŕے肳��邱�Ƃ�����j�B���̎x�����������ӂŌ���\�ł��邪�A���Ȃ���Ό㕥���ƂȂ�i���@�U�S�W���Q���{���j�B��������C�҂͔�p�̑O����������������i���@�U�S�X���j�A���Âɐ旧������p���x�������Ƃ�����B���Ô�͑S���Â��I�������Ƃ��Ɏx����������������̂ł͂Ȃ��A���܂���I�ɁA����̎��Â��I������Ƃ��Ɏx������B���ꂪ���s�I�����ł���B
�@�������҂��i�K�I���Ô��s�����̏ꍇ�ł���Ñ��͐f�Ë��ۂ͂ł��Ȃ��Ƃ���Ă���i��t�@�P�X���P���A���Ȉ�t�@�P�X���P���B�O�c�B���ق��Ғ��w�㎖�@�x�L��t�V�R�Łj�B���������̉����`���ᔽ�ɂ͌Y���K��͂Ȃ��i�h�C�c�ł͈�t�ɉ����`���͂Ȃ��j�B
�@
�i�W�j�����_��ɂ�������҂̍��͈��̌��ʂ̎�����ړI�Ƃ��邪�A�ϔC�_��ł͌��ʂ̎����܂ł͖ړI�Ƃ��Ă��炸�A���ʎ����̂��߂̉ߒ���ړI�Ƃ���A�Ƃ����Ă���B�O�҂��u���ʍ��v�A��҂��u��i���v�Ƃ������Ƃ�����B��������҂ł����ʎ����Ɍ����čőP���������Ƃ��v�������i���@��U�S�S���B���c�M�w���@�V�����_�E�S�ە����x�P�T�A�P�U�ŎQ�Ɓj�B
�i�X�j��ÐN�P
�@���Ȉ�t�����҂ɑ��Ď��Â��s���Ƃ��A���҂̎����������A���������肷�邱�Ƃ͊��҂̓��̂�N�Q����B�R�������𓊗^���Ă������̗L�v�����������ł���Ƃ�������p��^����_�ŐN�Q�ɓ�����B������t�̐N�Q�s�ׂ͈�ÐN�P�܂��͒P�Ɂu�N�P�v�ƌĂ�邪�A���̍s�ׂ͌Y�@�̋Ɩ���ߎ��v�����߁i�Y�@�Q�P�P��O�i�E�Ɩ���K�v�Ȓ��ӂ�ӂ�A����Đl�������������҂́A�ܔN�ȉ��̒����Ⴕ���͋Ŗ��͌\���~�ȉ��̔����ɏ�����B�j�ɓ�����Ȃ����B���Ȉ�t�͑i�ǂ���Ȃ��̂����ʂł���B���̂��H�Y�@�R�T���́u�@�ߖ��͐����ȋƖ��ɂ��s�ׂ́A�����Ȃ��B�v�ƋK�肷��B���Y�̎��s����ȑ��c�s�ׂ���@�Ƃ���Ȃ��̂͂��̋K��ɂ��B����͈�@���j�p���R�Ƃ������A���̋K��̂ق��ɂ��u��Q�҂̓��Ӂv����@���j�p���R������B��O�́A��t�̐N�P�͂��̋K��A���Ȃ킿�u�����ȋƖ��s�ׁv�Ƃ������_�ň�@����j�p����Ƃ����Ă������A���͊��҂̓��Ӂi�܂��͐���I���Ӂj����@����j�p����A�Ƃ�����悤�ɂȂ����B
�A�N�P�̈�@���j�p�̂��߂ɂ͊��҂̓��ӂ��K�v�ƂȂ邪�A���ӂ�����ɂ͎��O�̐������K�v�ƂȂ�B������informed
consent��inform���A�������K�v�ƂȂ�̂ł���B
�B���̐N�P�̈�@���j�p���Ƃ͕ʂɁA���҂ƈ�Ñ��Ƃ̏��ϔC�_���ł���t���͊��҂ɐf�Â̌��ʒm�蓾�������A�����̌`�Ŋ��҂ɓ`����`���i���j������Ƃ���Ă��邵�A�_��W���Ȃ��A�Ⴆ�Ύ����Ǘ��̏ꍇ�ł��قړ��l�̋`������������̂ł���B
�C�܂���Ö@��P���̂S��Q�����u��t�A���Ȉ�t�A��t�A�Ō�t���̑���Â̒S����́A��Â����ɓ�����A�K�Ȑ������s���A��Â���҂̗�����悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ɛ����`���ɂ��Ă̋K���u���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B
�D���̂悤�ɁA��Âɂ����ẮA��X�̊ϓ_�����Ñ��̊��҂ɑ���
�����A���ґ��̓��ӂ��K�v�ł��邪�A�����͒N�ɑ��ĂȂ���A�N�̓��ӂ�����悢���A�Ƃ�����肪����B
�@�������邱�ƂƓ��ӂ��邱�Ƃ͈قȂ�s�ׂł���B�Ⴆ�Ί��̕a�����m�͐e�������ɂȂ���āA���҂ɂ͂Ȃ���Ȃ����Ƃ����F����邱�Ƃ�����B�������݂̓E�o��p
�͐e�������ӂ��Ă��A���Җ{�l�����ӂ��Ȃ��ꍇ�ɂ͎�p�͋�����Ȃ��A�Ƃ����ׂ��ł���A�����̑�������Ɠ��ӎ�̖̂��͕ʌ̖��ł���B
�@�������A���ʂȏꍇ�������A���ʂ͐����̑�����Ɠ��ӎ�͈̂�v����B
�E
�����I�ɂ͊��Җ{�l������������ł���A���ӎ�̂ł���B��������Âɂ����Ă͑��̌_��W�ƈقȂ�A�Ƒ��̉ʂ�����������ϑ傫���B�×{���̂ɂ��Ă����ł͂Ȃ��A��Ô�̎x�����A���҂����S�����ꍇ�̈�̂̈��������l���Ă��A��Ñ��͉Ƒ��̖������d���݂�B������Ƃ����Đ����̑�����Ƃ��Ė������ɉƑ���D�悳������A�Ƒ������Җ{�l�ƕ���I�ɍl����̂͌��ł���B�Ƒ��������̑�����Ƃ��ēo�ꂷ��̂́A
���ꂪ�K�v�ŁA���̂��Ƃ����҂��������A�Ƒ����������]����ꍇ�ł���i�����n�ٕ����P�R�N�R���Q�P�������w�����x�P�V�V�O���P�O�X�ł́A���Җ{�l�ւ̐����A���ӂȂ��ɁA���̕v�ւ̐����A���ӂŎq�{��E�o�����̂���@�Ƃ��āA���Җ{�l�̑��Q����������F�e�j�B
�F
���Җ{�l�ɔN��A���_��Q�Ȃǂɂ��ӎv�\�͏�}�C�i�X�v�����傫���A�����̗���\�͂��s�����A���������Ӗ��ł�������A��p�̓��ӂ����߂Ă����̈Ӌ`�𗝉��ł����A�k�ɋ��|�̗]���p�����ۂ��邱�Ƃ��\�z�����悤�ȏꍇ�ɂ́A���҂̖@��㗝�l�i�e���ҁA�����N�㌩�l�A���l�㌩�l�j�������̑�����ƂȂ�A���ӂ̎�̂ƂȂ�B�����������N�҂ł��A����\�͂�����ꍇ�ɂ͐����̑�����A���ӂ̎�̂ƂȂ肦�邵�A�@��㗝�l�͕���I���݂ƂȂ�B���_��Q�҂ł����̎��_�ňӎv�\�͂�����A����l�Ƃ��Ď�舵���Ă悢�B��������A�ӎv�\�͂̏ؖ����K�v�ɂȂ邱�Ƃ��o�債�Ă����K�v������B������̏ꍇ�ł��A�d��ȐN�P�̑O��Ƃ��Ă̐������Ȃ����ꍇ�ɂ́A���҂��c���Ƃ��A���S�Ȉӎv���\�͎҂ł���ꍇ�ȊO�ɂ́A���Җ{�l�ɑ�������Ɠ��ӂ����߂�w�͂��K�v�ł���B
�G���Ȉ�Â̏ꍇ�A�����̒������x�̂��̂ł���A�ȒP�Ȑ����Ə��u�ɑ��铯�Ӂi���ۈȊO�͈Öق̓��ӂƂ݂Ȃ����j�ŏ�������邪�A���u���_�o���Ƃ�ȂǁA��x���ɁA���ʂ̏d�含�����܂�ɂ�Đ����͂��ڍׂɂȂ����ׂ��ł���A�������̔����͈��̎�p�ł��邩�炻�ꑊ���̑Ή����K�v�ł���A�C���v�����g���Â̂悤�ɕی��O�ō��z�̈�Ô�S����悤�ȏꍇ�ɂ͏\���Ȑ����A���ӂ��K�v�ƂȂ�B
�H�~�}���҂��ӎ��s���̏ꍇ�A��t�͑Ó��ȋً}�[�u���s�����Ƃ��ł���B�ߐe�҂̒����Ȃǂً͋}�[�u�ɂȂ����ׂ��ł���B�ً}�[�u�͐����A���ӂȂ��Ă���@����j�p����B���@�X�U�W�����A�ً}�����Ǘ��͊Ǘ��҂Ɉ��ӁA�d�ߎ����Ȃ�������Ɛӂ����A�ƋK�肵�Ă���B
�@�ӎ�������ΐ����A���ӂ͊��Җ{�l�ɑ��čs���邪�A�ӎ���Q������A�����̗×{���K�v�Ɨ\�z�����ꍇ�͐��l�㌩�l�̑I�C���K�v�ƂȂ낤�B�ߐe�҂��������Ȃ��ꍇ�͌��@���ɑ��k�A���҂��U�T�Έȏ�̏ꍇ�͘V�l�����@�R�Q���Ŏs�������ɑ��k���邱�Ƃ��ł���i���_��Q�҂̈�ÁA�ی�ɂ��Ắu���_�ی��y�ѐ��_��Q�ҕ����Ɋւ���@���v�Q�Ɓj�B
�I�ō��ّ�@�쏺�a�T�U�N�U���P�X�������w�����x�P�O�P�P���T�S�ł́A�P�O�̊��҂̊J����p�����ŁA��t�͎�p�̓��e�A�댯�������Җ��͂��̖@��㗝�l�ɐ�������`��������A�Əq�ׂĂ���B�P�O�̎q���ɂ�����\�͂�F�߂����̂��A�����́u���́v�Ƃ��Ă��邩��A�P�O�̎q���Ɩ@��㗝�l�̂ǂ��炩�ɐ�������Α����Əq�ׂĂ���̂��͂����肵�Ȃ�
�B
�J�{���͑㗝���x�͖@���s�ׂ̑㗝��ړI�Ƃ�����̂ł��邪�A�e���ҁA�㌩�l�Ƃ����{�l�̖����n�A���_��Q�Ȃǃ}�C�i�X�v����O��Ƃ���@��㗝���x�ł͖@���s�ׂ̑㗝�����ł͂Ȃ��A�{�l�̋���A�×{�Ō�Ɋւ��錠���������Ă���i�e���҂͑Ó��Ȕ͈͂Ŗ����N���ł��邵�A���l�㌩�l�͐g��Ō�Ɋւ��邠���錠�������Ƃ���Ă���B���@�W�Q�O�A�W�Q�Q���A�W�T�W���B���я��F�E��勧�Ғ��w�V���N�㌩���x�̉���x�����P�S�P�ňȉ��j�B
�K��Â̌����͖@���Ƃ̏펯�I�v�l�����Ƃ���œ����Ă���B�Ⴆ�ΐ[���Ȋ��̏ꍇ�A���Җ{�l�ɂ��Ƒ��ɂ��������m���Ȃ����Ƃ��s���A���������F���Ă��Ă���i�ō��ّ�O���@�약���V�N�S���Q�T�������w�����x�P�T�R�O���T�R�Łj�B������̂悤�ȏꍇ�ł���Ï��u�ɂ��Ă̏����͂Ƃ��Ă��邾�낤���A���̑O��ƂȂ�����͋��U�̂��̂Ȃ̂ł���B�@
�@�~�}��ÁA���_��Q�҂ւ̎��Âɂ����ẮA�����A���ӂ�ʂ��Ă̊��ҕی�͂��܂��@�\�����A���ʂ��悵�Ƃ���A�Ƃ������ʎ�`�������Ă���悤�Ɏv����B
�ڎ��ɂ��ǂ�B
�@���҂̌������ɂ��Ă͉p�Ă͐�i���ƌ�����B
�@�P�X�W�S�N�A�f�|�^�ی�@���������C�M���X�ł́A�R���s���|�^�|�������\�ȃf�|�^�Ɋւ��A�f�|�^��́i�Ⴆ�Ί��ҁj�̓f�|�^���p�ҁi�ۗL�ҁj�Ƀf�|�^�ۗL�̗L���A���̃R�s�|�̌�t��v���ł��錠����F�߁i�Q�P���j�A�f�|�^���s���m�̏ꍇ�͂��̏C���������\�ƋK�肵���i�Q�S���j�B�P�X�X�O�N�ɂ͈�ËL�^�A�N�Z�X�@�𐧒肵�A�d��������Ă��Ȃ���ËL�^�Ɋւ��Ă����҂ɓ����悤�Ȍ�����F�߂��B
�@�A�����J�ł͂P�V�V�S�N�A�A�M�����Ȍ��O�q���Ǐ��ǂ̕a�@�ȂǘA�M���{�n�a�@�Ɋւ��Đ��肳�ꂽ�A�M�v���C�o�V�|�@�̓J���e�̉{���A�R�s�|������F�߁A�T�O�B�̂�����������������B�����҂̃A�N�Z�X����F�߂�@���𐧒肵�Ă���i�ێR�p��u��ËL�^�ɑ��銳�҂̃A�N�Z�X���E�p�Ă̖@���v�W�����X�g�P�P�S�Q���S�X�ňȉ��j�B
�@
�@���{�ł͂ǂ����B�w�W�����X�g�x�P�P�S�Q���S�ňȉ��̍��k��u�J���e���̐f�Ï��̊��p�Ɋւ��錟��������߂����āv�ɂ��ƁA�P�X�X�U�N�P�P���̍�����Ñ��������R�c��ԕ��y�ї^�}��Õی����x���v���c��́A�J���e�A���Z�v�g�i�f�Õ�V�����Ereceipt�j���ɂ���Ï��̌��J�A�J���̐ϋɓI�Ɏ��g�ނׂ��A�Ƃ����ӌ����q�ׂĂ��邪�A���{��t��͂���ɔ����Ă���B�ŋ߁A�s���^���Ƃ��Ă��J���e�A���Z�v�g�̊J�������߂鐺�����܂�A���̒c�̂̃z�|���y�|�W������������B
�@���̃J���e�A���Z�v�g���J�A�J���̉^���Ƃ��X���̓C���t�H�|���h�E�R���Z���g�iinformed consent�j�̗���Əd�Ȃ���̂ŁA����̐����Ƃ��킴������Ȃ��B
�@
�@�Ƃ��낪�A�i���I��t���J���e���J�A�J���ɂ͔��Ƃ����ԓx���Ƃ�l������B�Ⴆ�ΐ_�O�i��t�͂��̒����w���Ҋw
�x�}�K�W���n�E�X�Łu���҂ɂ͏\���ɐ�������悢�B�J���e�͊��҂Ɍ����邽�߂ɏ����Ă͂��Ȃ�����A���҂����Ă�����Ȃ��B���҂ɔ���悤�ɏ����Ƃ���ƙˑ�Ȏ��ԂƘJ�͂�������B�J���e�͈�Éߌ�i�ׂ̂��߂ɂ������p�������̂ł���B�v�Əq�ׂĂ���i�����W�R�Łj�B
�@
�@��t�@�Q�S���P���́u��t�́A�f�Â������Ƃ��́A�x�Ȃ��f�ÂɊւ��鎖����f�Ø^�ɋL�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�A�����Q���͂��̕ۑ����Ԃ��T�N�Ԃƒ�߂�
�i���Ȉ�t�@�Q�R���P�A�Q���͓��|�̋K��j�B���̕ۑ����Ԃ͒Z���߂���B���@�V�Q�S���ɂ��A�s�@�s�\���̏ꍇ�A���ˊ��Ԃ͂Q�O�N�ł��邩��A�Œ��Q�O�N�Ԃ̕ۑ����K�v�Ǝv����i���|�O�c�ق�
�O�f�w�㎖�@�x�V�U�Łj�B�J���e�͈�Éߌ뎖���ɂ����āA���ґ������ɖ𗧂��̂ł͂Ȃ��A��t�A�a�@���ɂ��𗧂��̂ł���B
�@
�@�J���e�̋L�ڎ����͈�t�@�{�s�K���Q�R�����u�f�Â����҂̏Z���A�����A���ʁA�N��v�u�a������ю�v�Ǐ�v�u���Õ��@�i���u����я����j�v�u�f�@�̔N�����v�ƋK��
�i���Ȉ�t�@�{�s�K���Q�Q�������|���K��j���邾���ł���A�p����܂߁A��̓I�ȋL�ڕ��@�A�L�ڕ����͈�t�̑I���Ɉς˂��Ă���B�P�X�U�S�N�ɃC�M���X��weed,L.L���������u���V�X�e�������iProblem Orented System�j�̃J���e����������Ă��邪�i�_�O
�O�f
�w���Ҋw�x�W�T�Łj�A�ق��ɂ��쐬���ԒZ�k�̂��߁A�l�X�Ȏ��݂��Ȃ���Ă���B
�@�Ⴆ�Έ�m���T��t��POS�����̃J���e��O��Ƃ��āA�R���s���|�^�|�ɂ��J���e�쐬�Ɗ��҂ւ̉{������Ă���i��m���T�u�J���e�ԋp�ɂ��Ă̎��āv
�w�N��㎖�@�w�x�P�S���V�V�Łj�B���Z�ȓ��{�̈�Âł́A�R���s���|�^�|�����ɂ��J���e�L���̓������K�v�ł��낤�B
�@
�@�Ƃ���ŁA����͈�Ì_���O��Ƃ��ăJ���e�̊J�������߂����҂̐�����ے肷��B�������ُ��a�U�P�N�W���Q�W������
�w�����x�P�Q�O�W���W�T�ł�����ł���B
�u�����v�����̏�Q�̂��ߍ����a�@�ŃC���^�|�t�F�����ɂ�鎡�Â������҂����Ì_��y�ь_��̓��ꐫ�Ɋ�Â��J���e�̉{���𐿋������B
�u�����v��Ì_��ɂ̓J���e�J���`���܂ł͊܂�ł��炸�A�_��̓��ꐫ���l���Ă������ł���A�Ƃ��Đ������p�B
�@
�@���̔����͊��҂��i�O�ŃJ���e�̉{���𐿋����������ł��邪�A�����������i�ׂɂȂ�Ί��҂������i�ז@�̋K��ŁA�������t�A�a�@���J���e���ٔ����ɒ�o����|�̖��߂̔��z�����߂邱�Ƃ��ł���B�����i�ז@�Q�Q�O���̕�����o���x������ł���B��t�A�a�@�����i�ׂŃJ���e�����p�����ꍇ�͊��ґ��͓����P���ŁA���̒�o�����߂邱�Ƃ��ł��邵�A�����łȂ��Ă������R���i���������؎҂̗��v�̂��߂ɍ쐬����A�͋��؎҂ƕ����̏����҂Ƃ̊Ԃ̖@���W�ɂ��č쐬���ꂽ�Ƃ��j�ŁA���̒�o�����߂邱�Ƃ��ł���B�������i�ז@�R�P�Q���R���͌��s�K��Ɠ���̋K��ł��邪�A�����O�i�ɓ�����Ƃ������̂�
���a�T�R�N�U���Q�O����㍂�ٌ���w�����x�X�O�S���V�Q�ŁA���a�T�R�W�N�V���R�P���������ٌ���w�����x�X�O�W���T�Q�ł�����A������i�ɓ�����Ƃ������̂�
���a�T�R�N�R���U����㍂�ٌ���w�����x�W�W�R���X�ŁA�����Q�N�X���W���������ٌ���w�����x�P�S�W�R���V�P�ł�����B
�@
�@���̒�o���߂����z���ꂽ�̂ɃJ���e����o����Ȃ��Ƃ��́A�ٔ����̓J���e�̋L�ڂɊւ��銳�ґ��̎咣��^���ƔF�߂邱�Ƃ��ł���B�J���e���s��o�ł����ꂾ���ň�t�̉ߎ��A�L�ӂ��������킯�ł͂Ȃ����A�Ⴆ�A��t�������҂ɑ����鏈�u�������Ǝ咣���A���҂������۔F���A�J���e�ɂ����̂悤�ȋL�ڂ͂Ȃ��A�Ƃ����咣�����Ă���ꍇ�A��t������o���߂ɉ������A�J���e���o���Ȃ����Ƃɂ��A�퍐�̎咣���������ƍٔ����͔F��ł���̂ł���B
�@
�@��������O�ҏ����ł���ꍇ�́A�R�q�̂�����o���߂����z����邪�i�����i�ז@�Q�Q�R���Q���j�A��O�҂��������o���Ȃ��ꍇ�͂Q�O���~�ȉ��̉ߗ��̏�������i�����i�ז@�Q�Q�T���P���j�B
�@
�@���ґ�����t�A�a�@����C�ӂɃJ���e�̃R�s�|�𑗕t���ĖႤ�A�Ƃ����P���ȕ��@����������\���͏��Ȃ��B���҂��ٌ�m�ɈϔC���Ĉ�t�A�a�@����J���e�R�s�|���擾���邱�Ƃ́A���Җ{�l���s�����́A�������������i����h���t�����`�����ٌ�m����̈˗�������A�S�O�Ȃ��J���e��������A�ƌ����Ă���B����h��
�w�J���e�ƃ��Z�v�g���킩��{�x�������X�R�P�Łj�B
�@
�@�܂��ٌ�m�ٌ͕�m�@�Q�R���̂Q�ɂ��A�����ٌ�m��ɑ��Ĉ�t�A�a�@�ɕK�v�Ȏ����̒��������߂�A�Ƃ����`�ŃJ���e���t�����߂邱�Ƃ��ł���B
�@
�@�J���e���̓���ōł��L���s���Ă���̂��A�����i�ז@�Q�R�S���ȉ��̏؋��ۑS���x�𗘗p���čs���J���e�̌��ł���B����͑i�ג�N�O�ɍs����̂����ʂł��邪�A��N��ł��\�ł���B�葱�̓��ꐫ����ٌ�m�ɈϔC���čs���̂��]�܂����B
�@
�@�����i�גS���̍ٔ����������̎���������A�咣�A�؋�����������A���Y�^�Ƃ��āA�������ƂɁu��T���v�����B����͈��̃J���e�ł���B��T���͓����҂̐����A�咣�A�؋��̋L�ڂ����S�ƂȂ邪�A�^��_�A�ߖ��_�A�\��Ȃǂ̂ق��A�����ҁA�㗝�l�̐��i�A�X���A�@��ł̑ԓx�A�����ȂǓ����ҁA�㗝�l�ٌ�m�̌l����������Ă���A�i�ׂ̌��_�\�������������Ă��邱�Ƃ�����B�]���āu��T���v�̌��J�Ȃǂ͂��肦�Ȃ��B���Ƃ��ƈ�t���������̘J���ɑ���V���Ⴆ���ÊW�Ƃ͈Ⴂ�A�ٔ��͌������Ƃ��Ă̐E����s����̂ł��邩��A�J���e���J�Ǝ�T�����J�͑S���̕ʘ_�ł���B
�@�������ٔ������A�����҂̎咣�̐����A���̐����Ɋւ��镔���A����Αi�ׂ̋q�ϓI�����E�E�N���ώ@���Ă��哯���قł���ׂ������E�E�͓����҂Ɍ��J���āA���������̂悤�Ɏ咣�A�؋��̐��������Ă���A�Ƃ������Ƃ��������Ƃ͂��肤�邱�Ƃł���B
�@
�@�J���e�ɂ��Ă������ŁA���J�������Ȃ킿�q�ϓI�����Ɣ���J�������Ȃ킿��ϓI�������Ă͍��Ȃ����낤���B��t�����҂ɂ͌��������Ȃ������͕ʕ����i�Ⴆ�Ί��҃����j�ɋL�ڂ���̂ł���B�����ċK�����K�肷��q�ϓI�����͌��J���邱�Ƃɂ�����ǂ����낤���B
�@
�@��t�͈ꃖ�����Ɋ��҂̌��N�ی��̎x������A�܂��͍��ۘA����ɐf�Ö����i���Z�v�g�j�𑗂��ĕی����̎x�����𐿋�����B����ɂ͈�Ís�ׂ��_��������A�P�_�P�O�~�Ƃ���Ă���B
��N�ɐ����Ƃ������Z�v�g���쐬����Ă���B�@
�@��Ë@�ց����Z�v�g���R���E�x���@�ց����Z�v�g���ی��ҁi��Ƃ̌��ہA�s�����̍��ہj
�@�@�@�@�@�@�@�@���x�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x����
�@�R���E�x���@�ւ͎Љ�ی��f�Õ�V�x������A�������N�ی��c�̘A����ł���B�@��ی����i���ҁj�͈�Ë@�ւɈꕔ���S�����x�����A�ی��҂ɕی������x�����B
�@���̐}�����画��悤�ɁA���N�ی����x���ł́A��t�͐f�Õ�V�����ҁA�f���E�x���@�ցA�ی��҂̎O�҂ɐ����ł���d�g�݂ɂȂ��Ă���i�_�˒n�ُ��a�T�U�N�U���R�O�������w�����x�P�O�P�P���Q�O�ł́A�R���E�x���@�ւ���Ë@�ւ̎x���������ߏ�Ƃ��Č��_�����̂�s���Ƃ��Ĉ�Ë@�ւ��x�����������Ċ��p���ꂽ����ł���B���l�n�ٕ����P�T�N�Q���Q�U���w�����x�P�W�Q�W���W�P�ł����|�B�A���퍐�͍������N�ی��c�̘A����j�B
�@���Z�v�g�i�f�Õ�V�������E��Ô�̖��ׂ�_���i��_�P�O�~�j�ŕ\���������́j�Ɋւ��āA�����Ȃ͂P�X�X�V�N�U���Q�T���A���Җ{�l�A�⑰�A�@��㗝�l�A�ٌ�m����㗝�l�̐���������ΊJ������悤�ɐR���E�x���@�ւɒʒB���o��������A�K�v�ȏꍇ�̓��Z�v�g�����邱�Ƃ��ł���
�B
�@
�P�@���Ȉ�t�i���Ȉ�t�@�Q���j
�@���Ȉ�t�@���ŏ��ɐ��肳��A���F�̎��Ȉ�t�identist�j���x�����������̂͂P�W�O�O�N�̃A�����J���O���ŁA�C�M���X�A�h�C�c�A�t�����X�͂���ɏ����x��Đ��肳��A���{�͂P�X�O�U�N�i�����R�X�N�j�ɐ��肳�ꂽ�B���{�ł����a�̏������܂ł͓k�퐧�x�Ŏ���
��t���{������A������Ď��Ȉ�t�ɂȂ��Ă������A���͑�w����Ɉ�{�����Ă���B����������A�W���ɂ͌��F�A�������͖ٔF�̓����m�Ƃ����k�퐧�x�ŁA��w����A��������Ɏ��Ȉ�Âɏ]������҂�����i���R�O�f�w�T�_�x�P�R�Q�`�P�R�R��
�j�B
�@
�Q�@�⏕��
�i�P�j���ȋZ�H�m�E���҂̌��o�����ۂ��Ē���������Ɩ͌^��ŁA���Ȉ�t�̎w���ɏ]���Ċe��̏C�����A��ԕ���������⏕�ҁB�P�X�T�T�N�Ɏ��ȋZ�H�m�@�����肳��A���Z���ƌ�A��N�ԁA�Z�H�m�w�Z�Ŋw�сA���莎�����o�ĖƋ����^�����邪�A���Ȉ�@�A���ȋZ�H���ł͖Ƌ����Ă��Ȃ��҂����������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�@
�i�Q�j���ȉq���m�E�P�X�S�W�N�i���a�Q�R�N�j���ȉq���m�@�����肳��A�����̉����ʼnq���m�̒S���Ɩ����g�傳��A���ȕی��w���Ɩ��܂ŒS�����邱�ƂƂȂ����B���̉q���m�̉ߎ��s�ׂɂ��Ă͌ٗp��̎���
��t���ӔC���i���s�⏕�ҁA�g�p�ҐӔC�j�B
�i�R�j���ȏ���E�@�I�ȑ��݂ł͂Ȃ����A���{���Ȉ�t��̒�߂��P����ɏ]���ė{������A��t�����Ƃ��A�f�Î����Ŋ��̏��ŁA�����Ȃǂ��s���⏕�҂ł���B�S�O�O���Ԉȏ�̌P�����o���b��ƁA�P�O�O���Ԉȓ��̌P�����o�����킪����i�w�R�O�f�w�T�_�x�P�R�U�Łj�B
�@
�@���{���Ȉ�t��Japan Dental Association�͂P�X�O�R�N�Ɍ�������A�e�s���{���ɂ͓s���{�����Ȉ�t�����B
�@
�R�@���̍\���A��ށA���a
�@ 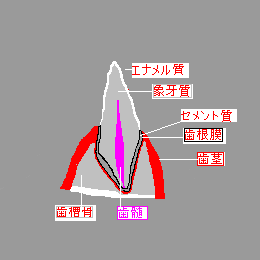 �@
�@
�@
�@���̕\�ʂ͑̂̉������������G�i�������B���̉��͏ۉ县�B�ۉ县�̒����Ɏ����������Ă���B���͎������ňێ�����Ă��邪�A���͎������ɒ��ڐڂ��Ă͂Ȃ��A���҂̊Ԃɂ͎������A�Z�����g���Ƃ����N�b
�V�����ƕt���̍�p��������̂���݂��Ă���B�X�Ɏ������̌��o���\�ʂ͎��s�i�����j�ŕ����Ă���B
�@���l�̎��͏�{�Ɖ��{�ɁA�n����ɓ�����������̂����ʂł���B
�@���l�̏�{�̎�������ƁA���̏��ԂƖ{���́A���̒������獶�E�Ɂu���莕�v�e��{���A�u���莕�v�e��{���A�u�����v�e��{���A�u���P���v�e��{���A�u��P���v�e�O�{���i�P����
�������牜���Ɍ������đ��A���A��O�Ɩ��t�����邪�A��O�P���͂�����u�q���A�e�m�炸���v�ł���j�B��������v����Ə�{�Ɏ��͂P�U�{���邱�ƂɂȂ�A���{�������z��łP�U�{���邩��A���l�̎��̐��͍��v�R�Q�{�ł���i�q���̐������ł��̐��͈قȂ�j�B
��P���b���P���b�����b���؎��b���؎��b���؎��b���؎��b�����b���P���b��P��
�R�{�@�@�Q�{�@�@�P�{�@�P�{�@�@�@�P�{�@�@�P�{�@�@�P�{�@�P�{�@�Q�{�@�@�R�{���P�U�{
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���؎����؎�
�@�@�@�@�@�@�@ ���؎��@�@ ���؎�
�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@ ��ꏬ�P���@�@�@�@�@��ꏬ�P��
�@�@�@�@ ��P���@�@�@�@�@��P��
�@�@�@�@����P���@�@�@�@�@�@����P��
�@�@�@�@����P���@�@�@�@�@�@����P��
�@�@�@�@��O��P���i�q���j�@�@��O��P���i�q���j
�@���{�l�̎��̐��͏��a�R�W�N�ɂ͂V�O�̘V�l�͂W�E�X�U�{�ł��������A�����T�N�ɂ͂P�P�E�U�R�{�ƂȂ����Ƃ̂��Ƃł���i�ɓ����ꓙ�ҁw���ƌ��̌��N�S�ȁx�㎕��o�łR�P�X�Łj�B
�@���Ȉオ�������a�̐��͋ɂ߂đ������A���Ȏ��Âōł������̂́u�����iꚐI�j�v�Ɓu�����a�v�Ƃ����Ă���B
�@����ȊO�ɒ����⎕���a�ɂȂ�₷���u�e�m�炸�v�A�i�ׂɂȂ�Ղ��u�{�ߏǁv�A�u���ꎕ�v�A�u�V���u�����g�v�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂����펯���x�̃��x���ł݂Ă݂悤�B
�@
�i�P�j�����́uꚐI�ƌĂ��B���@���̒E�D�A�L�@��̗n������F�Ƃ��鎕��̐ΊD���g�D�̎����ł���B
�@
�i�Q�j���o���̍ہi�~���|�^���X�ہA���_���ۂȂǁj���Y������_���d��������n�������ƂŔ����B���̍ۂ͐H�����̍��������āA�O���J���Ƃ����s�n���̌Ђ̂悤�Ȃ��̂�����A���̒��Ɏ_���A����n����������i�H��R���ԂŒ����ۂ͐H�ׂ����点�A�R�O����ɂ͎_�����Ď���n�����A�Ƃ����Ă���i�ɓ����O�f�w�S�ȁx�Q�T�O�Łj�B
�@
�i�R�j���̈�ԕ\�ʂ̃G�i�������ɔ�������������C1�iC=calies�����Z����a�C�j�A�G�i�������̉��̏ۉ县�܂ŐZ������������C2�A�ۉ县�̒��̎����i�_�o�⌌�ǂ������Ă���j�ɂ܂ŒB���������ɂ͔������č��ǎ��Â��K�v�ƂȂ�A���̒i�K�̒�����C3�ƌĂԁB
�@
�i�S�j�������Âŏ[�U���s����̂�C2�ł���AC1�͏��������ŏ[�U���Ȃ������ǂ����A�����������邽�ߏ[�U���s�����Ȉオ�����Ƃ̂��Ƃł���i�ۋ��O�f�w�ǂ����Áx�R�Q�Łj�B
�@
�i�T�j�����̏[�U�Ɏg����A�}���K���Ƃ͐���A��A���Ȃǂ̕�������荇�킽���̂ŁA�����ŁA�[�U���ȒP�ŁA�Ĕ�����B����������Ő���L���A�A�����M�|���N�����₷���A�����ϐF���Ղ��Ȃǂ̌��_������i�ۋ��O�f�w�ǂ����Áx�R�V�C�R�W�Łj�B�ŋ߂͎g��ꂸ�A���Ȉ�͋l�ߑւ������߂Ă���B
�@
�i�U�j�������ɂ��Ȃ�Ǝ����ɒB�����؋��B���̏ꍇ�͍��ǎ��Â��s����B���ǎ��Â͖������ɐ_�o�A���ǂ��Ƃ�A���Ǔ����̓�炩�������i���̑O�g�v���f���e�B���Epri-dentine�j��~���o���A�`�𐮂��A��������A���������A���ԁi���|�P�b�W�E���o�j�Ȃ��A�����Ƀ��b�N�X�Ȃǂ�z�������[�U�ނ��[�U����i�ۋ��O�f�w�ǂ����Áx�T�T�Łj�B�@���ǎ��Â����Ď������Ƃ�Ǝ��͎キ�Ȃ�̂ŁA�O���ɕ�Ԃ��s���N���E�����Â��s�����A�N���E���ɂ́A�����̈ꕔ�ɍs���A�����|�A�����̑S���ɍs���N���E���A�����ł��Ԃ��A�ڂɌ����₷���A�R�����̋��߂���O���A�j���ɂ̓|�|�Z������d�����W�����Ă�����O����������i�ۋ��O�f�w�ǂ����Áx�X�O�ňȉ��j�B
�@
�i�V�j�������Č�������������O��̎��i�x�䎕�j�����r�̂悤�Ɏx���ɂ��Ă������ڒ����̋��i�_�~�|�j���u���b�W�Ƃ����A����������s���鎕�Ȏ��Â̈�ł���B
�@
�i�P�j���镶���ɂ��Ɣ��������̖�T�O���������a�A��R�V���������A��P�R�����O���ȂǁA�Ƃ������ƂŁi����r�p�w����Ȃ玕���a�x�㎕��o�łR�ňȉ��j�A���ꂾ���ł������a�̕|�����킩��B
�@
�i�Q�j�����a�͎����̂̕a�C�ł͂Ȃ��A�����x���Ă�����͑g�D�̎��a�ł���i����O�f�w�����a�x�T�Łj�B
�@
�i�R�j���̒��S�ɂ͐_�o�A���ǂ����鎕��������A���̎�����ۉ县���͂݁A�X�ɂ��̎���𔖂����ł��G�i���������͂�ł���B����V���^�̎������ɂ͂܂��Ă��邪�A�������̊O���ɂ͐Ԃ����s�i�����j�������āA����ێ����Ă���A���s�Ǝ��̓Z�����g�������鎕�����Őڒ�����Ă���B�ڂŌ����鎕�͎��̈ꕔ���ɉ߂��Ȃ��B
�@
�i�S�j�����a�Ŏ��������_���|�W���Ď�����l�q��X���ʐ^�ł悭����B�����a�͐̎����^�R�ƌĂꂽ���A�P�X�Q�O�N��ȍ~�A���Ăł́A�����^�R�Ƃ������t�͕s�K���Ƃ������ƂŎg���Ȃ��Ȃ����B�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�i�T�j�����a�͐悸�A���s�̉��ǂŌ����B������������ł���B�������̒i�K�ł͉��ǂ͎��s�����ŁA�������A�������ɋy��ł��Ȃ��B�]���Ă��̒i�K�Ŏ��Â��邱�Ƃ��]�܂����B
�@
�i�U�j�����a�̌���
�@
�@���C�i�ۂ̏W�cplaque�v���|�N�j�Bplaqre�͒P�Ȃ�H�ן�ł͂Ȃ��A�ۂ̏W�c�ŁA���ɂ�������t�����Ă��āA�������łȂ��Ƃꂸ�A�������ł͂Ƃ�Ȃ��iplaque�͌��o��ۂƂ��̎Y��������Ȃ��炩������
�������ŁA�v���[�N�Pmg���ɂ͂P�O�O�O���ȏ�̍ۂ��܂܂�A���̂Q�O���͐������ہB�ɓ����O�f�w�S�ȁx�Q�R�R�Łj�B
�@
�A�S�g�̌��N��ԁB�S�g�̌��N��Ԃ̕s�ǂ͎����a�̌����ƂȂ�B���e頏ǁA���A�a�A�D�����ُ��Ȃǂ͎����a�̑S�g�I�v���ł���i����r�p�w����Ȃ玕���a�x�㎕��o�łQ�P�`�Q�Q�Łj�B
�@
�i�V�j�����a�͂P�Q�̎q���Ŗ�T�O���A���l�ł͖�X�W�����늳�i����O�f�w�����a�x�Q�R�Łj�B
�@
�i�W�j�����a�̑�G
���̂P�E��������B���͎�������ɂ�鉡����̗͂Ɏア�B�}�E�X�s�|�X�����Ď��������h�~����i����O�f�w�����a�x�Q�X�Łj�B
���̂Q�E���ċz�B�������������ăv���|�N�����ɂ�苭���t������B�@�̕a�C�������ł���Ύ��@�ȂŎ��ÁB�o�����������ł�������i����O�f�w�����a�x�R�O�`�R�P�Łj�B
�@
�i�X�j���L
�@���L�ɂ͎O��ނ���B
���E���L�͕��ʒ��x�Ȃ̂ɁA�Ђǂ��A�Ǝv������ł���ꍇ�i���L�ǁj�B
���E���L�����ł��鎕���a�A�����A��ۂ������Ă���ꍇ�B���̌������������邱�ƂŎ���i��ۂ͓���ȃu���V�ŏ����ł���j�B���̌�������ԑ������A���C�̒��⎕�Ǝ��s�̊Ԃ̌��ԁi�����|�P�b�g�j�ɏZ�ݒ����Ă���ۂ��o���őf�Ƃ��^�̏L�������L�̌����ƂȂ�B�u���b�V���O�Ƃ��A�����a�̎��ÂŁA�����|�P�b�g���Ȃ����邱�Ƃ��K�v�B
��O�E���ȊO�Ɍ����A�Ⴆ�Έݕa�A���A�a�A�x�̕a�C�������Ă���ꍇ�B�����̌����a���������ƂŌ��L�͂Ȃ��Ȃ�i����O�f�w�����a�x�S�S�`�S�T�Łj�B
�@
�i10�j�����a�̎���
�@���������x�̏ꍇ�͎������ɂ�鎕�C�����Ŏ���B�⏕�I�ɂ͍R�ۍ܂̋Ǐ����^�A�ܚu�܁i��������j��p����i����O�f�w�����a�x�U�S�Łj�B
�@���C���ΊD���������́A�������㎕�Ǝ����������i�����ɕt���Ă�����́j������A��҂͎��ɂ����B����������Ȉ�Ŏ��ׂ��ł���i���̍ۂ͖w�ǎ���ł���̂ŁA�����͎̂��C�ł���A�Ƃ������Ă���B�ɓ����O�f�w�S�ȁx�Q�R�R�Łj�B
�A�������ɐi�s���Ă���ꍇ
A��p��K�v�Ƃ��Ȃ��ꍇ�B�����������A�s���^�̎�p�X�P�|���|�Ŏ����ʂ�ɂ��āA�ۂɂ��őf�ʼn������ꂽ�Z�����g���̖ʂ���������A�Ƃ����X�P�|�����O�E���|�g�v���|�j���O���s���B���̖ړI�͍ۂ��t���₷�������������čۗʂ����炵�A���nj����̓őf�������ʂ��珜�����A�����ʂ�ɂ��Ď��s�ւ̎h�������炷���Ƃł���i����O�f�w�����a�x�U�W�`�U�X�Łj�B
B ��p���K�v�ƂȂ�ꍇ�B�����|�P�b�g���[�����Ċ��S�Ȏ��Ώ������ł��Ȃ�������A�����̌`�����G�Ŏ����|�P�b�g�����ł��Ȃ��ꍇ�́A���s��؊J���Ē������Ŏ��⊴���������s����������B�����Ƃ���ʓI�Ȏ����O�Ȏ�p�̓t���b�v�I�y���|�V�����ŁA���s�ɖ������{���A���X�Ő؊J���A���s���������甍�����A�������Ŏ��⊴���������s���������A�D�����Ď��s�̎��͂ɕ�сi�p�b�N�j���A��T�ԂŃp�b�N�����A��������B���̊O�ȓI���ÂƂ������͈��ՂɑI�����Ă͂����Ȃ��B�U�X�|�V�P��
�B �V������p�@
A �l�H���ɂ�鎡�ÁB�Z���~�b�N�ނ����ɈڐA������@�i����O�f�w�����a�x�V�S�`�V�U�Łj�B
B�@GTR�@�i�g�D�Đ��U���@�j�B����͕ی��O�ł���i����O�f�w�����a�x�V�V�`�V�W�Łj�B
�C���|�U�|���Ö@�B���������Ώ����A�����|�P�b�g���Ǝ˂ɂ��őf�̏����A�����̃����j�������ɑ��鏈�u�A�ۉ县�m�o�ߕq�ǂ̏��u�Ƀ��[�U�[�����p����Ă���i����O�f�w�����a�x�W�O�`�W�Q�Łj�B
�@
�i11�j�����a�̗\�h�E�u���b�V���O�i�]�莕�����܂��g��Ȃ����Ɓj�B���ԃu���V�̗��p�B������f�B�։��B���N�����i�X�g���X�������ƂȂ�j�B
�@
�i�P�j�u�e�m�炸�v�Ƃ́B
�@���͊{���̒��Ŏ���i���̌���j��������B�����̎���͔D�P���T�ځi�S�X���j������ł��͂��߁A�i�v���̎���͏o���̍�����ł��͂��߂�B�����͐���Z���������牺�̑O�����琶���͂��߁A��́A
�R���܂łɏ㉺�P�O�{���A���v�Q�O�{�͂���B�i�v���͂U��������P���ƑO�����琶���͂��߁A��̂P�Q�̍��܂łɐe�m�炸�E�q���i��O�P���j���������Q�W�{���������낤�B�u�e�m�炸�v�͑����l�łP�S������A�x���l�łQ�O�����琶���͂��߂�B
���̎��͐e���m��Ȃ������ɐ�����̂Łu�e�m�炸�v�ƌĂ�A�m�b�����Ă��琶����A�Ƃ����Ӗ��Łu�q���v�Ƃ��Ă��i�Ėڒ���E��ؕq�v�w�e�m�炸�̂͂Ȃ��x�㎕��o�łQ�`�R�Łj�B
�i�Q�j����l�͌�������]��H�ׂȂ��̂ŁA�{���̔��B���s�\���B�]���Đe�m�炸�̐�����ꏊ���s�����A�e�m�炸���F�X�ȕςȏꏊ�ɐ����Ă���B����Ȑe�m�炸�́A�P���̖��[�ɐ����A�㉺��������ƙ������Ă��邪�A�����Ɋ{���ɖ��܂������̂Ƃ��A�j����㑤�Ɍ������Đ�������̂Ƃ��A���S�ɐ�������Ȃ����̂Ƃ��A���܂��܂Ȍ��אe�m�炸������A�����̌����ɂȂ�����A�����т����������肷��B�i�Ėړ��O�f�w�e�m�炸�x�R�`�T�Łj�B
�i�R�j���אe�m�炸�̕��u�ɂ���ċN����a�C�͉��{�q�����͉�����ԑ������A���P������Ɉ������邽�߁A����S�̂�������A���P���⌢���i���莕�j�̈ʒu������A�����т������Ȃ�B�܂��펞�A���P������������̂ŁA���̈ʒu������A������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B�e�m�炸�̐���������Ǝl�{�Ȃ��ꍇ�͙����s�S�ɂȂ�����A�e�m�炸�̐����Ȃ����s��
���Α��̐e�m�炸���������Ē�ᇂ���邱�Ƃ�����i�i�Ėړ��O�f�w�e�m�炸�x�U�`�W�Łj�B
�i�S�j���{�q�����͉�����u����ƁA��A�ɉ��ǂ��L����A����������N��������A�{�ɂ���J���Ȃǂɉ��ǂ��N�����ĊJ������ɂȂ�A�S�g��Ԃ������ƈ����A���M�Ȃǂ��N�����B���Õ��@�Ƃ��ẮA�����Ǐ�͓K�Ȏ������A���e�Ń|�P�b�g�̂Ȃ��̕��s�����������邱�ƂŌy������B�Ǐi��ł���ƍR�������A��M�܁A���ɍ܂Ȃǂ�o�p����B�d�ǂ̏ꍇ�͓_�H�Ő����⋋�A�؊J���Ĕr�^�A�����ɂȂ����e�m�炸�̔����Ȃǂ��s���i�Ėړ��O�f�w�e�m�炸�x�X�`�P�R�j�B
�i�T�j�e�m�炸�̔����B���{�q�����͉��Ŏ��Ă���ꍇ�͖����������ɂ����A�o���������A��ꂪ���傷��̂ŁA�������Ȃ��B�ُȂ��ꍇ�ɏ����ɔ����Ĕ������邱�Ƃ����邪�A�ċx�݂Ȃǂ̋x�{���Ԃɔ�������̂��悢�B�N��͂P�O�|�Q�O�Α䂪�x�X�g�B�������A���A�a�A�A�����M�|�A�l�H���́A�S�؍[�ǁA�s�����A�S���ٖ��ǁA�]���Ǐ�Q�A�b��B�@�\�ُ�A���t�����A���t�玿�z���������Ò��̐l�͔����ɗv���Ӂi�Ėړ��O�f�w�e�m�炸�x�P�S�`�S�O�Łj�B
�i�U�j�e�m�炸�ł��A�㉺����������������Ă�����ꍇ�͔�������K�v�͂Ȃ��i�Ėړ��O�f�w�e�m�炸�x�P�P�S��
�B���{�̐��������q��������̂ɖ�Ԃ�����A���{�����܂������������B�����n�ُ��a�T�V�N�P�Q���P�V�������w����^�C���Y�x�S�X�T���P�T�R�ŁA��c������w��Éߌ�S�I�x�P�W�U�Łj�B
�@
�@
�@ 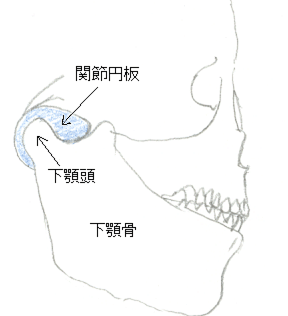 �@ �@ �@
�@ �@ �@
�@
�P�@�{�ߏǂƂ́A�{�ߕ����u�ɁA�J���̎G���A���u�ɁA�J�������Ȃǂ̊{�^����Q����Ǐ�Ƃ���{���o�n�̋@�\��Q�Q�̑��́i��R���w��w�厫�T�x�Q�V�P�Łj�B
�@
�Q�@���{�{�ߏNJw��ł͊{�ߏǂ�
�T�^�E�̏�Q���咥�Ƃ�����́B
�U�^�E�����O�����a�ρi�������O���E�����s�Ǖ�ԕ��A����s���A�������̑r���AꚐI�ɂ��G�i���������Ȃ킿�����̕���j
�V�^�E�߉~�i���{���̏�̉����̉~�j�ُ̈�i����Ȃǁj���咥�Ƃ�����́B
�W�^�E�ލs���a�ρi�g�D�̑�ӏ�Q�A�Ȃǁj���咥�Ƃ�����́B
�X�^�E�S�g��w�I�v���ɂ����́B
�@
�R�@�f�f�͖�f�A���o�������A�{�ߕ��̐G�f�A���f�̂ق��A�{�߃����E�}�`�����O���邽�߂̌��t�A�A�����A�������ɂ����������AX�������A�ؓd�}�AMRI�i���C���B�������j�Ȃǂ��s����i�ɓ����O�f�w�S�ȁx�S�S�R�W�ňȉ��j�B
�@
�S�@��Ǐ�Ƃ��Ă͊J�������u�ɁA�ߎG���A�J����Q�����邪�A���Ǐ�Ƃ��ē����A�A���A�w���A���A�葫���u�ɁA��a���A�߂܂��A����A�����A��̏[���A�@���A�����_�o�����ǂ̏��Ǐ�A�{�ʂ���܂�Ȃ��A�����ُ�Ȃǂ�����B
�@
�T�@�����Ƃ��Ă͙����ُ�ɋN������_�o�؋@�\�ُ̈�A�{�ߍ\���A�ʒu�̕ω��i�ُ�j�A���_�I�X�g���X������ُ�ɂ��؊����ُ̈i�A�X�g���X��S���I�v���A�S�g�I�����A�ُ���o�K�ȂȂǂ��������Ă���B
�@
�U�@���Õ��@�E�u�ɂ��傫���ꍇ�͒��ɍ܂�ア�ؒo�ɍ܂̓��^���s���A�a�^�ɉ����ę��������A�s�Ǖ�ԕ��̏C���A����g�Ö@�A�k��ɂ��߉~�̕��ʁA��p�A�S�g�I���Â��s����i�ɓ����O�f�w�S�ȁx�S�R�X�ňȉ��j�B
�@
�V�@�ۋ��O�f�w�ǂ����Áx�P�S�S�ňȉ��ɂ��ƁA�{�ߏǂ͍ŏ��A���A��̂��肩��͂��܂��Ď���ɂЂǂ��Ȃ�B�H�����̗���A�^���s���A�X�N���Ȃǂ̗��R�ő̗͂��ቺ����ƏǏ��B�t�Ɍy�x�Ȃ�A�^�������Ŏ��邱�Ƃ�����B�Ǐ�̓V���h���|���i�nj�Q�j�Ƃ��ĕ����Ō����B�����s�S�������̏ꍇ�������B�X�O���͙����C���Ŋ������A�y������A�Ƃ���Ă���B
�P�@���ꎕ���Â̂����A���ꎕ����Ƃ����ʂ����ώ@����ƁA�����I�Ȉ�ۂ��������A��������Ȉ�Â̈�ł����āA��Öʂ�����Ȃ����̂ł��邱�Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���
�i�A���\���p�̓��ꎕ�̒P���ȃR�s�[����͐����ł��낤�j�B
�@
�Q�@���ꎕ�Ƃ�����ԕ��͎��O���\�i�P���j�ŁA�L���̂��̂��w���B��{�ȏ�̎����c���Ă��邪�A�u���b�W�ɂ���ɂ͎c���������Ȃ����A�����������傫���ꍇ�ɂ̓u���b�W�ɂ����A�������ꎕ�ɂ���B�c�������F���̏ꍇ�́A�����鑍���ꎕ�ƂȂ�B
�@�ǂ����ꎕ�Ƃ́A���̖ʐς��K���ŁA�`�����ێ����邽�߂̋������X�g��N���X�u�̐v���������A�������������m�Ȃ��̂��w���B�������ꎕ�́A�s����ŐH�����b�ł͂��ꂽ��A�悭�������߂Ȃ��A�Ƃ��A�ɂ݁A��������悤�Ȃ��̂ł���i�ۋ��O�f�w�ǂ����Áx�P�P�P�ňȉ��j�B
�@
�R�@�ۋ��O�f�w�ǂ����Áx�Q�O�O�Q�N�P�Q���łP�S�P�ňȉ��ɂ��ƁA�����ꎕ�̏ꍇ�A���N�ی��ł͂Q���R�U�W�O�~�ŁA���ȋZ�H�m�������A���Ȉ�t���O���Ƃ�A�Ƃ������Ƃł���B
�@
�\��
�@�C���v�����g �iimplant�j
�@�����������ꍇ�̏��u�Ƃ��ẮA�Ȃ��Ȃ������̗��ׂ̎��ɉ��H���Đl�H�����Œ肷��u���b�W�Ƃ������@�Ƃ��A���ꎕ��������@�����邪�A���҂ɋ����A�����M�[������Ƃ��A�c�����𑝂₷���߂��߂����ɁA�{���ɐl�H�����i
�C���v�����g�j��A�����ނƂ������@������B���̃C���v�����g�Ɏ��������Ԃ���ƁA���R�̎��̂悤�ɂ��g����B
�@
�@�l�H�����̓`�^�������p�����A���̃`�^�����C���v�����g���{���ɓ���ĂR�A�S�����Âɂ���ƃC���v�����g�Ɗ{���Ɋ��S�ɂ������A�l�H�������ł���B
�@���������̂��߂̊O�ȓI��p���s���O�ɁA�{�������e頏ǂɂ������Ă��炸�A�l�H��������������\���ȍ��ʂ������A���҂����A�a���̑��̎����ŖƉu�����ቺ���Ă��炸�A�R�������ɑ���ُ����Ȃ��Ȃǂ�
���O�`�F�b�N
���K�v�ł���A��p���̂���{�̏ꍇ�͏�{���ɓ˂��������肹���A���{�̏ꍇ�����{�ǁA���Ƃ����_�o�����Ȃ����Ƃ��K�v�ŁA�����̏n���x���v�������B
�@
�@���̃C���v�����g�͕ی��O�ł��邪�A�����Ε����A�i�ׂ̑ΏۂƂȂ�B
�ڎ��ɂ��ǂ�B
�P�@�Y������
�@
�i�P�j��㍂�ُ��a�T�Q�N�P�Q���Q�R�������w�����x�W�X�V���P�Q�S�Łi�v���悤�Ɍ����J���Ȃ��c�����҂����ŁE�L�߁j
�u�����v�T�̒j���̎��������ÂʼnE�㉜�����Ԗڂ̎��Ɏ����܃p���z�����p�X�^���[�U���A�����A�j����f�@��ɋ��ɐQ�����āA��������o�����Ƃ������A�|�����Č����J���Ȃ��̂ŁA�x�e���A�ܕ���Ɍ����J���悤�����Ă��J���Ȃ��̂ŁA�{���Ď��Ȉ�͈�j������ʼn��ł������A����ł��J���Ȃ��̂ŁA������x�A���j��ʼn��ł��A�j�������J���Ă̂ŁA�������ď[�U�܂����o�����B�j���͉��ł̌��ʁA�S���T���Ԃ̑Ŗo�����A���Ȉ�t�͏��Q�߂ŋN�i����A��R�͔����Y�i���z�͕s���j��I���������A���s�P�\�͂Ȃ��B�퍐�l���́A���Ȉ�t���J�����ۂ̗c���Ɏ��͍s�g�����Ă��A�Y�@�R�T���̐����s�ׂł���A�ƈ�@���j�p���咣���čT�i�B
�u�����v���Ȉ�t�͊J�����ۂ̗c���̎��̎��ÂŁA�J���̂��߁A������x�̎��͍s�g�͂ł��邪�A���ł���͎̂Љ�I�Ó������������͍s�g�ł���B�p���z�����p�X�^�͌���ł��邪�A���͔���ł���A�����Ă܂Ŏ��o���K�v���͂Ȃ������B�������퍐�l�͖Ƌ��擾��Ԃ��Ȃ����Ȉ�ŁA������A�Ԏӗ��W���~��������A���ۂ���Ă���A�����͒Ⴂ�A�Ƃ��Č������j�����A�P���~�A�P�N�Ԏ��s�P�\�B
�u�����v�}���A���|�U�E�_���E�R�X�^�Ғ����c�R���A���۔���q��w��w�̖\�͂ɂ��炳��鏗�����E�C�^���A�ɂ�����q�{�E�o�x�C���p�N�g�o�ʼn�ŃJ�������E���I�E�t�B�I���g�Ƃ��������i����S���w�ҁj�́A���Ǒ��e�����ŋ�ɂɔ��������Ƃ���A��t�ɕ���ł���H���A�̂̂���ꂽ�A�Ə،����Ă���i�����P�T�O�Łj�B
�@���̎����ł́h�t���Y���̕�e�̏��������Ȃ��܂܂ɁE�E�h�Ɣ����ɋL�ڂ���Ă��邪�A��e�̏����������Ă����ł͈�@�ł���i���R�F������E�W�����X�g�w��Éߌ딻��S�I���Łx�P�X�U�ňȉ��Q�Ɓj�B
�@
�i�Q�j�D�y�n�ُ��a�T�T�N�W���P�������w�����x�X�W�V���P�R�T�� �i���ȋZ�H�m�������i�f�ÁE�L�߁j
�u�����v���ȋZ�H�m�����a�T�R�N�A�ƂƂ��Ė�S�����ԁA�Q�T���ɖ�f�A�����Ȃǂ̎��Ȉ�Ƃ��s���A���Ȉ�t�@�P�V���ᔽ�ŋN�i�����B
�u�����v�L�߁B�����W���A���Q�͏��Ȃ��Ƃ��Ď��s�P�\�R�N�B
�@
�i�P�j�����n�ُ��a�S�V�N�R���V�������w�����x�U�V�W���T�U�� �i���ɂ̎�Y���҂Ƀs�����n���ɍܓ��^���A��]�E�F�e�j
�u�����v���a�S�P�N�A���ّ̎��̒j����Y�ҁi���Ɂj�Ƀs�����n�̒��ɍ܃O���������ܓ��^�������ʁA��]�ʼnA���i�T���j��ፍ������B
�u�����v����ɓ�����A��Y�҂̃A�����M�|�̎����m�F���钍�Ӌ`����ӂ����A�Ƃ��ĈԎӗ��T���~�m��B
�@
�i�Q�j�����n�ُ��a�T�R�N�P�Q���P�S�������w�����x�X�T�Q���X�U�Łi���{�̃G�i����������ʼn߁E���p�j
�u�����v���a�T�O�N�R���A���̎��s�ɂł������a�P.�T�������ᎏ�ˋN�ɂ��Ď��Ȉ�̐f�f�����Ƃ���A��ł��邩��S�z�Ȃ��A�Ƃ����A�������B���N�A��w�a�@�Ń����g�Q�����������Ƃ���A�G�i��������Ɛf�f����A���{���Ȃǂ̐؏���p�����B ������ӂ𗝗R�ɑ��Q���������B
�u�����v��ʓI�ɃG�i��������̔���A�i�s�͊ɂ₩�ŁA�퍐�K�͂̎��Ȉオ�����g�Q�����������Ă���������A�I�m�Ȑf�f�������͍̂���B�퍐���Ȉ�̏��u�͂�ނ������Ȃ��B�������p�B
�@
�i�R�j���n�ُ��a�T�V�N�W���Q�O�������w�����x�P�O�V�P���X�X�� �i���s�^ᇂ̏��u�s�ǂŃ����|�}�`���Ђǂ��Ȃ����ȂǂƎ咣�E�F�e�j
�u�����v�@���a�T�Q�N�U������T�J���ԁA�퍐�J�Ǝ��Ȉ�@�ʼn��E��ꏬ�P���̎��s�^�E�ɑ��č��ǎ��ÁA�[�U�̂����A�����������Ԃ���Ƃ������Â��s�������A���s�̔^�E�͏��ł��Ȃ������B���̂��߁A���̎��Ȉ�@�ʼn��E�����A��P���A����P��������������Ȃ��Ȃ����B�A�܂����a�T�R�N�P������Q�J���ԁA�㍶�E�̂P�Ԗڂ̎��i���莕�j�̌p�����Â��s�������A���ǎ��Â���
������|�X�g�����Ǖǖʂ�����A�����ɐH�������߁A��ꕁi���s�̂��Ɓj�^ᇂɂȂ�A���@�ō��㒆�莕������������Ȃ��Ȃ����B�B�܂��A�̎��Ì�A��E��Ԗڂ̎��t�߂ɔ^�E���ł������A���Â���u�������߁A���@�ʼnE���Ԗڂ̎�������������Ȃ��Ȃ����B�����͂���玕���^�E�A��ꕔ^ᇂ������Ō��A���A�w�Ȃǂ������|�}�`�ǂ��A�����|�}�`��̕��p�ɂ��t�����N��������A�g�̏�Q��
�O���ɔF�肳�ꂽ�A�Ƃ��Ĉꉭ�~�ȏ�̑��Q�����B���s���s�܂��͕s�@�s�ׂɊ�Â��A���̈ꕔ�̂P�O�O�O���~�̑��Q���������i�ג�N�B
�u�����v�@�ƇB�̂��Ă͎��Ȉ�Ƃ��Ă̒��Ӌ`�����ʂ����Ă���B�A�̂����E��P�Ԃ̎��ɂ��Ă͉ߌ�͔F�߂��Ȃ����A����P�Ԃ̎��ɂ��Ă͋����|�X�g�����ǕǖʂɌ���Đ��E�����ƔF�߂����A�Ƃ��āA�x���������Ƃ̎��Ô�V���T�O�O�O�~�A�V���Ô�Q�S���~�A�Ԏӗ��P�O�O���~�A���v�P�R�P���T�O�O�O�~��F�e�B�����|�}�`�Ƃ̈��ʊW�ɂ��ẮA���������a�T�S�N���A�����|�}�`�Ɛf�f���ꂽ���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A���̗��R�ň��ʊW�ے�B
�@�i�؋��ɂ��Ɓj���̖���������������J������(�a������Y�o���ꂽ�a�łƕa���ۂƂ��ꏏ�ɂȂ������̂��R���ƂȂ�A�����Â����Ԃɂ킽���čR���h�������邱��)�̌��ƂȂ�A����ɂ��
�����|�}�`���䂫�N�������Ƃ��邢����a�������������݂��邱�Ƃ�F�߂邱�Ƃ��ł���B�������A�����A�i�؋��ɂ��Ɓj�A�a���������͂P�X�R�O�N�ォ��P�X�T�O�N��ɂ����ėL�͂ł��������A����͌��ǂ̂Ƃ��댴���a������菜�����Ƃɂ���ēI�ɕa�C�����������Ƃ������������ł����Ċw��I�Ȏ��͂قƂ�ǂł��Ȃ��̂��ʏ�ł��������ƁA�P�X�T�O�N��ȍ~�ɂȂ�ƌ������̕a�������S�Ɏ������Ă����̕a�C�͎������Ȃ�������A�]���a�������ɂ���ċN����ƍl�����Ă����a�C�̌����ɂ��Ă̌����̌��ʁA���Ɍ��������邱�Ƃ����������肷�邱�Ƃɂ��A�a�����������̂��̂��^�⎋����A���݂ł͐��Ƃ̊Ԃł͂��܂�d�v����Ă��Ȃ����ƁA����
�����|�}�`�̌����ɂ��ẮA�a�������̂ق��n�A�ۊ����A�}�C�R�v���Y�}�������������邪�A���̂�����ɂ����ߎ肪�Ȃ���Ԃł��邱�Ƌy�я]���a�����������a���ƂȂ鎕�̎����Ƃ��ċ����Ă����͎̂������̓����A�����^�E�A�����^�R�ł��邱�Ƃ��F�߂��邱�Ƃ��ł��A�܂������́A�O�F��̂Ƃ���A���a�T�T�N�Q���W���ɍ����Ԃ����Ă���A�i�؋��ɂ��Ɓj�����́A���a�T�S�N�T�����@�i�k�쎕�Ȉ�@�j�ɂ����ĉE���S�ԁA�T�ԁA�U�Ԃ������Ƃ���A�^���o�Ă��̒��ォ�玕�����̖c��݂͑S���Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ȃ���A
�����|�}�`�͌��݂ɂ����Ă��ɖ��Ȃ��爫��������Əq�ׂĂ��邱�Ƃ��F�߂��B���Ƃ��A�i��̈��ʊW�̏ؖ��͈�_�̋^�`��������Ȃ����R�Ȋw�I�ؖ��ł͂�<�A����̎���������̌��ʔ��������������W�F�����鍂�x�̊W�R�����ؖ����邱�Ƃł���A���̏ؖ��̒��x�͒ʏ�l���^�����������܂Ȃ����x�ɐ^�����̊m�M
������������̂ł��邱�Ƃ�K�v�Ƃ��A���A����ő������̂Ɖ����ׂ��ł��邪�A�ȏ�F��̎����𑍍�����ƁA�����̃����|�}�`���O�L�F��̍����Ԃ̎��Éߌ�ɂ���Đ�������ꕔ^ᇂ������Ƃ��Ĕ��a�����W�R���͓��ꐄ�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�u�����v�����̃����|�}�`�늳���A�̈�Éߌ�ɂ�蔭�a������ꕁi���s�̂��Ɓj�^ᇂ������ɂȂ������ǂ������d�v�ȑ��_�ł��������A�A�ɂ�鎕ꕔ^ᇂ̎������������
�����|�}�`�͎������Ă��Ȃ����Ƃ���̗��R�ƂȂ��Ĉ��ʊW���ے肳��Ă��邪�A���{�I�ɂ́A�����|�}�`�Ƃ�����a�̌����s�����������̗����������̂ł��낤�B
�@
�i�S�j���l�n�ُ��a�T�W�N�P�O���Q�P�������w�����x�P�O�X�S���W�T�Łi�O���̎��ÂŔ��ς��邱�Ƃ̐����s�����咣�E���p�j
�u�����v�����i�T�P�̒j���H���j�͏��a�T�V�N�V���A���P���ɏ[�U���Ă����������͂��ꂽ�̂ŁA�퍐�J�Ǝ��Ȉ�@�Ŏ�f���A���̎��Ì�A��莕�S�{�̎��Â����߂��A�����̋���{���邾���A�Ƃ����̂Ō����Ɖ����Ƃ̊ԂɈ�{�̋�������̂Ǝv���Ď��Â����������Ƃ���A�O�ʂ��c���Ă���ȊO�̖ʂ�����ċ���������l���̎O�����{�s�����̂ŁA��ʂ̎��������ꂽ�ق��A�O���ɋ����̋��ܖ{�����邱�ƂƂȂ����A�Ƃ��ĉ�p�S�O���~�A�Ԏӗ��T���~�̑��Q���������i�ג�N�B
�u�����v�����́A���P���̎��Â��������Ì_��̎�|�ł������Ǝ咣���邪�i�؋��ɂ��Ɓj�A�����Ƃ���͑S�����Â���A�Ƃ�����|�ł������B�����́A�퍐���l���̎O�����{���ɍۂ��āA���Â̑ΏۂƂȂ�ׂ����̏Ǐ�y�щE���Â̌��ʂ��O�e�ɋy�ۂ��e���ɂ� ��̓I�Ȑ������Ȃ��ׂ����Ӌ`�����Ă���|�咣����Ƃ���A���Ȉ�Â����̑ΏۂƂ��Ă��镔�ʂ��O�e�ɉe����^������̂ł��邱�Ƌy�ё��̈�Õ���ƈقȂ莡�Õ��@�̑I���ɂ����҂��ӌ����q�ה��ߌ��肷��x�����������Ƃ���l���āA��Â��s�����Ȉ�t�Ƃ��ẮA�ꍇ�ɂ���Ă͗Ⴆ�Ί�
�҂̈˗��ɉ�������w��̓K�Ȏ��Â��s���Α����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�E���Â̌��ʂ����҂̊O�e�ɋy�ۂ��e���ɂ��Ă��[���ɐ��������A���̈ӎv���m�F���Ď��Âɂ�����ׂ����Ӌ`�����ꍇ�̂��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ�
��
�B�������A��ʓI�ɂ́A���Ȉ�t�Ƃ��ẮA���҂̐g�̓I�A�����I�����ɏ]���ĕa���ɑ���q�ϓI�ɏ��u�����Α������̂ł����āA���҂���i�ʂ̐\���o������Ƃ��A�E�ƁA���ʁA�N����ғ��L�̎���Ɋӂݖ��炩�ɔ��e��̌��ʂ��d�����ׂ����Ƃ��\�z�����ꍇ�ł���Ƃ������i�̎��R���Ȃ�����A����X�̊��҂̐R���Ⴊ�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩���m�F���A����ɉ��������Â��Ȃ��ׂ����Ӌ`���܂ŕ������̂ł͂Ȃ��B�퍐���Ȉ�t�̎��Â͌����̈˗��̎�|�����E���Ă��Ȃ��E�E�E
�Ƃ��Đ������p�B
�u�����v�������Ⴂ�����ł�������A���_�͕ς���Ă����Ǝv����B
�@
�i�T�j�����n�ُ��a�T�W�N�W���Q�Q�������w�����x�P�P�R�S���P�O�S�� �i����ɂ킽���ĉˍH�̃u�b���W���s��Ŋ{�ߏǁE�F�e�j
�u�����v�����i�吳�Q�N���܂�̎�w�j�͏��a�T�O�N�P�O�����痂�T�P�N�R���܂ł̊ԁA�J�Ǝ��Ȉ�t�ł���퍐����E����A���P���̕�ԁA�����A�V�������Ă�������̉ˍH�`���i�u���b�W�j�̕�C�A���ւ��A�������̎��Ó����˗����A�퍐���Ȉ�͇@�E��O��P���Ȃ����E���P���Ԃ̉ˍH�`���쑕���A�A�E����O��P���Ȃ����E����ꏬ�P���Ԃ̊����̉ˍH�`�����������ĐV���ɉˍH�`���쑕���A�B�E�㒆�莕�Ȃ��������ꏬ�P���Ԃ̉ˍH�`���쑕���A�C��L�A�̉ˍH�`�����������������A�V���ɉˍH�`���쑕�������B�A�̉ˍH�`���̑������ꂽ���a�T�O�N�P�Q���ォ��A�����͉��{�̉^����Q�A�����s�S�A�㕔�̈������A�玞�̌ċz����A�㉏���A�j���̙����������A���a�T�P�N�R��������͙،Q�A�{�߂��u�ɂ������A���o�S�̂ɖ����I���ǂ����������A�Ƃ��Ĕ퍐���Ȉ�̉ˍH�`���̐���̕s��ہA������̊ώ@�A���P�`����ӓ��𗝗R�ɁA���s���s�A�s�@�s�ׂɊ�Â��A�x�Ƒ��Q�P�O�O���~�A���ǂɂ��편���v�ƈԎӗ��R�O�O���~�A�Ԏӗ��Q�O�O���~�A���v�U�O�O���~�𐿋��B
�u�����v
�@�ˍH�`���̐��쑕����̉ߎ��ɂ��āB
�@���Ȉ�t����҂͊��҂̈˗��ɉ����ĉˍH�`���쑕������ɂ������ẮA�ˍH�`���̌`�A���`�A����A���W�A�j���A��e�̑g���A��ۂɂ��Ă͂��Ƃ��A������Ԃ����
�@�\�A�㕔�A���j�����̌��o���̏�Ԃ���̔����A����@�\�ɂ��Ă��d��ȉe�����y�ۂ����̂ŁA���̌`���҂ɓK�����Ȃ��Ƃ��́A�����s�S�ɂ��n�@�\��Q�A�㕔�y�ѓ��j���ɂ���������A�Ђ��Ă͂����ɋN�����閝���I���Ǔ��̏��Q����N������̂ł��邩��A�����̏�Q�y�я��Q��h�����ׂ���Ï�y�ыƖ���̒��Ӌ`���S
������̂Ƃ����ׂ��ł���B�������Ȃ���A������Ԃ́A���̗]�̎���A����y�ъ{�����̍\�����тɊ��Ҍl�̚n�ȂƂ����ւ��A�ˍH�`���̙�����ԓ��ɋy���e��
�͂���߂Č��I�A���A�����ł��邤���ɁA���u��̎g�p�ɂ���āA���̎���A�㕔���̐���ɏ������A�܂��͂��������������߁A�����ēK���Ȍ��o��Ԃ��`���ێ����邱�Ƃ����҂�������̂ł��邱�Ƃ����炩�ł��邩��A�J�Ǝ��Ȉ�t�Ƃ��ẮA���҂̏]�O�̎���A�`���̌`��y�љ�����ԂɊi�ʈُ��F�߂Ȃ�����A���̌`��Ə�Ԃ��Q�l�Ƃ��āA�J�Ǝ��Ȉ�t�̗L����ʏ�̐ݔ��A���Ȉ�w�I�Z�ʂ������āA�ʏ�̕��@�ɏ]���ĉˍH�`����A��������A�ꉞ�O�L���Ӌ`����s�������̂Ƃ����ׂ��ł���E�E�E�A�̉ˍH�`���̐��쑕���ɂ͒��Ӌ`���Ɍ�����Ƃ���͂Ȃ��B
�A�ˍH�`��������̋����ɂ��āB
�@�ˍH�`���쑕�������J�Ǝ��Ȉ�t�Ƃ��ẮA�ˍH�`���̌`������ԋy�ь��o���̏�ԂЂ��Ă͙@�\�A�����A����@�\���ɂ��Ă��d��ȉe�����y�ڂ����Ƃɑz�������A�����㑊�����ԁA����x�A�Œ�x���̐ÓI������Ԃ̂ق�
�A������ԋy�ь��o���ɂ�����㕔�̓��ÁA���{�^���ւ̉e�����̗L���y�ђ��x�ɂ��Čp���I�Ɋώ@���A���ɋ@���p���Đ������A�s�K���Ƃ̐f�f�ɒB���A�܂��͏�Q�A���o���e���̑����A���Ǔ��������Ƃ�.�́A�����ɉE�ˍH�`���̌`����A��C���A�E�����A���Ǔ��̎��Â����Ȃ��ׂ���Ï�y�ыƖ���̒��Ӌ`���S������̂ł����āA�O�L�����̙�����ԋy�т��̉e���̑їL����l���y�є������Ɋӂ݁A���҂ɑ����f�y�љ����̎��s�����Ȃ�͂������A���̎g�p���A��i�����\���ɍl�����邱�Ƃ�v������̂Ɖ�����B�����͇A�̉ˍH�`���쑕���������a�T�O�N�P�Q�����납��A���{�^���̏�Q�A�����s�S�A�㕔�̈������y�ы�ʂɂ�����ċz��������o���A�㕔�y�ѓ��j����������
���݁A�����̕��ʂə�������悤�ɂȂ�A�E�Ǐɂ��Ă͂��̔����̓s�x�퍐�ɑ��i���Ă������Ƃ����炩�ł���A�܂��E�㉺��O��P�������{�̉^�����ɕϑ��I�ɐڐG���邽�߁A���̉^���Ɋ����ď�Q����N����Ƃ��A�J�Ǝ��Ȉ�t�Ƃ��Ă͒ʏ�̈�Ëy�ѕ���g�p�̙�����ɂ���ėe�Ղɔ�����������̂ł���A�{�����Ís�ד����ɂ������ʊJ�Ǝ��Ȉ�t�̐����ɂ���Ă��A�����s�S�A���{�^����Q���A���̖��̂͂Ƃ������n���Ɉُ�������炷�����ƂȂ邱�Ƃ͎��m�̎����ł������̂ɁE�E�E�퍐�͌����̑O�L�Ǐ̎�i�Ȃ����i���ɂ��āA����Ɋ֘A���������Ԃ̐����A�E��i���Ƒ��o�I�����Ƃ̑Δ�Ȃ����q�ϓI�����̌��A�E��i���̔��������̒T�����Ȃ����A���ǂ��������Ï�w�ǝΎނ��Ȃ��������Ƃ��F�߂��A���̌��ʁA�퍐�͌����̎�i���ɂ��Ă̕]�������A�E�㉺��O��P���̉��{�^���ւ̊��̎��Ԃ������������Ƃ�
�͂��߂Ƃ��āA�������Ɍ����ɔ��ǂ��Ă��������s�S�A���{�^����Q�A�㕔�̈������y�љ����̔������̏��Ǐ���ʼn߂��Ă����̏��Ǐ�̑�����h�~����[�u���Ȃ����A�Ђ��Č�ɔ��������،Q�y�ъ{�߂��u�ɁA���o���̖����I���Ǔ��̏Ǐ�\���������āA�����̏Ǐ̌����̏����y�ё������Â̋@����킵�A�E�Ǐ���g�傹���߂����̂ł����āA�퍐�ɂ͉ߎ�������E�E�Ƃ��ĈԎӗ��݂̂P�T�O���~��F�߁A���ꂩ��O���̉ߎ����E�i�퍐��@�ł̎�f���N�ȏ�
�A���Ȉ�@�Ŏ�f�������u�������ߏǏ����j������̂P�O�T���~��F�e�B
�u�����v�u�b���W���܂ߐ��쑕�������`���ɑ��銳�҂̕s���x�͍����A�����ɂȂ�₷���B�K�ȋ`���ł��邩�ǂ����ɂ��Ă̊Ӓ���s���邪�A���҂̑������ɂ͐S���I�ȗv�f������A����͑�ρA����B
�@
�i�U�j�����n�ُ��a�T�W�N�P�P���P�O�������w�����x�P�P�R�S���P�O�X�� �i�����ɂ��ؖ��͏ǁA���_�E�F�e�j
�u�����v�����i�����j�͏��a�S�V�N�R���A�ؖ��͏ǁi�����I�͈͂������i�̈Ք�J���A�E�́A���ԓ��̏Ǐ�j�Ɛf�f����A���Â��Ă������A���a�T�P�N�R�����A�퍐���Ȉ�@�Œ������ÁA�`���쐬�����B���̍ہA����
�ɂ��ؖ��͏Ǐ}���ɑ������邱�Ƃ������A���������Ȃ��悤�Ɉ˗��������A���a�T�P�N�T���P�O���A��{���V�Ԏ��̔����A���NJg�厡�Â̍ہA�퍐���L�V���J�C���𒍎˂����Ƃ���A�����͌ċz�A���s����Ȃǂ͖̋ؗ��ԂɊׂ�A�܂������Q�T���A�������Â̍ہA�L�V���J�C���̔���e�X�g���s�����ہA�S�g���ԂɊׂ�A����ɓ��N�P�P���P�X���A
���{���S�ԁA�T�Ԃ̎��̎��Â̍ہA�퍐�͏C�K�X���z���������̂ŁA�����͂��炭�̊ԁA�ӎ��s���ƂȂ����A�Ƃ��āA�Ԏӗ��R�O�O���~�̐����i�ג�N�B
�u�����v�ȏ�̎����𑍍�����ƁA�퍐�́A��������A���a�T�O�N�P�O���ɓ�����Ȏ��ȑ�w�Œ������Â����ۂɋǏ������ɂ���Ĉُ킪���������ƁA�������d�Njؖ��͏ǂł���A�b��B�@�\�ސi�̋^�������邱�ƂȂǂ̐������A���A�����܂��g�p���Ȃ��悤�˗�����Ă����̂ł��邩��A�퍐�ɂ́A��t�Ƃ��Đ��m�ɂ�����Ƃ��������A�E�v�]�ɂ��������Ė����܂��g�p�����A���Ɏg�p����K�v�������Ă��A�g�p�O�Ɏg�p��܂̌����ɋy�ۂ����ʂ̈��S�����\���m�F���A�����ɑ������܂̐��������ď\���ȏ����[�u���u���钍�Ӌ`��������̂ɁA�����ӂ�A���a�T�P�N�T���P�O�ڂƓ��N�P�P���P�X���Ɍ����ɖ����܂��g�p�����ߎ�������ƔF�߂邱�Ƃ��ł���B�������A���N�T���Q�T�ڂ̖����g�p�́A�P�ɃA�h���i���\���ܗL���Ă��Ȃ��L�V���J�C�����A�����ɑ��Ďg�p�ł��邩���e�X�g���邽�ߌ����̘r�ɂ���𒍓������̂ł���A���O�Ɍ����ɉE�e�X�g�̐��������Ȃ������_�́A�s�����ƌ��킴������Ȃ��Ƃ���ł��邪�A����������Ē����ɔ퍐�ɉߎ�������ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��E�E�E�Ƃ��ĈԎӗ��R�O�O���~�m��B
�u�����v�L�V���J�C���̓A�X�g���[�l�J �А��̋Ǐ������܂ŁA�s�����̎��Ö�Ƃ��Ă��g���Ă���B����҂����ł͂Ȃ��A��ʓI�Ɉ�t�̓L�V���J�C�����ȒP�Ɏg�����A�{���̂悤�ɋؖ��͏ǂ̊��҂łȂ��Ă��A�L�V���J�C���ŃV���b�N������Ⴊ���邩��A�����g�p�͗v���ӂł���B
�@�����ɂ��ƁA�����͏��a�S�V�N�R���A�ؖ��͏ǂ̐f�f���Ď��Â���悤�ɂȂ�A���a�S�X�N�P�P���A���B�E�o��p�����A�Ƃ����̂ł��邩��A�����͂�������ّ̎��ŁA�A�i�t�B���L�V�V���b�N�̉\�����߂Ă��銳�҂Ǝv����B��t�Ƃ��ẮA�����ǂ̏ڍׂ��f���āA����ɑΉ����Ȃ���Ύ��̂̊댯�����傢�ɂ���A�Ƃ����ׂ��ł���B
�@
�@�L�V���J�C���Ɋւ����Éߌ뎖���͑����B
�����n�ُ��a�T�T�N�R���R�P�������w�����x�X�W�S���W�R�ŁE�킫�����ÂŃL�V���J�C���������Ȃ������҂����S�i���p�j
����n�ُ��a�U�O�N�Q���Q�V�������w�����x�P�P�W�V���P�P�S�ŁE�����ɂ̌����̂��߃L�V���J�C����߉t�ł��������A���Y�nj�Q�Ɋׂ�i���p�j
�Y�a�n�ُ��a�U�O�N�X���R�O�������w�����x�P�Q�O�S���P�R�X�ŁE���L�i�V�j�����i���p�j
�É��n�ٕx�m�x�����a�U�S�N�P���Q�O�������w�����x�P�R�Q�R���P�Q�W�ŁE���܊��҂��ό��I������p�̍ۂɃL�V���J�C�������ŃV���b�N���i�F�e�j
�����n�ٕ����U�N�S���Q�V�������w�����x�P�T�R�P���U�P�ŁE�������������҂ɋ��������p���s���ۂɃL�V���J�C���g�p�A�V���b�N���i���p�j
�������ٕ����U�N�P�Q���Q�O�������w�����x�P�T�R�S���S�Q�ŁE�ݓ����������̍ہA�L�V���J�C���ł��������������Ƃ���A�V���b�N���i�F�e�j
�@
�i�V�j�Y�a�n�ُ��a�U�O�N�X���R�O�������w�����x�P�Q�O�S���P�R�X�Łi�����̍ۂ̃L�\���J�C�������Ō��ǔ����E���p�j
�u�����v���a�P�P�N���܂�̏������҂͐e�m�炸�i�E����O�P���j�����̂��߁A���a�T�P�N�V���A�퍐���Ȉ�@�Ŏ�f���A�L�V���J�C���̒��ˁi�Q���L�V���J�C��1cc�����A�Q���L�V���J�C��2cc����v3cc�j��������A���葫��Ⴢꊴ�A�ċz�ُ�A���r���k�i�ؓ����s�N�s�N�����ԁj�Ȃǂ������A���@�ɓ��@���Â������A�E���g�m�o�ݖ��Ȃǂ̌��ǂ������A�܋��̏�Q�Ҏ蒠�����Ɏ������E�E�Ƃ��ĈԎӗ��T�O�O���~�A�편���v�V�Q�O���~�Ȃǂ̑��Q���������i�ג�N�B
�u�����v�i�퍐�͖�f��s�����Ă��Ȃ��A�Ƃ��������̎咣�ɑ��j�������A�{�������ȑO�ɖ�����̓��^���Ă���A���̍ۉ���ُ̈킪�Ȃ��������Ƃ́i�؋��ɂ��j���炩�ł���A�i�؋��ɂ��j�������@���A�������A�����Ȑg�̓I�ُ�������Ă��Ȃ����Ƃ��F�߂��邩��A�������ł�������邽�߂̖�f�Ƃ��ẮA�����̓����̐g�̂̏�Ԃɂ��Đq�˂邱�Ƃő����Ɖ������Ƃ���A�i�؋��ɂ��j�퍐�́A�{�������O�ɁA�u�ǂ��ł����v�ƌ����ɐg�̂̒��q���܂߂Đq�ˁA�����́u�����������ɂ��v�Ƃ̕Ԏ��ɑ��A�O�X���̂P�X�ڂɏ���������̕��p�̗L����q�ˁA�����́A�݉��̂悤�ɂȂ��Ă��邽�ߖ������ł��Ȃ��|�����A���ɔ��M�̎������������ق��A����ȏ�̐g�̓I�ُ��i���Ȃ��������ƁA�����Ŕ퍐�́A�G�f�ɂ�荂�M�łȂ����Ƃ��m���߂����Ƃ��F�߂���B�E���炷��A���Ȉ�t����퍐�ɂ́A����ɖ�f���Č����̐g�̂������^�������ׂ���Ԃł��邩�ǂ����̔��f������ׂ��`���͂Ȃ������A�ƔF�߂���E�E�Ƃ��Ă��̎咣��r�ˁB
�i�̒��s�ǂ̌����ɂ͖������^�������ׂ��ł������A�Ƃ��������̎咣�ɑ��j�����́A���Ґ��㎞�̖����������T����ׂ��|�咣���邪�A���ǂɋN������ƔF�߂��锭�M�Ȃǂ̏Ǐ�ɂ��ẮA���ǂ̂��߂̎�p�A�Ђ��Ă͂��̂��߂̖����̎{�s�𑊓�����ꍇ���l������̂ł����āA���M�A�����s���ȂNJ��҂̐g�̓I�����̗ǍD�łȂ��ꍇ�ɁA���Ȉ�t�����Â̕K�v�㖃����
�g�p���邱�Ƃ��ً}��p�̂ق��A�ꗥ�ɍ����T����ׂ��|�̎咣�Ƃ�����Ƃ�莸���łł����āA������̓��^�̓��ۂ́A����Ɋ��҂̐g�̂̏₻�̏Ǐ�̌����Ȃǂ����̓I�Ɍ��������ׂ������ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��Ƃ���ł���B�O�L�F��̂Ƃ���A�퍐�́A�����̐g�̓I�����ɂ��Ă͈݉��̂悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂƑ������M���Ă��邩������Ȃ����Ƃ�F�����Ă������i�؋��ɂ��j�A�����A�e�m�炸�̎��͉��͑O��̎��Î��i�O�X���̂V���P�X���j�Ɠ��l�̏�ԂŁA�e�m�炸�̐㑤�ɂ͎���w�ǔF�߂�ꂸ�A�����Ԃ��Ȃ��Ă����
�����Ȃ��������ƁA�������퍐�ɑ��A�������e�m�炸�̒ɂ݂������i���A���ꂪ�O��̐f�@���Ɠ��l�̒ɂ݂ł���A�ݒ��̕s���̂��߁A�ɂݎ~�߂̖������ł��Ȃ��|���������Ƃ��F�߂���B�i�؋��ɂ��j�L�V���J�C���̍ő勖�e�ʂ�200mg���x�ŁA200mg�͂Q���L�V���J�C��10cc�ɑ�������Ƃ���A�{�������͂Q���L�V���J�C���Pcc��Z�������̕��@�Œ��˂��A������2���L�V���J�C��2cc��`�B�����̕��@�Œ��˂������̂ł���A�{���������x�̖�ʂŁA�������łɂȂ�����͌����炸�A�����͖{�������ȑO�ɔ�����p�̂��߂Q���L�V���J�C���̖����^�������A���̍ۈُȂ��������Ƃ��F�߂���B�E�E�ȏ�𑍍�����ƁA�퍐�������ɑ��A���̐e�m�炸�̒ɂ݂��������߁A�O�ȓI���u���̂邱�ƂƂ��A�{���������������Ƃ͕s���Ƃ͂������E�E�E�Ƃ��Đ������p�B
�u�����v�d�v�ȈӖ�������̂́A�������ߋ��ɓ���̖������ĈُȂ������A���������ł���B�O��̖�����̌����̉����ω��ŃV���b�N����悤�ɂȂ����̂ł���A�ʏ�̖�f���x�ł͊댯�͔F������Ȃ��ł��낤�B���̖��͈�Éߌ�ł̈�Ԃ̓��ł���B
�@
�i�W�j�Y�a�n�ٌF�J�x�������Q�N�X���Q�T�������w�����x�P�R�V�R���P�O�R�� �i���������c���̓������C���ɓ��蒂�����E�F�e�j
�u�����v���a�U�P�N�W���Q�P���A�S�̗c���i�����j����̕t���Y���Ŕ퍐���Ȉ�@����f���AD�����̋}�����^�����됫�����͉��Ɛf�f����A�����Q�T���AD�����̔������Â����Ƃ���A��q���甲�����ꂽ���������o���ɗ������A���剺���ɗ�������ŁA�C��������A�Ԃ��Ȃ����҂͒��������A���e�����Q���������i�ג�N�B
�u�����v���Ȏ��Â̍ۂɌ��o���Ɉٕ��i��������������܂ށj�𗎉��������ꍇ�̎��Ȉ�t�̑Ώ��Ɋւ��鎕�Ȉ�Â̐����͎��̂Ƃ���ł������ƔF�߂���B�E�̏ꍇ�ɂ͈ٕ��ɂ��C���ǂ��\�z����
�A���������Ȏ��Î��ɂ́A���������H�����ƈႢ�A�J�����ꂽ��Ԃɂ��邽�߁A���̔����p�x�������B�����Ă��ꂪ������ƁA�K���ɋC���m�ۂ̑[�u���u�����Ȃ�����}���ɒ������Ɏ���B�]���āA���o���Ɉٕ��𗎉��������ꍇ�A�܂��C���ǂ������Ă��Ȃ����ǂ����𑬂₩�Ɋm�F���A�܂��C���ǂ�������܂łɎ����Ă��Ȃ��Ƃ��́A�����ʈ�Âł���A���҂����ɂ����܂܊�����Ɍ�
�����A���o���ٕ̈��̈ʒu���m�F������A��q���Ŏ�苎��Ƃ����[�u���u���A�����āA�C���ǂɎ��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɏ��u������r���Ƃ�ׂ��ł���A���̏ꍇ�A�����Đ����ʂ̊��҂����ʂɋN���オ�点�鋓�ɏo�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă��邪�A����͐����ʂ�����ʂɋN�������Ƃɂ���āA�����o�ɗ������ٕ����C�ǂɗ������₷����ԂɂȂ邩��ł���Ɛ�������Ă���B�Ƃ�킯���҂������Ă���Ƃ�����o���Ă���Ƃ��͐��傪�J���Ă��邩��A���̓_�����ɋ����v������Ă���Ƃ���ł���B�Ƃ���Ŗ{���ł͔퍐��t�́A���炪D���������҂̌��o���ɗ����������ہA���҂��吺�ŋ����o���Ă���A�]���Ă��̎��_�ł͂܂��C���ǂ̏Ǐ�������܂łɂ͎����Ă��Ȃ������̂ł��邩��A�����ʂ̂܂܁A���Ȃ킿�A���҂̏㔼�g���N�������ƂȂ��ٕ�����苎��[�u���Ƃ�ׂ��ł������B�R��ɔ퍐��t�͂������Ă��̋��ɏo�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���Ƃ���̊��҂𐅕��ʂ�����ʂɋN�����[�u���̂����̂ł���A����͉E�Ɏ��Ȉ�Ð����ɂ���݂āA��Ï�s�����ׂ����Ӌ`���Ɉᔽ���Ă���E�E�E�Ƃ��Ĉ편���v�A�Ԏӗ��ȂǍ��v�S�T�O�O���~�]��F�e�i�����͍��v�W�S�O�O���~�]�j�B
�u�����v�{���́A�퍐��t�͊��҂𐅕��ʂɐQ�����A������ɔ����������A���҂���������A�}�Ɏ��U�����̂ŁA��q�����҂̓����j�ɓ������Ĕ����������������������A�Ƃ��������ł���B�ٔ����́A��q���甲���������������������͎̂d���Ȃ��ƍl���A���̌�̑[�u��s�K�Ƃ������̂ł���A���҂̎��U�����s�ׂ͉ߎ����E�̌����Ƃ݂͂Ă��Ȃ�
�iD�����Ƃ͓��P���̂��Ƃ��H�j�B
�@
�i�X�j���s�n�ٕ����S�N�T���Q�X�������w�����x�P�S�V�X���U�S�� �i�s�ǃu���b�W�����E�F�e�j
�u�����v�������҂͏��a�S�V�N�A�����Ȉ�@�ŁA�������Ă����㍶���؎��ɂ��ˍH�`���i�u���b�W�j�̐����Ԃ������A���a�T�W�N�A�u���b�W�̎����������ϐF�����̂ŁA���N�T���A�퍐���Ȉ�@�ň�Â����B�퍐���Ȉ�t�́A�E�u���b�W�ɂ����āA�Z���~�b�N�ɂ��`����O�����A���e�|�i�|���̋������i�������M�����Ŏd�グ��\���́A������Z���~�b�N�O���������u���b�W�ŕ�Ԃ��������Ƃ������߁A��p�͈�{�V���T�O�O�O�A�O�{�łQ�Q���T�O�O�O�~�A�ی��O�ł���A�Ɛ�������A�������Ď��Â��˗����A�퍐����
��t��
�u���b�W�삵�A���E�אڎ����x�䎕�Ƃ��Ă�������A�����͎��Ô�Q�Q���T�O�O�O�~���x�������B���������a�U�O�N�S�����A�{���u���b�W���E�����A�퍐���Ȉ�t�͌����ɖ��f�ō��E�אڎ��ɂ��������̍��Ǐ��u���{���A������؏����A�����|�X�g�𗧂āA�R�A�i�z���́j��z�����Ė{���u���b�W�������B���a�U�Q�N�X���A�{���u���b�W���ĂђE�����A�퍐����
��t����đ����������A�o�����̂悤�ȏ�ԂŁA���ݍ��킹�������A�H�����Ƀu���b�W�̗����̋��������ɓ������Ēɂ��̂ŋ����q�ׂ�ƁA�퍐���Ȉ�t�̓u���b�W������߂�����A�u���b�W��Ԃ��ė~������
�A���Â����ۂ���A�����͋��s�{����ȑ�w�a�@�ō��E�אڎ��̍��ǎ��Â��A�V���ȃu���b�W��Ԏ��Â����A�Ƃ��č��s���s�i�s���S���s�j�𗝗R�ɑ��Q���������i�ג�N�B
�u�����v�u���b�W��ԂƂ́A�������̗אڎ��̎����܂��͎����Ɍ������ċ����̗��_�ɂ���Č������̎����`�ԁA�@�\�y�ъO�ς��Ȃ������P�����Ԏ��Â������B���������̃|���e�B�b�N�i�ˍH���A���́j�A�אڎ��ɑ��郊�e�|�i�|�i�x�䑕�u�A���r�j�y�ї��҂���������A��������Ȃ�B�u���b�W�́A�x��z���y�у��e�|�i�|�̑������m���ɍs���A���o���̏������ɑς���悤�ɐv����Ă���ƁA�O����̑��t�̐N�����w�ǂȂ��A���Ȃ��Ƃ��P�O�N�̒����ɂ킽���ĕێ��\�̕�ԕ��ł���B���a�T�W�N�T���A�퍐����
��t�͌����ƌ������ɂ��ăZ���~�b�N�O���������̃u���b�W��K�ɕ�Ԃ��邱�Ƃ�ړI�ɂ������Ì_�����������̂ł��邩��A�퍐���Ȉ�͎x��z����u���b�W�̐v�A�����K�ɍs���A���Ȃ��Ƃ��P�O�N�Ԃ̒����g�p�ɑς���悤�ȃu���b�W��Ԃ��{���ׂ������Ă���
�B���s���s�m��B���Q�Ƃ��Ė{���u���b�W����̂W�O���Ƌ��s�{����ȑ厡�Ô�P�U���X�T�Q�O�~�A�Ԏӗ��Q�O���~�A�ٌ�m��p�U���~�F�e�B
�u�����v���̔����͎��Ȏ��Ì_��̐����_���m�肵�����̂ł͂Ȃ����A�ƕ]������Ă��邪�i�A�ؓN�O�f�w��Ô���K�C�h�x�Q�S�Łj�A�����͎��Ì_����Ƃ͎咣���Ă��炸�A�����ɂ������Ƃ����悤�ȕ\���͂ǂ��ɂ��Ȃ��B
�@
�i10�j�����n�ٕ����T�N�P�Q���Q�P�������w�����x�P�T�P�S���X�Q�� �i�C���v�����g���Â̕s�����咣�E�F�e�j
�u�����v�����i���a�P�O�N���܂�̏����j�͏��a�T�V�N�T���A�퍐���Ȉ�t����A���̂Ȃ������̍��Ɉ��̎x���ߍ��݁A����Ɏ����͂ߍ��ށA�Ƃ���
�C���v�����g�@���Â������߂��A���{�Ƀs���E�C���v�����g���A��{�Ƀu���|�h�E�C���v�����g�̑����������A���a�U�P�N�P���A�C���v�����g�����炮�炷��̂ŁA�퍐���Ȉ�@�Ŏ�f�����Ƃ���A�퍐���Ȉ�t�͏�{�̃u���|�h�E
�C���v�����g�����O���A���N�Q���A�������C���v�����g�������B�������A�C���v�����g�͈ˑR�Ƃ��Ă��炮�炵�ęł����A���L������̂ŁA������Ȏ��ȑ�w�t���a�@�Ŏ�f�������ʁA���s�ɉ��ǂ�����A
�C���v�����g�����O���A���s�̐؏���p�����A�Ƃ��ċx�Ƒ��Q�A�편���v�A�Ԏӗ��ȂǍ��v�S�Q�S�U���~�]�̑��Q�{�ܐ����i�ג�N�B
�u�����v�i���a�U�P�N�P���A�������C���v�����g�I���y�ю{�p��̉ߎ��ɂ��āj
�i�؋��ɂ��j�C���v�����g�@�̒��ł����ɍ������C���v�����g�@�́A�����C���v�����g�@�ł͎{�p�s�\�ȍ��z�����������Ǘ�ɓK�p�������̂ł��邪�A�C���v�����g�̂��x������ɕK�v�Ȉ��肵���������݂��A���A���������C���v�����g�̂����Ɛ��m�ɖ������Œ肳��Ă��邱�Ƃ������̏����Ƃ���Ă��邱�ƁA�����āA���ʈ�ۂ̍ۂƃC���v�����g�t���|�������̍ۂɓ�x�ɂ킽�莕����؏�����Ƃ����傫�Ȏ�p�����邱�Ƃ��K�v�ł���A�S������������ɂȂ铙�A�����C���v�����g�ɔ�r���ĕ��G���x�ȋZ�p���v������邱�ƁA�܂��{�p��ɓ��h���ɂ����
�C���v�����g�����Ɏ������ꍇ�ɂ́A�������̋ɓx�ȋz�����A���ɐ[���ȑ�����^������̂ł���A���̂悤�Ȋ댯�����炵�ėՏ���Ƃ��ẮA�܂��L�������ꎕ�ɂ�鎡�Â����݂�ׂ��ł���A���҂ɑ�������
�C���v�����g�̊댯���������������������ŐT�d�ɂ�����s���̂��]�܂����A���Ղɍ������C���v�����g���{�p���ׂ��łȂ����Ƃ����ꂼ��F�߂���B���Ƃɖ{���ɂ����ẮA�O�F��̂Ƃ���A�����͖{��������
�C���v�����g�{�p�O�ɑO�L�u���|�h�E�C���v�����g�ɂ�鎡�Â������A���z���ɂ���Ď��s�����Ƃ̑O��������A���҂��錴�����A�C���v�����g�Ɋւ���O�L�V���L����
���āA��{�ɍ������C���v�����g���{�����Ƃ͖����ł͂Ȃ����Ɗ�䂵�A�퍐�ɂ��̎|���₵���̂ɁA�퍐�́A�����̉E��������グ���A���a�U�P�N�P���Q�Q���A�퍐�͖{���u���|�h�E�C���v�����g���������A���̈�T�Ԍ�̓����Q�X���Ɍ����̏�{�ɍ��ʈ�ۂ��s���������A���̂U����ł��铯�N�Q���S���A�{���������C���v�����g���������̂ł���A�����āA�O�L�Ӓ�̌��ʂɏƂ炷�ƁA�{���u���|�h�E�C���v�����g������ɂ����ẮA�����̏�{�{���͑S�{�ɂ킽���ċ}���ɍ��z�����N���邱�Ƃ����炩�ł���A�x���������肵����ԂƂ͂����Ȃ��������Ƃ��F�߂���B�����āA���̌��ʁA�E�������C���v�����g�{�p������̓��h�͎��܂炸�A��{�������ɜ늳���āA���ǂ͑i�O�t���a�@�ʼnE�C���v�����g�̏�����p�������
���Ȃ��Ȃ������Ƃ��O�F��̂Ƃ���ł���B�E�̂悤�Ȏ���ɂ����ẮA�������C���v�����g���{�p���悤�Ƃ��鎕�Ȉ�t�Ƃ��ẮA�����Ȃ��Ƃ��U�����ȏ�{���̈����҂��č��ʈ�ۂ��s�����A�{���ƃC���v�����g�E�t���|���Ƃ��m���ɖ��������Ԃ����҂�����K�Ȏ����ɍ�����
�C���v�����g�{�p�Ɉڍs����悤�A�T�d�Ȕz�������ׂ����Ӌ`�������������̂Ƃ������Ƃ��ł��A�퍐���{���ōs�����������C���v�����g�̎{�p�́A��������̑O�L�뜜�̔O��}���������Ő��}�ɂ�������{�����Ƃ̂������Ƃꂸ�A���̎����A���@�A���тɌ��ʂɏƂ炵�A�퍐�ɂ͗Տ����Ȉ�t�Ƃ��ẲE�̒��Ӌ`����s�����Ȃ������ߎ�������E�E�Ƃ��āA���v�R�P�S�R���~�]�̑��Q����������F�e�B
�u�����v�C���v�����g�͎��������������l�ɂ��K�����鎡�Ö@�ł���A�ŋ߁A���Ȃ�s���Ă��邪�A���҂̊{���̎��A�ʂ̔c���Ȃǂ̎��O�`�F�b�N���d�v�ł���Ƃ���Ă���i�ۋ��O�f���Q�O�U�ňȉ��j�B
�@
�i11�j�����n�ٕ����U�N�V���Q�Q�������w�����x�P�T�Q�O���P�P�V�Łi�{�ߏǂ̎��Âɂ��Ă̐����s���Ȃǂ��咣�E���p�j
�u�����v���a�P�Q�N�Q�����܂�̐�Ǝ�w�͏��a�U�O�N�P�O���A�������ȑ�w�������a�@�Ŋ{�ߏǖ��͂���ɋN�����鉼���O���_�o�ɂƐf�f����A���a�U�P�N�U���A�|�{���Ȉ�@�Őf�@���A�`���C��������������A���a�U�R�N�V���A�퍐��@�Ŏ�f�B�_�C�i�o�|�e�B�ɂ��͌^�f�f�̌��ʁA�������a���Ⴂ�ȂǂƐf�f����A���E�̏㉜���̌��������ɕ������`�����쐬���A����̂ق��Ɏ��̙����ʂ�������t���č���̙����ʂ����邱���Ƃ��A�������N�S���Q�W���A���㉜���O�{�ɘA�������������������B���̌�A���҂͗��w�Ö@�������A�퍐��@�̎��Â����A�����ُ�Ƃ̐f�f�͌�f�A���������Ȃ��ɍ���������������A���u�ɂ��Ẵ��X�N�̐����Ȃ��A�Ǝ咣���āA���������A��A�������̒ɂ݂𗝗R�ɑ��Q���������i�ג�N�B
�u�����v���҂ɂ��Ă͙����ُ�̒����̕K�v��������A���̓_�Ɍ�f�͂Ȃ��B���ґ��咣�̂悤�ȍ���������������؋��͂Ȃ��B���u�ɂ��Ă̐����`���ᔽ���Ȃ��B�������p�B
�u�����v���҂͊{�ߏǂ̉e���̂������A�����_�o�����ǂŁA�i�|�o�X�Ȋ��҂ł������B�{�ߏǂ͌������肪����ŁA���Ö@���m�肹���A���푽�l����A�����̋N����₷�����a�ł���B
�@
�i12�j�����n�ٕ����U�N�R���R�O�������w�����x�P�T�Q�R���P�O�U�Łi�C���v�����g���Â̕s��Ȃǂ��咣�E�J���e�s��o��肠��E�F�e�j
�u�����v�����͎q���̍����玕���^�R�i���̎����a�j�ŁA���a�T�O�N���A������Ȏ��ȑ�w�t���a�@�Ŏ�x��Ɛ鍐����A���a�T�R�N�W�A�X���A����s���̎��Ȉ�@�ŁA�E��{�R�A�S�A����{�R�A�S�A�E���{�Q�A�R�A�W�A�����{�R�A�W���c���Ĕ��������B���N��ꍠ�A�퍐���Ȉ�@�Őf�@���A���T�S�N�P���A���a�T�V�N�U���A�C���v�����g��p���A���a�T�W�N�W���A�ꕔ�̃C���v�����g���������A���N�X���A�ĂуC���v�����g��p���A���a�U�Q�N�X���܂Ő���ɂ킽���āA����p�Ȃǂ������A�{�̎��A�ɂ݂��Ђǂ��̂ŁA���N�P�O���A������Ȏ��ȑ�w�t���a�@�Őf�@�����Ƃ���A�{�ߏǁA�E��{�����Ɛf�f����A���̌���퍐���Ȉ�@�ŃC���v�����g���ߍ��ݎ�p��`�����t����p�Ȃǂ��A�������N�Q���A������Ȏ��ȑ�w�t���a�@�Ŗ������^�����������Ɛf�f����ď�{�̃C���v�����g�̏�����p���A�����S�N�A���{���ȑ�w�t���a�@�ʼn��{�̃C���v�����g��������p�����B�����͕s�K�ȃC���v�����g��p�A�C���v�����g�̖��f�����A��{�����E�̔�����ӁA����ɑ��鎡�Â̕s�K�Ȃǂ��咣����
�A���Ô�A�편���v�A�Ԏӗ��ȂǍ��v�Q�Q�T�Q���~�]�̑��Q���������i�ג�N�B�Ȃ��{���ɂ͌�������̎咣�͂Ȃ��������A�؋��ۑS�ɂ��J���e�̌��ňꕔ�J���e�̒�o���ӂ������Ƃ��������i�ז@�R�P�V���̏ؖ��W�Q�ӔC�����ɓ����邩�Ƃ������Ƃ����ƂȂ����B
�����O�̋������i�ז@
�R�P�U���i�����҂̕s��o�̌��ʁj
�����҃J������o�m���j�]�n�T���g�L�n�ٔ����n�����j�փX��������m�咣���^���g�F�����R�g����
�R�P�V���i�����҂̎g�p�W�Q�̌��ʁj
�����҃J������m�g�p���W�N���ړI���ȃe��o�m�`���A���������ʖŃV���m���V���g�p�X���R�g�\�n�T���j�����V���^���g�L�n�ٔ����n���m�����j�փX��������m�咣���^
���g�F�����R�g����
���s�����i�ז@
��Q�Q�S��(�����҂�������o���߂ɏ]��Ȃ��ꍇ���̌���)
�@�����҂�������o���߂ɏ]��Ȃ��Ƃ��́A�ٔ����́A���Y�����̋L�ڂɊւ��鑊����̎咣��^���ƔF�߂邱�Ƃ��ł���B
�A�����҂�������̎g�p��W����ړI�Œ�o�̋`�������镶�������������A���̑�������g�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɂ����Ƃ����A�O���Ɠ��l�Ƃ���B
�B�O�ɋK�肷��ꍇ�ɂ����āA��������A���Y�����̋L�ڂɊւ��ċ�̓I�Ȏ咣�����邱�Ƌy�ѓ��Y�����ɂ��ؖ����ׂ������𑼂̏؋��ɂ��ؖ����邱�Ƃ�����������ł���Ƃ��́A�ٔ����́A���̎����Ɋւ��鑊����̎咣��^���ƔF�߂邱�Ƃ��ł���i������Y�w����V�����i�ז@�x�L��t���u���T�V�ŎQ�Ɓj�B
�u�����v
�������i�ז@�R�P�V����ɂ��āB
�Ƃ���ŁA�{���ɂ��ẮA�i����N�O�Ɏ��̂悤�Ȏ��������������Ƃ��w�E����K�v������B�����̐\���ɂ��A�����n�ٔ����q�x���ٔ������A�N�i�O�̏؋��ۑS�Ƃ��Ĉ�Ø^���̏��ނ������s�����߁A�����Q�N�P�O���R�O��
�A���j�o�|�T�����ȃN���j�b�N�i�퍐�^�c���Ȉ�@�j�ɕ������ہA�ٔ����A���L���y�ь����㗝�l��͏��a�T�S�N�P���P�O�����畽�����N����܂ł̈�Ø^�̑��݂��m�F�������A�퍐���s�݂Ƃ������Ƃœ��e�̒͋��ۂ��ꂽ�B�����ŁA���؊������ēx���肳��A���N�P�P���P�U���ɓ�x�ڂ̌����s��ꂽ���A�퍐�͏��a�U�O�N�T���Q�T���ȍ~�̈�Ø^���������A����ȑO�̈�Ø^�ɂ��ẮA�ٔ���������̌��؊����ɂ����Ă��̑��݂��m�F�����|�������Ă��u��������Ȃ��v�Ƃ̂ݕى����Ē����ۂ����B�E�̌o�߂ɂ��A�퍐�́A���a�U�O�N�T���Q�T���ȑO�̃J���e���ɂ��āA���ꂪ�ٔ��̏؋��Ƃ��Ē����߂��Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ���A�����Ĕp�������Č������؋��Ƃ��Ďg�p�ł��Ȃ���Ԃɂ������̂Ɛ��F�����B��Ø^�́A������t�̈�Â��K���ɍs���Ă���Ȃ�A���̂��Ƃ��ؖ�����ŗǂ̏؋��ƂȂ�͂��̂��̂ł���B�������t���炪�؋��Ƃ��邱�Ƃ�W�Q����̂́A��Âɕs�K���ȓ_���������Ƃ̔F��Ɍ��т��L�ڂ���Ø^���ɑ��݂����̂ł͂Ȃ����Ƃ̋^���������ɑ����s�ׂł���Ƃ����ׂ��ł���B��������ƁA���a�U�O�N�T���Q�T���ȑO�̈�Ø^�ɋL�ڂ���Ă����\���̍��������̏Ǐ���Ó��e���ɂ��ẮA�����̋��q���e��
���ɕs�����ł͂Ȃ��A������ƈقȂ�퍐�̋��q�ɏ\���ȍ������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����i�ז@�R�P�V���̎�|�ɏ]��(�����́A���������p������A��Ø^�̓��e�ɂ��ċ�̓I�Ȏ咣�������肵�Ă���킯�ł͂Ȃ���)�A
�����̋��q��^���ƔF�߂�̂������ł���B
�C���v�����g�ɂ���{�����E�ɂ��āB
�@�C���v�����g��p���̂��̂ɂ���ď�{�����E�����������ƁA���邢�͂��̌�Ԃ��Ȃ���{�����E��������悤�Ȏ�p���s�������Ƃ́A�{�p�ɉߌ낪�������ꍇ�ł���A���������C���v�����g��I���������Ƃ��邢�̓C���v�����g�̋Z�@�̑I���Ɍ�肪�������ꍇ�ł���A���i�̎���Ȃ�����A���Ȉ�t�Ƃ��Ă̔퍐�̈�Ì_���̑P�ǒ��Ӌ`���Ɉᔽ������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�A�퍐����{�����E��F�߂Ď��Â��J�n�����̂́A��p��W�P�����o�߂��A������������Ȏ��ȑ�w�t���a�@���o�O�Ȃŏ�{�����E�̉\�����w�E���ꂽ���Ƃ�퍐�ɍ�������̏��a�T�W�N�W�����ƔF�߂���B�������A�����ɂ��ẮA�O�L�̂Ƃ���A��p�㕷���Ȃ����爫���ȏ�{�����̏Ǐ���ꂽ�̂ł���A���̒i�K�ł����E�̔����̉\���͂��������̂Ɛ��F����(�E�\���̗L�����m�F�ł��Ȃ�����́A��Ø^�̕s���݂ɂ���ƍl������̂ŁA�퍐�ɕs���v�ɔF�肷�ׂ��ł���)�A���N�S���ɂ͓��i���@��A�ȂŎ����̒~�^�ǂƐf�f����A���N�U�����댴������ɂݓ���������ꂽ�̂ł��邩��A�x���Ƃ����̎����ɂ͏�{�����E�̉\�����^���A�����ɂ�����m�F���āA��{���ƌ��o�Ƃ̌�
�ʂ��[�u���u����ׂ��ł������ƔF�߂���B���������āA�퍐�ɂ́A��{�����E�̔������x�ꂽ���Ƃɂ��A�����ɑ��s���ɒ����ɔr�^�A�]�ɁA�y��A�����ɓ��̋�ɂ�^�����Ƃ����_�ɂ��Ă��A��Ì_���̒��Ӌ`���ᔽ���F�߂���Ƃ����ׂ��ł���B
�B�E�o�߂ɏƂ点�A�������C���v�����g�������̖ړI��B���������s�ɏI��������Ƃ͔ے�ł����A�{���̏ꍇ�A�������C���v�����g����{�����E�̕����@�Ƃ��ėL���K�Ȃ��̂ł��������ǂ����ɂ��ẮA���ʘ_�Ƃ��Ăł͂Ȃ��^�₪����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�݂̂Ȃ炸�A���ɂ킽���ăC���v�����g���s�����ɏI���A�O�̃C���v�����g��������������̕��ʂցA�Z�@�͈Ⴄ�Ƃ͂����A�O�x�C���v�����m��p���s�����Ƃɂ��ẮA�T�d�łȂ���Ȃ�Ȃ������ƍl������B�������C���v�����g�ɂ��ẮA������Ԃ��Ȃ����o�ɍs���̂͋֊��Ƃ���A���Ȃ��Ƃ��P�W�Ȃ����Q�O�����̌o�ߊώ@��Ɏ{�s���ׂ��ł���Ƃ���Ă���̂ł����āA���̓_�͔퍐���g�̒���ɂ����Ă��L�q������B�C���v�����g������ɂ��Ă͔�����Ɠ��i�Ɏ���قȂ�Ƃ��l����̂ł����āA�ȏ�̂悤�ȏ��_���l������ƁA�{���������C���v�����g�́A�C���v�����g���̂��̂Ƃ��Ă��A��{�����E�̕����@�Ƃ��Ă��K�Ȃ��̂ł������Ƃ͎v��ꂸ�A�������C���v�����g��p��I���A���{���A���̏�{���̕��p��I���A���{���Ȃ������_�ɂ����āA�퍐�ɂ́A�P�ǒ��Ӌ`���ᔽ������ƔF�߂���B
�C�{���X�E�F�|�f�����C���v�����g��p�̎{�p�Ƀ~�X�����������Ƃ��M�킹��؋����Ȃ��̂ŁA�����̊{���̏�ԓ����C���v�����g�ɓK�����Ȃ����̂ł������A���邢�͏]�O�̎�p�̌��ʂ��łɓK�����Ȃ����̂ƂȂ��Ă������ƂɌ��������������̂Ɛ��F����邪�A�퍐�Ƃ��ẮA�����⌴���̎��ÂɌg������҂Ƃ��āA���R���̂��Ƃ�F�����ׂ��ł������ƔF�߂��邩��A�E�C���v�����g��p���s���A���������^�����������ɜ�点���퍐�̍s�ׂ́A��Ì_��ɂ�����P�ǒ��Ӌ`���Ɉᔽ������s���s�ɂ�����Ƃ�����E�E�E�Ƃ��đ��Q�T�P�X���~���m��B
�u�����v��Éߌ뎖���ɂ����Ă̓J���e�̕s��o�A������Ȃǂ̖�肪�Ƃ��ǂ��N����B�{�������̈��ł���B
�@
�i13�j�����n�ٕ����U�N�P�Q���Q�U�������w�����x�P�T�T�Q���X�X�� �i�A�X�s�����b�����҂ɋ֊��Ƃ���Ă�����ɍ܂𓊗^�A���S�E�F�e�j
�u�����v�Q�O�N���A�X�s�����b���œ��މ@���J��Ԃ��Ă����j�����҂͕����Q�N�R���A�퍐���Ȉ�@�Œ����̎��Â̂��ߔ������u�������A���҂͗\�f�^�́u���Ȃ��̑̎��́v�̍��Ɂu���ّ̎������v�ƁA�u�g���Ȃ���́v�̍��Ɂu�s�����n��܁v�ƁA�u���܂ł��������a�C�v�̍��Ɂu�����v�ƋL�����A���u�O�̖�f�ł����l��|�̕Ԏ��������B�������퍐���Ȉ�t�͓����A�A�X�s�����b���̊T�O�A���ɍ܃��L�\�j�����A�X�s�����b�����N���������ꂪ���邩��A�A�X�s�����b�����҂ɑ��Ă͓��^���Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ̒m����L���Ȃ������B���̂���
�A�퍐���Ȉ�t�͔�����A���҂ɉ��^�~�߂̂��߃P�t���b�N�X���A���ɂ̂��߃��L�\�j���𓊗^�����i�㐙�E�������^���A���҂͋A��㕞�p�����悤�ł���j�B���҂͋A���Ԃ��Ȃ��������b��������N�����A�Ԍ�Ɏ��S���A�⑰��
�Ԏӗ��ȂǂQ�T�T�O���~�̑��Q���������i�ג�N�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u�����v�i�A�X�s�����b���ƃ��L�\�j���Ƃ̊W�ɂ��j�A�X�s�����b���́A���ׂĂ̎_����M���ɖ�i�_����X�e���C�h���R���Ǎ܁j�ɂ���Ĕ��삪�U�������b���ł���A���l�̋C�ǎx�b���̖�P�O�Ȃ����P�T�p�|�Z���g���߂Ă���A���̓����Ƃ��ẮA�@�d�Ǔ�Ⴊ�����A�����X�e���C�h�ˑ����ł���A�A���삪�ʔN���ɔF�߂��A�ӎ���Q���قǂ̑唭����o�����Ă���ǗႪ�����A�B�������@�o���A�@���̍����Ⴊ�����A�C���N�ɂȂ��Ă��甭�ǂ��邱�Ƃ������A�R�O�Α�ɚb�����ǂ̃s�|�N������A�D��A�g�s�|���ł���A������IgE�͒�l�A��ʃA�����Q���ɑ���畆�����̓J���W�_�Ȃǂ̐^�ۗނ������ĉA���A�������̊e��R�����ٓIIgE�͉A���A�����b���Ȃǂ̃A�����M�|�����̊����ǂ͂܂�ł���A�A�����M�|�����̉Ƒ��������Ȃ��Ȃǂ��������Ă���B�܂��A�A�X�s�����b���ɂ�锭��͂����Έӎ���Q���قǂ̑唭��ɂȂ�A�����̏ꍇ�͐l�H�ċz��̑����܂ŕK�v�Ƃ���B�A�X�s�����b���́A���a�T�T�N���납��ċz���A�����M�|�����̐���̖�Œ��ڂ����悤�ɂȂ�A���a���w��G����U���Q���i���a�U�P�N�X�����s)�ɂ͊��ɃA�X�s�����b�����҂̎��Ȏ��Ìo���Ƃ��āA�A�X�s�����b�����A�X�s�����݂̂Ȃ炸�A���̑��̒��ɖ�ł��b�����삪�U����������Țb���ł���A�������ɍ܂̐T�d�ȓ��^���K�v�ł���|�̋L�ڂ�����B����ɁA�����Q�N�R�����s�́u���Ȉ�̒m���Ă���������w�펯�P�O�R�I�v�ɂ́A�C�ǎx�b�����҂̎��Ȏ��Î��̒��ӂƂ��āA�A�X�s������C���_�V�^���Ȃǂ̔�X�e���C�h�n�����܂̓��^�͏Ǐ�����������邱�Ƃ�����̂Ŕ����������悢�|�́A�܂������S�N�P�P�������́u���E���Ȉ�̒m���Ă���������w�펯�X�T�I�v�ɂ́A�A�X�s�����b�����҂̗Տ����̓����⓯���҂̎��Ȏ��Î��̒��ӂƂ��āA���L�\�j�����̎_�����ɏ����܂͂��ׂĔ����U������\��������ƍl����ׂ��ł���A��_���̒��ɍ܂��邢�͏����܂�I�����ׂ��ł���|�̋L�ڂ�����B���L�\�j��(���L�\�v���t�F���i�g���E���j�́A���a�U�P�N����A�O��������Ђ���̔�����n�߂��t�F�j���s���s�I���_�n�A��X�e���C�h���̒��ɁA�R���Ǎ܂ł���A�����߃��E�}�`�A�ό`���ߏǂȂǂ̊��҂��p�A������Ȃǂ̒��ɁA�����ɍL���g�p����ė��Ă���A�����ǂ���z�����ꂽ�̂��̑��Ŋ�����ӕ��ɕϊ�����č�p����̂ŁA�o�����^�����܁Z���o�ߌ�ȍ~�ɂ��̖�p�������������B���a�U�P�N�U������Љ����̃��L�\�j���̎g�p�������ɂ́A���Ɏg�p��̒��ӂƂ��āA�A�X�s�����b�����͂��̊������̂��銳�҂ɂ͓��^���Ȃ����ƁA�C�ǎx�b���̂��銳�҂ɂ͐T�d�ɓ��^���邱�Ƃ��A����ɂ́A����������Ƃ��ē���m��������ꂼ��L�ڂ���Ă���(�Ȃ��A�����S�N�R�������̎g�p�������ɂ́A�A�X�s�����b���ɔ�X�e���C�h���������ɍܓ��ɂ��b��������U���Ƃ̐������lj�����Ă���j�B
�i�퍐���Ȉ�̉ߎ��ɂ��j
�O�L�F�肵���Ƃ���ɂ��A�퍐���Ȉ�t�́A�b���ɂ̓A�X�s�����b�������邱�Ƃ�{�����̓����m��Ȃ����������߂ɁA�\�f�^�y�і�f�ɂ�芳�҂ɂ͚b���̊����������邱�Ƃ�m���Ă����ɂ�������炸�A�A�X�s�����b�����͂��̊������̂��銳�҂ɑ���g�p�͋֊��ł��郍�L�\�j������ɁA�R���Ǎ܂Ƃ��Ċ��V���ɓ��^�������ʁA���҂����S����Ɏ��点�����̂ƔF�߂�̂������ł���B���������A��t�����҂ɖ�܂𓊗^���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A��܂́A����ł͓���̎��a�Ȃ����a��ɑ��Ă͗L���ł�����̂́A�����ł͕���p���g�̂Ɉ��e�����y�ڂ��댯������ɗL������̂ł���̂�����A��t�Ƃ��ẮA���̋Ɩ��̓��ꐫ���炵�āA�܂��A�\�ߓ��Y��܂Ɋւ���m�����̍Ő�[�ɋy
�Ԕ͈͂̂��̂܂Ŗ�܂ɓY�t����Ă���g�p�������ɂƂǂ܂炸���̈�w�������������i����g���ďK�����������˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��������錤�r�`�����Ă��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����肩�A�����ɖ�܂𓊗^����ɂ������ẮA�E���r�ɂ��擾�����m���Ɋ�Â��A���҂����Y��܂̓��^���֊��Ƃ���Ă���҂ɊY�����邩�ۂ��Ɋւ��鎖�������ғ�����ڍׂɕ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����f�`�����Ă�����̂Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��A����ɂ́A���̂����ŁA�E��f�œ���ꂽ���҂̕a��Ȃǂ̖�f���ʂ₻�̑��̊e�팟�����瓾��ꂽ�������ʂ��犳�҂ɂƂ��ē��Y��܂��֊��łȂ����Ƃ��m��I�ɔ��f�ł��Ȃ��ȏ�͉E��܂𓊗^���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������^�ɂ����钍�Ӌ`�����Ă�����̂Ɖ�����̂������ł���B�Ȃ�قǁA�E��t�ɉۂ�����`���̂����A�����`���ɂ��ẮA��Â̍��x���ɔ����Ĉ�t���ɓx�ɐ�剻���Ă��邪���߂ɁA��܂̒m���ɂ��Ĉ�w�̑S��啪��ł��̍Ő�[�̒m�����C�����邱�Ƃ��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A���₵�����l�̐����y�ь��N���Ǘ�����Ƃ�����t�̋Ɩ��̓��ꐫ�Ɩ�܂��l�̂ɗ^���镛��p���̊댯���Ɋӂ݂�A�E�̂悤�Ȉ�t�̐�剻�𗝗R�Ƃ��đO�L�̂悤�Ȍ����`�����y������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����ׂ�����B
�O�L�F��̂Ƃ���A�O��������Ђ��쐬���ď��a�U�P�N�U���ɉ����������L�\�j���̎g�p�������ɂ́A���Ƀ��L�\�j���͎_�n�A��X�e���C�h���̖�܂ł���A�g�p��̒��ӂƂ��ăA�X�s�����b�����͂��̊������̂��銳�҂ɂ͓��^���Ȃ����Ƌy�ыC�ǎx�b���̂��銳�҂ɂ͐T�d�ɓ��^���邱�Ƃ��L�ڂ���Ă���A����������Ƃ��ē���Ј���̋L�ڂ����������ƁA���a�U�P�N�X�����s�̎��w��G���ɃA�X�s�����b�����҂̎��Ȏ��Ìo�����L�ڂ��ꂽ�ق��A�����Q�N�R�����s�́u���Ȉ�̒m���Ă���������w�펯�P�O�R�I�v�ɂ͋C�ǎx�b�����҂̎��Ȏ��Î��̒��ӂȂǂ��A�܂��A�����S�N�P�P�����s�́u���E���Ȉ�̒m���Ă���������w�펯�X�T�I�v�ɂ̓A�X�s�����b�����҂̎��Ȏ��Î��̒��ӂȂǂ����ꂼ��f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�{�����̓����A�퍐���Ȉ�t�́A���L�\�j���𓊗^����ɂ����肻�̋֊��ǂł���A�X�s�����b���Ɋւ���m���̏C���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ȉ�t�Ƃ��Ă̌����`�����Ă������̂Ƃ����ׂ��ł���A����ɂ�������炸�A�O�L�F��̂Ƃ���퍐���Ȉ�t�̓A�X�s�����b���̊T�O��A�X�s�����b���ƃ��L�\�j���̊W�ɂ�����m��Ȃ������̂ł��邩��A�E�����`����s���������̂Ƃ͓��ꂢ�����A���̓_�ɂ����Ċ��ɔ퍐�̃��L�\�j�����^�ɂ͉ߎ����F�߂��邱�ƂɂȂ�E�E�E�Ƃ��ĂP�X�Q�O���~��
����������F�e�B
�u�����v�����͔퍐���Ȉ�t�̌��r�`����ӂ𗝗R�ɉߎ����m�肵�����A����͋֊��Ƃ�����ܓ��^�̉ߎ��̈�̗��R�t���ł���B�Ȃ��A�{�����͕̂����Q�N�R�������ł��邩��A�����S�N�P�P�����s�́u���E���Ȉ�̒m���Ă���������w�펯�X�T�I�v�������o���̂͂��������B
�@����������IgE��Ig�Ƃ́A�Ɖu�O���u�����A���Ȃ킿���̓��ɓ���ۂȂǂ̎h���ŎY�������`�����̂��ƂŁAIg�ɂ�G�AA�AM�AD�AE�̌�ނ�����B
���̂�����E�A���Ȃ킿IgE�͖Ɖu�Ɋւ�����̂ŁA����l��0.002�`0.05mg/dl�ł���B
�@
�i14�j�����n�ٕ����P�Q�N�P�Q���Q�T�������w�����x�P�V�S�X���U�P�� �i�{�ߏǎ��ÂŎ��R���f�ō��ꂽ�Ǝ咣�E�F�e�j
�u�����v�����i�����j�́A����s���ɂ������s�S�ȂǂŋN�������{�ߏǂɂ���̒ɂ݂ȂǂŔ퍐���Ȉ�̐f�@���A�퍐���Ȉ�͕�Ԏ��Ái���R�����퍇���ċ������̊��Ŕ핢���鎡�Ö@�j�̂��߁A���ɂ킽���Ď��R����啝�ɍ퍇�����B�����͂��̍퍇�ɂ͏\���Ȑ������Ă̏����͍s���Ȃ������A�Ƃ��đ��Q���������i�ג�N�B
�u�����v�{�ߏǂ͑����̈��q�����݂ɕ��G�Ɋ֘A���鐮�`�O�ȓI�v�f�����a�C�ŁA���Ö@�����푽�l����A���R���̍퍇����Ԏ��Â͐N�P���̍�����̎��Ö@�ŁA�������ً}���͂Ȃ��������̂ŁA�����͎��̍퍇�ɂ͋��|��������Ă����̂ł��邩��A���Ղ���̓I���@�Ŏ��Õ��@�A���Â̌��ʁA���R���͎g���Ȃ��Ȃ邱�ƂȂǂ�������Đ��m�ȗ����Ɋ�Â�����������ׂ��ł��������A�퍐���Ȉ�̂Ȃ��������͕s�\���Ȃ��̂ł������B�����̈ꕔ�i�Ԏӗ��T�O���~�ƕٌ�m��p�P�O���~�j��F�e�B
�u�����v�Ó��Ȕ����ł���B���̔����ɂ����鎖���W���݂�ƁA�{�ߏǂƂ����a�C���́A���G���q���������Ȃ��̂ł����������A�������҂͔퍐���Ȉ�@�̂ق��A���ӏ��Ŏ��Â��A�A�����M�|�̎������A�i�|�o�X�Ȋ��҂ł��邱�Ƃ���������B�O�L�̂悤�ɁA�����̑ΏۂƂȂ銳�ґ��ϓI���z�I�Ȃ��̂ƍl���Ă͂����Ȃ��B�����Ώېl�͈�t�̊�O�ɂ���A�獷���ʂ̌�������̓I���݂Ƃ��Ă̐l�Ԃł���B���̐ڋq�Ǝ҂Ƃ������t�ٌ͕�m�A�����Ɠ������A�����A���e�Ŋ��҂̐��i���������\�͂������˂Ȃ炸�A�o���ɂ�莩�R�ɂ��̂悤�Ȕ\�͂������̂ł���B���̎����̎��Ȉ���a�C�̐����A���҂̐��i�ɑ��������Ή����Ƃ�A���������Ă���A�i�ׂ��N������邱�Ƃ͂Ȃ������ł��낤�B��t�����҂̒N�ɂ������悤�ȑΉ������邱�Ƃ́A�ꌩ���������ɂ݂��邪�A���͈��Ղȕ��@�ł���A�����������I�Ɍ���ƁA�s���ł�������A�댯�ł������肷��B
�i15�j�R���n�ى��֎x�������P�T�N�R���P�V�������w�����x�P�W�R�V���V�W�� �i���������܃A���[���ʼn��{�������Ȃǂ��N���������u�ɂ͓���ł���Ǝ咣�E�F�e�j
�u�����v���a�Q�Q�N���܂�̎�w�����a�U�Q�N�A�����P���������Đ�ɓ�����̂Ŕ퍐���Ȉ�@��f���A��������������A���Â��n�܂����B���Â̍ہA���҂͎��������܃l�I�A���[���u���b�N��E���Ȃɕ���|���ɓh�z�����ȗp�Z�����g�ʼn�������A�Ƃ������������[�u���A���̌�A�����A���ǎ��Â����B���̌�A���{�̒ɂ݂��Ƃꂸ�A���@�ō����������_�o�j���[���p�V�[�ineuropathy�����_�o��Q�j�A�������{�������Ɛf�f���ꂽ�B���҂́A�����u�ɂ͓���̂��̂ŁA�͒ቺ�Ȃǂ̌��ǂ��������A�Ǝ咣���đ��Q���������i�ג�N�B
�u�����v�����܃A���[�����R�o����Ɗ댯�ł��邩��A���̎g�p�ɓ������Ă͎����̌`��Ȃǂ��[���`�F�b�N���邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A�퍐���Ȉ�t������ӂ����A�Ƃ��ĂQ�T�Q�T���~�]�̑��Q���m��B
�u�����v���������܃A���[���͈���_�ł���A�����������Ĕ�������̂Ɏg�p����Ă��邪�A��f���R�o����ƁA���̓Ő��ɂ���u�ɁA�[���Ȃǂ�������B�{�����ɂ��ƁA���̊댯���͏��a�S�O�N�ォ�玕�ȑ�w�̋��ȏ��Ŏw�E����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�ŋ߂̃C���^�[�l�b�g��ł������܂Ƃ��Ă̈���_�i�A���[���j�g�p�̊댯�����F�X�Ǝw�E����Ă���B
�i16�j���É��n�ٕ����P�T�N�V���P�P�������w�����x�P�W�T�Q���P�O�S�Łi�C���v�����g��p��̉��O�Ȃǂ��Ⴢ��咣�E�F�e�j
�u�����v�����V�N�V���A�����͔퍐���Ȉォ�牺�{���E�U�A�V�ԂɃC���v�����g�A����p�������A�C���v�����g�ɓ��h������̂œ��N�X���A�ĐA����p�����B���̌�A���O������Ԋ�������̂ŁA���̕a�@�Őf�@�����Ƃ���A�C���v�����g�Ɛ_�o���Ђ����Ă��邱�Ƃ�����A�Ö@�A���[�U�[���Â������������Ȃ��̂Ŏ��Ô�A�Ԏӗ��ȂǂU�X�S�T���~�]�̑��Q���������i�ג�N�B
�u�����v�ĐA����p�̍ہA�������ɂ݂�i�����Ƃ��͕s�\���Ȗ������ʂ̂������A�؍킪���{�Nj߂��ɋy���Ƃ̒��\�ł��邩��X���B�e�Ŋm�F���A���{�Ǔ����������Ȃ��ʒu�ɃC���v�����g��}�����ׂ����Ӌ`�����������̂ɂ���Ɉᔽ���A���{�Ǖt�߂܂Ő؍킵�A�����̒ɂ݂̑i���ɑ��Ă�X���B�e�ɂ��m�F��Ƃ��s�����ƂȂ����R�ƒlj��������{���Ď�p�s���A���{�ǂɐڋ߂����ʒu�ɃC���v�����g��ł�����ʼn��{�Ǔ��̈����ɂ�鉺�����_�o��Ⴢ��������A�m�o��Ⴢ��o�����������̂ƔF�߂���E�E�E�퍐���Ȉ�̉ߎ����m�肵�A�U�V�S���~�]�̑��Q����������F�e�����B
�u�����v�ߗ�������X���ɂ���C���v�����g�����̈�ł���B
�b�ڎ��ɂ��ǂ�B�b�g�b�v�y�|�W�ɂ��ǂ�B�b
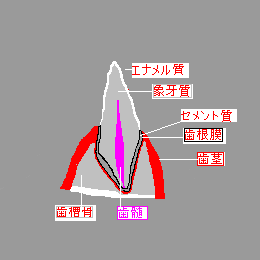 �@
�@
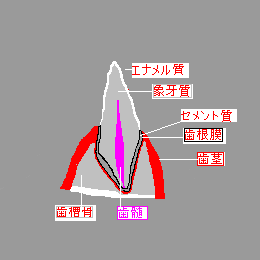 �@
�@
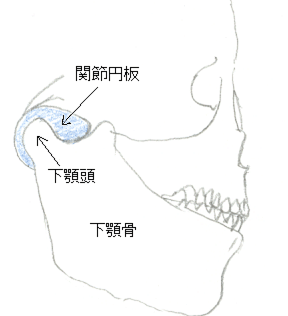 �@ �@ �@
�@ �@ �@