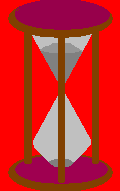
新作詩15 |
206「砂時計・その2」207「決心」208「昨日の出来事」209「峠を二つ越え」210「見知らぬ女性」211「待つ」212「落としもの または 忘れもの」213「北野天満宮」214「参ったなあ」215「讃辞」216「大雪」217「帰省」218「川釣り」219「深泥が池」220「嫌いなこと」221「介護」222「ぶらぶら」223「賢人」224「昼夜」
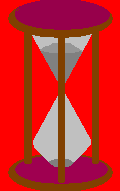
206「砂時計その2」
紅茶を入れたり
卵を茹でるとき
砂時計を使う
三分計の砂時計の砂は
三分で 上から下に全部 落ちる
五分計の砂時計の砂は
五分で 上から下に全部 落ちる
一時間は60分
一日は1440分
一年は52万5600分
七五年は3942万分
寿命七五年の男の3942万分砂時計は
生まれたとき
どさり
何処かに立てられる
上の砂は段々 下に落ち
段々 人生が過ぎて行き
七五年で全部
砂が上から下に落ちたとき
男の死が待っている
僕の砂時計の砂は
殆ど下に落ち もう
余り上に残っていない
どのくらい残っているか
見たいが
見ない方がよい
見えるようで見えない時計
感じられるだけの時計
砂時計
平成13年3月1日作。砂時計という詩を作るのは二回目である。前作は旧作詩15「砂時計」・目次にもどる。
2月28日
雨が降ると
「二月終わりの雨」
という詩を書き
3月1日
また雨が降ると
「三月はじめの雨」
という詩を書こうとする僕に
”詩って そんなにできるものなの?”
と 妻はわらう
2時50分
魚が釣れ
3時10分
魚がかかると
それを釣るのが釣り師
一日中
いや 何日も釣れないことを
釣り師は知っているからだ
何日も 何ヶ月も 何年も
詩が書けないことがあった
それに
僕には余り 時間は残っていない
だから毎日でも
詩を書く
これからも
日常の些事とか
季節 天気の変化とか
鳥 雲 風 花 人 芸術とか
に 感応して
びっしり
詩を書いて行こう
3月2日
雨
のち曇り
のち晴れ
平成13年3月2日作。目次にもどる。
昨日
僕は時計を落とし
女性ニュースキャスターが
亡くなった
時計は正月 9割引で買った
ダイヤが12もついた派手な時計
ベルトも緩んでいたので
落としても
後悔はない
女性キャスターは40歳
前から僕の贔屓の人だった
去年 10月下旬
”しばらく休みます”
と 淡々とテレビで
休職宣言をしたが
3月1日早朝
がんで亡くなった
しばらく 貴女の写真を
デスクトップに貼り付け
貴女を思い出し
死について考えて行こう
かって仕事上
老人の葬式に行った
男子高校生が一人
泣き伏しているのを見て
”良い人だったのだろう”
と思った
今日は三月三日
翁と姥のひな祭り
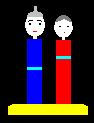
平成13年3月3日作。目次にもどる。
209「峠を二つ越え」
最初の峠を越すと
田んぼと畠が続き
途中に肥料工場があった
僕たちは 鼻をつまみ
はあはあ 言いながら
工場の前の道を走った
次の峠を越すと
ずうっと向こうに
真っ青な海が見えた
田んぼの間の
つづら折りをおりきると
丸い石ころの浜だった
どんなに波が高くても
海は濁らなかった
岩に置き竿して 僕たちは泳ぐ
竿が沖に走るので 慌てて戻ると
大きいギザメが釣れている
午後 高い処から見ると
赤い魚が群れて 岩棚で昼寝し
つられて昼寝する僕たちの肌に
しわしわと 風が渡り
眠りから覚める頃
海は満ち来る
帰りは何時も
腹ペコだった
野イチゴをとって食べたり
一房五円でブドウを買って食べた
次の夏も その次の夏も
僕たちは
峠を二つ越え
海に通った
平成13年3月3日作。僕がその頃住んでいた町は今の韓国プサン(釜山)市で、海はプサン市郊外の大浦湾。新作詩2にも23「大浦湾」がある。僕の思い出の海だ。目次にもどる。
210「見知らぬ女性」
大阪梅田
阪神百貨店の九階にある
大きなうどん屋「美々卯」
昨日の昼
満席なので
入り口で順番を待っていると
一人だけの客が目立つので
”一人の客が多いね”
と右横の妻に言うと
左横の見知らぬ女性が
”私も一人よ”
と言った
驚いて顔を見ると
五〇歳くらいの
女性だった
さらにその人は
”主人が三ヶ月前に亡くなったの”
と問わず語りに話した
”淋しいですね”
と言うと
”とても淋しいわ”
と言った
間もなく店員に案内され
僕たちは大きい相席のテーブルについた
隣の椅子には先ほどの女性が坐った
僕は鴨なんば 妻は天麩羅ソバ
隣の女性は しっぽくうどん
先ほどは不意に話しかけてきのに
隣の女性は黙ってうどんを食べている
”夫とこの「美々卯」に何度か
来たに違いない
思い出して泣きたい気持ちなんだな
と勝手に想像する
近親者を失ったときの対応は人様々だ
宗教者は 早く悲しみから離脱するように勧め
僕も今までそう人に忠告してきた
しかし 何年も何年も
悲しみを背負って生きている人を
幾人も知っている
下りのエスカレーターに乗りながら
彼女はどうかな と思った
平成13年月4日作。目次にもどる。
待たなくても
必ずやって来る 死
待てども なかなか訪れない
若い頃の夢の続き
父母は癌 姉も癌だった
覚悟 というのか
待つ というのか
step by step
一月も前にデートの約束をし
暦を必死にたぐり寄せ
節分の一番寒い日
停留所の前で待ったことがあった
はやる思いで 30分も前に来ていたのに
”いや 今来たの・・・”
と 見栄を張って
凍えたこぶしを ポケットに入れた
平成13年3月4日作。目次にもどる。
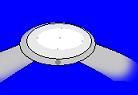
近頃 落とした
または 忘れたもの
財布
腕時計
鰤の切り身二つ
財布
すぐバス会社に電話し 無事回収
腕時計
駄目
鰤の切り身二つ
慌てて引き返した銀行の待合室で 無事回収
古い俳優の名前を忘れると
アイウエオ カキクケコ・・・
と 口ずさみながら
思い出そうとするが
大抵は駄目
最近はYahooで
日本映画
と検索すると
大抵は見付かる
気になることは二つ
一つは
忘れたことを忘れること
もう一つは
もっと もっと 大事なものを落とすこと
平成13年3月6日作。目次にもどる。
213「北野天満宮」
学問の神様
菅原道真を祭る
北野天満宮
参拝客であふれている
時まさに受験シーズン
梅も満開
絵馬堂の前では
息子の合格を願う
中年女性が絵馬に
せっせと 祈願文を書いている
吹きさらしの絵馬堂には
何万もの絵馬がゆれている
”○○大学合格祈願
××高校に合格させて下さい”
というのが多いが
”一生 幸せに”
という贅沢なものもある
ざん言で九州 太宰府に流され
901年 昌泰四年
九州 太宰府権師に左遷された
右大臣道真は
903年 延喜三年
かの地で憤死した
その後 京では天変地異が続き
慰霊のため 道真は
正一位太政大臣を贈られた
正一位で慰められたわけではないが
天変地異は間もなく収まった
おそらく道真は祟るのに疲れたのか
飽きたのであろうが
その道真は今でも若者の
面倒を見てくれるだろうか
今更 受験でもないので
五円のお賽銭をあげて
早々に退散
平成13年3月7日作。目次にもどる。
他人の手紙の方が
僕の詩より 素敵なことがある
随分前に亡くなった僕の母の
最後の手紙の書き出しの言葉
「暑かった夏も過ぎ
夢のようです」
過ぎてしまえば 夏も人生も同じ
妻の姉からの最近の手紙
「愛犬風子と顔を見合わせながら
散歩しています」
風の中を歩く風子はもう老犬だ
今日 僕のホームページの掲示板に書き込まれた
F君の言葉
「朝起きると雪で 六年前 大学一年生で目覚めた
不安な雪の朝を思い出しました
まるであれからの六年間のように
その雪はすぐ消えました」
彼は僕の元ゼミ長だが 詩人でもあったのだ
誰でも時に 詩人になる
そして僕の詩より素敵な詩を書いて
僕を悲しませる
もっと非道いことがあった
大分前のこと
匿名の男性読者が僕のホームページの掲示板に
僕の詩の感想を書き
何行かの自作詩を添えていた
それを読んだ僕は 呆然となった
その詩は僕の詩の何倍も何倍も
良かったからだ
しかし 僕はまだ懲りずにいる
そういうこともあるんだ!
平成13年3月7日作。母の手紙は旧作詩の12「夢のよう」、新作詩6の「夢のよう・その2」で詩にしており、妻の姉の手紙も新作詩14の198「手紙」で詩にしている。目次にもどる。
215「讃辞」
僕は サムホール版の小さいキャンバスに
油絵を描くことがある
将来は個展を開きたい
素人画家の個展やグルール展に現れ
もと美大教授とか ○○会員
と自称し お菓子を食べ散らし
時には 何かを売りつけて帰る
凄い爺さんがいる
素人画家は讃辞に弱い
自分の絵の前に立って
爺さんが
”うーん いいな”
なんて言うと つい
爺さんから版画の一枚も買ってしまうのだ
平成13年3月8日作。貼り付けているのは僕の「木彫りのカラスと南瓜」の絵・目次にもどる。

もう 三月中旬というのに
にわかの 大雪
東京から長岡に転勤した
最初の冬
一週間も雪が降り続いた
来る日も 来る日も
雪と同じ色の空から
止めどもなく 落ちてくる
雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪
雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪
雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪
雪のほか 何も見えない世界
眩暈がした
ある日
何処からか飛んで来た雀が
雪に飲み込まれるのを見た
真綿のような ふわふわの雪から
雀は出て来なかった
地表で餌をあさる 鳥たちには
地表を隈無く覆う大雪は 大敵だ
雪が続いた日
公民館前の広場で
鳩が沢山 死んでいるのを見た
京都の雪は 一夜限り
もう 初春の日がさしている
平成13年3月9日作。目次にもどる。
217「帰省」
学生時代
夏休みになると
いつも 帰省した
朝早く 暗い頃
駅に着く
30分くらい歩いて
家に帰る
玄関をノックすると
母が いそいそ 戸を開けてくれた
その日から 僕は
海に泳ぎに行くか
海に臍まで入ってキスを釣るか
川で鮒かハヤを釣るか
田んぼの畔を網を持って走り
小鮒をとるか
の毎日だった
とった小鮒は母が作った
小さい池に全部 放った
小鮒は母の大切な金魚のしっぽをかじるので
僕がいなくなると
母は小鮒を全部 川に放した
翌年も
僕は小鮒を池に放ち
母は小鮒を川に放した
社会人になり
結婚しても
時々 帰省していた
父は無口で
僕と2人で
黙々とビールを飲んでいた
母は
”あれでお父さんは喜んでいるのよ”
と かげで言っていた
真の帰省は父母健在の間だけだろう
その父母はとっくに亡くなった
墓参帰省
きょういだいに会える楽しみはあるが
真の帰省の
あの不思議な 胸のざわめきは無い
平成13年3月10日作。僕の郷里は山口県下松市で瀬戸内海沿いにある小さい町である。目次にもどる。
218「川釣り」
僕の郷里には
近くに 川が二つある
一つは荒神川
澄んだ水を泳ぐ魚が
天然遡上の鮎とは
長い間 判らなかった
鉛錘に白いペンキを塗って
引っかけで捕っていたが
鮎だと判って 鑑札が要るようになった
一つは末武川
河口にチンタが回遊する夏
びっくりする程 チンタが釣れた
本虫 という餌で釣るが
釣れ過ぎて 餌が無くなると
一度捨てた本虫の固い頭を探して
釣ったものだ
雨の日には大きいチヌがかかり
よく 糸を切られた
中流ではハヤが釣れた
一度 母と叔母がバケツを持って
ハヤ釣りの僕のお供をしたことがある
僕は釣れたハヤをバケツに入れ
母は叔母とおしゃべりをしながら
時々 息子の顔を見ていた
僕は母に随分 心配をかけたが
その時の母の嬉しそうな顔は
何よりの免罪符だ
末武川の河口に火力発電所が出来てから
奇形のハゼが釣れるようになった
その時 僕の郷里での川釣りは
終わった
平成13年3月11日作。郷里は山口県下松市。チンタとはチヌの子のこと。本虫はゴカイを何倍か大きくした釣り餌。頭は固いので最初はちぎって捨てるが、餌が無くなると探したものだ。目次にもどる。
|
地底に七メートルもの 粘土の堆積があるという 京洛北の深泥が池
昔は貴族の遊猟地だったとかで 池に飛来するカモ類も多く 水性植物 食虫植物の保護区である
数年前の冬 始めて此処に来たときは カルガモ マガモ はいうに及ばず ハシヒロガモ オナガカモ コガモ ヨシガモ それに 僕の大好きな小柄な ヒドリガモ が群れ 葦の蔭から アオサギが首を出し 遠くで カイツブリの鳴き声も聞こえた
ところが カモたちは余りに人なつっこく 僕の足下に寄って来るので 誰か餌をやっているな と思った
という看板はあったが 至近距離で写真が撮れる という魅力は大きい 今日 久しぶりに来てみると 鴨は一羽もいなかった 皆 北に帰ったのかしら それにしても 留鳥化した カルガモやマガモもいない
池沿いの道には 一時間数便のバスが走り 池の横には マンションが建ち 池の前には 戸建て分譲の旗がはためいている
じわじわ じわじわ 人間の匂いが池に迫り 鳥たちは何処に去ってしまった 平成13年3月12日作。目次にもどる。 |
判事時代
注意していたことが三つあった
一つは判決書の誤記
誤記とは形式的なものだが
形式的なミスは判決の内容である
事実認定とか 法律判断とか
内容的ミスを連想させる
実際 誤記だらけの判決書は
内容も怪しいのが多い
誤記がないように頑張っていたが
矢張り 時々 誤記があり
自分の限界を感じていた
もう一つは 難しい表現
民法自体 難しい言葉を使う
”出捐 囲繞 瑕疵 代位 耗弱”
このような言葉は世間では使わない
こういう言葉が飛び交う判決書は
難しいものにならざるをえない
できるだけ 難しい言葉を使わず
表現もやさしいものにしても
限界がある
余り平易にすると
判決書が
小説とか ドキュメンタリー風になってしまう
もう一つは 威張ること
威張る判事を反面教師として
自らが判事になったのだから
自分が威張るわけにはいかない
しかし 長年 判事をしていると
段々 判事の顔になってしまう
判事の顔は真面目であり
真面目な顔は恐い顔である
だから 自分は威張っていなくても
威張ってるな
と思われたかも知れない
威張らない ということは
意外に難しいことなんだ
平成13年3月14日作。目次にもどる。
221「介護」
88歳の父に
息子が歳を聞くと
44歳
と答える
とっくに死んだ弟を探して
夜中 徘徊する父を見守る息子
弟を求めて玄関に行こうとする父に
息子は
今日は泊まりだから帰らないよ
と 言う
死んだ
と言っても納得しない父も
泊まり
なら納得する
ああ 泊まりなら 明日は帰ってくるのだ
平成13年3月14日作。目次にもどる。
222「ぶらぶら」
僕は今
殆ど ぶらぶら 暮らしている
生来怠け者の僕も
44、5年 背広を着て
働いて来た
今は もう
大手を振ってぶらぶらして良い筈だ
屋根の上のバイオリン弾きでも
真面目な牛乳売りの主人公は
金持ちなら ぶらぶら 暮らしたい
と うたい
転職を繰り返した詩人カーヴァーも
僕の不変の目標は ぶらぶら 暮らすこと
と うたう
まさに 我が意を得たり
だが ジャンバー着て
街でぶらぶらしていて
同業のバッジが歩いて来ると
ひょい と顔をそらすか
路地に逃げ込んでしまうのは
一体 何故なんだろう
ぶらぶら暮らすことは
実は大変 難しいことなんだ
平成13年3月16日作。ぶらぶらして暮らしたい、というカーバーの詩はレイモンド・カーヴァー「水と水が出会うとき/ウルトラマリン」村上春樹訳・中央公論社350頁にある。目次にもどる。
高名の賢人が
数日 寓居に足をとめた
礼を尽くして歓待され
賢人も喜んで
それを受けた
遂に 賢人が去る日が来た
主人は玄関で
賢人に辞を低くして 乞うた
”先生 何とぞ 御教示下さい
人生で最も大事なものは
一体 何でしょうか”
賢人は直ちに部屋に帰られ
暫時して 封書を持ってお出でになり
”あとでこれを見るように”
と 主人に差し出した
賢人の姿が街道の向こうに消えたとき
主人は封書を開けた
中には 紙が二枚 入っていた
一枚は 何も書かれていない
真っ白な紙だった
もう一枚には
”人生に大事なものは
人それぞれ
時それぞれ
処それぞれ
によって異なるものである”
と 書かれていた
賢人も悩まれていること
また
大事は自ら決すべきであること
それが教えだと判った
遠くに消えた賢人の方角に
主人は頭を下げた
平成13年3月16日作。目次にもどる。
224「昼夜」
旧約聖書創世記には
”闇が深淵の表にあった
神が
光あれ
と言われると
光があった
神は
光を昼と呼び
闇を夜と呼ばれた”
とあるから
世界は闇から始まったことになる
また 人の多くは 夜の闇の中で生まれる
原始の頃 闇の出産の方が安全だったからだ
出産だけではなく 繁殖も闇がふさわしい
”night and day”
は繁殖の歌である
ナチスから逃げた詩人ブレヒトは
”夜は12時間 それから朝が来る”
と 夜の長さを歌う
逃避には 闇が必要だった
療養や安静にも 闇がふさわしい
病人や老いた人は 夜の人だ
しかし
働き盛りの健康青年には
”昼夜兼行”
の精神が必要
だから
働き者のユダヤ人は
”sun rises, sun sets”
と歌う
日本と韓国は
日本では”日韓”と言い
韓国では
”韓日”と言う
”昼夜”が正しいか
”夜昼”が正しいか
これも似たような
政治問題なのだ
平成13年3月17日作。創世記は日本聖書教会・新共同訳「聖書」によった。ブレヒトの詩は長谷川四郎訳「ブレヒト詩集」みすず書房78頁以下「モルダウ河の歌」にある。”sun rises, sun sets”はミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」の結婚式の場で歌われる歌。旧約聖書の「コヘレトの言葉(伝道の書)1ー5にも「日は昇り、日は沈み」とある。イラストは1954年当時のブレヒト。目次にもどる。