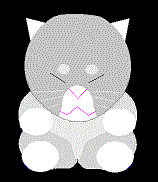
349「藤棚」 350「縫いぐるみ」 351「静」 352「ボス」 353「教訓」 354「海」 355「きれぎれの一生」 356「花言葉」 357 「介護犬ドン」 358「電気剃刀」 359「僕の夕食」 360「鱧しゃぶ」 361「涼」 362「平安騎馬隊」 363「紙切り虫」 364「懐かしきもの」 365「戻る」366「元禄の小鮒」
349「藤棚」
遠くから見ると
藤棚は
優雅
に見える
かっちり 組まれた棚に
みどり が茂り
うすむらさき の花が
重たげに 垂れ
床しい 匂いが ただよい
二つ 置かれたベンチでは
乳母車押した 若い母親が
葉陰に憩う
という風情だが
近寄ると 違う
藤棚の下
風は 澱み
匂いに ひかれた
虻や蜂が
恐ろしげな 熊蜂までもが
ぶんぶん 飛び回り
棚からは 花ばかりか
毛虫 青虫までもが ぶら下がり
豆の花そっくりの 花は
放射線状に てんで ばらばら
あっち こっち向きに 咲き
ベンチには
虫の糞まで落ちている
遠くから見ると
優雅
藤棚に怨みはないが
遠目だけの
優雅
平成14年5月3日作。本ホームページ氷室町雑詠・その一の13に俳句「藤棚」も掲載。細見綾子にも「藤はさかり或る遠さより近よらず」という句がある。目次にもどる。
生きているのか
死んでるのか
頭を ひと振りするだけで
生死の世界を 行き来する
縫いぐるみ
死んでいる とも 思えるし
生きてる とも 思える
僕の家には
いぬ の 縫いぐるみが 三匹いる
チビは チビだが 重い
一日中 眠っている
チャチャは ひょろひょろ
手足が長く 気だてがよい
ドグは 哲学者
伏し目がちに もの思いにふける
三匹 横に並べると
ひそひそ 彼らの声で しゃべる
bow-bow
いま 彼らは ソファーの背もたれに
跨って 僕を
笑っている
平成14年5月8日作。目次にもどる。
雨後の鴨川 水かさが増し
堰の下に 白い渦が巻く
魚は せわしく 泳いで 流れに逆らい
岸辺で蒼鷺が一羽 じーっと 魚を狙う
「死」は 生者にとっての「死」であり
「死者」には 「死」は無い
だから 「死」は騒々しく
忘れられて はじめて 静かになる
平成14年5月8日作。目次にもどる。
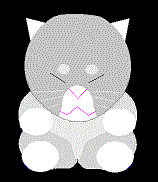
猫の名は ボス
何時も 目を閉じ
腕を 組んでいる
人が寄っても
犬が 吠えても
ボスは 目を閉じ
腕を 組んでいる
そのわけは 簡単
怒っているのだ
自分が 猫であること
しかも 縫いぐるみであること
を 怒っている
それだけではない
自分が神のように 不死なのか
人のように 死ぬのか
死ぬなら いつ死ぬのか
いくら考えても 判らぬので
怒っているのだ
猫の名は ボス
何時も 目を閉じ
腕を 組み
考え 悩み 怒っている
平成14年5月20日作。目次にもどる。
僕が下宿していた頃
小母さんは 50前の
色っぽい 未亡人だった
それが 今は 年取って
90 をこえ
体は 昔の半分くらいで
独り暮らし
久しぶりに見舞いに行く
耳が遠く筆談するが
頭もボケはじめている
僕の妻を 僕の母だと思い
年の割に 姿勢が良い
と 10回以上も 繰り返す
僕が 僕だとも うっすらしか
判らないようだ
筆談するにつれ
だんだん 悲しくなる
また 来ます
と 紙に書いて 帰る
小母さんは 玄関で
ずうっと 見送る
今日の教訓
90までは 生きないぞ
平成14年5月20日作。目次にもどる。
海辺に育った僕には夏の海は とてつもなく 広く 大きく
左右に うすものの翼垂れた水平線は いつも少し霞んで
近眼のような ぼーっとした目つきで 僕を誘惑した だが
知恵の実を食べた今は違う 海は墜ちた月になってしまった
無数の成分と あの休みない動きで 海は
生命を産んだらしい しかし 子供達は母親に恩返し
するどころか 母の脛をも喰い尽くそうとしている
しかし この母は 何故か それを許すのだ
平成14年6月6日作。目次にもどる。
右に向けた顔を
左にゆっくり向ける30秒間
昨日 一日のことを
ざっと 思い出せるが
自分の一生全部は 一年 かかっても
思い出せない
しかし うたた寝の間とか
崖から落ちる間に
一生を思い出した
という話がある
思い出したのは 恐らく
きれぎれの一生だろう
死に際にも 一生を思い出すという
死に際とは 崖から落ちるのに近いから
死に際に思い出すのも
きれぎれの一生だろう
誰もが 崖からは落ちないが
誰もが 死に際は迎える
きれぎれの一生の映像は
自分が作るのだが
きれぎれでなくても 詰まらぬ一生
きれぎれなら 一層詰まらぬだろう
きれぎれでなく
びっしり 詰まった美しい風景とか
懐かしい人の顔のクローズアップとか
そんな映像であって欲しい
平成14年6月10日作。 中国の故事に「邯鄲の夢」、または「黄粱一炊の夢」というのがある。廬生という書生が出世を望んで官吏登用試験を受けるため都へ上る途中、邯鄲という里の茶店で道士の枕を借りて寝ている間に自分の一生の栄枯盛衰の夢を見るが、寝たのは黄粱が炊けるほんの短い時間であった、という話である(中村草田男・蕪村集・講談社文庫11頁参照)。目次にもどる。
花言葉は 国により
時代により 違う
一六世紀 ヨーロッパでは
チューリップは
間抜け 阿呆を 指していたが 今では
永遠の愛とか 正直を指す
薔薇の 花言葉は
愛 嫉妬 だという
やはり 愛と嫉妬は一緒なのか
いつの頃からか 僕は
赤い薔薇を 別れの花
と決めている
悲しい別れの場面には 淋しい白い花ではなく
明るい赤い花を 登場させたいからだ
姉が不治の病に 倒れたとき
僕は 見舞に行かず
赤い薔薇の花を 贈った
姉からも 涙で しわしわになった
別れの手紙が来た
つい忘れて 赤い薔薇を 妻に贈り
睨まれたことがある
さあ いつ 僕は 赤い薔薇を
受け取るだろう
平成14年6月20日作。新潮美術文庫7ボスの「阿呆の治療」にチューリップが描かれている。目次にもどる。
体のでっかい 介護犬ドン
介護に行って 転んで 脚を折り
介護犬が 介護を受け
物笑いの 種になってしまった
以来 ドンは落ち込み
臆病になり 内気になった
ネコや 警察に追われ
逃げ続けている ネズミの忠太は
そんなドンを頼った
毎晩 ドンの脚の間とか
脇腹にかくれて 寝た
大きいドンの体は 忠太に
安らぎを与え 忠太は久しぶりに
安眠した
次に 老犬ちゃちゃが来た
暖かいドンの体を 枕にすると
冷えた体が 暖まり
ちゃちゃは ふ−っと
ため息をついた
学者犬 ドグも来た
読書で痛んだ頭も 眼も
いつの間にか 治った
体の小さい コッカスパニエルの
プチも来た
ドンの蔭にいると 人に
踏まれることはなかった
次第にドンは元気になった
ドンは 立ち上がった
僕は まだ役に立つんだ
頑張るぞ
平成14年6月23日作・目次にもどる。
午前の今頃
北は北海道から
南は沖縄まで
何台の電気剃刀が
回っているだろうか
低いモーター音とともに
何らかの部品が回転 または震動し
男たちの髭が刈られる
運の良い髭は 顎の下などで
生き延びるが
たいていは はかなく
命を 断たれる
髭を剃るのは 律儀な 働き者だけではない
愛人の部屋で 物憂く
電気剃刀を 回す遊び人もいる
妻の葬儀のために 髭を剃る男もいるし
死んだ父の白い髭を剃る 孝行息子もいる
髭や 皮膚や 塵埃と共に
無為 無心も 倦怠 悔恨も
裏切りも 哀切も
叙情も 歴史も
電気剃刀が 刈って
吸い取り
捨てる
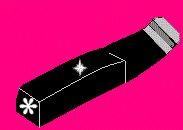
平成14年6月23日作・目次にもどる。
明治屋で
赤ワインの クオター瓶を買い
無添加の のし烏賊を買う
のし烏賊は 長崎壱岐の産
高島屋で
明石の蛸の脚を買い
地下鉄で帰る
地下鉄の出口近く
シベリヤ抑留死没者
鎮魂碑がある
そのうしろに 大きな泰山木が
花をつけている
大人の掌を広げても 包みきれないような
大きい 白い花だ
大きいから 花びらは ゆっくり落ちる と思い
落ちていた しゃもじのような 花びらを拾い
空に 投げてみた
花びらは 驚くほどの早さで
ひらひら 回りながら 地面に落ちた
自然の動作は すべて
驚くほど 合理的だ
夕方
蛸は さっと茹でて
刺身と 酢蛸で食べ
のし烏賊は 少し あぶって
壱岐の友達を思い出しながら
くちゃくちゃ 食べ
ワインと ビールを飲み
田中長の 西瓜の味醂漬で
茶漬けを
さらさら 食べた
平成14年6月27日作・目次にもどる。
京都 錦市場で
しゃぶしゃぶ用の
鱧(はも)を 買う
首切られた鱧を 選ぶ
どれが 新しいの
と 聞くと
魚屋の大将
皆 生きてまっせ
と 篭を揺する
数匹の 首無し鱧が
皆 身を揺する
一番 身を揺すったのを
指名する
大将 さっと 骨切りする
鱧は やっと 静かになる
鱧しゃぶを 食べる
祟りか 舌を噛んだ
ああ
篭の中で 身を揺った鱧たちよ
首切られてるのに 何故
わたしが 一番よ
なんて 身を揺するんだ
平成14年6月29日・目次にもどる。
深夜 救急車が近くで止まった
熱帯夜
堪りかねて クーラーのスイッチを入れると
死神の手のような冷気が 頬を撫でる
若い頃 願わなくても 明日は
どんどん やって来た
今は 熱帯夜のさなかの 涼気のように
いくら探しても 明日は見付からない
園芸店の店先で
風鈴付きの「忍」をつい落としてしまった
仕方なしに買って帰って 窓辺に下げたら
風鈴が チリン と鳴った
平成14年7月11日作。「忍」とはシダ類ウラボシ科の落葉多年草。水苔で包んで軒に下げる。風鈴を付けることもある。目次にもどる。
宝ケ池野鳥公園の片隅
平安騎馬隊厩舎がある
数頭の栗毛にまじって
葦毛の馬が二頭
オーストラリア産だが 父母不詳
この葦毛二頭が連れだって
公園の緩やかな坂道を
訓練歩行
道わきの草むらでは
日本のキリギリスが 鳴いている
カンガールの国では
聞いたことがないだろう
厩舎の札には
年齢14歳 と書いたある
もう少し 歳とっているかも
あの国の馬は 血統も 年齢も
曖昧なんです
と 隊員は言う
年齢も 父母も不詳で
この国に買われてきた葦毛の馬よ
野鳥の声を聞きながら
騎馬隊生活は優雅だが
広々したあの国の草原を
ふるさとを
ちちははを
思い出し
黒いまなこ 曇らすことはないのか
平成14年7月12日作。目次にもどる。
力を入れて 掴むのだが
掴んだ指を
紙切り虫は 解いて仕舞う
もう一度
力を入れて 掴むのだが
紙切り虫が
体をゆするか
胸のあたりで きりきり鳴くと
少年の僕は 負けて
指の力を ゆるめて仕舞うのだ
固い甲皮を開くと
柔らかい 羽根が出て
紙切り虫は
虫の世界に 飛んで行く
あちら 虫の世界
こちら 人の世界
そのあいだに
往還の 途はない
平成14年7月21日作。北原白秋にも「紙きり虫」という詩がある(白州叙情詩抄・岩波文庫101頁)。目次にもどる。
懐かしきもの
それは
風邪のとき 飲まされた
茶色い 甘い みず薬
いくらでも しゃぶれる 肉桂紙
赤や青の肉桂水 入った
くびれた細いビン
いつまでも 捨てられなかった
くびれた細いビン
なかなか音 出ない
竪琴がたの 海ほおづき
もんで もんで作って
ぎゅ ぎゅ 鳴らした 真っ赤な ほおづき
一寸 値が張る 小豆が甘い
小倉かきごおり
川岸の店先で はためく
四角い「氷」の小旗
乾パンの中 ほんの少しだけ 入ってる
金平糖
お座敷でつく 紙風船
びー玉入れた ブリキ缶
メンコを入れた もっと大きなブリキ缶
金のペン先
拾った誰かの指輪
誰かの金歯入れた 宝物箱
富山の売薬入れた 大きな箱
菓子屋がかつぐ 菓子見本が入った おっきい箱
夜店が燃やす アセチレンガスの匂い
玄関に近づく 父の靴音
母の 乳の匂い
平成14年7月22日作。目次にもどる。
関西では 格好付ける者を かっこうし という
シェーン カムバック 少年は叫んだが
かっこうしのシェーンは戻らなかった
その後 彼がどうなったか 判らない
夢のなか 戻れる家が あるときと
ないときがある ないときの恐ろしさ
月夜のなかでも ぽくぽく
歩いて戻れる家が 欲しい
平成14年8月9日作・目次にもどる。
元禄5年12月上旬
洒堂 許六 芭蕉 嵐蘭の四人は
「洗足に」という歌仙連句を 巻いたが
その第5句で 許六は
「月の色氷ものこる小鮒売」
と 詠んだ
春が近づくと 行商人は
近郊で すくい捕った小鮒を
小桶に入れ 江戸の町を
売り歩いた
「えーっ こぶな かわんかねー」
とか
「こぶな こぶな ようー」
なんて おらびながら
几帳面なお内儀さんは
寒鮒名残りの小鮒を
炭火で炙り
ごとごと煮詰め 佃煮にして
可愛い子供の 惣菜にしたり
惚れた亭主の 酒の肴にした
小鮒が全部 売れると
小鮒は全部 佃煮になる
売れ残ったら 最後の客に
「いいや まけときやしょう」
と 客の器に残った小鮒を
ほうり込んだかも知れない
ケチな行商人は
残った小鮒を持ち帰り
自分用の佃煮にしたり
明日売る小鮒に 混ぜたかも知れない
万が一 心優しい行商人だったら
残った小鮒を 何処かの川か
池に ほうり込んだかも知れない
しかし 鮒の寿命は知れている
いずれにしろ
許六が詠んだ元禄の小鮒たちが
平成14年の今 すべて死んでいることは
間違いない
元禄の江戸
小鮒売りが担ぐ 小桶の中
じゃぼんじゃぼん
揺れていた 小鮒たちよ
310年後の今
お前たちの 黒い目を想う
平成14年8月10日作・歌仙を巻く、とは36句からなる連句をつくる、ということ。許六の句は、中村俊定、萩原恭男校注・芭蕉連句集・岩波文庫207頁にある。 絵本の「ドンの前身 物語」参照・目次にもどる。