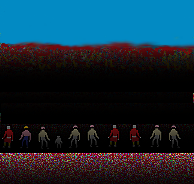新作詩41
目次
739「蘆刈・その2」740「変化」741「イカルとモズ」742「桃太郎君」743「111111」744「近況報告
・その2」745「大原行きバス」746「こころ旅」747「カタバミ」748「ミニトマト」749「説教」750「夢のボレロ」751「小さい
池」752「忍路」753「誤記誤植」754「ココ・シャネル」755「第2詩集」 756「逝ったひと」 757「ちゃんちゃらおかしい」 758「二年坂」 759 「つばめ」
739「蘆刈・その2」
大和物語第148段の蘆刈伝説
に触発されて書いたといわれる
谷崎潤一郎の小説”蘆刈”
この小説でワキ役を勤める主人公の”わたし”は
氏名不詳の50歳前後の男
シテ役を勤める語り部の男も
氏名不詳の50歳前後の男
大和物語では
あし おぎ すなわち蘆荻は
大阪難波の海岸辺に連なるが
小説”蘆刈”では
大阪と京都の中間よりやや京都寄りの
山崎辺で北から流れきた
木津川 宇治川 加茂川 桂川が合流して
淀川になる辺りの中洲に見られる

ワキ役の”わたし”は秋9月
渡し舟でこの中洲に渡り
酒を飲みながら月を観ていると
同じように月を観ていた
シテ役の男と遇い この男から
以下のような
長い思い出話を聞く
”わたしは7歳頃から
毎年9月の15夜には
父愼之助に連れられ
月下の途を何里も歩き
巨椋の池に浮かぶ
泉殿で月見の宴を開いている
臈長けた女性を覗き見に来ていました
この女性はお遊さん
という 伏見の酒屋のご寮さんでした
昔 いいとこのぼんぼん 若旦那だった父は
芝居の席で
当時未亡人だったお遊さんに
一目惚れし 求婚しましたが
男の児がいたお遊さんは
再婚できない身
仕方なく 父はお遊さんの妹
お静と結婚しました
しかし 父がお遊さんを熱愛し
お遊さんも父を愛していることを知っていた
お静は姉に義理立てし
夫婦の契りを結ばず
お遊さんとお静と父の3人は
3年ほど 人目につくほど
仲睦ましく暮らしていましが
男の児が病死し ほかの事情もあって
お遊さんは泣き泣き
金持ちの伏見の酒屋の老人と再婚し
贅沢三昧な暮らしを送るようになりました
誓いを解いたお静と父が結ばれて
私が生まれ後も
零落した父はお遊さんが忘れられず
私が7歳の頃から
毎年9月の15夜には
月見にかこつけて
巨椋の池で月見の宴を開いている
お遊さんを覗き見するようになりました
その後 父愼之助 母お静も他界しましたが
わたしは今も
9月15夜には
巨椋の池に行っているのです”
わたしは
お遊さんはもう80歳近い
年寄りであることに気づき
シテ役の男に声をかけようしたら
”風が草の葉をわたるばかりで
汀にいちめん生えていたあしも見えず
そのおとこの影もいつのまにか月の光に
溶け入るようにきえてしまった”
で この小説は終わる
大和物語の蘆刈伝説には後日談はなく
”後にはいかがなりにけん、知らず”
と 読者の想像に委ねられているのに着目して
谷崎潤一郎は
慎之助とその子の
親子二代にわたるお遊さんへの
思慕を書いた可能性がある
大和物語の貧しい蘆売り男が
もと妻のあでやかな姿を垣間見るため
物乞いしながら
京に出た可能性はないわけではなかろう
シテ役の男の父慎之助も貧しい身であったが
中秋の名月の日には必ず巨椋池に現れている
それにしても
今の人は
愼之助 お遊さん
の
禁欲的 或いは偏執的慕情に驚くも知れない
思えば 風のように消えたシテ役の男は
お遊さんと慎之助間の子かもしれないし
或いは慎之助その人 その亡霊だったかも知れない
中空の名月 水面に揺れる月影 中洲を囲む蘆荻
この物語に格好な書き割りである
平成23年10月30日作。谷崎潤一郎の「蘆刈」は『吉野葛・蘆刈』岩波文庫87頁以下、後日談の指摘は同書千葉俊二の解説170頁にある。
私の直感では、お遊さんの風貌のモデルは間違いなく、谷崎潤一郎が49歳の時に三度目の結婚をして、終生、生活を共にした松子夫人である。松子夫人の写真は新潮文庫『文豪ナビ・谷崎潤一郎』113頁にある。大和物語第148段は雨海博洋、岡山美樹全訳注『大和物語』(下)136頁以下で読める。巨椋の池は、かって京都伏見と宇治などにまたがってあった大きな池。目次に戻る。
740「変化」
変化のうち
最も顕著なのは
老いによる変化
老化であろう
連れ合いがボクと結婚したのは
24歳になったばかり
言動に若さが滲んでいた
中年になっても
スキー・スクール
で
習ったばかりの新しい滑走法
腰を少し落とし
足を踏み換え 踏み換え
て
パラレル・ターンを決めていた
その彼女が 今は
椅子から立ち上がり
移動する時の足の踏み換えに失敗し
よろめく始末
彼女の変化を上回るのが
年上のボクの変化だろう
それは
剃り残しの髭を抜いている
ボクを眺める彼女の目つきで判る
彼女は
生まれ変われるなら
大好きな小鳥
イカルに生まれ変わりたいという
Nami
そういえば
この頃
近くの山から
しきりに
キーコ キーコ
イカルが鳴いている
ひよっとすると
あのイカルは・・
平成23年11月4日作。目次に戻る。
741「イカルとモズ」

ある日
加茂川沿いの植物園を歩いていたら
頭の上で
”キーコ キーコ”
鳴き声がした
と
思ったら
木の梢から芝生に さっと
イカルの群れが
10羽も降りてきて
餌を漁りだした
黄色い くちばし
ずんぐりした からだ
奈良斑鳩里 法隆寺 聖徳太子
植物園でイカルを見てから
すっかり イカルが好きになった彼女
突然
”わたし 生まれ変われたら
イカルになるわ
キーコ キーコ
鳴くイカルになるわ”
と言い出した
”ボクもイカルになるかな”
と
慌てて言うと
”駄目!駄目!
あなた
モズが好きなんでしょっ!
モズになりなさい
!
けど わたし追っかけたら駄目よ
!”
と睨まれた
”ボク モズ好きなんやはね
子供の頃
モズの巣から赤ちゃん1匹失敬して
餌付けして育てたんだ
モズ 大きくなってね
家の中 飛び回っていたよ
キーキー鳴きながらね
名前呼ぶと飛んできたよ
名前はね
「キーキー」だったよ

それにね
モズの雄 きりっとしてるんや”
”大分 違うね”
”えっ・・・”
平成23年11月6日作。鳥たちのうた46の詩をここにも載せた。目次に戻る。
742「桃太郎君」
Wikipediaで桃太郎をひくと
かなり膨大な記事が出てくる
各地に色々な伝説があるらしいが
ボクは子供の頃の教育
まあ
軍国主義的教育というか
そういうものの影響だろう
桃から生まれ 爺婆に育てられ
黍団子持って
犬猿雉を連れ
鬼退治に行く
岡山吉備の国の
少年武者
桃太郎
君が好きだ
 Nami
Nami
しかし
かねて
桃太郎君に
幽かな疑問を感じていた
”あの鬼は赤い顔しているが
あれは島に漂着した外人ではなかろうか
外人でもいじめてはいけないな”
”鬼は金銀珊瑚の財宝を持っていたが
あれは周りの住民からとったのかな
随分 住民には金持ちがいたんだな”
”鬼が悪いとしても
桃太郎は宝物全部持って帰っていいのかな”
最後の疑問に関しては
桃太郎は一旦住民に財宝を返し
お礼を貰って帰った
という説もあるらしい
昔の人も同じことを考えていたんだ
源頼光が退治したという
大江山の鬼も外人説がある
巨躯で赤顔は外人を意味するらしい
”英米打ちてし止まん”
の戦争中は英米人は鬼であったから
ちょうどよかったが
今はどうかな
先日 テレビで
桃太郎の紙芝居を見た小学生の男の子
”鬼が可哀想”
と言っていた
矢
っ張りね
平成23年11月8日作。
Googleの記事によると、福沢諭吉も
自分の子供への家訓「ひゞのおしへ」で、桃太郎の行為は卑劣千万、と言っている。目次に戻る。
743「111111」
毎日 日付入りの1行日記を
ホームページ
トップページの冒頭に書いている
今日 書いていて 今日が
2011年11月11日
すなわち20111111
でああることに気付いた
千と百の桁20をとると
111111
再びこのような数字が揃うのは
100年
1世紀後の
2111年11月11日
この日は1111111
と1が一つ増えている
今日 ボクは生きているが
次の1111111には
間違いなく死んでいる
今の地球人のうち何人かは
1111111を迎えるだろうが
殆どの人
何十億人は死んでいる
その死に方は千差万別だろうが
死であることは完全に共通している
アマゾンに注文していた
アンスネスのショパン・ピアノソナタ
のCDが今日 着いた
回すと
しばらくして第2番第3楽章が
この詩を書いているボクの背中で鳴り出した
”葬送”だ
外は初冬の
しとしと雨
2011年11月11日作。目次に戻る。
744「近況報告」
その後 如何ですか
お元気でしょうね
突然ですが
ボクが芭蕉を好きになったのは
彼の若い頃の句
”京は9万9千くんじゅの花見かな”
を読んでからです
芭蕉は若い頃
伊賀上野の侍大将藤堂良清の嗣子
藤堂良忠の小姓をしていました
良忠
の俳号は蝉吟
芭蕉は良忠に愛され
俳句の手ほどきも受けていましたが
良忠は25歳で病没
傷心の芭蕉は
京に出たらしいです
京の人口はその頃 10万人
桜の時期にはそのうちの98000人は
花見に狂奔していましたが
落ち込んでいた芭蕉には
花見る気持ちは無かったようです
そこで作ったのが前掲の句
くんじゅ は群衆という意味
ボクも
わいわい がやがやの花見は嫌いですし
好きな主人を失った芭蕉の気持ちを思い
あの句に瞼が熱くなりました
それから芭蕉が好きになり
岩波文庫の芭蕉俳句集の句を全部
パソコンに入力したり
膳所義仲寺の芭蕉の墓に詣ったりしました
と言っても
人に知られていない
桜の名所をこっそり訪ねるとか
自宅近くの桜道を歩くことはあります
矢張り 桜は綺麗です
特に 散るときはね
今は紅葉の時期ですが
ボクは群衆の紅葉鑑賞も嫌いです
秋更けた頃 京都の人が競って
リュック背負い わいわい がやがや
紅葉狩りに行くのを見ると
紅葉狩りは植物の最後 つまり
死を見に行くようなものだ
と くさしたり ぼやいたりしますが
実はこっそり 修学院離宮西の楓の林に
落ち葉の真っ赤な絨毯を観に行きます
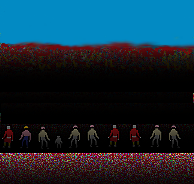
紅葉で一番感動したのは
群馬片品村と日光間の
金精道路の紅葉です
紅葉の時期
群馬から日光に向かって
車で金精道路を登ると
ヘヤピン・カーブの坂道の両側は
最初は黄 次は赤 最後は白




 Nami
Nami