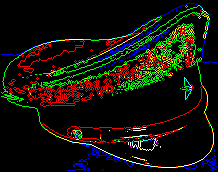新作詩45
目次
810「Piano Duo Recital」 811「自律神経」
812「2匹の鹿」 813「賢治80年」 814「サヨリ」 815「トビウオ」 816「今年のサクラ」 817「春樹の新作・その1」 818「春樹の新作・その2」 819「爺さんの店」
820「今年の5月」
821「人生の終期」 822「ボクの母」 823「もと軍人」 824「老老介護」
825「鼠と羊と」
826「カフカとカラス」827「ブルーライト・ヨコハマ」
828「わが妻よ」 829「ノルウェイの森」
830「狂った老鶯」
810「Piano Duo Recital」
弁護士ながら
ピアノの上手な男性と
若くて可愛い女性ピアニストとの
Piano Duo Recital
小雪降る日の
Piano Duo Recital
曲目前半は
三善晃の唱歌の四季
バーンスタインのウエスト・サイド・ストーリー
聴き慣れたやさしい曲
弾く人もさらりと弾く
後半はまず
スクリャービンの遺作
幻想曲イ短調
悲しげなメロディ
ふと思い出す
今日の弁護士と同期の某判事
ボクは仲良くしていたが
彼もピアノがうまく
スキーで泊まったホテルのピアノで
ベートーベンのピアノ・ソナタの何番かを
一気に弾いて
拍手喝采を浴びた
なのに
その後
彼は
九州の海で
自死した
オフェリアのように
上向いて
海に流れる
彼の夢を何度かみた
弁護士のピアノが
一休みのとき
前席の何処からか
”ヒュー”
細い笹笛のような音が聞こえた
笛の音
ボクにしか聞こえなかったかも知れない
或いは空耳か
ボクの喉が鳴ったのか
笛の音
すぐ消えた
笛の音
気がついた
判事が
友達のリサイタルを聴きに来ていたのだ
ボクは
そう感じ
そう思い
そう信じた
平成2
5年2月18日作。目次に戻る。
811「自律神経」
ボクは以前
”自律神経の主は
もちろんボクだが
自律神経は
主人のボクのことを
考えているような
考えていないような
曖昧模糊自由気まま”
とか
”もともと自律神経
生まれつきの気分屋で
怠けもするが働き過ぎもあり
その過敏過誤の結果は
全部ボクにはね返る”
などと批評非難したが
これは撤回する
最近
ボクは
肺動脈の血圧が高いことが判った
これは普通の高血圧症と同じように
治しにくい 或いは治せぬ病気だが
体重が2キロ増え
脈拍が早くなり
血圧も高くなっていることに気づいた
肺機能が落ちたり
体重が増えると
全身に酸素栄養を配るために
血圧とか脈拍を上げねばならない
ボクが病気に気づく前に
ボクの自律神経はちゃんと
この異変に気づき
対抗措置として
血圧を上げ
脈拍を上げ
色々やってくれているのだろう
どうもそうらしい
早く自律神経にお詫びせねば・・・
いや
詫びなくても
彼はボク
ボクは彼
ちゃんとやってくれるだろう
そう思い
そう信じている
平成25年2月27日作。新作詩44の809
の「ボクという存在は」という詩で自律神経を批判した。目次に戻る。
812「2匹の鹿」
春の陽がさす奈良公園の端
2匹の鹿が
向かい合って坐っている

公園の鹿が春日山の鹿に話しかける
”君 君
公園の鹿は大変なんだ
1年に1回 角切りで
追っかけられるし
食事も時間制だから
必死に走って帰らないと
餌はなくなってるんだ”
”贅沢なこと言って”
春日山の鹿が言う
”君たちは観光客から
煎餅も貰うんだろう
僕たちは自分で餌を探すんだ
猟師や犬に追われるし
大変なんだ”
公園の鹿は考える
”少し不自由だが
もの貰って生きる方が楽だな”
春日山の鹿は考える
”辛いことあるが
矢張りボクたちには自由がある”
春日山の鹿は
”さようなら”
と公園の鹿に声をかけてから
頭を東に向け
ぴよんと跳んで走り去った
折から餌遣りのホルンが鳴った
”やれやれご飯だ・・”
公園の鹿は
頭を西に向け
ぴよんと跳んで走って行った
ボクは悩む
食べ物か自由か
どっちが大切か
がつん
天啓がくだった
”どっちもだ”
平成25年3月7日作。奈良公園の東には春日山原生林がある。目次に戻る。
813「賢治80年」
ずっと前
賢治学会に入ったことがある
賢治全集を全巻買ったこともある
しかし
学会は脱退したし
全集もひとにあげた
賢治は
好きで
嫌いだった
好きなのは
ボクの知らない化学を知っていたからで
嫌いなのは
難解な詩や長大な詩があったからだ
今は2013年
賢治が死んで80年経った
だから
”賢治80年”
とメディアは
大騒ぎする程の価値はないので
少し騒ぐ
賢治の銀河鉄道も
好きで
嫌いだ
銀河鉄道で好きなところは
カンパネラが消えて
ジョバンニが
”カンパネラ”
と叫ぶシーン
嫌いなのは
銀河鉄道の車両番号が33−0921と
わざとらしく書かれていること
死者が十字架に向かって歩くシーン
賢治は熱烈な法華経信者のはず
もっとも
これらは
賢治ではなく
制作者の責任だろうけどね
賢治80年
ボクが生れた頃
賢治が生きていたことに愕然とする

平成25年3月8日作。宮沢賢治・1896年(明治29年)8月27日生、1933年(昭和8年)9月21日没。賢治については新作詩43の788にも書いている。目次に戻る。
814「サヨリ」
サヨリ
ダツ目・サヨリ科
銀色の短剣のように
細長い魚で
海岸近くを遊弋する

昔
堤防や岩場で釣りしていると
サヨリの群れが寄ってくることがある
海面すれすれを泳いでくるから
餌釣りでも
引っかけでも
捕れる
ヒトの気配で潜るか
散れば助かるのに
彼らは平気で寄ってくる
”馬鹿だな”と思いつつ
サヨリを釣った
先日
行きつけの魚屋
頭をとり
開いて薄く塩振ったサヨリを
売っていた
昔のサヨリ釣りを思い出し
顔なじみの店
の女性に
”サヨリは馬鹿だよ”
と言うと怪訝な顔をしていた
買って帰ったサヨリ
焼いて食べたが
美味しかった
食べながら
”サヨリ君
捕られ
殺され
頭刎ねられ
腹開かれ
塩振られ
焼かれ
食べられ
そのうえ
馬鹿だと言われるとは”
と思い
次ぎに魚屋に行った時
店
の女性に
”サヨリは馬鹿だと言ったの
撤回するよ”
と言うと
彼女
にっと笑った
平成25年3月27日作。目次に戻る。
815「トビウオ」
トビウオ
サヨリと同じダツ目の魚
そういえば
いずれも
短剣のような形
似ているが
似て非なるは
トビウオの飛翔
敵に追われると
ジャンプ台なくても
100メートルは飛ぶ
生協に行ったら
まるまる肥ったトビウオを
売っていた
3枚におろしてもらい
ソティして食べた
何回か空飛んだトビウオの身
しまっていて美味
空を飛ぶどころか
もう海も泳げないじいさんが
シャブリ飲みつつ
空飛ぶ魚を食する贅沢
折から桜は満開
花明かりの中
しきりに
飛び交
うもの
がある
平成25年3月31日作。目次に戻る。
816「今年のサクラ」

京都
3月末の寒波が去ると
一斉に
今年のサクラが咲き
芭蕉の句
”9万9千くんじゅの花見”ならぬ
99万群衆の花見が始まる
だが
芭蕉の頃にも
花見に行かぬヒトがいたように
今でも
サクラ咲いても
体
や心を病むヒトあり
病まなくても
サクラ見とうないヒトもいる
元気なヒト
憂き心抱かぬヒトは
あちらのサクラ
こちらのサクラ
ぞろぞろ
歩いたり
立ち止まったり
上を向いたり
カメラかざしたり
ぞろぞろ
あちらのサクラ
こちらのサクラ
見て歩く
このヒトたち
よく見ると
日中ほとんど
あの世に
片足かけた老人ばかり
昨日あそこで
今日はこちらで
毎日花を見ているヒトもいる
”何故毎日花を見る”
聞くと
”体にいいから”
というヒトがいて
”何故かわからん”
というヒトもいる
”花飽きないの”
と聞くと
”3日で飽きる”
というヒトがいて
”花はみな違うから飽きない”
というヒトもいる
サクラ満開の頃には
もうサクラに飽きているボクも
散り始めると
慌てて
また花を見る
散り際のサクラが
美しいからではない
サクラは
来年も咲くが
ボクは
どうかなと思うからだ
花が散ると
シベばかり
汚いサクラ
開花 散華
人目はばからぬ
サクラの生殖
これが終わると
暫くは青葉若葉
来年に向けて
サクラは
静養し準備する
平成25年4月5日作。芭蕉の「京は九万九千くんじゅの花見哉」は中村俊定校注『芭蕉俳句集』岩波文庫14頁にある。”くんじょ”は群衆。この句は、愛する主人が身まかった自分は花見に行かない、行く気分ではない、という句であるが、芭蕉は花の中では桜を最も愛していたし、「さまざまな事おもひ出す桜かな」という句も作っている。芭蕉が9万9千くんじゅという位だから、その頃も1%の人は花見をしていなかったことになる。花見に行かない人、今はもっと多いだろう。
目次に戻る。
817「春樹の新作・その1」
今日
2013年4月12日
村上春樹の新作長編
”色彩を持たない
多崎つくると、
彼の巡礼の年”
の3日繰り上げ発売日
3年振りの新作長編小説
内容は絶対秘密
この作戦と彼の人気で
東京の書店では
午前0時発売に
140人並んだ
のんびり京都
今日
4月12日
川端北大路のある書店には
春樹の新作が山積み
34年前1979年
彼の処女作
”風の歌を聴け”
以来の約30年間
彼の小説は100%
エッセイ類は90%くらい
読んでいるが
小説もエッセイ類も
彼の人間性の具現物
約30年間
彼の小説エッセイ類からつかんだ
彼の人間性
今度の新作
彼が何を書くか
読む前から
大体わかるような気がする
1996年出版の
彼と河合隼雄の対談集で彼は
”ボクは時々
死後のことを考えています”
と話していた
彼ももう64歳
恐らく新作で
”死”
を重要テーマにしているような気がした
4月13日午後
新作を読み始めた
果たして書き出しは
”大学2年生の7月から、
翌年の1月にかけて、
多崎つくるは
ほとんど死ぬことだけを考えて生きていた”
だった
すぐに”死”が出ていた
さて
あとはどうなるか
読後の感想はまた後で
平成25年4月14日作。村上春樹の新作は、文藝春秋社2013年4月15日第1刷発行となっている。目次に戻る。
818「春樹の新作・その2」
名古屋の進学公立高校
仲良し5人組
男子は
赤松君
青海君
多崎君
女子は
白根さん
黒埜さん
みな姓に色がつくが
主人公の男子生徒
多崎君の姓だけ
色をもたない
大学進学後の20歳
多崎君にふりかかる
突然の不幸
あの親友4人からの
突然の絶交
集団行動
理由不明
これはイジメに近い
絶交された後の
多崎君
激しい鬱的自殺願望
拒食
体重減少
息切れ
若年老化
だが
ある日ある時
多崎君は立ち直る
ジムでマシン運動
プールでクロール
体力体重回復
顔も険しく鋭く
大人に変貌
ここで想記する
あの三島由紀夫のマッチョイズム
剣道
ボディビル
軍隊
右翼
クーデター
切腹
死
多崎君がやったことに
マラソンを加えると
春樹の健康生活
日本の私小説作家の
典型的不健康生活を嫌う
春樹の健康生活は
春樹人気の原因のひとつ
唐突として登場する
白根さんがよく弾いていた
リストのピアノ小品集
"
巡礼の年"
ベルマンのピアノで
第1年スイスのなかの
"Le Mal du Pays"
メランコリー或いはノスタルジア
が出てくる
春樹
しばしば小説またはエッセイで
ジャズまたはクラシック音楽の
お気に入り曲を披露する
今回もそうだと思い
持っているベルマンの
CDで聴く
ボクが鈍感なのか
別にどうということない
少し憂鬱な曲
大学に入ってからの唯一の
友人灰田君
これも色つき
灰田君
死ぬ予定者緑川に
”死んだらどうなる”と聞くが
答えは釈迦孔子の答えと同じ
”わからぬことは考えない”
恐らく春樹も同説だろう
多崎君
今は36歳
宿望の
駅舎建築も手がける鉄道会社勤務
春樹が経験したことのない
サラリーマン生活
服も靴も春樹よりぱりっとしている
恋人の沙羅さん
年上38歳
沙羅さんの勧めで
多崎君
16年振りに
絶交理由を
青海君から聞く
理由は多崎君が
白根さんをレイプしたということ
このレイプ
白根さんの創作虚言だったが
6年前
彼女は誰かに絞殺されていた
多崎君
赤松君にも会い
フィンランドに行って
女性の黒埜さん
にも会う
虚言者白根さんは精神を病んでいて
絶交は
白根さんを護るためだったと
黒埜さんは告白する
彼女は
白根さんも自分も
多崎君が好きだったと話す
昔ある人から
主人公がもてる小説は読者に嫌われる
と忠告されたことがある
主人公がもてるのは執筆者の特権
主人公がもてる小説は駄目だと言えば
源氏物語も駄目になる
まあ程度ものだと思うが
春樹の小説では主人公がもてている
口惜しければ読むな
ということだろうか
それに春樹はナルシスト
主人公の多崎君は
赤松君青海君よりも
格好良くて男前
これも執筆者の特権
しょうないな
多崎君は黒埜さんの家で
ブレンデルが弾く
巡礼の年を聴きながら
すべてを宥恕し
黒埜さんとハグハグする
多崎君
沙羅さんが
すてきな50歳台熟年男性と
仲良く街を歩くのを目撃
果たして多崎沙羅との恋は成就するか
いずれにしても
恋物語
ヒトを感動させることは
難しいなあ
4月13日午後11時読了
小説
批評は容易だが
書くのは難しい
3年かけて新作書いた春樹さん
ご苦労様
30年余も追っかけきた春樹
間違いなく最も関心を持つ作家
もう少し経って
再読しよう
新作買うため
深夜並んだ140人
ご苦労様
平成25年4月13日作。マッチョmachoとはメキシコで使われるスペイン語で”男性美、筋肉美”。ラザール・ベルマンのCDは、フランツ・リスト”巡礼の年”全曲グラモフォンPOCG-3413〜5。目次に戻る。
819「爺さんの店」
時々
修学院の歯医者に行くが
その帰り
爺さんの店に寄って
200円くらいで
サツマイモを買うことがある
店といっても
間口2間くらいの小店で
置いている品物は
夏はナスビとか胡瓜
冬はサツマイモとか大根
ジャガイモなどの少しの野菜を
プラスチックの容器に入れ
床几か林檎箱の上に置き
奥の棚には菓子を置いている
小さい店
エアコンが回っていることはなく
吹きさらしの店をやっているのは
爺さんと婆さん
爺さんは60歳くらいで
真っ白い髪はばさばさ
愛想笑いはせず
腰は曲げず
無用な口はきかず
藤沢周平の小説に出てくる
老いた岡っ引きのような
鋭い面構え
連れ合いの婆さん
爺さんよりは
大分若く
髪は真っ黒
笑わないが結構しゃべる
”買って売る”
の商売が
手に取るように判る
単純平明な店
亡友カトウちゃんを思い出す
根っからの商売人だったカトウちゃん
”買って売る”
ことが好きだった彼が開きそうな
単純平明な店
若狭に抜ける街道筋の集落
一乗寺とか修学院
の住人の顔は
京都市内の住人の顔と少し違う
一乗寺とか修学院
田畑が広がる田園地帯ではなく
くねくね曲がる街道のあちこちに
茶や団子を売る茶店か
京都で儲けた旅客に
とろろ飯とか酒を売る料理屋が
点在する小さい集落
冬には蘆荻が風に揺れ
粉雪がちらちら
時には刃かざして旅客を襲う盗賊
それを追う岡っ引き
何か潜んでいるような集落
昔を暗示するような
爺さんの面構え
こんな戯れ言をつぶやく
ボクは余所者
高野川沿いの若狭街道
鯖街道ともいわれた道路近くの
マンションにひっそり暮らし
ひっそり死んでいく運命
平成25年4月21日作。目次に戻る。
820「今年の5月」
去年の5月
”美しき5月”
という詩を書いたが
1年経
ち
今年の5月がやって来た
もともと5月は
桜の花が終わり
春が熟し
雨期が始まるまでの
青葉若葉の時期だが
いつでもそうとは限らない
例えば
戦争が始まり
この街が戦火に見舞われれば
青葉若葉も燃えるだろうし
大隕石の地球衝突でも
青葉若葉は消えるだろうし
世界的核戦争にも
青葉若葉は耐えられないだろう
そう思えば
年ごとの青葉若葉は
まあまあ
幸せな時空の象徴といえる
今日は友人の告別式
欠席してイタ
飯で友に献杯
帰宅して時計をみると
火葬の時間
青葉若葉の時期であれ
ヒトは死に
ちりにかえる

薤露青の空をみると
折良く白い雲がながれていた
青葉若葉の今年の5月
知人がいくたりも死んだ
傲慢な5月
平成25年5月4日作。去年の詩は新作詩42の776。葬式をさぼる理由は一つ・・葬式が嫌いだから。明後日も葬式。これも欠席、家内が出席。薤露青(かいろあお)とは、らっきょうの葉にたまる露の青さ。天沢退二郎編『新編・宮沢賢治詩集』新潮文庫182、419頁。目次に戻る。
821「人生の終期」
人生の始まりの時点
始期は誰もがはっきりしていて
それは
平成昭和などなど
或いは西暦
何年何月何日
の誕生日で表すことができるが
人生の終わりの時点
終期ははっきりしていない
生まれたばかりの赤ん坊でもそうだし
瀕死の病人でもそうだし
自殺しようとしている人でも
(自殺の成功には確率が働くから)
やはりそうだし
誰の人生の終期はぼーっと
霞がかかっていて判然としない
はっきりしている始期と
ぼーっとしている終期の間の途には
死に至る落とし穴が開いていて
1歳の赤ちゃんも
乳幼児突然死症候群
の落とし穴に落ちて死ぬことがあるし
20歳の青年も
急性骨髄性白血病
の落とし穴に落ちて死ぬことがあるし
40歳の壮年も
スキルス胃がん
の落とし穴に落ちて死ぬことがあるし
60歳過ぎると
落とし穴の種類や数は増えて
脳梗塞や心筋梗塞や自殺や事故
の落とし穴に落ちて死ぬことがある
つねづね
”貴方は100歳まで生きるよ”
と言っていた
呼吸器科の医師
先日
ボクに循環器障害が見付かったニュースを聞き
”
100歳は無理かな90歳だな”
と言ってからボクの顔を見て
”いや95歳かな”
と言い直した
平成25年5月22日作成。目次に戻る。
822「ボクの母」
ボクの母は
ええ格好しい
で
声も
ボクらとの話し声と
電話での話し声は
違っていた
百貨店に行くときは
きちんと着物着て
最後には
帯の胸のところを
ポンと叩いた
留守番のボクたちは
玄関の前で
うろうろ
母の帰りを待っていた
お土産は紙袋くるくるまいた
クリームパン ジャムパン
母は
歳をとり 腰が曲がっても
急ぎ足であちこち
よく買い物に行っていた
ボクは母が
だんだん歳をとるのは自然で
腰が曲がるのも自然で
最後に大腸がんで逝ったのも仕方ない
と思っていたが
母が死んで40年経った今
自然とか仕方ないと思った
若かった自分に腹が立つ
母を思うと
ギリシア文字のβ
を連想する
胸は大きくなかったし
痩せてお腹は出てなかったのに
何故か
βを連想する
平成25年5月25日作。β
→ベーター。目次に戻る。
823「もと軍人」
背の高いその男は87歳
肩は少し丸くなっているが
背筋はしゃきっと真っ直ぐ
人目に気づくと
一層しゃきっとする
旧陸軍士官学校出身
大尉で終戦
その後は軍と無関係の職を選んだが
一旦身についた正しい姿勢は崩れない
歳のせい
滑らかな動作は消え
瞬発力 動体視力は落ちたが
肝心の背筋伸ばしは忘れない
ヒトに会うときは必ず
顔も背筋もしゃきっとする
誰にも迷惑かけず
彼の軍は彼の中に
脈々と生きている
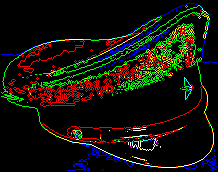
棺に入るとき
彼は
真っ直ぐ
しゃきっと
礼儀正しい
不動の姿勢をとるだろう
平成25年5月26日作。目次に戻る。
824「老老介護」
家内の咳が止まらず
熱が段々上がり
風邪が治らず
1週間経ったので
肺炎かも
と近くのクリニックに行く
先年 ボクの肺炎を治した医師が
白血球を調べ
X
線胸部撮影後
肺炎だと抗生物質の点滴開始
3日通院して
熱が下がり咳も止まった
家内通院中はボクが臨時主婦
バスで百貨店に行き
タクシーで
帰宅
息切れ症候群のボク
2キロ以上の荷物は禁止
そんなこと言っておれないので
野菜果物豆腐ハムぼた餅が入った
2キロ以上の荷物を持ってハアハア
息を切らして帰る
そんなことしている間に
ボクも風邪ひいて
8度近い熱が出て
夜は頭を冷やして寝る
今日は日曜日
家内もボクもぐったり
今夜のおかず
どうするかな
と悩んでいると
ピンポン
宅急便
家内の友達からの救援
物資
魚の味噌漬けが届く
老老介護なんて
他人事のように思っていたが
ボクんちではもう始まっている
平成25年6月2日作。目次に戻る。
825「鼠と羊と」
作家村上春樹
1949年生 早大卒後
ジャズ喫茶経営を経て小説を書き始め
1779年処女作「風の歌を聴け」
1780年「1973年のピンボール」
1782年「羊をめぐる冒険」
を発表
第1、2作は都会風の私小説だが
第3作の「羊をめぐる冒険」は
その後かずかずの幻想小説をものにする
フイックション作家村上を予言する
先進作品
ボクが最初に興味を持ったのは
この3作品に登場する
”鼠”
と呼ばれる男である
鼠男で想起されるのは
遠藤周作の小説「沈黙」に登場する
鼠男キチジロー
彼は28、9歳の漁夫で
カトリック信者だったが
踏絵のたびに棄教改宗し
司祭を密告し銀をもらう
ユダ的卑劣な存在
遠藤周作
主人公のポルトガル人司祭が
遂に改宗するまで
何故かこの鼠男キチジロ−を
しつこく描いている
キチジロ−のような卑劣な男も
主は赦されるのだろうか
という問いかけが「沈黙」の一つのテーマ
村上の前記3作品における”鼠”は
卑劣男の代名詞ではなく
主人公男性と同列の友人的存在として
第1作から登場する
そして
第3作の終わり近く
夜9時頃
闇の中に
幽霊として主人公の前に登場し
”ボクは
背中真ん中辺に★印のある超能力羊を
飲み込んでいたが
主人公が山荘に来る1週間前
この羊を殺すために
首つり自殺した”
と告白して消えてゆく
一見この鼠は他者的存在に見えるが
第1作からの鼠をみると
主人公男性とよく似ていて
作者の頭脳にある多数の創作エピソードを
主人公とこの鼠男に分配しているように思われる
遠藤周作における鼠は全くの他者だが
村上における鼠は他者的に見えて
実は主人公の分身であるというのが
ボクの結論
とすると
最終エピローグで
砂浜で2時間も泣いたのは何故か
分身の鼠の自殺を
この時になって泣くのはおかしい
もともと主人公は泣き虫で
羊のイベントが終わった感激の涙だと解したい
人に入魂して
その人を変身させ操作する
超能力羊
この羊をめぐる冒険話の発端は
広告業者の主人公らが出版したPR誌掲載の写真に
背中の真ん中辺に★印がある
奇妙な羊が写っていることを理由に
誌の出版中止を求められることに始まる
この羊の話し
荒唐無稽であるから
流し読みでは判り難く
メモとりながら
眉に唾付けながら
真面目に読むことが必要
平成25年6月11日作。村上春樹→作家1948年〜。「羊をめぐる冒険」は『羊をめぐる冒険』上、下講談社文庫で読んだ。遠藤周作→作家1923〜1996年。「沈黙」は新潮文庫平成25年4月20日第54刷で読んだ。羊が人間に入りこむ、入魂する、という話しは蒙古など大陸には昔からあったよう。背中に★印を持つ超能力羊が先生(右翼のボス)に入魂したのは1936年頃で、入魂により先生は大きく変わる。この羊は羊博士にも入魂しており、最後は鼠に入魂し、鼠の自殺で生命を終わる。羊男は羊の縫いぐるみを着た身長50センチの小柄な男。鼠は主人公が山荘、草原に来る1週間前に自殺し、遺体は羊男が埋葬した。がから鼠の死後、鼠は羊男の身体を借りて主人公に会っていることになる。目次に戻る。
826「カフカとカラス」
昔昔
京都に住む貧しき人は
加茂川東の鳥辺野
あたりに遺体を棄て
鳥葬ないし風葬を行っていた
禿鷲禿鷹いない鳥辺野での鳥葬実行者はカラス
鴉 烏 カラス
かあかあ カラス
カラスはチェコ語でカフカ
人が一夜で大きな芋虫に変わる小説「変身」
その著者はフランツ・カフカ
カフカの祖父は屠殺業者
ユダヤ人が姓を持つことが許されたとき
祖父はカフカ
Kavkaカラスと名乗り
父も商標にカラスを描いた
チェコでも日本でもカラス
はカラス
美しくも可愛くもなく声も汚い
縁起悪く黒い怪奇なトリ
嫌われもののカラス
これを姓にした人の心を思え
フランツ・カフカ
法学部を出た神経質な中堅公務員
昼はそうだが
夜は怪奇な物語を紡ぐ芸術家
反骨精神旺盛作家村上春樹
ある小説では鼠を友の通称とした村上春樹
カフカやカラスを人の名とするくらいは
平気の平左
古代ギリシャ悲劇詩人ソポクレスが
紀元前427年頃書いた
憂鬱な戯曲「オイディプス王」
オイディプスの父ラーイオスは神から
子を作ればその子に殺されるという神託を受けるが
オイディプスが生まれる
いろいろあった後
オイディプスは父を殺し
母を妻とする
村上の小説
「海辺のカフカ」の主人公
田村カフカ少年の父も息子に
”お前は父を殺し
母姉を犯す”
と予言する
シルクハットかぶり
ジョニー・ウォーカーに扮したカフカの父
奇妙なおじさんナカタに殺され
主人公カフカ少年の分身であるカラスに
空から襲われ 2度殺される
田村カフカ少年はは母と姉と慕う女性と
うつつの間夢の間に交わる
こんなテーマ
非村上であるボクは
書けないし書きたくない
村上の小説「羊をめぐる冒険」の終わりのエピローグで
主人公は万感胸に迫り 2時間も泣いたが
東京に帰り 中学に復学
というまともな選択をしたした
「海辺のカフカ」の主人公田村カフカ少年は
終章で一筋の涙を流すだけ
平成25年6月21日作。村上春樹→作家1948年〜。フランツ・カフカ→チェコ人作家1883年7月3日〜1924年6月3日。池内紀「カフカ短編集」岩波文庫2012年11月5日第50刷259頁にカフカの姓についての記述がある。村上春樹「海辺のカフカ」は新潮文庫(上)平成25年4月25日41刷、(下)同日39刷で読んだ。空飛ぶカラスがジョニー・ウォーカーを襲う場面は下巻446頁以下。日本人が嫌う動物の1番は蛇で、カラス、鼠は10番目前後。カラスも「三羽がらす」ではカラスが良い意味に使われているし、野口雨情は童謡「7つの子」で”カラスなぜ啼くの カラスは山に可愛い7つの子があるからよ・・・・”という謎深い詩を書いている。カラスの歳が7つにもなれば、可愛い子とはいえないからだ。目次に戻る。
828「ブルーライト・ヨコハマ」
若い頃
と言っても30歳代の終わり頃
ボクは東京地裁にいて
ある日の夕方
ぶらぶら歩きの散歩の途中
有楽町の小さい劇場に入った
入ったら
いしだあゆみが舞台の花道を
”街の灯りがとてもきれいなヨコハマ
ブルーライト・ヨコハマ・・・”
彼女のヒット曲
の頭を唄いながら
軽いステップで歩いていた
その頃のいしだあゆみ
若く可愛いかった
その後
4年間横浜地裁に勤務したが
ブルーライト・ヨコハマ
という印象を受けることはできなかった
今
NHKBS
で長山洋子が
ブルーライト・ヨコハマ
を唄っている
”歩いても 歩いても
小舟のように 私は揺れて・・”
同じブルーライト・ヨコハマでも
20歳のいしだが唄うブルーライト・ヨコハマと
40歳
代の長山の唄うブルーライト・ヨコハマは
何処か違う
唄を聞くボクも有楽町で聞いたときから
40年歳を重ねている
唄は歳をとらないが
唄う人聴く人は
どんどん老けていく
平成25年6月29日作。いしだあゆみ歌手→1948年3月26日〜。長山洋子歌手1968年1月13日〜。ブルーライト・ヨコハマは1968年12月、リリースされた歌手いしだあゆみの26枚目のシングル盤。目次に戻る。
828「わが妻よ」
80に近づいた妻が
そわそわ寄ってきて言った
”見て見て私の顔・・”
鼻の下にできた
何本かの細い縦皺が気になるのだ
”判ってるよ”
ずっと前からその縦皺に気づいていたボクは
”滑走路ができたんだよ”
と慰めた
”仕方ないわね”
諦め顔で妻は買い物に出かけた
鼻の下の滑走路と一緒に
”わが妻よ
君がボクと結婚した24歳当時
君の顔には皺一つ
しみ一つなかったと
ボクは宣言しよう
無慈悲な歳月が無断で
ひとの顔に飛行場をつくったんだよ”
平成25年7月7日作。目次に戻る。
829「ノルウェイの森」
ボクが暮らしている京都上高野の
マンション東側リビングからは
低い御陵型の山と
その上の空が見える
もっとも
ベランダには庇があるから
空は庇と山に区切られた
横に細長い矩形の空である
この矩形の空
四季で少しずつ変わる
山の色に空の色に空飛ぶ雲の形
いろいろ変わる
早朝ホトトギスがけたたましく空を横切ることも
あるし
牛若丸が素襖をなびかせて北に空飛ぶこともあ
るし
現実やら幻想やら
詩の材料には事欠かない
暑い今年の夏
弱くクーラーをかけ
ウォークマンに入っている古いリュート曲を
ソニーのドックで低く鳴らしながら
昔読んだ村上春樹の小説「ノルウェイの森」を再
読した
この小説が出た1987年頃読んだ時の印象は
屈折した恋愛小説だ
というものだったが
再読印象も同じだ
村上クラスの作家になると
平凡普通の恋愛小説は恥ずかしくて書けない
大学生の主人公は高校生時代の友人キズキの
自殺後
その恋人直子の恋人になるが
その直子は精神病んで施設で療養中
主人公は直子を見舞いに行き
一緒に寝たりするが
直子の病は治らず
直子も林の中で縊死する
直子の友人レイコと主人公の二人だけの
淋しい葬式
レイコは鎮魂のためギター曲を弾く
ビートルズの「ノルウェイの森」は二度弾く
ボクもYou Tubeで
「ノルウェイの森」聴いてみた
歌詞も読んでみたが
歌詞も曲もボクの脳を素通り
この本は年寄り向きではない
というのがボクの読後感
平成25年7月18日作。目次に戻る。
830「狂った老鶯」
ヒトは
狭い道から血だらけで出て
来て
老いて
病んで
死んでいく
7月21日朝
ボクは体調悪く
救急車で医大病院に入院したが
当日夜
心不全で意識不明に陥り
危篤だと子供達も東京から駆けつけた
翌日
集中治療室で子供達に会ったが
意識不明に陥ったことも知らないボクは
不思議そうに子供達を見て
”お医者さんにお礼を言って
早くお帰り”
と言った
春に歌を覚えた雄ウグイスは
夏には一人前の歌い手となって
夏山で歌いまくる
その頃
彼はすでに歳をとっており
老鶯
と呼ばれ
余命いくばくもない身となっているが
それには気づいていない
折角危篤の父に会いに来た子供達に偉そうに
”早くお帰り”
などという父は
狂った老鶯
後日事情を知って恥かしい思いをしたが
ひととき命助かった悦びに
ボクはまた
秋の歌を歌おうとしている
平成25年8月23日作。狭い道、とは勿論、産道のこと。目次に戻る。
|トップページ|詩の目次|